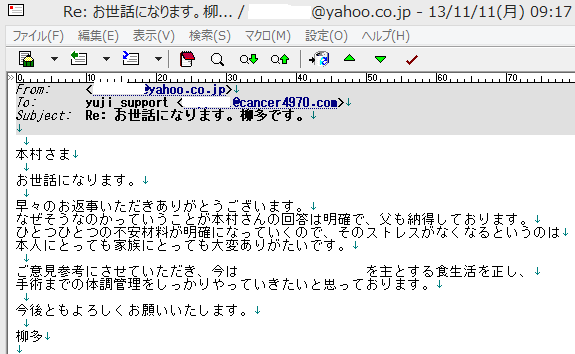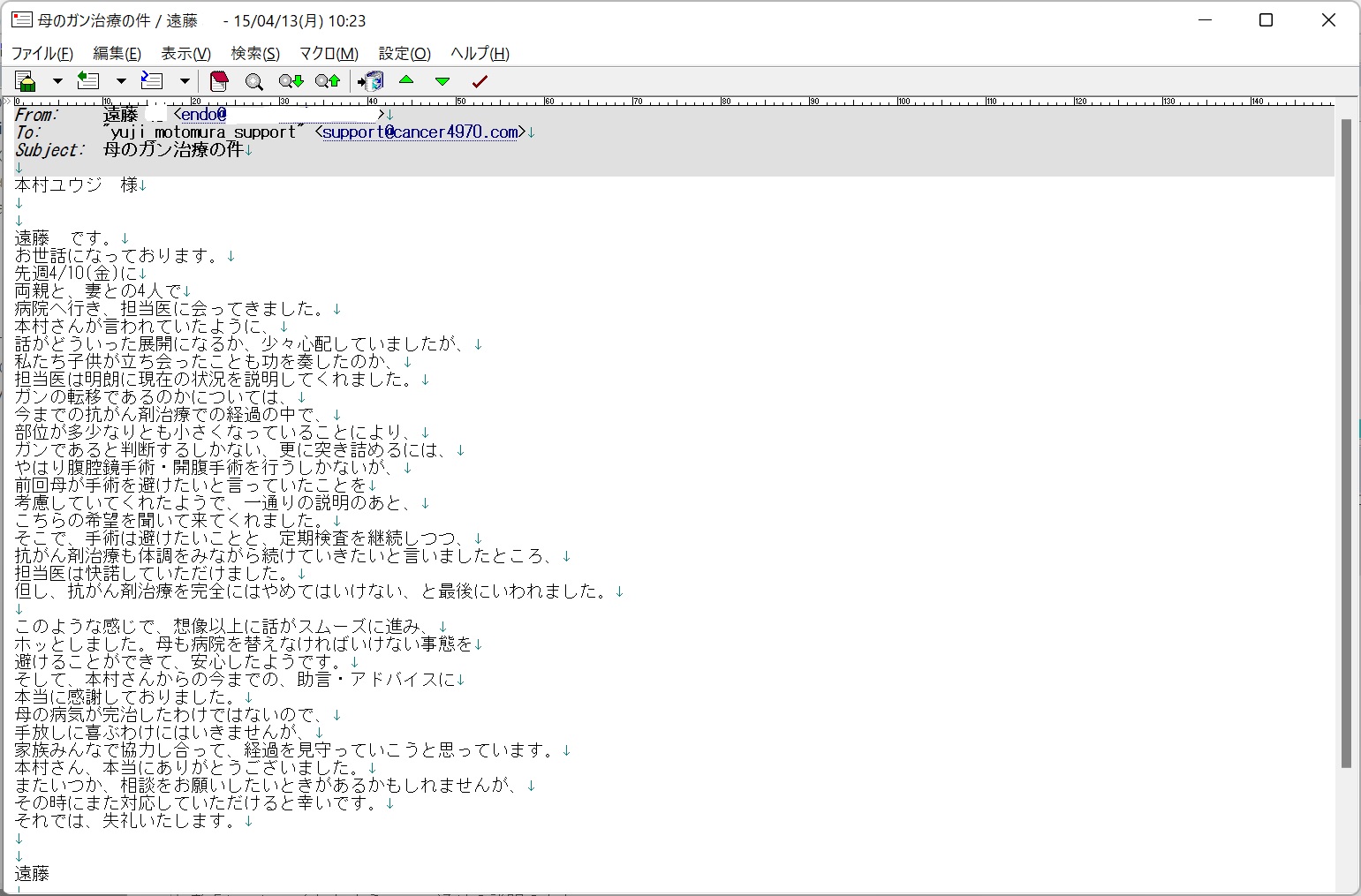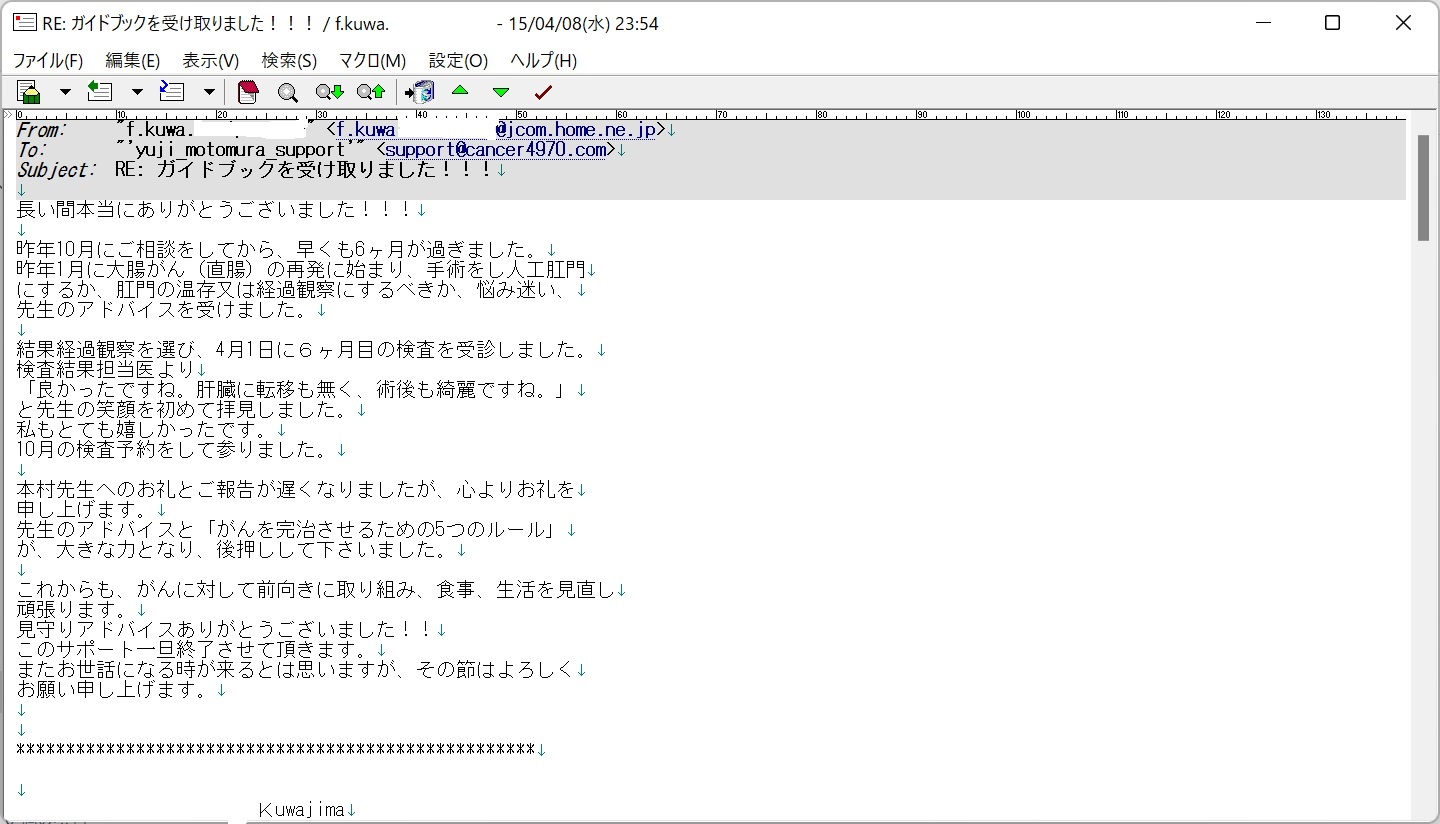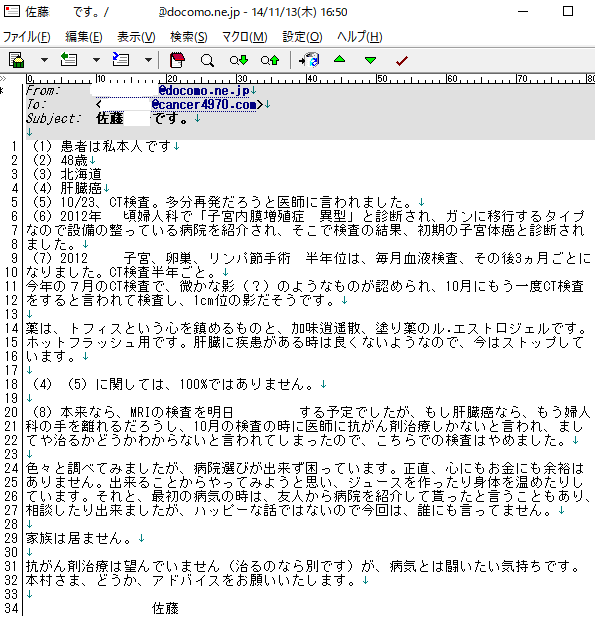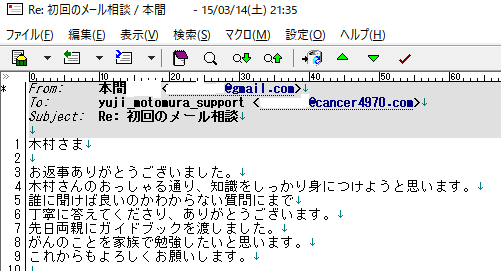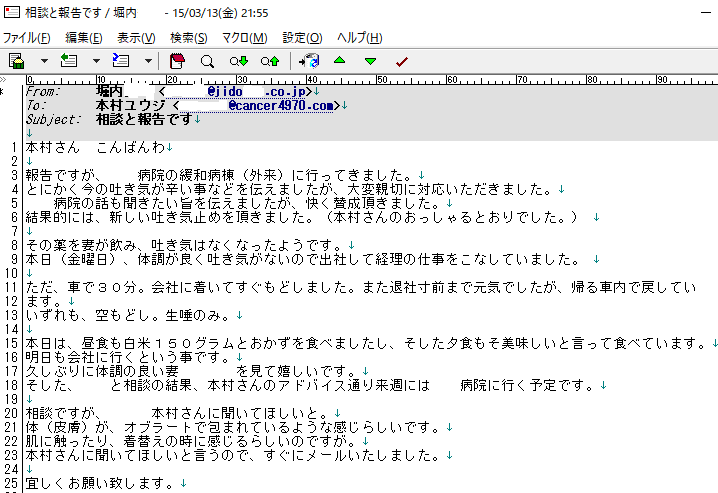膵臓がん治療における術前・術後化学療法
膵臓がんの化学療法は、手術前に行う術前化学療法と手術後に行う術後補助療法に分けられます。
術前化学療法の目的と効果
術前化学療法は、手術前にがんを縮小させることで切除率を向上させ、微小転移を制御することを目的としています。また、術前に化学療法に対する反応性を確認することで、その後の治療戦略を決定する上で役割を果たします。
術前化学療法レジメン
ゲムシタビン+S-1併用療法(GS療法)
投与方法:
- ゲムシタビン1000mg/m² 静脈内投与(第1日、第8日)
- S-1 80~120mg/日 経口投与(第1日~第14日)
休薬期間:7日間(3週間で1コース)
実施期間:通常2コース実施後に手術を検討
ゲムシタビン+ナブパクリタキセル療法(術前GnP療法)
投与方法:ゲムシタビン1000mg/m² + ナブパクリタキセル125mg/m² 静脈内点滴投与
投与スケジュール:第1日、第8日、第15日に投与
休薬期間:第22日から7日間休薬(4週間で1コース)
実施期間:通常4コース実施後に手術を検討
GnP療法は原発巣に対して十分な腫瘍縮小効果を期待でき、4コースの化学療法後に比較的短期間で手術が安全に施行可能であることが確認されています。実際に術前GnP療法を開始してからの切除率は良好で、8割以上の患者さんが安全に切除まで施行可能であり、以前の切除先行時代と比べて2倍近い長期生存成績を得ています。
術後補助療法レジメン
膵臓がんの手術後に行う術後補助療法は、目に見えない微小ながん細胞を消失させ、再発のリスクを減らすことを目的としています。現在、日本では主にS-1(TS-1)療法が術後補助療法の標準治療として確立しており、ゲムシタビン療法よりも生存期間を延長させることが証明されています。
S-1(TS-1)療法(6週ごと6コース)
投与方法:S-1 80~120mg/日を朝夕2回に分けて服用
投与期間:28日間服用、14日間休薬(6週間で1コース)
総治療期間:約6コース(36週間)
JASPAC-01試験の結果によると、S-1療法はゲムシタビン療法と比較して死亡のリスクを44%減少させることが明らかになりました。S-1は経口薬であるため、患者さんにとって負担が軽く、外来での治療継続が可能です。体表面積に応じて投与量が決められ、腎機能の状態も考慮して調整されます。
ゲムシタビン療法(4週ごと6コース)
投与方法:ゲムシタビン1000mg/m² 静脈内点滴投与
投与スケジュール:第1日、第8日、第15日に投与
休薬期間:第22日から7日間休薬(4週間で1コース)
総治療期間:約6コース(24週間)
ゲムシタビンは従来から膵臓がんの標準治療薬として使用されてきた薬剤です。現在では術後補助療法においてS-1療法がより効果的であることが示されていますが、S-1が使用困難な患者さんに対してはゲムシタビン療法が選択される場合があります。術後補助療法では、手術の侵襲により体力が低下していることも多く、患者さんの状態に応じた適切なレジメン選択が重要です。
集学的治療戦略の変遷
2019年に術前化学療法の有用性が示されて以降、膵臓がん治療は大きく変化しました。現在では、切除可能境界域膵臓がんに対して、術前化学療法(GnP療法)→手術→術後補助療法(S-1療法)という集学的治療アプローチが標準的となっています。この治療戦略により、従来の手術先行治療と比較して治療成績が向上しています。
術前・術後化学療法の適応基準
| 病期・状態 | 術前化学療法 | 術後補助療法 | 推奨レジメン |
|---|---|---|---|
| 切除可能 | 通常実施しない | 実施 | 術後:S-1療法 |
| 切除可能境界域 | 実施 | 実施 | 術前:GnP療法、術後:S-1療法 |
| CA19-9高値 | 実施を検討 | 実施 | 術前:GnP療法、術後:S-1療法 |
| 局所進行 | 実施(手術移行目的) | - | FOLFIRINOX、GnP療法 |
進行・再発がんに対する治療レジメン
手術不能または再発した膵臓がんに対しては、複数の化学療法レジメンが用意されています。近年の臨床試験の結果から、一次治療では主にゲムシタビン+ナブパクリタキセル(GnP)療法が第一選択となってきています。
ゲムシタビン+ナブパクリタキセル療法(GnP療法)
投与方法:ゲムシタビン1000mg/m² + ナブパクリタキセル125mg/m² 静脈内点滴投与
投与スケジュール:第1日、第8日、第15日に投与
休薬期間:第22日から7日間休薬(4週間で1コース)
GnP療法は、FOLFIRINOX療法と並んで最も推奨度の高い治療法の一つです。最新の臨床試験でGnP療法がFOLFIRINOX療法よりも良好な成績を示したことから、現在では第一選択として位置づけられています。ナブパクリタキセルはアルブミンにパクリタキセルを結合させたナノ粒子製剤で、従来のパクリタキセルよりも副作用が軽減されています。
FOLFIRINOX療法(2週ごと)
投与薬剤:
- オキサリプラチン85mg/m² 静脈内投与(第1日)
- レボホリナートカルシウム200mg/m² 静脈内投与(第1日)
- イリノテカン180mg/m² 静脈内投与(第1日)
- フルオロウラシル400mg/m² ボーラス投与(第1日)
- フルオロウラシル2400mg/m² 46時間持続静注(第1日~第2日)
休薬期間:12日間(2週間で1コース)
FOLFIRINOX療法は従来のゲムシタビン単独療法に比べて全生存期間を有意に改善(6.8ヵ月から11.1ヵ月)していますが、副作用の頻度も高く、十分な体力があり全身状態が良好な方が対象になります。日本では副作用を軽減するため、修正FOLFIRINOX療法(mFFX)として減量した投与法が採用されています。
ゲムシタビン単独療法(4週ごと)
投与方法:ゲムシタビン1000mg/m² 静脈内点滴投与
投与スケジュール:第1日、第8日、第15日に投与
休薬期間:第22日から7日間休薬(4週間で1コース)
体力的にFOLFIRINOX療法やGnP療法が対象とならない患者さんに対して選択される治療法です。副作用が比較的軽く、高齢の患者さんや全身状態がやや不良な患者さんでも実施可能です。
S-1単独療法(6週ごと)
投与方法:S-1 80~120mg/日を朝夕2回に分けて経口投与
投与期間:28日間服用、14日間休薬(6週間で1コース)
経口薬であることから利便性が高く、外来での治療継続が容易です。消化器系の副作用(下痢、口内炎など)に注意が必要ですが、点滴による治療が困難な患者さんにとって有用な選択肢です。
二次治療・三次治療の選択肢
一次治療で効果が不十分になった場合、患者さんの全身状態が許す限り二次治療への移行が検討されます。一次治療で使用した薬剤と系統の異なる治療法を選択することが原則です。
リポソーマルイリノテカン・5-FU/LV療法(Nal-IRI/FL療法)
投与方法:
- リポソーマルイリノテカン70mg/m² 90分投与(第1日)
- レボホリナートカルシウム200mg/m² 2時間投与(第1日)
- フルオロウラシル2400mg/m² 46時間持続投与(第1日~第2日)
投与間隔:2週間ごと
2020年6月に保険承認されたNal-IRI/FL療法は、ゲムシタビンベースの一次治療後の二次治療として有効性が証明された治療法です。リポソーマル化によりイリノテカンの副作用軽減と効果増強が期待されています。
治療成績の変遷と最新の動向
2020年代には、抗がん剤を高分子化してがんに選択的に取り込まれやすく工夫されたナノリポソーマルイリノテカンや、BRCA遺伝子変異に対するオラパリブなどの個別化治療も登場し、治療成績は確実に向上しています。
| 治療法 | 生存期間中央値 | 対象患者 | 主な特徴 |
|---|---|---|---|
| mFOLFIRINOX | 11.1ヶ月 | 全身状態良好 | 強力だが副作用も多い |
| GnP療法 | 8.5ヶ月 | 標準的体力 | 現在の第一選択 |
| ゲムシタビン単独 | 6.8ヶ月 | 体力やや不良 | 副作用軽微 |
| S-1単独 | 9.7ヶ月 | 経口薬希望 | 利便性が高い |
治療選択の考慮事項
膵臓がんの化学療法選択においては、患者さんの年齢、全身状態(パフォーマンスステータス)、臓器機能、合併症の有無などを総合的に評価する必要があります。また、治療効果だけでなく、副作用の種類や程度、患者さんの生活の質(QOL)も重要な判断材料となります。
副作用管理の重要性
FOLFIRINOX療法では好中球減少、下痢、末梢神経障害が、GnP療法では末梢神経障害、脱毛、骨髄抑制などがみられます。特に末梢神経障害は生活の質(QOL)を低下させるため注意が必要です。副作用の程度によっては減量や休薬を適切に行い、治療継続を優先することが重要です。
最新の研究開発動向
2025年には、膵臓がんに対する重粒子線治療の予後予測バイオマーカーの特定や、新たなMEK阻害剤の開発など、治療成績向上につながる研究成果が次々に発表されています。また、家族性膵がんに関する研究や遺伝子変異に基づく個別化治療の開発も進展しており、将来的にはより効果的で副作用の少ない治療法の登場が期待されています。
既存の抗がん剤とは異なる作用機序に基づく新たな治療薬の開発も進んでおり、膵臓がんの微小環境下で有効に作用する治療法の研究が続けられています。これらの新規治療法は、従来の化学療法の限界を克服する可能性を秘めています。
治療継続のポイント
膵臓がんの化学療法は長期間にわたることが多く、治療継続のためには患者さんと医療チーム双方の努力が必要です。
参考文献・出典情報
- 国立がん研究センター がん情報サービス「膵臓がん 治療」
https://ganjoho.jp/public/cancer/pancreas/treatment.html - がん研有明病院「膵がんの化学療法」
https://www.jfcr.or.jp/hospital/cancer/type/pancreas/006.html - 静岡がんセンター「膵がん患者のS-1術後補助化学療法の臨床試験結果」
https://www.scchr.jp/press/20130123.html - 国立がん研究センター中央病院「mFOLFIRINOX療法について」
https://www.ncc.go.jp/jp/ncch/division/pharmacy/010/pamph/pancreatic_cancer/030/index.html - 富山大学和漢医薬学総合研究所「新たな膵臓がん治療薬候補化合物の創製」
https://www.inm.u-toyama.ac.jp/result/2023_0605/ - NPO法人キャンサーネットジャパン「すい臓がんの薬物療法」
https://www.cancernet.jp/cancer/pancreatic/pancreatic-chemo - 国立がん研究センター東病院「膵がんの薬物療法の進歩」
https://www.ncc.go.jp/jp/ncce/info/shonai_ncche/1126/index.html - ファーマスタイル「FOLFIRINOX療法とGem/nabPTX療法」
https://ph-lab.m3.com/categories/clinical/series/basicknowledge/articles/309 - GI cancer-net「切除後膵癌に対するmFFX療法の多施設共同試験」
https://report.gi-cancer.net/beirinsyo2018/report/lba4001/