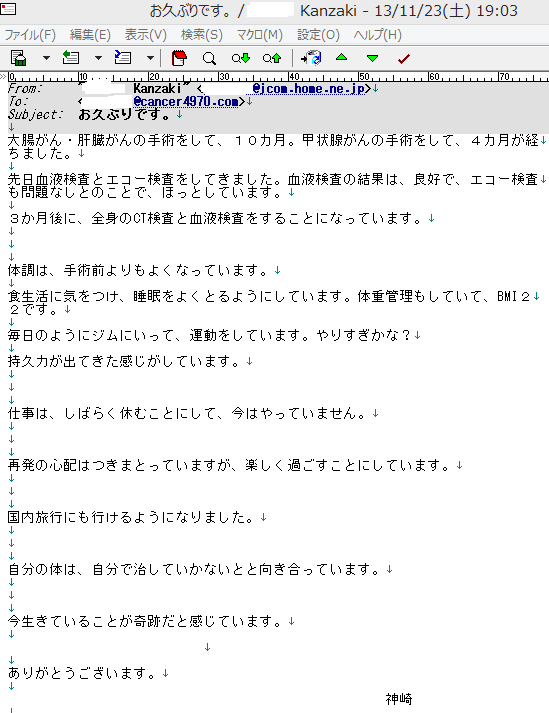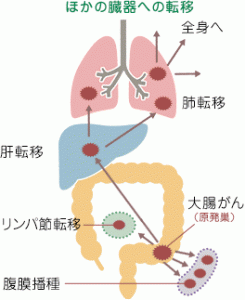
大腸がんは日本人に最も多いがんの一つで、進行すると他の臓器に転移することがあります。中でも肝転移は最も頻度が高く、大腸がんの転移の約90%を占めます。大腸がんの肝転移は、初回診断時に約12%の患者に認められ、根治手術後の遠隔再発としても約7.1%に見られる重要な病態です。
しかし、適切な治療により良好な予後が期待できる場合も多く、特に手術による完全切除が可能な場合には5年生存率が30~50%に達します。大腸がん肝転移の症状、診断、治療法、そして最新の生存率データについて詳しく解説します。
大腸がん肝転移の基本知識と発生メカニズム
大腸がんの肝転移は血行性転移の一種で、がん細胞が血液の流れに乗って肝臓に到達し、そこで増殖することで発生します。消化管から栄養分を含む血液は門脈という血管を通って肝臓に集まるため、大腸がん細胞も同じ経路を通って肝臓に到達します。
肝臓は血液中の毒物を無害化し、栄養分を蓄える重要な働きを持つ臓器です。この特性により、大腸がんの転移先として最も多い臓器となっています。肝転移は大腸がんの再発パターンの中で最も頻度が高く、局所再発と並んで重要な治療対象となります。
大腸がん肝転移の症状と進行段階別の特徴
初期段階の症状
肝転移の初期段階では、多くの場合で明確な症状は現れません。これは肝臓が「沈黙の臓器」と呼ばれるように、初期の病変では自覚症状が少ないためです。この段階では、定期的な画像検査や腫瘍マーカーの測定によって発見されることが一般的です。
進行した肝転移の症状
肝転移が進行すると、以下のような症状が現れる可能性があります。最も特徴的な症状は黄疸で、皮膚や白目が黄色っぽくなります。これは肝臓で作られた胆汁が十二指腸に流れ出るのを、肝臓や胆管にできたがん病巣が妨げるために起こります。
黄疸がさらに進行すると、皮膚は黒ずんでカサカサとした状態になり、尿も紅茶色に変色します。また、腹水の貯留や両下肢のむくみ、上腹部のしこりや圧迫感、痛みなども現れることがあります。肝臓が大きくなることで、腹壁から触れて分かるようになる場合もあります。
診断に用いられる検査方法と腫瘍マーカー
画像検査による診断
肝転移が疑われる場合、まず腹部超音波検査が行われます。これは痛みがなく放射線を浴びることもない、最も手軽に行える検査です。超音波検査では、大腸がんの肝転移は外周が黒く内部が白いリング状の腫瘤として観察されます。
より詳細な診断には、腹部CTやMRI検査が用いられます。CT検査は造影剤を使用することで肝臓の正常部分と腫瘍のコントラストがはっきりし、より正確な診断が可能になります。MRI検査は磁力を利用した断層検査で、CT検査では判別困難な良性腫瘍との区別ができることがあります。
重要な腫瘍マーカー
大腸がん肝転移の診断と治療効果の判定には、複数の腫瘍マーカーが用いられます。最も重要なのがCEA(がん胎児性抗原)とCA19-9(糖鎖抗原19-9)です。
CEA(がん胎児性抗原)
CEAの基準値は5.0ng/ml以下とされており、大腸がんに対する陽性率は30~40%です。CEAは大腸がんの他にも、食道がん、胃がん、肺がん、乳がん、肝がんなどでも上昇します。また、肝炎や糖尿病、腎不全、喫煙などでも上昇することが知られています。
CA19-9(糖鎖抗原19-9)
CA19-9の基準値は37.0U/ml以下で、大腸がんでは30~50%の陽性率を示します。膵臓がんや胆道がんでより高い陽性率を示しますが、大腸がんの肝転移においても重要な指標となります。がんの進行度が高い場合により上昇しやすい傾向があります。
ALP(アルカリフォスファターゼ)
ALPは肝臓、胆管、骨などに多く含まれる酵素で、基準値は38~113U/L(IFCC法)です。肝転移により胆汁の流れが妨げられると、ALPが血液中に漏れ出て値が上昇します。特に閉塞性黄疸や胆道疾患で顕著に上昇するため、肝転移の診断において重要な指標となります。
大腸がん肝転移の治療選択肢と最新アプローチ
手術療法(肝切除術)
大腸がん肝転移に対する最も効果的な治療は手術による肝切除です。近年、肝切除の適応基準が拡大され、以前は困難とされた病変でも手術可能になりました。手術の適応を決定する際は、以下の条件を総合的に評価します。
肝臓のどの部分に転移巣があり、転移巣がすべて取り切れるかどうか、肝臓以外に転移している臓器がないか、手術後の生活に支障がないだけの肝臓が残せるか、患者が手術に耐えられるかなどを慎重に検討します。肝臓の機能が正常な場合、肝臓の70%まで切除可能です。
切除範囲は、がんの大きさと進行度、肝機能の状態に基づいて決定されます。葉切除(肝右葉切除、肝左葉切除)、区域切除、部分切除などの術式があり、病変の状況に応じて最適な方法が選択されます。
化学療法
手術による完全切除が困難な場合、化学療法が選択されます。近年、分子標的薬をはじめとする化学療法が大幅に進歩し、治療効果の向上により当初手術困難とされた病変でも、化学療法後に切除可能となる場合が増えています。
抗がん剤の投与方法として、全身への点滴投与や内服薬が一般的ですが、肝転移に対しては肝動注療法という特殊な治療法も行われることがあります。これは肝動脈にカテーテルを挿入し、直接肝臓に抗がん剤を注入する方法で、より少量の薬剤でより高い効果が期待できます。
熱凝固療法
転移巣の大きさが3cm程度以下の場合、マイクロ波凝固療法(MCT)やラジオ波焼灼療法(RFA)などの熱凝固療法が適用されることがあります。これらの治療では、体外から特殊な針をがんに刺し、高熱でがん細胞を凝固・壊死させます。
MCTは直径2cm程度までの病変に適し、電子レンジと同じマイクロ波を使用するため温度上昇が早く、数分で治療が完了します。RFAは直径3cm程度の病変に適し、高周波電流を使用するため治療には10分前後を要しますが、より大きな病変に対応可能です。
手術後の生存率と予後データ
最新の生存率データ
大腸がん肝転移の手術後生存率は、転移の状況や治療法により大きく異なります。完全切除が可能な場合の5年生存率は30~50%とされており、良好な予後が期待できる条件が揃っていれば、さらに良好な結果が期待できます。
具体的な生存率データとして、初回手術時に他に転移がなかった患者における肝転移後の生存率は、1年後生存率40%、3年後生存率30%、5年後生存率20%という報告があります。肝切除例全体では5年生存率35%となっています。
| 期間 | 生存率 | 備考 |
|---|---|---|
| 1年後 | 40% | 初回手術時他転移なし例 |
| 3年後 | 30% | 初回手術時他転移なし例 |
| 5年後 | 20% | 初回手術時他転移なし例 |
| 5年後 | 35% | 肝切除例全体 |
予後に影響する因子
生存率は統計的なデータであり、個々の患者の予後は様々な因子により左右されます。良好な予後が期待できる条件には、転移巣の数が少ない、転移巣のサイズが小さい、肝機能が良好、他臓器への転移がない、完全切除が可能などがあります。
また、腫瘍マーカーの値も予後に関連することが知られており、治療により腫瘍マーカーが正常化する場合は良好な予後が期待できます。一方、治療後も腫瘍マーカーが上昇し続ける場合は、治療効果が不十分である可能性があります。
治療成績と化学療法の効果
肝動注化学療法の成績
大腸がん肝転移に対する肝動注化学療法の奏効率(CTにおける腫瘍の断面積が半分以下になる頻度)は50~80%とされており、全身化学療法よりも高い肝転移の縮小頻度が多くの研究で確認されています。
しかし、欧米で行われた全身化学療法との比較試験では、肝動注化学療法が生存期間の延長につながるという明確な結果は得られませんでした。これは肝動注化学療法が肝臓以外の病巣には効果がないため、肝転移以外の病巣の出現や悪化が原因として挙げられています。
最新の化学療法の進歩
近年の化学療法の進歩により、分子標的薬をはじめとする新しい治療法が開発されています。これにより、従来は手術困難とされていた症例でも、化学療法により腫瘍が縮小し、手術可能となるケースが増加しています。
ただし、化学療法は肝機能障害を引き起こす可能性があるため、漫然と継続することは推奨されません。適切なタイミングで手術への移行を検討することが重要で、切除のタイミングを逃さないことが治療成功の鍵となります。
腫瘍マーカーによる治療効果の監視
治療効果判定における重要性
腫瘍マーカーは治療効果の判定に重要な役割を果たします。治療により腫瘍マーカーが低下すれば治療が効果的であり、がんが縮小している可能性が高いと判断できます。逆に治療を行っても腫瘍マーカーが上昇する場合は、治療が無効でがんが増大している可能性が高いと考えられます。
特に、正常域内であっても右肩上がりに数値が上昇する場合は、がんが増殖してきている兆候であることが多く、治療方針の変更を検討する必要があります。定期的な腫瘍マーカーの測定により、早期に再発や転移を発見できる可能性があります。
複数マーカーの併用
より正確な診断と治療効果の判定のため、複数の腫瘍マーカーを併用することが一般的です。CEA、CA19-9、ALPなどを組み合わせて測定することで、診断精度の向上と治療効果のより詳細な評価が可能になります。
ただし、腫瘍マーカーはがん以外の要因でも上昇することがあるため、画像検査や他の検査結果と総合的に判断することが重要です。また、がんがあっても腫瘍マーカーが正常域にとどまる場合もあることを理解しておく必要があります。
患者と家族が知っておくべき重要なポイント
早期発見の重要性
大腸がん肝転移は初期段階では症状が現れにくいため、定期的な検査による早期発見が極めて重要です。大腸がんの治療後は、定期的な画像検査と腫瘍マーカーの測定により、肝転移の早期発見に努める必要があります。
早期に発見されれば手術による完全切除の可能性が高まり、良好な予後が期待できます。また、化学療法の効果も早期であるほど高く、後の手術につなげられる可能性も向上します。
治療選択における重要な考慮事項
大腸がん肝転移の治療は、個々の患者の病状、肝機能、全身状態、社会的背景などを総合的に考慮して決定されます。同じ「大腸がん肝転移」でも、転移の大きさ、場所、数などは患者ごとに異なり、最適な治療法も異なります。
治療選択にあたっては、主治医との十分な対話が重要です。治療のメリットとリスク、期待される効果、副作用などについて十分に理解した上で、患者自身の価値観や生活環境を考慮して治療方針を決定することが大切です。
多職種チームによる包括的ケア
大腸がん肝転移の治療は、大腸外科、肝臓外科、腫瘍内科、放射線科、病理科など多くの診療科が協力して行われます。また、看護師、薬剤師、栄養士、ソーシャルワーカーなどの多職種チームによる包括的なケアが提供されます。
このような多職種連携により、個々の患者に最適な治療計画の立案と実行が可能になり、治療効果の最大化と副作用の最小化が図られます。患者と家族は、このチームの一員として治療に積極的に参加することが重要です。
まとめ
大腸がん肝転移は確かに深刻な病態ですが、適切な診断と治療により良好な予後が期待できる場合も多くあります。手術による完全切除が可能な場合の5年生存率は30~50%に達し、化学療法の進歩により治療選択肢も拡大しています。
参考文献・出典情報
- 日本大腸肛門病学会「大腸がんが肝臓に転移したら…?」
- 国立がん研究センター がん情報サービス「腫瘍マーカー検査とは」
- 東京都立駒込病院「大腸がん肝転移の診断と治療について」
- 国立がん研究センター「大腸がんファクトシート 2024」
- がん研有明病院「転移性肝腫瘍の手術と成績」
- 東京医科歯科大学「転移性肝がん:肝臓の病気と治療」
- がんハートサポート「大腸がんの腫瘍マーカーであるCEAやCA19-9などについて」
- 健診会 東京メディカルクリニック「ALP(アルカリフォスファターゼ)の検査について」
- MEDLEY「大腸がんの肝転移:診断、治療、生存率について解説」
- 兵庫医科大学病院「転移性肝がん(外科治療)」