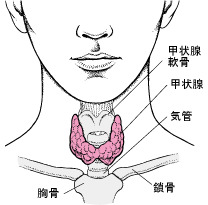
甲状腺がん治療における手術の重要性
甲状腺がんの場合、悪性リンパ腫を除くすべてのタイプにおいて、手術で病変部分を摘出するのが現在では最も効果的な治療法とされています。甲状腺がんは、他の臓器のがんと比較して、発育も緩やかで、他の部位への転移も比較的少ない、おとなしい性質を持っています。
その反面、抗がん剤や放射線照射治療は甲状腺がんには効果が限定的です。したがって、甲状腺がんを根治するには、手術が第一選択となります。
甲状腺がん手術の主要な合併症・後遺症
甲状腺がんの手術では、切除範囲が大きいほど、甲状腺機能の低下、副甲状腺機能の低下、反回神経の麻痺などの合併症のリスクが高くなります。甲状腺がんが早期に発見された場合は、手術で切除する範囲も限定的で、合併症が起こることはほとんどありません。
一方、がんが進行して広範囲の手術をした場合、起こりやすいのは、声帯の麻痺や副甲状腺機能低下症です。
反回神経麻痺による声への影響
甲状腺の右葉と左葉は声帯につながり、声帯の働きをコントロールしている反回神経(甲状腺の後ろを走っている)とも接しています。反回神経は声帯を動かす太さ1-2ミリ程度の神経です。
反回神経は太さ1-2mmと細く、手術操作で神経を直接触ることにより容易に麻痺が起こりやすいとても繊細な神経です。がんが反回神経まで浸潤しているケースでは、反回神経まで手術で切除せざるを得ない場合があります。
片方の反回神経を切除すると、声がかすれ、しゃがれ声になります。また、ものを飲み込むときにむせるようになります。左右いずれかの声帯麻痺であれば、声のカスレや飲水時のむせなどの症状が出ますが、呼吸の上では問題ないことが多いです。
しかし、反回神経を両方とも摘出すると、声が出なくなり、呼吸が困難になります。両側の声帯麻痺が生じてしまうと呼吸困難を生じてしまいます。そのような場合は、気管切開をしなければなりません。
反回神経麻痺の発生率と回復の可能性
とても細くて弱い神経で、丁寧に剥がして見た目にはきれいに温存されていても、5%程度では、一時的な機能不全(反回神経麻痺)に陥ってしまいます。
当院のバセドウ病手術後の反回神経麻痺の発生率は約1%で、そのうち90%以上は一過性の(一時的な)麻痺で半年以内に自然に回復しています。
どんな熟練した甲状腺外科専門医が手術しても、0.2-0.4%の確率で永続性反回神経麻痺の合併症がおこるとされます。神経が確実に温存されていれば、この反回神経麻痺(声帯麻痺)のほとんどは、数か月以内に回復します。
上喉頭神経外枝への影響
甲状腺手術による音声機能に対する影響としては、反回神経麻痺による声帯麻痺が代表的ではありますが、さらに細い神経である、上喉頭神経外枝という神経も関与していると考えられています。
甲状腺の上極(頭側)を処理するときに損傷しやすい神経で、この神経が損傷されると、高い声が出にくくなったり、長く話し続けると疲れやすくなったりするといわれています。
副甲状腺機能低下症
甲状腺を全摘出する場合は、甲状腺の背部にある副甲状腺が切除されてしまうことがあります。副甲状腺は米粒ほどの大きさで、とても小さな臓器です。
副甲状腺は、血中のカルシウムの代謝を調節するホルモンを分泌していますので、それが切除されると血中カルシウムが低下して、テタニー症状(手指や口の周囲のしびれ)が起こることがあります。甲状腺術後の一過性の副甲状腺機能低下症の頻度は比較的高く、6.9%から46%と報告されています。
甲状腺術後の永続的な副甲状腺機能低下症の頻度は、0.9%から1.6%と報告されています。
副甲状腺機能低下症の治療法
テタニー症状は、カルシウム製剤やビタミンD3製剤を内服すれば改善されます。副甲状腺ホルモン不足による副甲状腺機能低下症に対する治療は、活性型ビタミンD3製剤の投与が主体となります。
甲状腺がん手術の安全性向上への取り組み
術中神経モニタリング
最近は、術中神経モニターの電気刺激での確認により、以前から比べて、より高い確率で、神経の同定、温存が可能になりました。
隈病院では、この神経モニタリングを、2011年からすべての甲状腺手術で実施しています。術中神経モニタリングにより、手術中の神経の位置を確認し、損傷を避けることが可能になっています。
術前・術後の声帯運動評価
甲状腺腫瘍診療ガイドライン2024では、術前、術後の声帯運動の評価が甲状腺手術で推奨されています。これにより、手術前後での声帯機能の変化をより正確に評価できるようになりました。
手術後の甲状腺がん再発について
甲状腺がんの再発は、他の部位のがん(胃がんや乳がんなど)と比較すると、頻度は少ないといえます。再発する場合、大部分はリンパ節に起こります。再発した場合でも、他のがんと違って、再び手術をすることができます。
乳頭がんの再発パターン
乳頭がんの場合は、ほとんどが局所(甲状腺)での再発で、肺や脳への転移はめったにありません。再発するにしても遠隔転移ではなく、片方の甲状腺がんを切除したあと、もう一方の甲状腺に転移・再発する、というケースがほとんどです。
甲状腺乳頭がんや濾胞がんといった一般的な甲状腺のがんは、ほかのがんと比べるとゆっくりと大きくなります。甲状腺のがんの場合、術後15年、20年たってから再発してくる例は珍しくありません。
再発しても予後は良好
再発したからといって心配することはありません。再手術で腫瘍をきちんと取り切れば、治療は成功といえます。再発していない患者さんと、ほぼ同じ生存率が確保されます。
低危険度群の場合でも10%以下の確率で再発が見られるので、退院後は定期的に外来を受診していただき、再発の有無をチェックします。
術後の経過観察と定期検査
手術後1〜2年間は1〜3カ月ごと、手術後2〜3年間は半年ごとぐらいの通院が一般的です。
特に、乳頭がんや濾胞がんでは、10年あるいは20年たってから再発する可能性がありますので、長期の経過観察が必要になります。専門医の間では術後15年以上の経過観察が必要とする意見が大半を占めています。
なお、術後は1年から1年半に1回のペースで、超音波(エコー)検査と細胞診による定期検査を必ず受けるようにすることが重要です。
定期検査の内容
| 検査項目 | 目的 | 頻度 |
|---|---|---|
| 超音波(エコー)検査 | 局所再発、リンパ節転移の確認 | 定期的 |
| 血液検査(サイログロブリン等) | 再発マーカーの測定 | 定期的 |
| 胸部レントゲンまたは肺CT | 肺転移の確認 | 必要に応じて |
| 甲状腺ホルモン値測定 | ホルモン補充療法の調整 | 定期的 |
手術後の日常生活への影響
甲状腺ホルモン補充療法
甲状腺が半分以上残っていれば、多くの場合、治療を行う必要はありません。しかし、全摘術を行ったあとには、生涯にわたって、甲状腺ホルモン薬を飲むことにより甲状腺ホルモンを補います。
術後リハビリテーション
甲状腺がんの手術後には、早期に首のストレッチやマッサージを行うことで、首の周囲の違和感、ひきつれ、肩こりなどの症状の緩和に役立つといわれています。また、発声の練習で、特に高い声を出す練習を行うこともあります。
最新の甲状腺がん治療の進歩
微小がんの経過観察
1cm以下の無症候性の微小乳頭がんは、通常一生放置しても無害に経過することから、1995年以降、原則として手術を勧めず、十分な説明・同意のうえ経過観察する方針をとっています。
100名以上の微小がんの患者さんが外来で経過を見ていますが、がんが大きくなるのは10%以下です。
分子標的薬による治療
再発や転移した分化がんで放射線性ヨウ素内用療法が行えない場合は、分子標的薬を使った治療を検討することがあります。
合併症のリスクを最小化するための対策
現在、甲状腺がん手術の合併症を最小化するため、以下の対策が取られています:
1. 術中神経モニタリングの全症例への適用
2. 専門的な甲状腺外科医による手術
3. 術前・術後の詳細な評価
4. 低リスク症例での経過観察の選択肢
5. 最新の手術機器と技術の導入
低危険度乳頭がんの10年生存率は99%以上です。
参考文献・出典情報
- 甲状腺がん 治療|国立がん研究センター がん情報サービス
- 甲状腺がん|がん研有明病院
- 名古屋大学医学部附属病院 乳腺・内分泌外科
- 甲状腺手術の合併症|お茶の水甲状腺クリニック
- 甲状腺手術の合併症 (1)|野口病院
- 甲状腺手術後に発症した副甲状腺機能低下症の管理
- 声の障害を避けるための神経モニタリング|隈病院
- 甲状腺腫瘍診療ガイドライン2024 - Mindsガイドラインライブラリ
- 甲状腺がん 療養|国立がん研究センター がん情報サービス
- 7.いつまで外来通院が必要か?|日本臨床外科学会














