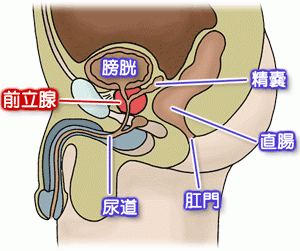
前立腺がん診断における基本的な検査の流れ
前立腺がんの診断は、段階的なアプローチで行われます。最初にPSA検査を行い、基準値を超えているときは直腸診を行います。これらの検査で前立腺がんが疑われる場合には、MRIを用いた画像検査を実施して確認し、最終的に経直腸エコーを用いた前立腺生検を行ってがんかどうかを診断します。
この流れは国際的に標準化されており、過剰診断を避けながら必要な患者さんを確実に発見するためのシステムとして確立されています。各段階の検査には明確な目的があり、患者さんの負担を最小限に抑えながら正確な診断を目指します。
PSA検査:前立腺がん診断の第一歩
PSA(前立腺特異抗原)検査は、前立腺がん診断における最も重要なスクリーニング検査です。PSAは前立腺でつくられるタンパク質の一種で、前立腺がんの腫瘍マーカーとして用いられています。がんや炎症により前立腺組織が壊れると、PSAが血液中にもれ出し、血液中のPSA量が増加します。
PSA検査の特徴と重要性
PSA検査は前立腺の異常に限って反応するため「前立腺特異抗原」と呼ばれています。この検査の最大の利点は、簡単な血液検査で実施できることです。PSA検査は、スクリーニング検査のひとつで、前立腺がんの可能性がある人を見つけるための検査です。
前立腺がんは初期段階では自覚症状がほとんどないため、PSA検査による早期発見が非常に重要です。自覚症状が出てから泌尿器科外来を受診し、発見される前立腺がんの約40%は他の臓器に転移しており、一方、PSA検査などの検診で発見された前立腺がんの約60%は早期のがんだったという研究結果があります。
PSA検査の基準値と年齢別推奨
PSAの値が高くなるにつれ、前立腺がんである確率も高くなっていきますが、年齢により基準値が設けられています。一般的には4ng/mLが基準値とされていますが、年齢や個人の状況により調整されることがあります。
日本泌尿器科学会の「前立腺がん検診ガイドライン」では、50歳を超えれば血液検査でPSAの値を測り、5年ごとを目安に定期的に検査を受けることを推奨しています。また、家族歴がある場合は、より早期からの検査が勧められています。
PSA値と前立腺がん発見確率の関係
PSA値は、前立腺がんの存在確率を示す重要な指標です。具体的には、PSA値が4~10ng/ml未満の人が針生検を受けると25~35%、10ng/ml~20ng/ml未満の人で30~45%、20ng/ml以上の人では50~80%の確率で前立腺がんが見つかるといわれています。
ただし、PSA値だけでがんの診断は確定できません。PSA値はあくまで前立腺がんを見つけるための道具であり、確定診断には後述する前立腺生検が必要です。
「自分の判断は正しいのか?」と不安な方へ

がん治療。
何を信じれば?
不安と恐怖で苦しい。
がん治療を左右するのは
治療法より“たった1つの条件”です。
まず、それを知ってください。
がん専門アドバイザー 本村ユウジ
前立腺がん以外でPSA値が上昇する要因
PSA値の上昇は前立腺がんだけが原因ではありません。様々な前立腺の異常でPSA値が上昇する可能性があります。これらの要因を理解することは、適切な診断プロセスを進める上で重要です。
前立腺肥大症による影響
前立腺肥大症は、前立腺が大きくなる良性の病気です。60歳代の男性の約半数、70歳を超えると70~80%の男性に認められるほど頻度の高い病気です。前立腺肥大症が悪化して前立腺がんになることはありませんが、合併していることはしばしばあります。
前立腺肥大症では、がんとは異なり、尿が出にくくなるや頻尿などの症状が見られることが特徴です。症状の有無は、前立腺がんとの鑑別診断において重要な情報となります。
前立腺炎による PSA上昇
急性・慢性前立腺炎が発症している場合もPSA値が上昇します。急性前立腺炎は高熱を伴うため気づきやすいのですが、慢性前立腺炎はほとんど自覚症状がありません。慢性前立腺炎は、病気自体の原因や概念もまだ十分に解明されていない部分があります。
医療処置による一時的な上昇
検査や治療によって前立腺が刺激されたときも、PSA値が一時的に高くなります。具体的には、針生検などの検査や手術、尿道からチューブを通して排尿できるようにする導尿、膀胱鏡検査の後も一時的に上昇します。
また、直腸診や前立腺マッサージなど、前立腺に物理的な力が加わったときにもPSA値が高くなることがあります。このような要因があるため、PSA値の解釈には慎重な判断が必要です。
PSA値の動的変化を重視した診断アプローチ
一回のPSA検査の結果だけで判断することは推奨されていません。前立腺がんの診断においては、PSA値の動的な変化を観察することが重要です。
PSA値の経時的変化の重要性
一般的には、一回のPSA検査の数値だけで判断せず、2~3カ月おきに数回PSA値を測定して、その動きを見た上で判断することになります。何らかの理由でたまたまPSA値が上がっていた時には、その後、数値が下がる傾向を示します。
PSA値が4ng/ml未満になった場合は、がんの心配はほとんどないといえるでしょう。これに対して、徐々にではあるが数値が上昇する、あるいは高かった数値がなかなか下がらず何回測っても似たような数値を示す場合は、がんが見つかる確率が高いといえます。
年間PSA上昇速度による評価
特に重要な指標として、1年間にPSA値が0.75ng/mlを超えて上昇する場合は、前立腺がんが見つかる危険性が高まるという報告があります。このような急激な上昇は、悪性腫瘍の存在を強く示唆する重要なサインです。
PSA値の読み方として、一回一回の値の高低のみではなく、連続的な変化として捉えることが重要です。一度PSA値が4ng/mlを超えたら、その後数回の測定を行い、がんの危険性を示すようであれば針生検を受けることが推奨されます。
直腸診による前立腺がんの診断
直腸診は、前立腺がん診断において重要な役割を果たします。直腸診は、医師が肛門から指を挿入して前立腺の状態を確認する検査です。前立腺の表面に凹凸があったり、左右非対称であったりした場合には前立腺がんを疑います。
直腸診の診断的価値
前立腺がんは体積が0.2mlを超えれば、がんのある場所によっては直腸診で検出が可能とされています。前立腺の背中側は直腸と接しているため、肛門から直腸に人さし指を入れると、腸壁越しに前立腺に触れることができます。
前立腺がんの一部のタイプには、PSA検査が無効であることがわかっています。直腸診は、このタイプのがんを見つけるのに役立ちます。特に自覚症状のない男性に直腸診を行った場合でも、0.1~4%の確率でがんが見つかるという統計もあります。
PSA検査と直腸診の併用効果
PSA値にかかわらず、この直腸診で「異常あり」とされた場合は、積極的に針生検が勧められます。PSA検査と直腸診の併用で、前立腺がんを見つける精度をより高められるといえます。
また、直腸診は前立腺がんが見つかった時には、そのがんが前立腺部にとどまっている(限局性)かどうかの判定、とどまっている場合はリスク分類を決めるためにも必要です。がんが明らかに前立腺の外まで広がっている場合は、手術や放射線治療の適応とならず、治療法は薬物療法のみになります。
MRI検査による画像診断の進歩
MRI検査は、磁気を使用して、体の内部をさまざまな方向の断面画像として映し出す検査です。がんの有無や場所の確認、がんが前立腺の外に広がっていないか、リンパ節などに転移がないかについて調べるために行います。
マルチパラメトリックMRIの導入
近年では、複数の画像を組み合わせて評価するMRI検査(mpMRI:マルチパラメトリックMRI)で生検の必要性を確認してから実施することもあります。この技術により、前立腺がんの検出精度が大幅に向上しています。
前立腺がんはこれまで「見えないがん」といわれ、どこにあるのか特定するのが難しい時代が続きました。それが2010年代に入り、MRIの進歩によって悪性度の高い前立腺がんの80~85%は見えるようになりました。
MRI検査のタイミングと注意点
生検の後にMRI検査を行う場合は、生検に伴う出血がMRIの診断能力を低下させるため、一定の間隔を空けてから行います。このため、多くの医療機関では生検前にMRI検査を実施することが推奨されています。
MRI検査は造影剤を使用することがあるため、アレルギー反応が起こることがあります。薬剤によるアレルギー反応を起こした経験のある方は必ず担当医に伝える必要があります。
前立腺生検:確定診断のための組織検査
前立腺がんの確定診断は、前立腺に針を刺して採取した組織を顕微鏡で調べる針生検によってのみ可能です。これ以外の確定診断方法はなく、これは世界共通の標準的な診断方法です。
従来の系統的生検
最近は系統的前立腺生検といって、前もって決めてある10-14箇所から針で組織を取る方法が一般的になっています。この方法では、前立腺全体を均等に区分し、各区分から組織を採取します。
従来は、事前に撮影したMRI画像を医師がイメージしながら、超音波の画像を見てがんが発生することが多い「辺縁域」といわれる場所に約12カ所針を刺す方法が主流でした。しかし、この方法は医師の記憶や経験に頼るところが大きく、針を正しい場所に刺せなければ、前立腺がんがあっても確定診断ができないという課題がありました。
最新のMRI融合標的生検
経直腸エコーの画像にMRI検査の画像を組み入れて、異常部位をねらって検査することもできるようになっています(MRI標的生検)。この技術は前立腺がん診断の精度を大幅に向上させています。
事前に撮影したMRI画像と生検時の超音波画像のズレを補正して融合。画像処理技術によりリアルタイムで超音波画像の上にMRIで見えた場所を指し示すことが可能になりました。
MRI融合生検の利点
MRI融合前立腺針生検では、1回目の生検で癌が確定することが多く、痛みや医療費負担を伴う複数回の生検を回避しやすくなります。また、生検を行った部位が3D画像で保存されるため、悪性の部位が3次元で明瞭となり、その後の手術の際に非常に参考になります。
さらに、一回目の生検で悪性が証明されなかった場合、2回目の生検の時に、1回目の生検部位の画像を融合することができ、生検部位が重複することなく、1回目と違った部位を生検することが可能になります。
前立腺生検の方法と実施方法
前立腺生検には、主に2つのアプローチ方法があります。それぞれに特徴があり、患者さんの状況や医療機関の方針により選択されます。
経直腸生検
直腸から針を刺入する方法で、麻酔なしでできる検査で、痛みもほとんどなく、外来でもできますが、まれに出血や発熱が起こることがあります。この方法は患者さんの負担が少なく、多くの医療機関で採用されています。
肛門から超音波を発する器具(プローブ)を挿入し、経直腸エコー(経直腸超音波検査)による画像を観察しながら、前立腺に細い針を刺して複数カ所の組織を採取します。
経会陰生検
会陰部(肛門と陰嚢の間の皮膚)から針を刺入する方法で、発熱の危険はほとんどありませんが、麻酔が必要となるため、一般的には2~3日入院して行います。この方法は感染のリスクが低いという利点があります。
針を進める経路として、肛門から直腸壁を経由して前立腺を穿刺する経直腸アプローチ、陰嚢付け根と肛門との間の皮膚(会陰部)を経由して前立腺を穿刺する経会陰アプローチとがあり、腫瘍の疑われる位置により、いずれかを選択あるいは両アプローチを同時に行います。
生検後の病理診断とリスク分類
採取した組織は病理検査により詳しく調べられ、がんの有無だけでなく、がんが見つかった場合はその悪性度も評価されます。この情報は治療方針の決定において極めて重要です。
病理診断の重要性
採取した組織を顕微鏡で観察し、がん細胞の有無を調べます。がんが発見された場合は、Gleasonスコアという国際的な基準によって悪性度が評価されます。このスコアは治療法の選択に直結する重要な情報です。
前立腺がんのリスク分類
がんであることが確定した後には、リスク分類が行われます。PSA値はその指標の一つで、PSA10ng/ml未満なら低リスクに入る可能性があり、10ng/ml以上20ng/ml未満なら中リスクまたは高リスク、20ng/ml以上なら高リスクと決定されます。
低リスクの可能性が残る、つまりPSA10ng/ml未満のうちに治療を開始できれば、手術であっても放射線療法であっても十分にがんを制御できるといえます。
診断後の追加検査
前立腺がんが確定診断された場合は、がんの進行度や転移の有無を調べるために追加の検査が行われます。
転移検索のための画像検査
がんの広がりや転移の有無は画像検査(全身MRI検査、CT検査、骨シンチグラフィなど)で調べます。これらの検査により、がんの進行度(ステージ)が決定され、最適な治療法が選択されます。
CT検査は、X線を使って体の内部の様子を画像に映し出す検査で、リンパ節や遠隔臓器への転移の有無を調べるために行います。骨シンチグラフィは、骨転移の有無を調べるための特殊な検査です。
継続的な経過観察
前立腺生検でがんが発見されなくても、PSA検査を継続的に実施して、PSA値が上昇したり高値が続いたりする場合には、再び生検を行うことがあります。これは、初回の生検でがんを見逃している可能性があるためです。
検査を受ける時期と頻度
前立腺がん検査を受ける適切な時期と頻度について、最新のガイドラインに基づいた推奨事項があります。
年齢別推奨事項
PSA基準値以下の進行がん(PSA陰性がん)を見逃さないためには、直腸内触診を。人間ドック受診の機会がある方、父、兄弟、子に前立腺がん患者がいる場合は、40歳からの定期検診を推奨されています。
一般的には50歳以上の男性に対してPSA検査が推奨されていますが、家族歴がある場合はより早期からの検査が重要です。「前立腺癌診療ガイドライン2016年版」では40-49歳の年齢層でも人間ドック等を契機にしたPSA検査を行うように推奨しています。
継続的な検査の重要性
PSA検査で異常がなくても小さい前立腺がんがかくれている可能性や、将来前立腺がんへと進んでいく可能性もあります。早期発見のために、一度PSA検査を受けて基準値以下だった方も、その値に応じて定期的に受けることが勧められています。
| 検査方法 | 侵襲性 | 精度 | 実施時期 | 主な目的 |
|---|---|---|---|---|
| PSA検査 | なし | スクリーニング | 50歳以上(家族歴あり40歳以上) | 前立腺異常の可能性評価 |
| 直腸診 | 軽度 | 中程度 | PSA高値時 | 前立腺の形状・硬さ評価 |
| MRI検査 | なし | 高 | 生検前 | がんの局在診断 |
| 系統的生検 | 中程度 | 中程度 | MRI異常なし時 | 組織学的確定診断 |
| MRI融合生検 | 中程度 | 高 | MRI異常あり時 | 標的組織の正確な採取 |
| CT検査 | 軽度 | 高 | がん確定後 | 転移検索 |
検査における注意点と副作用
前立腺がんの診断過程では、それぞれの検査に特有の注意点や副作用があります。これらを理解しておくことで、適切な準備と心構えができます。
PSA検査の注意点
PSA検査は基本的に副作用のない安全な検査ですが、前述したように様々な要因で値が変動する可能性があります。検査前には前立腺に刺激を与える行為(激しい運動、自転車乗車、射精など)を避けることが推奨されています。
MRI検査の制限事項
MRI検査は磁気を使用するため、体内に金属が入っている方は検査を受けられない場合があります。ペースメーカー、人工関節、歯科のインプラントなどがある場合は、事前に医師に相談する必要があります。
前立腺生検の合併症
前立腺生検には一定の合併症のリスクがあります。経直腸生検では出血や発熱、尿路感染症が起こる可能性があります。経会陰生検では感染のリスクは低いものの、麻酔に伴うリスクがあります。
これらの合併症は適切な予防策と術後管理により最小限に抑えることができ、多くの場合は軽度で自然に改善します。
将来の展望と新しい診断技術
前立腺がん診断の分野では、継続的な技術革新が進んでおり、より正確で低侵襲な診断方法の開発が進められています。これらの新技術により、将来的にはさらに精密で患者負担の少ない診断が可能になることが期待されています。
AI技術の活用
人工知能(AI)技術をMRI画像解析に応用することで、より客観的で正確な画像診断が可能になりつつあります。AIは人間の目では見落としやすい微細な変化も検出でき、診断精度の向上に大きく貢献することが期待されています。
新しいバイオマーカーの開発
PSA以外の新しい血液検査や尿検査によるバイオマーカーの研究が進んでいます。これらの新しいマーカーにより、より特異的で感度の高いスクリーニング検査が可能になる可能性があります。
低侵襲診断技術の進歩
将来的には、MRI融合生検の技術がさらに発展し、より少ない針刺しでより正確な診断が可能になることが期待されています。また、液体生検(リキッドバイオプシー)などの新技術により、血液検査だけでがんの診断が可能になる可能性も研究されています。
患者さんへのアドバイス
前立腺がんの早期発見と適切な診断のために、患者さんご自身にできることがあります。これらの点を理解し、実践することで、より良い医療を受けることができます。
定期的な検査の重要性
前立腺がんは初期症状がほとんどないため、定期的な検査による早期発見が極めて重要です。特に50歳以上の男性、または家族歴がある40歳以上の男性は、定期的なPSA検査を受けることを強く推奨します。
また、一度の検査で異常がなくても、継続的な検査により変化を捉えることができます。医師と相談して、個人のリスクに応じた適切な検査間隔を決めることが重要です。
症状の変化への注意
前立腺がんは初期には無症状ですが、進行すると排尿に関する症状が現れることがあります。尿が出にくい、頻尿、血尿、排尿時の痛みなどの症状が現れた場合は、早めに医療機関を受診することが重要です。
ただし、これらの症状は前立腺肥大症や前立腺炎などの良性疾患でも起こるため、症状があっても過度に心配する必要はありません。適切な検査により正確な診断を受けることが大切です。
医師との良好なコミュニケーション
検査の過程で不安や疑問が生じた場合は、遠慮せずに医師に相談することが重要です。検査の目的、方法、結果の意味について十分に理解することで、適切な医療判断ができます。
また、家族歴や既往歴、服用中の薬剤などの情報は診断に重要な影響を与えるため、正確に医師に伝えることが必要です。
検査費用と保険適用
前立腺がん診断のための各種検査の費用と保険適用について理解しておくことは、検査を受ける際の重要な情報です。
保険適用の検査
PSA検査、直腸診、MRI検査、前立腺生検はいずれも健康保険の適用となります。ただし、健康診断や人間ドックでのPSA検査は自費診療となる場合が多く、費用は医療機関により異なりますが、一般的には2,000円~5,000円程度です。
MRI融合生検の費用
MRI融合前立腺針生検は2022年から保険適応となったものの、特別な(やや高額な)エコー機器を必要とするため、いまだ限られた施設でしかその方法での生検を行っていません。実施できる医療機関は徐々に増加していますが、まだ全国的には普及していないのが現状です。
まとめ
前立腺がんの診断は、PSA検査から始まる段階的なアプローチにより行われます。各検査にはそれぞれ特徴と役割があり、組み合わせることでより正確な診断が可能になります。
最も重要なポイントは、早期発見のための定期的なスクリーニング検査の受診です。前立腺がんは早期に発見できれば治癒率の高いがんであり、PSA検査という簡単な血液検査で早期発見が可能です。
技術の進歩により、MRI融合生検などのより精密な診断方法も利用できるようになっており、不必要な検査や治療を避けながら、必要な患者さんを確実に発見し治療につなげることができるようになってきています。
50歳以上の男性(家族歴がある場合は40歳以上)は、定期的なPSA検査を受けることを強く推奨します。検査について不安や疑問がある場合は、遠慮せずに医師に相談し、個人のリスクに応じた最適な検査プランを相談することが重要です。
前立腺がんの診断技術は今後もさらに発展することが期待されており、より患者負担の少ない、正確な診断法の開発が進められています。



