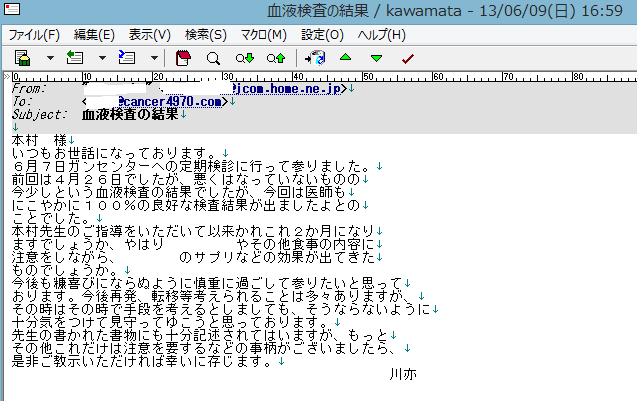がん専門のアドバイザー、本村です。
当記事では前立腺がんにおけるホルモン療法の副作用について解説します。
前立腺がんの治療において、ホルモン療法は中心的な存在になっているといえます。
早期がんでは「手術や放射線治療の補助療法として」使われることが多いですし、進行したり転移がある場合は薬物療法の第一歩としてホルモン療法が採用されます。

重用される最大の理由は「抗がん剤よりも副作用の影響が軽微で、それなりの効果があり、その効果が長期間持続する」ことにあります。
長期間使うことになる薬ですし、副作用がないわけではありません。この記事ではホルモン療法の作用や使われる薬ごとの副作用、その対策について触れたいと思います。
【サイト内 特設ページ】

がんを治すために必要なことは、たった1つです。
詳しくはこちらのページで。
→がんを治すための「たった1つの条件」とは?
ホルモン療法の効果
前立腺がんは男性ホルモン(テストステロン)によって増殖するという特徴があります。
ホルモン剤が登場する以前は睾丸(精巣)を取り除く=去勢することが前立腺がん治療の一環として行われていました(今でも実施されることがあります)。
ホルモン剤は男性ホルモンを抑える働きがあり、去勢したときとほぼ同様の効果を期待できます。
しかし男性ホルモンは、文字通り男性らしい体作りのために必要なものです。男性ホルモンを大幅に抑制することで起きる影響があります。それがホルモン療法の副作用になるといえます。
ホルモン療法の副作用とは
男性ホルモン(テストステロン)の数値が高い男性は、冒険心や野心が強く、リーダー気質を持つ傾向が高いとされています。同時に骨や筋肉が丈夫で体つきもしっかりしている人が多いそうです。
男性ホルモンは肉体的にも精神的にも「男性らしさ」の根源となっているため、このホルモンの産出が抑えられると筋肉量が減り脂肪が増え、今まで感じていた気持ちの張りや気力が衰える、ということが起ります。
身体的な症状としては骨密度の低下(骨粗しょう症)心筋梗塞や脳梗塞、高血圧やメタボ、記憶力や認知力の低下、性欲の低下などがあります。
前立腺がんの治療で使われるホルモン剤の作用と主な副作用の一覧は以下のとおりです。
【薬剤ごとの作用、投与法、主な副作用】
| 薬品名(薬剤名) | 分類 | 投与方法 | 主な副作用 |
| ゾラデックス(ゴセレリン) | LH-RHアゴニスト | 皮下注射 | フレアアップ現象(急激な分泌)、性機能障害、更年期障害のようなホットフラッシュ、骨粗しょう症 |
| リュープロレリン(リュープリン) | |||
| ゴナックス(テガレリクス) | GnRHアンタゴニスト | 性機能障害、更年期障害のようなホットフラッシュ、骨粗しょう症 | |
| カソデックス(ビカルタミド) | 抗男性ホルモン薬 | 経口 | 女性乳房化、乳房痛、肝機能障害 |
| オダイン(フルタミド) | |||
| イクスタンジ(エンザルタミド) | 疲労感、血小板減少、てんかん | ||
| ブロスタール(クロルマジノン) | 女性乳房化、乳房痛、性機能障害、脂質異常症(メタボ)、糖尿病悪化 | ||
| ザイティガ(アビラテロン) | CYP17阻害薬 | 高血圧、電解質異常、肝機能障害 |
上記のうち、エンザルタミド(イクスタンジ)とアビラテロン(ザイティガ)は「従来のホルモン剤の効果が薄れたときに使う二次的なホルモン剤」として近年(2014年)登場した薬です。
これらには従来のホルモン剤にはない特徴的な副作用があります。
エンザルタミド(イクスタンジ)の副作用
脳に影響することがあり、稀ですが神経に関する障害(癲癇(てんかん)、意識低下、けいれん)を起こすことがあります。これらの症状を投薬以前に経験したことがある人には注意が必要です。
その他、血液系の副作用も報告されています。具体的には血小板減少による「血が止まりにくい」ことや鼻血、血尿などです。
アビラテロン(ザイティガ)の副作用
心臓、肝臓に関する副作用が起きることがあります。心臓関連としては心不全や不整脈、動悸などです。心臓の既往症がある人には注意が必要です。肝臓関連としては肝機能障害です。自覚症状としてはかゆみ、黄疸、食欲不振、吐き気などがあります。肝機能が低下している人へは慎重な投与が必要になります。
このように従来のホルモン剤ではあまり影響がなかった人も、イクスンタンジやザイディガを使う場合は過去の既往症などを振り返り、医師に報告、相談したうえで慎重に投与を決めましょう。
【サイト内 特設ページ】

がんを治すために必要なことは、たった1つです。
詳しくはこちらのページで。
→がんを治すための「たった1つの条件」とは?
起きやすい副作用とその対策
投与を開始して間もなく起こりやすいのはホットフラッシュ(ほてり、発汗、のぼせ)です。女性の更年期障害の1つとして起こりやすいものですが、男性ホルモン減少により男性にも起きやすくなります。
全身がカーっと熱くなったと思えば直後に寒くなったりします。
ほてりやのぼせのような症状を感じたときは、額や首筋を少し冷やしましょう。また、夏でも一枚羽織るものを持ち歩くなど、急激な体感温度の変化に対応できるようにしておきましょう。
骨密度の低下による骨粗しょう症に関しては、投与後1~2か月後に現れてくることが多いです。医療的な対処としてはプラリアなどの薬を注射するなどの対策があります。カルシウムや亜鉛などのミネラル類をバランスよく摂取することも大切です。
その他には、脂肪が増える、倦怠感、性欲減退、認知力の低下、糖尿病の傾向が出てくる、などの問題が時間の経過とともに起きやすくなりますが、これらに関しては医療的な対策はないため対策としては具体的なものがありません。
重い症状になったときは、投薬の期間を空ける、いったん休薬するなどの対応を検討することになります。
投薬を休む=間欠療法とは
対策のしようがない副作用に関しては、「数週間から数か月、投薬を休止する」という対策を検討することになります。これを前立腺がんのホルモン療法においては「間欠療法」といいます。
いつ、どのタイミングで休薬するのか?はケースバイケースですが、主に「薬が効いてPSA値が落ち着いているが、副作用が顕著に現れている」ような場合に休薬して様子をみることが多いです。
「休薬することで治療効果が弱くなるのでは?」と考える人もいれば、「薬が耐性を獲得するまでの期間を延ばせるので間欠療法のほうがよい」と言う人もいます。
これに関しては具体的なエビデンスがないため、なんともいえません。副作用が厳しいと感じるときはいったん休薬する、というスタンスでよいと思います。
前立腺がんのガイドラインに記載されているホルモン療法副作用の解説
ガイドラインの2016年版には、ホルモン療法実施時の有害事象について記載があります。これを確認することでより具体的に、詳細に副作用を知ることができます。
第一に挙げられているのが「骨塩量の低下、骨折リスクの上昇」です。
12か月間で骨密度は2~5%減少し、骨折のリスクは1.5~1.8倍になる、と記載されています。対応としては経口ビスホスホネート製剤や抗RANKL薬(プラリアなど)を使用することでリスクを低下できるとしています。
その他、以下の内容が記載されています。
・性欲低下、勃起不全
ホルモン療法を受ける患者の9割以上に発症し「6か月間のホルモン療法は18か月間の実施と比べて性機能に対する影響は明らかに少ないことが報告されている」と記載されています。長期よりも短期の投薬のほうが影響が少ない、ということですがこれは当然のことといえます。
・ホットフラッシュ
ホットフラッシュは8割ほどの患者に発症し「シプロテロン、メドロキシプロゲステロン、低用量ガバペンチンの有用性が報告されている」としています。なお「シプロテロンについては治療に影響を与える可能性がある」とも記載されています。
シプロテロンは抗アンドロゲン薬。メドロキシプロゲステロンは女性ホルモンの働きを制御することでこれらの症状を改善させるホルモン薬です。ガバペンチンは抗てんかん薬です。しかしこれらの薬は前立腺がんやホットフラッシュへの保険適用はありません。
・疲労
約4割でみられ、その原因は男性ホルモン低下による筋肉量の低下、体脂肪の増加に加え、自律神経への影響による「うつ」などが原因とされています。
「有酸素運動やレジスタンス運動(ストレッチ、腹筋、腕立て伏せなど)」が効果があるとしていますが、疲労を感じているときにこれらの運動が積極的に、能動的にできるかどうかは難しい問題だといえます。
・女性乳房化
女性の乳房のように膨らみを持つことがあります。これはガイドラインでは約2割の人に起きるとしています。特に抗アンドロゲン薬単独療法では6~7割で起こると報告しています。
対応としては抗エストロゲン薬のノルバデックスの投与、乳房への放射線照射に効果が見られると掲載されていますが、ノルバデックスの使用は保険外ですし、薬に薬を重ねたり、放射線を当てるというのは対策としてあまり良いものだとはいえません。
以上、前立腺がんホルモン療法の副作用についての解説でした。