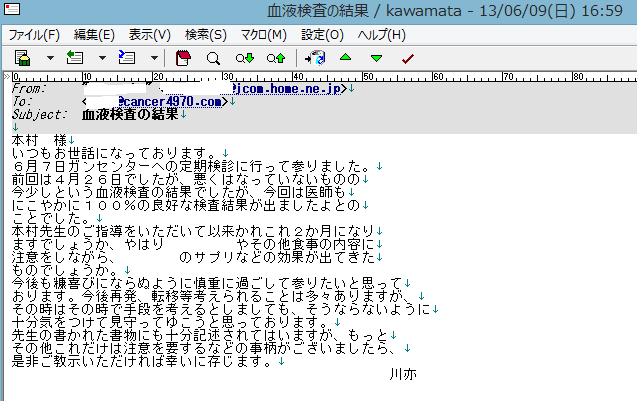前立腺がんの診断を受けた患者さんにとって、グリソンスコアという用語は治療方針を決定する上で重要な指標です。この記事では、がん専門アドバイザーの本村ユウジが、グリソンスコアの意味から数値ごとのリスク分類まで、最新の医学的知見に基づいて分かりやすく解説します。
【サイト内 特設ページ】

こんにちは。17年間の活動実績を持つ、
「プロのがん治療専門アドバイザー」本村ユウジです。
がんを治すために必要なことは、たった1つです。
詳しくはこちらのページでお伝えさせてください。
→がんを治すための「たった1つの条件」とは?
グリソンスコアとは何か?
グリソンスコアは、前立腺がんの悪性度を表す病理学的な分類システムです。アメリカの病理学者ドナルド・グリソン先生が開発したこのスコアは、前立腺がん細胞の形態を観察し、がんの悪性度を数値化したものです。現在でも世界中の医療機関で使用されており、前立腺がん診療において最も重要な指標の一つとなっています。
グリソンスコアの特徴は、前立腺がんの複雑な性質を反映していることです。前立腺がんは一つの前立腺の中でも悪性度の異なる複数のがん細胞が混在しており、これらを総合的に評価する必要があります。このため、グリソンスコアでは最も多くの面積を占める組織像(第一パターン)と2番目に多い組織像(第二パターン)を組み合わせて評価します。
グリソンスコアの評価方法と分化度
グリソンスコアの評価は、顕微鏡で前立腺がん細胞の構造パターンを観察することから始まります。正常な前立腺細胞の構造に近いパターンをグレード1、最も悪性度の高いパターンをグレード5として、がん細胞全体を5段階で評価します。ただし、現在の診断では最低がグレード3からとなっており、実際にはグレード3から5の範囲で評価されています。
分化度による分類は以下のようになっています:
- 高分化がん:正常細胞に近い形態を保持しており、増殖が比較的ゆっくり
- 中分化がん:正常細胞と低分化がんの中間的な特徴
- 低分化がん:正常細胞とはかけ離れた形態で、増殖が早く転移しやすい
グリソンスコアは、第一パターンと第二パターンの数値を合計して算出されます。例えば、最も多い組織がグレード3で、2番目に多い組織がグレード4の場合、グリソンスコアは「3+4=7」となります。同じパターンのみが見られる場合は、同じ数値を2回足して表記します(例:3+3=6)。
【サイト内 特設ページ】

こんにちは。17年間の活動実績を持つ、
「プロのがん治療専門アドバイザー」本村ユウジです。
がんを治すために必要なことは、たった1つです。
詳しくはこちらのページでお伝えさせてください。
→がんを治すための「たった1つの条件」とは?
グリソンスコア別のリスク分類
グリソンスコアによるリスク分類は、前立腺がんの治療方針を決定する際の重要な指標です。現在の医学的基準では、以下のように分類されています:
低リスク群(グリソンスコア6以下)
グリソンスコア6以下は高分化型の前立腺がんに該当し、比較的進行の遅い「おとなしい」がんとされています。このグループの患者さんでは、がん細胞の増殖が緩やかで、転移や再発のリスクが低いことが知られています。治療後の再発率も最も低く、予後良好とされています。
このリスク群では、すぐに積極的な治療を行わず、定期的な経過観察(PSA監視療法)を選択する場合もあります。特に高齢の患者さんや他の重篤な疾患をお持ちの場合、治療による副作用リスクとがんによるリスクを天秤にかけて判断されます。
中リスク群(グリソンスコア7)
グリソンスコア7は中等度の悪性度を示し、さらに詳細に「3+4=7」と「4+3=7」に分けて評価されます。同じスコア7でも、主要パターンが3か4かによって予後が異なるためです。「3+4=7」の方が「4+3=7」よりも予後が良好とされています。
中リスク群では、手術療法、放射線療法、ホルモン療法などの積極的な治療が検討されます。患者さんの年齢、全身状態、生活の質への影響などを総合的に考慮して治療方針が決定されます。
高リスク群(グリソンスコア8以上)
グリソンスコア8以上は低分化型の前立腺がんに該当し、悪性度の高いがんとして分類されます。このグループでは、がん細胞の増殖が早く、転移や再発のリスクが高くなります。予期せぬ被膜外浸潤、リンパ節転移、微小遠隔転移が潜んでいる確率も高く、予後は他のリスク群と比較して芳しくないとされています。
高リスク群では、複数の治療法を組み合わせた集学的治療が必要となることが多く、手術療法と放射線療法の併用、ホルモン療法の追加などが検討されます。
Grade Groupによる新しい分類システム
2015年の国際泌尿器病理学会(ISUP)では、より理解しやすい分類として「Grade Group(グレードグループ)」が導入されました。これは従来のグリソンスコアを1から5の段階に整理したもので、患者さんにとってより分かりやすい表記となっています:
| Grade Group | 対応するグリソンスコア | 悪性度 |
|---|---|---|
| Grade Group 1 | 3+3=6以下 | 低悪性度 |
| Grade Group 2 | 3+4=7 | 中悪性度(低め) |
| Grade Group 3 | 4+3=7 | 中悪性度(高め) |
| Grade Group 4 | 4+4=8 | 高悪性度 |
| Grade Group 5 | 4+5, 5+4, 5+5=9-10 | 最高悪性度 |
この新しい分類システムにより、患者さんやご家族にとってがんの悪性度がより理解しやすくなりました。現在では多くの医療機関でこのGrade Group分類も併記されるようになっています。
【サイト内 特設ページ】

こんにちは。17年間の活動実績を持つ、
「プロのがん治療専門アドバイザー」本村ユウジです。
がんを治すために必要なことは、たった1つです。
詳しくはこちらのページでお伝えさせてください。
→がんを治すための「たった1つの条件」とは?
リスク分類における他の重要な因子
前立腺がんの総合的なリスク評価では、グリソンスコアだけでなく、PSA値とTNM分類(がんの進展度)も重要な要素となります。これら3つの因子を組み合わせて、低リスク、中リスク、高リスクの3段階に分類します。
低リスク群の条件
- PSA値:10ng/ml未満
- グリソンスコア:6以下
- T分類:T1またはT2a
これら3つの条件をすべて満たす場合に低リスクと判定されます。
高リスク群の条件
- PSA値:20ng/mlを超える
- グリソンスコア:8~10
- T分類:T3~T4
これらの条件のうち、どれか1つでも当てはまれば高リスクと判定されます。
中リスク群
低リスクにも高リスクにも当てはまらない場合が中リスクに分類されます。
グリソンスコアの限界と注意点
グリソンスコアは非常に有用な指標ですが、いくつかの限界があることも理解しておく必要があります。まず、顕微鏡視野や観察者の主観に左右される面があり、絶対的な物差しは存在しません。このため、セカンドオピニオンを求める際には、プレパラート(病理標本)の持参が推奨されることがあります。
また、同じグリソンスコアでも、PSA値や病期によって予後が異なることもあります。例えば、グリソンスコア「3+4=7」の患者さんでも、PSA値が低い方と高い方では再発率に違いが見られます。このため、グリソンスコアは他の因子と組み合わせて総合的に評価することが重要です。
治療選択への影響
グリソンスコアは治療方針の決定に直接的な影響を与えます。低リスク群では経過観察が選択される場合もありますが、高リスク群では積極的な根治治療が推奨されます。
具体的な治療選択肢としては、手術療法(前立腺全摘除術)、放射線療法(外照射療法、小線源療法)、ホルモン療法、さらに最近では局所療法(フォーカルセラピー)なども検討されます。患者さんの年齢、全身状態、生活の質への配慮、個人の価値観なども含めて、最適な治療法を選択していきます。
最新の動向と今後の展望
前立腺がん診療は急速に進歩しており、2023年には最新の「前立腺癌診療ガイドライン 2023年版」が刊行されました。また、「泌尿器科・病理・放射線科 前立腺癌取扱い規約 第5版」も2022年に改訂され、最新の医学的知見が反映されています。
診断技術の進歩により、MRIを用いた画像診断の精度が向上し、より正確な生検が可能になっています。また、遺伝子検査やゲノム医療の発展により、個々の患者さんに最適化された治療選択が可能になりつつあります。
現在の日本では、前立腺がんは男性のがん罹患数第1位となっており、約9人に1人の男性が生涯のうちに前立腺がんにかかると推定されています。高齢化社会の進行とともに、今後もその重要性は増していくと考えられます。
まとめ
グリソンスコアの結果を聞いた時、多くの患者さんが不安を感じられるのは当然のことです。しかし、前立腺がんは比較的ゆっくり進行するがんであり、適切な治療により良好な予後が期待できるがんでもあります。
重要なのは、担当医師とよく相談し、グリソンスコアだけでなく、他の検査結果や全身状態を総合的に評価してもらうことです。治療選択においては、医学的な観点だけでなく、患者さんのライフスタイルや価値観も重要な要素となります。
また、定期的なフォローアップを継続し、病状の変化に応じて治療方針を調整していくことも大切です。前立腺がんの診断を受けた際は、焦らず、十分な情報収集と検討を行いましょう。
参考文献・出典情報
本記事は以下の信頼できる医学的情報源に基づいて作成されています:
- 国立がん研究センター がん情報サービス「前立腺がん」
- 日本泌尿器科学会 前立腺癌診療ガイドライン 2023年版
- 日本泌尿器科学会・日本病理学会・日本医学放射線学会編「泌尿器科・病理・放射線科 前立腺癌取扱い規約 第5版」
- がんプラス「前立腺がんのステージ診断と推奨される治療法」
- 国立がん研究センター がん統計「前立腺がん統計情報」
- 国立がん研究センター東病院 泌尿器・後腹膜腫瘍科「前立腺がん」
- 大阪国際がんセンター「前立腺がん」
- 東京国際大堀病院 泌尿器科「前立腺がんの病期診断・リスク分類」
- ブラキ・サポート「前立腺がん診断(PSA、グリソンスコアなど)」
- Mindsガイドラインライブラリ「前立腺癌診療ガイドライン 2023年版」