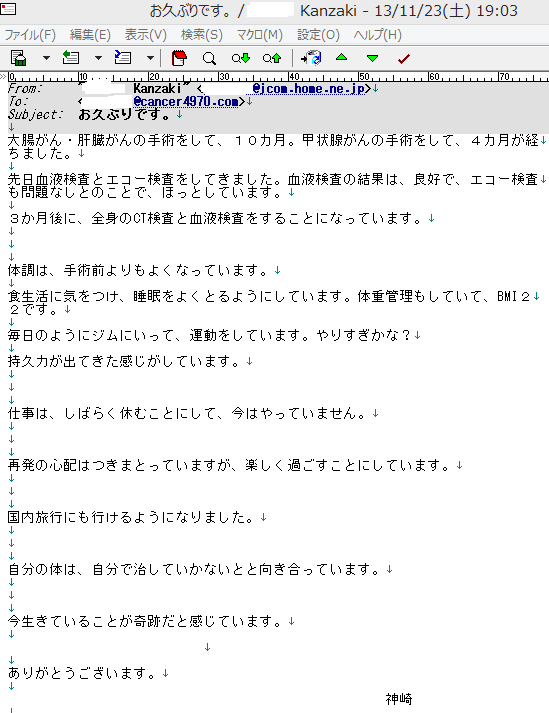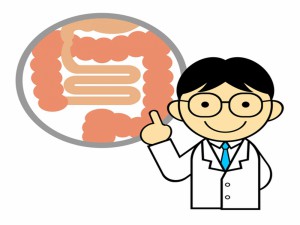
大腸がんの初期症状と進行症状の特徴
大腸がんは日本人に最も多いがんの一つで、2022年の統計では年間約5万3,088人が大腸がんで亡くなっています。大腸がんの大きな特徴は、早期段階では症状がほとんど現れないことです。
早期の大腸がんの症状
早期の段階では自覚症状はほとんどありませんが、がんが進行するにつれて以下のような症状が現れるようになります。
最初に現れる症状として最も多いのが「潜血」です。これは肉眼では確認できないほど微量の出血で、がんの表面が少しずつ崩れることで起こります。この段階では患者さん自身が出血に気づくことは困難ですが、便潜血検査という特別な検査によって発見することができます。
進行した大腸がんの症状
進行すると、便に血が混じる(血便や下血)、便の表面に血液が付着するなどの症状があらわれます。がんの発生場所により症状に違いがあります。
| 発生部位 | 主な症状 | 特徴 |
|---|---|---|
| 肛門に近い部位(直腸・S状結腸) | 赤い血便、便の狭小化、残便感 | 硬い便が通るため症状が出やすい |
| 上部大腸(盲腸・上行結腸) | 貧血、腹部のしこり、黒色便 | 便が軟らかいため症状が出にくい |
さらに進行すると、腸閉塞による腹痛、腹部膨満感、便秘と下痢の繰り返し、食欲不振、体重減少などの症状が現れます。腫瘍が大きくなり腸管の内腔が狭くなると腹痛、腹部膨満感、嘔気、嘔吐などの症状が出現します。
大腸がん診断方法の最新情報
大腸がんの診断は複数の検査を組み合わせて行われます。2025年現在、診断技術は大幅に進歩しており、AI技術を活用した最新の診断方法も実用化されています。
便潜血検査(スクリーニング検査)
便潜血検査は大腸がん検診の第一段階として実施される最も重要な検査です。便潜血検査免疫法を毎年受診することで大腸がん死亡が60%減ることが報告されています。
検査の精度と結果の解釈
便潜血検査免疫法の感度は、対象とした病変の進行度や算出方法によってかなりの差があり、30.0~92.9%でした。便潜血陽性の方から大腸ポリープが見つかる確率が、50%前後と言われています。大腸がんが見つかる確率は2~3%程度です。
受診者1000人中の約50人が陽性になり、その50人のうち1~2人が大腸がんであると報告されています。1回でも陽性になった場合は必ず精密検査を受ける必要があります。
大腸内視鏡検査(精密検査)
便潜血検査で陽性となった場合、最も精度の高い精密検査として大腸内視鏡検査が推奨されます。全大腸内視鏡検査の感度は95%以上であり、便潜血検査やS状結腸内視鏡検査の感度よりも高いことが確認されています。
AI技術を活用した最新の内視鏡診断
2025年現在、AI技術を活用した診断支援システムが実用化されています。国立がん研究センターと日本電気(NEC)が共同開発したAI診断支援システムは、大腸がんとポリープを内視鏡検査時に即時に発見するシステムとして承認されています。
比較的判断しやすい隆起型の病変では約95%、判断しにくい表面型でも約78%を正しく検出する性能を示しており、経験豊富な内視鏡医と同程度の診断性能があることが証明されています。
その他の診断検査
直腸指診
医師が指を肛門から挿入し、直腸内のしこりや異常の有無を確認する検査です。直腸がんの場合、この検査でほぼ診断がつくことがあります。
注腸二重造影X線検査
肛門から造影剤(バリウム)と空気を注入し、X線撮影で異常な影を調べる検査です。大腸内視鏡検査と比較すると精度は劣りますが、内視鏡検査が困難な場合の代替検査として使用されます。
腫瘍マーカー検査
大腸がんでは血液検査で腫瘍マーカー(CEA、CA19-9)を測定します。これらのマーカーの基準値と特徴は以下の通りです:
| マーカー名 | 基準値 | 大腸がんでの陽性率 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| CEA | 5.0ng/mL以下 | 30-40% | 進行した乳がんでは50-60%で上昇 |
| CA19-9 | 37.0U/mL以下 | 30-50% | 膵臓がんでは70-90%の陽性率 |
がんかどうかは、腫瘍マーカーの値だけでは診断できません。これらの検査は診断の補助や治療効果の判定、再発の早期発見に主に使用されます。
画像診断(CT・MRI・超音波検査)
がんの広がりや転移の有無を調べるために実施されます。特に肝臓や肺への転移、リンパ節転移の評価に重要な役割を果たします。
早期発見の重要性と対策
定期検診の重要性
便潜血検査を定期的に受診し、陽性になった場合には必ず精密検査を受けることで、大腸がんによる死亡がさらに減少すると考えられます。
台湾では、2004年に便潜血検査免疫法による大腸がん検診を導入し、40%の大腸がん死亡抑制が達成されたことが報告されており、検診の有効性が国際的に証明されています。
注意すべき症状の変化
以下のような症状がある場合は、痔などの良性疾患と自己判断せず、必ず医療機関を受診することが重要です:
- これまで便秘になったことがない人が急に便秘になった場合
- 血便や便に血液が付着する場合
- 便が細くなった場合
- 残便感が続く場合
- 原因不明の貧血
- 腹痛や腹部膨満感
痔との関係について
痔核(いぼ痔)と切れ痔はがんと直接関係がないとされていますが、痔瘻については10~20年経過すると稀にがんになる可能性があります。ただし、痔などの良性の病気でも起こりますが、自己判断せず、症状に気が付いたら早めに消化器科、胃腸科、肛門科などの身近な医療機関を受診しましょう。
進行した直腸がん患者さんの過半数は、初期の出血を痔からのものと誤解し、発見が遅れるケースが多いことが問題となっています。
大腸がん検診の受診方法と費用
検診の種類と費用
| 検診の種類 | 費用 | 対象年齢 | 実施頻度 |
|---|---|---|---|
| 市区町村検診 | 無料~1,000円程度 | 40歳以上(自治体により異なる) | 年1回 |
| 職場検診 | 無料~1,000円程度 | 企業規定による | 年1回 |
| 人間ドック | 1,000~2,000円程度 | 制限なし | 任意 |
最新の検診技術の展望
国立がん研究センターでは、人工知能によるコンピュータ検出支援を用いた大腸内視鏡検査の有効性を評価するアジア多施設共同臨床試験が進行中です。これにより、将来的には更に精度の高い検診が可能になると期待されています。
まとめ
大腸がんは早期発見により高い治癒率が期待できるがんです。検診で早期に発見して治療することにより、大腸がんで亡くなることを防ぐことができます。無症状のうちから定期的な検診を受け、便潜血検査で陽性となった場合は必ず精密検査を受けることが重要です。
最新のAI技術を活用した診断支援システムの導入により、今後さらに精度の高い診断が可能になることが期待されています。40歳を過ぎたら年1回の大腸がん検診を欠かさず受診し、早期発見・早期治療に努めましょう。
参考文献・出典情報
- 国立がん研究センター がん情報サービス「大腸がん(結腸がん・直腸がん)」
- 国立がん研究センター がん情報サービス「大腸がん(結腸がん・直腸がん)について」
- 日本生活習慣病予防協会「大腸がんによる年間死亡者数は、5万3,088人」
- 国立がん研究センター中央病院「大腸がんの症状について」
- 国立がん研究センター「大腸がんファクトシート 2024」
- 国立がん研究センター がん情報サービス「大腸がん(結腸がん・直腸がん) 治療」
- 日本対がん協会「3月は大腸がんの啓発月間です」
- 国立がん研究センター がん情報サービス「大腸がん検診」
- 国立がん研究センター「科学的根拠に基づくわが国の大腸がん検診を提言」
- 国立がん研究センター がん情報サービス「腫瘍マーカー検査とは」