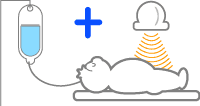
化学放射線療法とは何か
こんにちは。がん治療専門アドバイザー、本村ユウジです。
化学放射線療法は、放射線治療と抗がん剤治療を組み合わせて行うがん治療法です。それぞれの治療法が持つ効果を同時に活かすことで、より高い治療効果を目指します。
放射線治療は、がん細胞にX線などの放射線を照射して細胞を破壊する治療法です。手術と異なり、臓器を切除せずに治療できるため、体への負担が少なく、臓器の機能や形を保ちながらがんを治療できます。
一方、抗がん剤治療は薬剤を用いてがん細胞の増殖を抑える治療法です。血液を通じて全身に作用するため、目に見えない小さながん細胞や、遠隔転移の可能性がある病変にも効果を発揮します。
これら2つの治療法を組み合わせる化学放射線療法には、主に2つの目的があります。1つ目は、抗がん剤が放射線の効果を高める「放射線増感作用」により、局所のがんに対する治療効果を向上させることです。2つ目は、放射線が届かない範囲に広がった微小な転移を抗がん剤で制御することです。
2025年の研究では、食道がんに対する化学放射線療法と免疫チェックポイント阻害薬の併用により、完全奏効率が従来の15~20%から42.1%まで向上したことが報告されています。また、肺がんや子宮頸がんでも、化学放射線療法に免疫療法を上乗せすることで、さらなる治療成績の向上が得られることが明らかになっています。
化学放射線療法を同時に行う併用方法
化学放射線療法には、いくつかの併用方法があります。治療の時期によって、次のように分類されます。
導入化学療法は、放射線治療を始める前に抗がん剤治療を行う方法です。がんを事前に縮小させてから放射線治療を行うことで、治療効果を高めることを目指します。
補助化学療法は、放射線治療の後に抗がん剤治療を追加する方法です。放射線治療で残った可能性のあるがん細胞や、遠隔転移のリスクを減らすために実施されます。
同時併用化学療法は、放射線治療と抗がん剤治療を同じ時期に行う方法です。現在、多くのがん種で標準治療として採用されている方法で、放射線と抗がん剤の相乗効果が最も期待できます。ただし、副作用も強くなる可能性があるため、患者さんの全身状態を慎重に評価して適応を決定します。
交互併用は、放射線治療と抗がん剤治療を交互に行う方法です。それぞれの治療を分けて行うことで、副作用を軽減しながら治療を継続できる利点があります。
2026年現在、局所進行がんに対しては同時併用化学療法が最も多く用いられています。放射線腫瘍医と腫瘍内科医が連携して、患者さんの病状や体力、がんの種類に応じて最適な併用方法を選択します。
化学放射線療法が適応となるがんの種類
化学放射線療法は、多くのがん種において有効性が確立されています。主な適応となるがんとその治療状況をご紹介します。
食道がんにおける化学放射線療法
食道がんは、化学放射線療法が最も効果を発揮するがんの1つです。食道の手術は、のど、腹部、背中を大きく切開し、食道を切除した後に胃を引き上げてつなぐため、8時間以上かかる大手術です。頸部から腹部までのリンパ節も切除するため、出血量も多く、手術後の生活の質が低下する可能性があります。
このような状況で、化学放射線療法は手術を避けて治療できる選択肢として重要です。遠隔転移のない局所進行食道がんでは、化学放射線療法が標準治療となっています。一般的には、シスプラチンと5-FUという抗がん剤を使用し、放射線治療と同時に行います。治療期間は通常6週間程度で、1回2グレイを30回、計60グレイを照射します。
2025年の国立がん研究センターの研究では、化学放射線療法後に免疫チェックポイント阻害薬アテゾリズマブを追加投与することで、完全奏効率が42.1%に達し、1年生存率も65.8%と良好な結果が報告されました。従来の化学放射線療法単独の完全奏効率15~20%と比較して、治療成績が向上しています。
食道がんに対する化学放射線療法では、強度変調放射線治療やIMRTなどの高精度放射線治療技術を用いることで、心臓や肺などの周囲臓器への放射線の影響を最小限に抑えながら、がん病巣に十分な線量を投与できるようになっています。
頭頸部がんにおける化学放射線療法
鼻、口、舌、咽頭、喉頭などの頭頸部のがんでも、化学放射線療法が重要な治療選択肢です。これらの部位の手術を受けると、顔の外観が変わったり、発声機能が失われたりする可能性があります。再建手術を行っても、元の状態に完全に戻すことは困難です。
頭頸部のがんは放射線が効きやすい特性があり、咽頭がんや喉頭がんでは、進行度によって化学放射線療法が標準治療となります。一般的には、シスプラチンと5-FUという抗がん剤に加えて、ドセタキセルを併用すると効果が高まると報告されています。
2025年のASCO学会では、高リスクの頭頸部扁平上皮がんに対して、術後の化学放射線療法にニボルマブを追加することで、20年ぶりに新たな標準治療が確立される可能性が示されました。
肺がんにおける化学放射線療法
肺がんのうち、手術できない局所進行非小細胞肺がんに対しては、化学放射線療法が標準治療です。2025年5月、EGFR遺伝子変異陽性の切除不能なステージIIIの非小細胞肺がんに対して、根治的化学放射線療法後にオシメルチニブを維持療法として使用することが厚生労働省より承認されました。これは、EGFR遺伝子変異陽性の切除不能なステージIII非小細胞肺がんに対する分子標的薬として、日本で初めての承認です。
肺がんの化学放射線療法では、シスプラチンやカルボプラチンといったプラチナ製剤と、エトポシドやペメトレキセドなどの抗がん剤を組み合わせて使用します。放射線治療では、正常な肺組織や食道、心臓への影響を最小限に抑えるため、画像誘導放射線治療やIMRTなどの高精度技術が用いられます。
子宮頸がんにおける化学放射線療法
子宮頸がんでは、ステージIB期の腫瘍径が4cm以上の場合や、ステージII期以降の局所進行がんに対して、化学放射線療法が標準治療です。プラチナ製剤であるシスプラチンやネダプラチンを使用し、全骨盤への外部照射と腔内照射を組み合わせます。
治療は通常7~8週間程度で、外部照射を25~28回、腔内照射を3~5回実施します。骨盤の外から照射する外部照射では、50~50.4グレイを照射し、腔内照射では子宮や膣に専用の器具を挿入して、病変の近くに集中的に放射線を当てます。
2026年現在、子宮頸がんの化学放射線療法では、患者さんの全身状態が良好であれば、外来での治療も可能です。化学療法と放射線療法を組み合わせることで、放射線の効果を高めるとともに、遠隔転移のリスクを減らすことができます。
その他のがんにおける化学放射線療法
膵臓がんでは、切除不能な局所進行例に対して化学放射線療法が行われます。ゲムシタビンという抗がん剤を使用し、場合によっては手術中に放射線を照射する術中照射も実施されます。
直腸がんや肛門管がんでは、術前に化学放射線療法を行うことで腫瘍を縮小させ、人工肛門を避けられる可能性が高まります。また、膀胱がんでも、膀胱を温存しながら治療するために化学放射線療法が選択されることがあります。
化学放射線療法の目的と効果
化学放射線療法を行う主な目的は、治療効果を最大化することです。放射線治療と抗がん剤治療それぞれの利点を組み合わせることで、単独で行うよりも高い治療成績が期待できます。
放射線増感作用は、化学放射線療法の重要な効果の1つです。一部の抗がん剤は、がん細胞を放射線に対して敏感にする働きがあります。これにより、同じ線量の放射線でも、より多くのがん細胞を破壊できます。シスプラチンや5-FUといった薬剤は、この放射線増感作用が強いことで知られています。
遠隔転移の制御も重要な目的です。放射線治療は局所の治療であり、照射した範囲以外のがん細胞には効果がありません。しかし、抗がん剤は血液を通じて全身に作用するため、画像検査では確認できない微小な転移や、将来転移する可能性のあるがん細胞を抑制できます。
再発予防の観点からも、化学放射線療法は有効です。放射線治療でがんを縮小または消失させた後も、抗がん剤を継続することで、再発のリスクを低減できます。
治療成績について、多くの研究が放射線単独治療と化学放射線療法を比較しています。食道がんでは、放射線単独治療と比較して化学放射線療法の方が生存率が高いことが示されており、臨床試験が途中で中止されて化学放射線療法のみで継続されたこともあります。
化学放射線療法のメリット
化学放射線療法には、患者さんにとって多くのメリットがあります。
臓器温存が可能なことは、大きな利点です。手術では臓器を切除する必要がありますが、化学放射線療法では臓器を残したまま治療できます。食道がんや喉頭がん、膀胱がんなど、切除すると生活の質が低下するがんでは、この利点は特に重要です。
体への負担が少ないことも重要なメリットです。手術のように麻酔や出血のリスクがなく、高齢の方や持病がある方でも治療を受けられる可能性が高まります。放射線治療は基本的に外来で行えるため、入院期間も短縮できます。
治療効果の向上は、化学放射線療法の最大のメリットです。単独治療よりも高い完全奏効率や生存率が報告されており、多くのがん種で標準治療として確立されています。
QOLの維持も大切な利点です。臓器を温存できることで、治療前と同等の生活を送れる可能性が高くなります。音声機能、嚥下機能、排尿機能など、日常生活に必要な機能を保ちながら治療できます。
化学放射線療法のデメリットと副作用
化学放射線療法には、考慮すべきデメリットや副作用も存在します。
副作用の強さは、化学放射線療法の主なデメリットです。放射線治療と抗がん剤治療、それぞれの副作用が重なることで、単独治療よりも強い副作用が出る可能性があります。全身状態が良好でない方には、治療の継続が困難になることもあります。
急性期の副作用として、治療中から治療終了後数週間以内に現れる症状があります。照射部位の皮膚炎や粘膜炎、放射線食道炎、吐き気、倦怠感などが代表的です。抗がん剤による骨髄抑制も加わり、白血球減少や貧血が起こることがあります。
放射線食道炎は、胸部への照射を行う肺がんや食道がんで頻度が高い副作用です。治療開始後2週間頃から、食べ物を飲み込むときの痛みや胸の違和感が出現します。症状がひどい場合は、粘膜保護剤や鎮痛剤を使用し、柔らかく刺激の少ない食事を心がけます。
晩期合併症は、治療終了後数か月から数年経ってから現れる副作用です。放射線肺炎、心嚢水貯留、腸閉塞、膀胱炎、直腸炎などがあり、発生頻度は低いものの、一度発症すると回復に時間がかかることがあります。
子宮頸がんの化学放射線療法では、卵巣機能が失われることによる更年期症状、膀胱出血や直腸出血、リンパ浮腫などが晩期合併症として報告されています。発生頻度はグレード3以上の重篤なものでも、直腸炎・直腸出血が4~10%、膀胱炎・膀胱出血が5%以下、小腸障害が5%以下とされています。
適応の制限も考慮すべき点です。全身状態が悪い方、臓器機能が低下している方、以前に同じ部位への放射線治療を受けたことがある方などは、化学放射線療法が実施できない場合があります。
化学放射線療法の費用と保険適用
化学放射線療法の費用は、治療内容や使用する薬剤、放射線照射の回数によって異なります。
標準的な化学放射線療法は、健康保険の適用対象です。3割負担の場合、例えば食道がんや肺がんに対する6週間の治療で、総額は約200万円から300万円程度となり、自己負担額は約60万円から90万円程度となります。
放射線治療の費用内訳として、治療計画料、照射料、画像誘導放射線治療加算、外来放射線治療加算などがあります。照射回数が多くなるほど費用も高くなりますが、30回程度の照射で自己負担額は約20万円から30万円程度です。
抗がん剤の費用は、使用する薬剤の種類や投与量によって異なります。シスプラチンと5-FUの組み合わせでは、1クールあたり数万円から十数万円程度となります。
高額療養費制度を利用することで、月ごとの自己負担額に上限が設けられます。例えば、年収約370万円から770万円の方の場合、月の上限額は約8万円程度です。また、過去12か月以内に3回以上上限額に達した場合は、4回目からさらに負担が軽減される多数回該当の制度もあります。
高精度放射線治療であるIMRTや定位放射線治療も、保険適用となっています。IMRTの場合、照射回数にもよりますが、3割負担で約40万円から50万円程度の自己負担となります。ただし、高額療養費制度を利用することで、実質的な負担額は大幅に軽減されます。
先進医療である重粒子線治療や陽子線治療の場合、一部のがん種では保険適用となっていますが、適応外の場合は技術料が全額自己負担となります。重粒子線治療では約310万円から340万円、陽子線治療では約320万円程度が自己負担となります。
化学放射線療法を受ける際の注意点
化学放射線療法を受ける際には、いくつかの注意点があります。
治療前の評価が重要です。全身状態、臓器機能、栄養状態などを総合的に評価し、化学放射線療法に耐えられるかどうかを判断します。血液検査、画像検査、心機能検査などを実施し、治療の適応を慎重に検討します。
副作用への対策として、症状が出現する前から予防的な処置を行うことがあります。吐き気止めの薬、口腔ケア、皮膚の保湿などを治療開始時から実施します。また、症状が出た場合は、我慢せずに医療スタッフに相談することが大切です。
栄養管理も治療を完遂するために重要です。食道炎や口内炎により食事摂取が困難になることがあるため、高カロリー・高タンパクの補助食品や、場合によっては経管栄養や点滴による栄養補給が必要になることもあります。
定期的な通院が必要です。化学放射線療法は通常6~8週間程度続き、週5回の放射線照射と定期的な抗がん剤投与が必要です。通院の負担も考慮し、家族のサポートや通院方法を事前に検討しておくことが推奨されます。
まとめと今後の展望
化学放射線療法は、放射線治療と抗がん剤治療を組み合わせることで、それぞれの利点を活かし、治療効果を高める方法です。食道がん、頭頸部がん、肺がん、子宮頸がんなど、多くのがん種で標準治療として確立されています。
臓器を温存しながら治療できることや、手術と比較して体への負担が少ないことは大きなメリットです。一方で、副作用が強くなる可能性があるため、患者さんの全身状態や希望を考慮しながら、治療方針を決定することが重要です。
2025年から2026年にかけて、化学放射線療法と免疫チェックポイント阻害薬を組み合わせた治療法の有効性が相次いで報告されています。食道がんでは完全奏効率の向上、肺がんや子宮頸がんでも生存率の改善が示されており、今後さらに治療選択肢が広がることが期待されます。
また、IMRTや画像誘導放射線治療などの高精度放射線治療技術の進歩により、周囲の正常組織への影響を最小限に抑えながら、がん病巣に十分な線量を投与できるようになっています。これにより、副作用を軽減しながら治療効果を高めることが可能になってきています。
化学放射線療法を受けるかどうかは、主治医とよく相談して決めることが大切です。治療のメリットとデメリット、予想される効果と副作用、費用などを十分に理解した上で、ご自身の価値観や生活状況に合った選択をすることをお勧めします。















