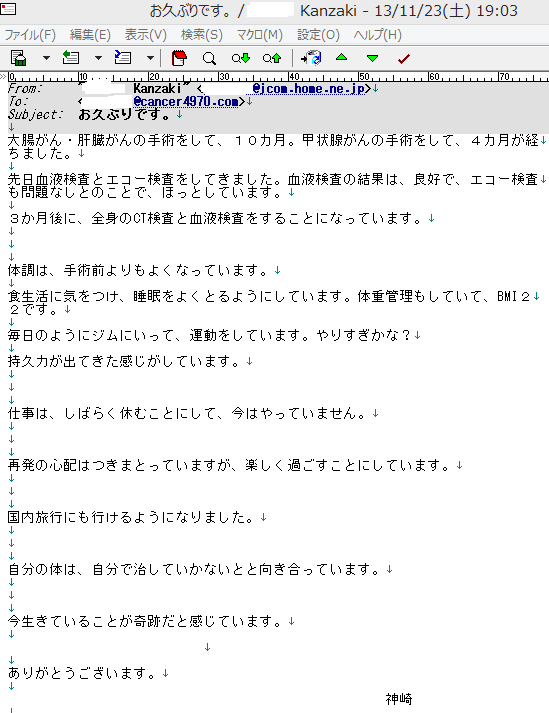【サイト内 特設ページ】

こんにちは。17年間の活動実績を持つ、
「プロのがん治療専門アドバイザー」本村ユウジです。
がんを治すために必要なことは、たった1つです。
詳しくはこちらのページでお伝えさせてください。
→がんを治すための「たった1つの条件」とは?
大腸がん手術後の抗がん剤治療とは
あらゆるがんの中でも、大腸がんは「手術治療」の比重が強い代表的ながんです。
がんが局所に留まる早期の大腸がんはもちろん、肝臓や肺に転移がある場合でも、転移した先の臓器の病巣を手術で切除するのは大腸がんの大きな特徴です。
これは大腸がんが一般的に進行が緩やかであることと関係しています。2025年3月現在の国立がん研究センターのデータによると、5年生存率はステージ0、Ⅰではそれぞれ90%を超え、ステージⅡでは84.4%、ステージⅢaで77.7%、ステージⅢbでは60.0%と他のがんに比べて良好な予後を示しています。
しかし、手術で目に見える病巣を完全に切除できたとしても、再発や転移のリスクは完全には除去できません。手術後の転移・再発の確率を下げる目的で行われるのが、術後補助化学療法(手術後の抗がん剤治療)です。
手術後の抗がん剤治療が推奨される場合
大腸癌研究会編「大腸癌治療ガイドライン医師用2024年版」に基づくと、手術後の抗がん剤治療が医師から提案されるのは、主に以下のケースです。
ステージⅢ(リンパ節転移がある場合)
ステージⅢの大腸がんでは、術後補助化学療法の一定の有効性が証明されています。ステージⅢでは再発率が約30%と比較的高いため、再発予防を目的とした治療が強く推奨されます。
高リスクステージⅡの場合
リンパ節転移のないステージⅡでも、再発の可能性が高いと判断される場合には術後の抗がん剤治療が検討されます。高リスクと判断されるのは以下のような場合です:
・がん細胞の悪性度が高い場合(分化度の低いがん)
・脈管侵襲(リンパ管または静脈侵襲)がある場合
・多臓器浸潤がある場合
・腫瘍による腸閉塞が起こり緊急手術となった場合
年齢と治療適応の関係
患者さんの年齢も術後の抗がん剤治療を決定する重要な要因です。2024年版ガイドラインでは「高齢者」の定義が従来の70歳から80歳に引き上げられましたが、高齢になるほど副作用のリスクが高くなるため、治療の適応は慎重に検討されます。
なお、実施される場合は手術後4~8週までに開始され、治療期間は6か月間が標準とされています。
【サイト内 特設ページ】

こんにちは。17年間の活動実績を持つ、
「プロのがん治療専門アドバイザー」本村ユウジです。
がんを治すために必要なことは、たった1つです。
詳しくはこちらのページでお伝えさせてください。
→がんを治すための「たった1つの条件」とは?
使用される抗がん剤の種類と治療法
大腸癌治療ガイドライン医師用2024年版では、術後補助化学療法として以下の治療法が推奨されています。
標準的な治療法
| 治療法 | 構成薬剤 | 投与方法 | 適応 |
|--------|----------|----------|------|
| 5-FU+ロイコボリン療法 | 5-FU、ロイコボリン | 注射薬 | ステージⅡ、Ⅲa |
| ゼローダ療法 | カペシタビン(ゼローダ) | 経口薬 | ステージⅡ、Ⅲa |
| UFT+ロイコボリン療法 | UFT、ロイコボリン | 経口薬 | ステージⅡ、Ⅲa |
| FOLFOX療法 | 5-FU、ロイコボリン、オキサリプラチン | 注射薬 | ステージⅢb |
| XELOX(CapeOX)療法 | カペシタビン、オキサリプラチン | 経口薬+注射薬 | ステージⅢb |
ステージⅡ・Ⅲaで選択される治療
ステージⅡやステージⅢaの場合、経口薬のゼローダ療法またはUFT+ロイコボリン療法が提案されることが多くなっています。特にUFT+ロイコボリン療法は食前食後1時間を空けるという服用ルールがありますが、副作用が比較的少ないため、患者さんにとって継続しやすい治療法です。
ステージⅢbで選択される治療
ステージⅢbの場合には、より効果の高いFOLFOX療法もしくはXELOX(CapeOX)療法が提案されます。これらの治療法は効果が高い反面、副作用も強くなる傾向があります。
FOLFOX療法とXELOX療法の選択基準
FOLFOX療法とXELOX療法のどちらを選択するかは、効果はほぼ同等であることが確認されていますので、利便性やライフスタイルが選択のポイントとなります。
FOLFOX療法の特徴
FOLFOX療法では、ロイコボリンとオキサリプラチンの2時間の点滴に加え、5-FUの注射、さらに5-FUの46時間の持続静注が必要です。持続点滴には特殊なポンプを携帯し、鎖骨部の皮下にポートを埋め込む手術も必要になります。通院回数は2週間に1回です。
XELOX療法の特徴
XELOX療法では、オキサリプラチンの点滴は同じですが、注射薬の代わりにカペシタビン(経口薬)を使用します。1サイクル(3週間)中、2週間にわたって1日2回服用します。ポート造設が不要で、通院回数も3週間に1回と少なくなります。
現在は患者さんの身体的負担が少ないXELOX療法を選択する方が多いですが、毎日の服薬が煩わしいという理由でFOLFOX療法を選ぶ方もいます。
【サイト内 特設ページ】

こんにちは。17年間の活動実績を持つ、
「プロのがん治療専門アドバイザー」本村ユウジです。
がんを治すために必要なことは、たった1つです。
詳しくはこちらのページでお伝えさせてください。
→がんを治すための「たった1つの条件」とは?
治療期間の最新動向
日本を含む国際共同臨床試験(ACHIEVE試験)の結果により、術後補助化学療法の治療期間について新たな知見が得られています。
治療期間短縮の検証
従来6か月間が標準とされていた治療期間を3か月間に短縮できるかどうかの検証が行われました。XELOX療法では、特に低リスクの患者さんにおいて3か月間の治療でも6か月間と同様の効果が得られる可能性が示されています。
個別化治療の重要性
この結果を受けて、患者さんの再発リスクや使用する治療法に応じて、治療期間を個別に検討することの重要性が高まっています。臨床現場では患者さんや家族とエビデンスで得られたメリット・リスクを共有し、治療方針を決定していくshared decision makingの姿勢が必要とされています。
オキサリプラチンの副作用と対策
大腸がんの抗がん剤治療で中心的な役割を果たすオキサリプラチンには、特徴的な副作用があります。
末梢神経障害の問題
オキサリプラチンの最も注意すべき副作用は末梢神経障害です。投与された患者さんの8~9割に感覚神経の末梢神経障害が生じます。重症になると、足の裏が痛くて歩けない、手の平が痛くて物が持てないなどの状態になることもあります。
長期的な影響
治療開始当初なら2~3日で消失しますが、治療を継続するに従って回復が遅れ、治療後4~5か月で1割の患者さんに機能障害(箸が持ちにくくなるなど)を来すといわれています。
このような副作用が現れた場合は、薬剤の減量や休薬によって症状の回復を待つことが重要です。再発リスクが軽減されても、日常生活に支障をきたすような障害が残ってしまうのは大きな問題であるため、適切な副作用管理が必要です。
最新の治療アプローチ
2024年版ガイドラインでは、従来の治療法に加えて新たなアプローチも取り入れられています。
個別化医療の進展
MSI-High/dMMR(遺伝子に入った傷を修復する機能が働きにくい状態)の場合や腫瘍遺伝子変異量高スコア(TMB-High)の場合に免疫チェックポイント阻害薬を使用する方法が新たに追加されています。
分子標的薬の位置付け
進行・再発大腸がんでは分子標的薬が効果を示していますが、現在のところ術後補助化学療法では有効性が認められていないため使用されません。
治療効果と再発予防の実際
治療効果の数値的評価
FOLFOX療法による再発の予防効果は、ステージⅢでは約2割と報告されています。つまり、100人中30人が再発するところを23~24人まで減らすことができます。
完遂の重要性
術後補助化学療法の目標は治療の完遂、つまり決められた用量・回数をすべて終えることです。一定の治療効果を上げるためには、決められた期間をやり遂げることが原則となります。
患者さんの年齢と治療選択
高齢者への配慮
術後補助化学療法を行うには、腎臓や肝臓といった重要な臓器の機能が保たれていることが必要条件です。特に高齢の患者さんでは、治療による利益と副作用のリスクを慎重に検討する必要があります。
治療適応の基準
手術でがんをすべて取り切れない場合でも、以下の条件を満たす方には薬物療法による治療が検討されます:
・少なくとも歩行可能で自分の身の回りのことができる
・肝臓や腎臓の機能が一定の基準を満たしている
・転移・再発がCT、MRIなどの検査で確認できる
治療選択における重要な考慮事項
メリットとデメリットのバランス
術後補助化学療法は再発リスクを下げることができますが、すべての患者さんに必要というわけではありません。
再発の可能性が低い方には、術後補助化学療法はあまり推奨されません。これは、抗がん剤による副作用のリスクと再発予防の利益を比較衡量する必要があるためです。
個別化された治療計画
病理学的ステージによっては治療期間を3か月とすることもあります。これは患者さんの状態や使用する薬剤によって最適な治療計画が異なることを示しています。
外来治療の普及と利便性の向上
外来化学療法の発展
従来は入院で行うことが一般的でしたが、最近は携帯型ポンプを用いることで外来での治療が普通となっています。これにより、患者さんの生活の質を保ちながら治療を継続することが可能になりました。
ポート造設の利便性
FOLFOX療法では中心静脈ポートの造設が必要ですが、外来で30分程度で済む手術で、その日はそのまま帰宅することができます。リザーバーを埋め込んでいても、入浴や運動もでき、普段通りの生活が送れます。
治療の継続性と中止基準
治療中止を検討する場合
化学療法を開始した後でも、以下のような場合は治療を中止することがあります:
・画像検査などでがんの縮小効果が認められない場合
・副作用が強すぎて治療継続が困難と判断される場合
・患者さんが治療中止を希望した場合
術後補助化学療法での継続重要性
術後補助化学療法に限れば、副作用が多少きつくても頑張って続けてもらうように努力します。決められた期間を遂行することで治療効果が現れるからです。
今後の展望
治療法の進歩
使用可能な薬剤が5-FUのみであった時代から、イリノテカンやオキサリプラチン、分子標的治療薬が登場し、進行再発大腸がんの生存期間の中央値は30か月程度まで延長してきました。
個別化医療の発展
遺伝子変異などに基づくPrecision Medicineの観点から、BRAF変異のある大腸がんに対するBRAF阻害薬や併用療法も開発されています。今後はより多くの患者さんが恩恵を受けられる治療法の開発が期待されています。
大腸がんの術後補助化学療法は、再発リスクを低下させる重要な治療選択肢です。しかし、その適応や治療法の選択、期間については患者さんの個別の状況を総合的に考慮して決定する必要があります。
参考文献・出典情報
1. 国立がん研究センター がん情報サービス「大腸がん(結腸がん・直腸がん)治療」
2. ケアネット「大腸癌治療ガイドライン2024年版の主な改訂ポイント」
3. 金原出版「大腸癌治療ガイドライン医師用2024年版」
4. 大腸癌研究会「大腸癌治療ガイドライン」
5. 日本大腸肛門病学会「大腸癌の化学療法」
6. QLife「大腸がんの抗がん薬治療」
7. 消化器癌治療の広場「ACHIEVE試験」
8. 済生会宇都宮病院「大腸がんの化学療法」
9. 国立がん研究センター「大腸がんファクトシート2024」
10. ファーマスタイルWEB「大腸がんは患者力を必要としている」