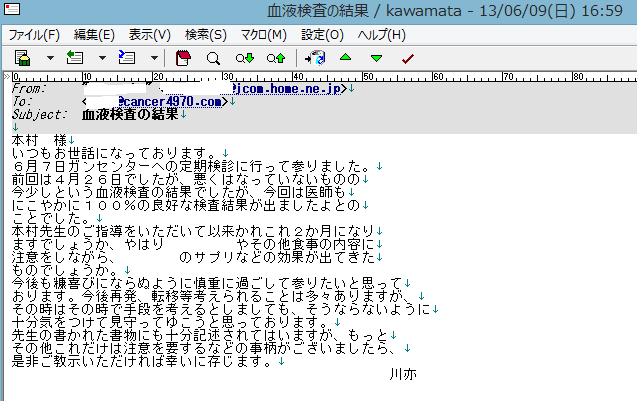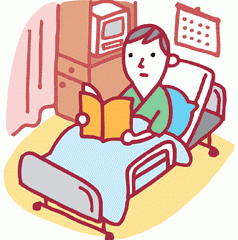
前立腺全摘除手術とは何か
前立腺全摘除術は、前立腺がんが前立腺内に限局している場合に行われる根治的治療法です。手術では前立腺のほか、精嚢、精管の一部、膀胱頸部の一部を切除し、関連するリンパ節も郭清対象となります。
手術方法には従来の開腹手術(恥骨後式、会陰式)と、近年主流となっているロボット支援腹腔鏡下手術があります。前立腺がんに対する前立腺摘除術は国内外を問わず広く行われていますが、開腹手術では手術中の出血量が多くなる可能性が高いこと、手術時間が長いこと、傷の大きさが約10cm前後と大きく術後の痛みが強いこと等の問題点があげられます。
ロボット支援前立腺全摘除術の特徴
現在、多くの医療機関でロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘除術が採用されています。2012年4月に保険適用となり、その後急速に普及しました。
この手術法では、腹部に5~12mmの小さな穴を複数あけ、そこから腹腔鏡や手術器具を挿入します。手術空間確保のため、腹部に二酸化炭素を送り込む「気腹」を行い、3次元の拡大画像を見ながら精密な操作が可能となります。
| 項目 | 従来の開腹手術 | ロボット支援手術 |
|---|---|---|
| 切開創の大きさ | 約10cm | 5~12mm×数個 |
| 手術時間 | 3~4時間 | 3~6時間 |
| 出血量 | 1000~2000ml | 比較的少ない |
| 入院期間 | 10日~2週間 | 5~7日程度 |
術後の主要な後遺症とその確率
前立腺全摘除術後には、主に以下のような後遺症が起こる可能性があります。これらの発症確率について、最新の医学文献に基づいて詳しく説明します。
尿失禁の発症確率と回復期間
尿失禁は前立腺全摘除術後の最も代表的な合併症です。尿失禁は前立腺全摘除術後の代表的な合併症で、患者さんの約9割は骨盤底筋群体操と薬剤を主とした保存的治療を行い術後1年程度で治りますが、約1割の患者さんでは尿失禁が残存します。
尿道の管を抜いた直後は、種々の程度の尿失禁が起こります。ほとんどの場合、術後1〜3ヶ月で生活に支障のない程度にまでよくなります。ロボット支援手術では、より精密な手術が可能なため、従来の開腹手術と比較して尿失禁の改善率が向上しています。
尿失禁は立ち上がったときや咳・くしゃみなどお腹に力を入れたときに尿が漏れる腹圧性のものが多いですが、90%以上の方が術後3か月以内におむつが1枚以下までに回復しています。
勃起機能障害(ED)の発症確率
勃起機能障害は、前立腺全摘除術後にほぼ確実に起こる合併症です。手術直後は、ほぼ確実に勃起障害が起こります。神経温存の程度、年齢、術前の勃起能などで異なりますが、勃起障害が完全に回復するのは難しいことが多いとされています。
ただし、神経温存手術を行った場合、部分的な回復が期待できます。神経を温存した手術後に起こる勃起障害に対しては、飲み薬による治療が有効な場合があります。
また、精のうを摘出し精管を切断するため、手術後は射精ができなくなります。ただし、精液は出なくても、射精の感覚は残ることがあります。
その他の合併症と発症確率
手術に関連する他の合併症として、以下のようなものがあります:
- 直腸損傷:比較的稀ですが、起こると重大な合併症になることがあります
- 尿道狭窄:術後長期経過での合併症として発生することがあります
- 鼠径ヘルニア:腹腔鏡手術やロボット支援手術後に稀に発生
- 血栓症:深部静脈血栓症や肺梗塞のリスク
術後のリハビリテーションと対策
術後の機能回復には、適切なリハビリテーションが重要です。特に尿失禁に対しては、骨盤底筋体操が効果的とされています。
退院後は骨盤底筋体操を毎日行うことを習慣にすることで、平均して1ヵ月くらいで、長くても1年くらいで改善されます。また、前立腺を刺激しないよう、1カ月程度は長時間の自転車やバイク乗車は避ける必要があります。
多くの医療機関では、専門的なケアチームによるサポートが提供されています。前立腺癌の手術後の尿失禁に対しては、入院・外来を通して、当院の多職種によって構成される排尿ケアチームがサポートします。
手術適応となる患者さんの条件
前立腺全摘除術の対象となる条件は以下の通りです:
| リスク群 | 条件 |
|---|---|
| 基本条件 | ・限局がん(がんが前立腺内にとどまっている) ・期待余命が10年以上 |
| 低リスク | PSA<10ng/ml、グリソンスコア6以下、T分類T1かT2aの3項目をすべて満たす |
| 中リスク | PSAが10~20ng/ml、またはグリソンスコア7、またはT分類T2bかT2c |
治療成績と長期予後
リスク分類に関係なく、摘出前立腺の病理組織検査で癌が前立腺に限局している場合は、術後5年のPSA非再発率(根治率)は90%以上です。
前立腺がん全体の生存率については、前立腺では97.8%、乳で85.9%、甲状腺で84.1%などとなっており、今後ますます「がんとの共生」(治療と仕事の両立など)が極めて重要な政策課題となってくる状況です。
ただし、手術後もPSA値の定期的な監視が必要です。PSA再発に約20%です。PSA再発に多くが手術後、2年以内が多いですが、その後も再発はあり得ますので、手術後8〜10年もの長期に渡り定期的にPSAを測定することになります。
最新の治療技術と再生医療
前立腺がん治療の分野では、合併症軽減を目指した新しい治療技術の開発が進んでいます。国立研究開発法人国立がん研究センターは、前立腺がんの根治的前立腺全摘後に合併症として発症する腹圧性尿失禁に対する再生医療を用いた臨床試験を開始しました。
また、フォーカルセラピーという新しい治療選択肢も登場しています。前立腺がん局所療法などとも呼ばれ、監視療法と手術などの根治的治療の中間に位置する治療です。正常組織を可能な限り残しながら、治療と身体機能温存によるQOL(生活の質)の維持の両立を目的として行います。
術後経過と外来フォローアップ
手術後の経過観察は長期にわたって行われます。経過観察は、病状にもよりますが、治療後2年間は3カ月ごと、それ以降2年間は6カ月ごと、その後は年1回程度受診します。
定期受診では、PSA検査を中心とした検査を行い、再発や転移の早期発見、治療後の合併症・後遺症の早期発見・治療を行います。患者さんは気になる症状がある場合、早めに受診して担当医に相談することが重要です。
生活の質(QOL)の向上への取り組み
手術後の生活では、規則正しい生活習慣が重要です。禁煙すること、飲酒をひかえること、バランスのよい食事をとること、適度に運動することなどを日常的に心がけることが大切です。
尿失禁に対するケアについては、尿もれに対しては、尿もれ用パッドや必要に応じ紙おむつを使用します。尿かぶれを予防するために、こまめに尿もれ用パッドの交換、シャワーや入浴を行うなどの対処が必要です。