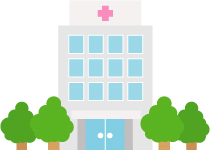
薬物療法を行う上で、大きな障害となっているのが、副作用です。
従来の抗がん剤で起こる副作用のほか、10年ほど前に登場した分子標的薬にも特有な副作用が起こることが分かっています。
副作用は、苦痛やQOL(生活の質)の低下をもたらしますし、副作用が強いからといって薬の量を減らせば、十分な治療効果が得られません。薬を使って薬の効果を引きき出すためには、副作用対策をしっかり行うことが大前提となってきます。
がんの薬物療法というと新しい薬の有効性ばかりに目が行きがちですが、最近では副作用対策についても、少しずつですが進歩しています。
例えば、あらかじめ副作用が起こると分かっている薬については、薬を使う前に予防薬を投与して、症状を未然に食い止めたり、投与法や投与量を調整して副作用を防いだり、軽くしたりするようになってきています。
とくに、大腸がんなどで使われるイリノテカンでは処方前に遺伝子診断薬を使って副作用が出やすい体質かをチェックすることができるようになっています(検査は健康保険が使えます)。
副作用は現れやすい時期がほぼ決まっています。薬の投与中には、異物に対する生体防御システムが過剰にはたらくことでアレルギー反応が起こり、発熱や皮疹が生じます。また、薬でおう吐中枢が刺激されれば吐き気・おう吐が起こります。その後は細胞が抗がん剤によるダメージを受ける時期によって、さまざまな症状が現れます。
薬の種類やこうした時期などを考盧して、副作用対策を講じることで、以前よりも副作用による苦痛を減らすことができるようになっているといえます。














