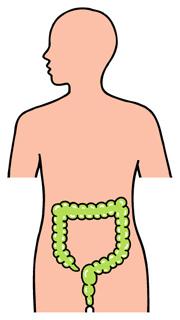
大腸がん内視鏡手術の基本概念と適応範囲
大腸がんの治療には「内視鏡治療(手術)」「開腹手術」「腹腔鏡手術」「化学療法」「放射線療法」などがありますが、早期がんにおいては内視鏡治療が第一選択となります。2025年現在、内視鏡技術の進歩により、従来は開腹手術が必要とされていた症例でも内視鏡での治療が可能になるケースが増えています。
大腸がんのステージは0期からⅣ期まで分類されており、Ⅲ期がaとbに分かれているため実質的には6段階となります。この分類は主にがんの進達度、リンパ節転移の有無、遠隔転移の有無によって決められます。
大腸の壁構造は内側から「粘膜」「粘膜下層」「固有筋層」「漿膜下層」「漿膜」の5層構造になっています。内視鏡治療の適応となるのは基本的に「ステージ0期」と「ステージⅠ期」の一部です。
| ステージ | がんの深さ | 内視鏡治療の適応 |
|---|---|---|
| 0期 | 粘膜内 | 適応 |
| Ⅰ期 | 粘膜下層浅部 | 条件により適応 |
| Ⅰ期 | 粘膜下層深部 | 適応外 |
| Ⅱ期以上 | 固有筋層以深 | 適応外 |
内視鏡手術の適応条件と最新の判定基準
内視鏡治療の適応は、がんの深さだけでなく、形状、大きさ、分化度、脈管侵襲の有無などを総合的に評価して決定されます。2025年現在の治療ガイドラインでは、より詳細な適応基準が設けられています。
大腸がんの形状は主に「ポリープ型」と「陥凹型」に分類されます。ポリープ型は粘膜面から盛り上がった病変で、茎のある有茎性ポリープや、茎のない無茎性ポリープがあります。一方、陥凹型がんは粘膜面が凹んだタイプで、ポリープ型と比較して悪性度が高く、転移のリスクも高いとされています。
内視鏡治療の適応となる具体的な条件は以下の通りです:
・粘膜内がん(ステージ0期):サイズや形状に関係なく適応
・粘膜下層浸潤がん(ステージⅠ期):浸潤距離1000μm未満、分化型、リンパ管侵襲なし、静脈侵襲なし、budding Grade 1
・腫瘍径2cm以上でも、深達度が適応範囲内であれば治療可能
内視鏡手術の種類と技術的特徴
現在行われている大腸がん内視鏡手術には、主に3つの方法があります。それぞれに適応となる病変の特徴と技術的な違いがあります。
ポリペクトミー(内視鏡的ポリープ切除術)
ポリペクトミーは最も基本的な内視鏡治療法です。肛門から内視鏡を挿入し、先端からスネアと呼ばれるループ状のワイヤーを出してポリープの茎部分にかけ、ワイヤーを締めながら高周波電流を流して焼き切ります。
この方法は主に茎のある有茎性ポリープに適用され、治療時間は通常10分から30分程度です。合併症のリスクは比較的低く、出血率は1-3%、穿孔率は0.1%未満とされています。
内視鏡的粘膜切除術(EMR)
EMRは茎のない無茎性病変や、わずかに陥凹した病変に対して行われます。病変の下に生理食塩水や止血剤を含んだ薬液を注入し、人工的に隆起させてからスネアで切除します。
EMRの適応サイズは原則として2cm未満とされています。これは物理的にスネアで一括切除できる限界サイズであり、それを超えると分割切除となり、病理診断の精度低下や再発リスクの増加につながるためです。
内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)
ESDは2012年4月から保険適用となった比較的新しい治療法で、現在最も注目されている内視鏡治療です。特殊な高周波ナイフを使用して病変を粘膜下層で剥離することで、大きな病変でも一括切除が可能です。
ESDでは「フレックスナイフ」「デュアルナイフ」「ITナイフ」「SBナイフ」などの各種ナイフが使い分けられます。病変の形状や部位、術者の技量に応じて最適なナイフが選択されます。
大腸ESDの技術的特徴として、胃ESDと異なりマーキングを省略することが多く、止血薬と青色色素を混合した薬液を注入します。青色色素により正常粘膜が青く透けて見えるため、がん部分との境界が明瞭になります。
「自分の判断は正しいのか?」と不安な方へ

がん治療。
何を信じれば?
不安と恐怖で苦しい。
がん治療を左右するのは
治療法より“たった1つの条件”です。
まず、それを知ってください。
がん専門アドバイザー 本村ユウジ
内視鏡手術の入院期間と治療の流れ
内視鏡手術の入院期間は治療方法と病変の大きさによって異なります。2025年現在の標準的な入院期間は以下の通りです。
| 治療方法 | 入院期間 | 食事開始 | 退院後の制限 |
|---|---|---|---|
| ポリペクトミー | 日帰り~1泊2日 | 当日夕食から | 1週間程度 |
| EMR | 1-3日 | 翌日朝食から | 2週間程度 |
| ESD | 3-7日 | 翌々日から段階的に | 4週間程度 |
治療前日には下剤による前処置を行い、腸管内を清浄にします。治療当日は絶食状態で臨み、治療後は合併症の監視のために一定期間の絶食が必要です。特にESDでは切除面が大きいため、より慎重な管理が求められます。
合併症とその対策
内視鏡手術の主な合併症は出血と穿孔です。出血は治療中に止血処置を行うことで多くの場合対処可能ですが、術後出血の場合は再度内視鏡による止血術が必要になることがあります。
穿孔は腸壁に穴があく合併症で、ESDで最も注意が必要です。軽度の穿孔であれば内視鏡的にクリップで閉鎖できますが、重篤な場合は外科手術が必要になります。
再発率と長期予後について
内視鏡治療後の再発率は治療方法と病理結果によって異なります。最新のデータによると、適切な適応で行われた内視鏡治療の5年生存率は98%以上と良好な成績を示しています。
局所再発率については以下の通りです:
・ポリペクトミー:1-2%(完全切除例)
・EMR:3-5%(一括切除例)、15-20%(分割切除例)
・ESD:1-3%(一括切除例)
ESDの一括切除率は95%以上と高く、これが低い再発率につながっています。ただし、病理結果で断端陽性や深部浸潤が判明した場合は、追加の外科手術が必要になることがあります。
治療成績を左右する因子
内視鏡治療の成功率と再発率は以下の因子に影響されます:
・腫瘍の大きさ:大きいほど技術的困難度が増加
・腫瘍の部位:右側結腸は壁が薄く技術的に困難
・腫瘍の形状:陥凹型は隆起型より困難
・線維化の程度:既往の生検や治療により線維化があると困難
・術者の経験:習熟度が成績に大きく影響
内視鏡手術と外科手術の比較
内視鏡手術と外科手術(腹腔鏡手術・開腹手術)を比較すると、適応となる症例では内視鏡手術の方が患者さんへの負担が少なくなります。
| 項目 | 内視鏡手術 | 外科手術 |
|---|---|---|
| 侵襲度 | 低い | 中〜高い |
| 入院期間 | 1-7日 | 7-14日 |
| 社会復帰 | 1-4週間 | 4-8週間 |
| 合併症率 | 3-5% | 10-20% |
| 医療費 | 安い | 高い |
ただし、内視鏡手術はリンパ節郭清ができないため、リンパ節転移のリスクがある場合は適応となりません。また、技術的困難例では外科手術への移行が必要になることもあります。
最新の技術動向と将来展望
2025年現在、大腸がん内視鏡治療の分野では以下のような技術革新が進んでいます。
AIを活用した診断支援システムの導入により、がんの深達度診断の精度が向上しています。また、新しいナイフの開発や牽引デバイスの改良により、ESDの安全性と確実性が向上しています。
内視鏡の高画質化も進んでおり、4K内視鏡や特殊光観察(NBI、BLI等)の普及により、微細な病変の検出能力が向上しています。これにより、より早期での発見と治療が可能になっています。
また、外来での日帰りESDの試みも始まっており、患者さんの負担をさらに軽減する取り組みが進められています。
治療後のフォローアップ
内視鏡治療後は定期的なフォローアップが重要です。一般的には治療後3ヶ月、6ヶ月、1年後に内視鏡検査を行い、その後は年1回の検査を継続します。
フォローアップの目的は局所再発の早期発見と、新たながんの発見です。大腸がんは多発する傾向があるため、治療後も継続的な観察が必要です。
また、病理結果によっては腫瘍マーカー(CEA、CA19-9)の測定や、CTによる画像検査も併用されます。これらの検査により、万が一の転移再発も早期に発見できるようになっています。
参考文献・出典情報
日本消化器内視鏡学会
大腸癌研究会
国立がん研究センター
がん情報サービス
日本消化器病学会
日本大腸肛門病学会
医薬品医療機器総合機構
厚生労働省
日本がん研究グループ
日本癌治療学会



