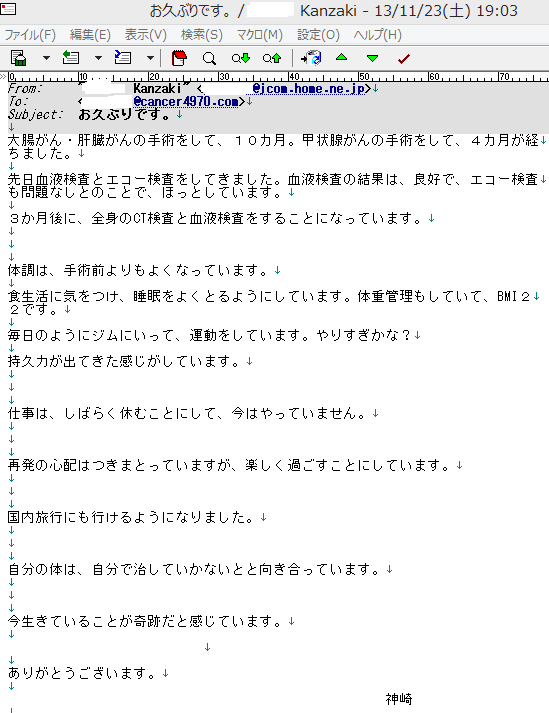肝臓がんに対する動注療法の副作用には2種類あります。1つは抗がん剤によるもの、もう1つはリザーバーとカテーテルを体内に埋め込んでいることによって生じる問題です。
抗がん剤の副作用
動注療法の場合、抗がん剤の副作用は一般に、それほどひどくはありません。ほとんどの抗がん剤は、動注で投与する場合、全身を流れる血液にはあまり入り込まないからです。とくに「低用量FP療法」といわれる方法は、体に与える影響が少ないと見られています。
とはいえ、抗がん剤の総投与量が多くなると、肝臓に障害を与える危険が高くなるので、投与はつねに慎重に行われなくてはなりません。もし、肝機能に異常が生じたら、いったん治療を中止し、肝機能が回復するのを待ちます。
抗がん剤の深刻な副作用の1つに、血球をつくる能力の低下(骨髄抑制)があります。この場合、貧血になったり、免疫力が低下して重い感染症にかかりやすくなったりします。骨髄抑制がひどいときには、抗がん剤の投与をしばらく休みます。
さらに、動注療法特有の問題として、抗がん剤が別の臓器に流入することがあります。胃や腸に入ると、粘膜が炎症を起こしたり、潰瘍が生じたりします。また、肌嚢や胆管に流れ込むと、胆嚢炎や胆管炎を発症することもあります。
そのほか、抗がん剤の一般的な副作用として、吐き気、嘔吐、脱毛、口の渇き、口内炎、下痢などが生じることがあります。とりわけ、注入の初期には体が薬に慣れず、強い副作用が起こることがあります。しかし、その後は通常、副作用は軽くなっていきます。
患者は、治療中や治療後に体の異常を感じたら、すぐに医師に連絡しなければなりません。医師は、異常がリザーバーやカテーテルによるものではないことを確認した後、副作用を抑える薬を投与したり、水分をよくとるようにという指示を出したりします。
また、患者は必ず、別の病気のために使っている薬を医師に知らせなくてはなりません。抗がん剤と併用することで、深刻な副作用を引き起こす薬もあるからです。以下は各抗がん剤で起こり得る副作用です。
1.フルオロウラシルの副作用
代謝拮抗剤と呼ばれる種類の薬です。DNAの材料分子であるチミジンという物質ができないようにして、DNAの合成を妨げ、がん細胞の増殖をストップさせます。
これまでのところ、低用量の動注で使用するときには、骨髄抑制、嘔吐や吐き気、下痢などの一般的な副作用は、生じても軽いと報告されています。
しかし、動注では肝臓に障害を与えるおそれがあるため、肝臓の障害度の高い患者には慎重な投与が必要です。さらに、胆嚢炎や胆管の壊死が起こる可能性もあります。全身投与では下痢、ものが二重に見える、肌が日光に敏感になる、皮膚や爪が乾燥したり炎症を起こしたりする、発疹が出る、目がうるむなどの症状が現れることがあります。
2.シスプラチンの副作用
シスプラチンはプラチナ製剤で、本来はがん細胞中のDNAに作用してガン細胞を殺します。しかし、フルオロウラシルと同時に使用するときには、フルオロウラシルの作用を増強させる効果があると考えられています。
シスプラチンは、他のほとんどの抗がん剤とは異なり、肝臓に動注しても、そこにとどまらず全身の血液中を流れるという性質をもっています。そのため、全身への副作用を与える反面、肝臓外に転移したがんにも効果が期待されます。
シスプラチンのもっとも重大な副作用は、腎臓に障害を与える可能性があることです。しかし、低用量FP療法では、シスプラチンの使用量は通常の化学療法よりはるかに少ないことが一般的です。
そのため、これまでのところ、低用量FP療法で腎臓に障害が出たとする報告はほとんどないようです。しかし、十分に水分をとるなどして腎臓を保護する必要はあります。
そのほか、通常の全身投与のときには、聴力障害、吐き気や嘔吐、"金臭い味"がするなどの味覚の変化、末梢神経の異常、脱毛、骨髄の抑制、肝臓の障害、心臓の異常、視覚の異常、アレルギーなどが報告されています。
3.ドキソルビシンの副作用
抗がん性抗生物質の1つで、アンスラサイクリン(アントラサイクリン)系という種類の薬です。DNAの複製を助ける酵素のはたらきを妨げて、がん細胞のDNAを破壊します。薬の色が赤いため、投与後1~2日は尿が赤くなりますが、これは異常ではありません。
動注では、吐き気や嘔吐、骨髄抑制などの副作用がしばしば発生します。肝臓に障害を起こすおそれもあります。
また、ドキソルビシンは皮膚や粘膜に接触すると炎症を起こします。そのため、動注で胃や腸にこの薬がもれ出すと、強い痛みを感じます。また、カテーテルが詰まって逆流したときも、皮膚が炎症を起こして痛みます。こうしたときは、すぐに医師に連絡しなければなりません。
そのほか、全身投与の際の副作用として、脱毛、口の渇き、下痢、発熱、寒気、腹部の痛みなどが報告されています。アンスラサイクリン系の薬の特徴として、まれに心臓に障害を与える可能性があります。
4.エピルビシンの副作用
ドキソルビシン同様、抗がん性抗生物質の中でも、アンスラサイクリン系と呼ばれる薬です。DNAやRNAの合成を妨げることによって、がん細胞を殺します。ドキソルビシン同様、薬の色のために投与後1~2日は尿が赤くなります。
動注では、嘔吐や吐き気、骨髄抑制などの副作用が生じることがあります。また、肝臓にもダメージを与えることがあるので、肝障害度が高い患者には慎重に投与しなければなりません。さらに、動注の際、胃や腸にエピルビシンがもれ出すと、炎症を起こして痛みます。
全身投与の場合の副作用として、脱毛、下痢、口の渇きや口内炎などがあります。まれに、心臓に障害を与えるおそれがあります。
5.マイトマイシンの副作用
抗がん性抗生物質の一種です。がん細胞のDNAに結びついて、その複製を妨げます。動注の場合、肝細胞が破壊されたり、胆嚢炎や胆管炎などを起こすおそれがあります。また、ドキソルビシンなどと同様、皮膚や粘膜にもれ出すと炎症を起こします。
動注の場合には、胃や腸の動脈に流入すると、胃や腸に潰瘍ができたり、出血したりします。全身投与の場合の副作用として、骨髄抑制、吐き気や嘔吐、口の渇き、脱毛などがあります。また、まれに肺炎を起こしたり、腎臓に障害を与える、溶血性貧血を起こす(尿が赤くなる)などの深刻な副作用が起こります。
6.インターフェロン
前述したように、抗ウイルス剤の一種です。免疫のはたらきを担う物質であるため、専門的には「生物学的応答調節剤」ともいいます。
肝細胞がんに対しては、少なくとも2つのはたらきがあると考えられています。1つは、免疫のはたらきを活性化してがん細胞を攻撃する効果です。もう1つの効果は、肝臓のウイルスの活動を抑えて、新しいがんの発生を予防することです。
これは、肝細胞がんに特徴的ながんの多発を抑えることにつながります。ほかにも、がん細胞を直接的に攻撃するはたらきがあると考えられていますが、くわしくはわかっていません。
インターフェロンの効果は、がん細胞がインターフェロンを受けとる専用のたんぱく質(レセプター、受容体)をもつときには高いとみられています。しかし、治療前に必ずしもレセプターの有無を確認するわけではありません。
インターフェロン・アルファの副作用は、インフルエンザや風邪の症状に似ており、発熱、寒気、頭痛、筋肉や関節の痛みなどが生じます。眠気やひどい疲労感、吐き気や嘔吐、下痢もしばしばみられます。
ときには、低血圧や不整脈、手足の感覚がいつもと違う、目の見え方がおかしいなどの異常が起こることもあります。インターフェロンの量が多いときには、精神的に不安定になったり、うつ状態に陥ったりすることもあります。
7.リピオドールの副作用
抗がん剤ではありませんが、動注でリピオドールを使用するときには、慎重さが必要です。リピオドールは粘度(ねばりけ)が高く、また血管を傷つけやすいので、血管やカテーテルが詰まりやすいためです。
また、肝動脈と肝静脈がつながっているときには、リピオドールが肝静脈へと流入して、さらに肺まで到達することがあります。その結果、肺の血管が詰まり、呼吸困難など重大な副作用を起こす危険があります。
リザーバー留置やリザーバーの異常による問題
リザーバーポートは、体内に埋め込んでも問題がないよう、生体になじみやすい材質でできています。表面は、血液の凝固を妨げるヘパリンという物質で被覆してあります。とはいえ、異物を体内に入れることには変わりないので、さまざまな問題が生じる可能性があります。
比較的よく起こるのは、カテーテルが詰まったり、その先端が留置した位置からずれてしまうことです。また、リザーバーから感染を起こす危険もあります。
さらに、リザーバーの耐用年数(約2年)を上回って留置すると、抗がん剤がもれ出すなどのトラブルが生じる可能性があります。
1.リザーバー周辺の出血/血腫
リザーバーを留置する手術の後、リザーバーを埋め込んだ部分が出血したり、内出血を起こして血液がたまったりすること(血腫)があります。肝臓がんの人は、肝硬変を合併することが多く、血小板や血液凝固因子が欠乏しています。この場合、出血が止まりにくくなります。
また、リザーバー埋め込み部の縫合が不完全なときや、安静時に患者が動いたときなど、さまざまな原因で起こり得ます。
自転車に乗る、しゃがみ込む、などの動作で、カテーテルが血管を傷つけた例もあります。縫合した場所からの出血は圧迫で止め、必要なら縫合し直します。血腫は、血液を絞り出すか、注射器で抜きとります。
2.カテーテル・血管の閉塞
リザーバーを留置した後、血液の固まり(血栓)などでカテーテルや血管が詰まって、動注ができなくなることがあります。治療がある程度進んでから詰まることが多いものの、まれに留置後、すぐに詰まる例もあります。
詰まる原因はまだはっきりしてはいません。しかし、血液が逆流したり、抗がん剤の結晶ができる、血管がカテーテルや抗がん剤で傷ついたり、弱くなったところに血の固まりができる、などが原因ではないかと推測されています。
また、まれにカテーテルが血管に持続的に刺激を与えることにより、血管の壁が厚くなっていき、閉塞する例もあります。抗がん剤を注入するときに抵抗を感じてなかなか入らない、患者が注入時やその後に腹などに痛みを感じる、などのときには、カテーテルや血管が詰まっている可能性があります。このようなとき、無理に抗がん剤を注入すると、抗ガン剤が逆流して目的でない臓器や皮膚に達し、臓器の粘膜や皮膚が炎症を起こしたり、壊死したりすることがあります。
カテーテルの閉塞を防ぐには、カテーテルを使用しないときでも、その内部を1~2週間に1回くらいは、ヘパリンを注入して洗浄する必要があります。
また、血管の閉塞を防ぐには、カテーテルの先端を固定して血管を刺激しにくくする、抗がん剤の濃度を低くして血管への障害を少なくする、抗がん剤注入後に生理食塩水などで洗浄する、などの方法がとられます。血管障害を少なくするため、ステロイド剤を投与することもあります。
しかし、こうした予防措置を行っても、詰まってしまうことは少なくありません。詰まったときは、カテーテルをはずしてふたたび入れ直すか、それが難しいときには別の治療法に移行します。血栓ができたときには、血栓を溶かすウロキナーゼという薬を用いることもあります。
3.カテーテルの逸脱
カテーテルの先端が、留置したところからずれてしまうことがあります。これは、おもに先端を固定せずにカテーテルを留置したときにみられます。
カテーテルがずれると、抗がん剤が腫瘍に達しないだけではなく、他の臓器に流入して、腹痛や、胃や腸の潰瘍などの副作用を起こす可能性があります。
そこで患者は、治療中や治療後、腹や背中に痛みや張りを感じたときは、すぐに医師に連絡します。注入の止め方を教わっている場合は自分で止めます。
医師は、X線やCTなどの撮影を行い、カテーテルがきちんと留置されているか、血流が予想通り流れているかを確認します。症状がとくになくても、カテーテルを留置したとき(とりわけ先端を固定しなかったとき)は、3カ月に1度くらいX線やCTの撮影を行い、カテーテルの状態を確認したほうがよいとされます。
4.リザーバー周辺の感染
リザーバー留置後、リザーバーを埋め込んだ部分が炎症を起こしたり、細菌に感染することがあります。原因は、血腫の形成や抗がん剤のもれ、留置手術時の細菌混入、薬の注入時の穿刺(針を刺すこと)などが考えられます。
抗がん剤がもれるのは、おもに、カテーテルや血管が閉塞したときに無理に薬剤を注入しようとしたときに起こります。ひとたびリザーバーを埋め込んだ部分が感染すると、リザーバーは異物なので、そのままでは治りません。そこで、できるだけ早くリザーバーとカテーテルを取り除く手術を行います。
以上、肝臓がんの動注療法についての解説でした。