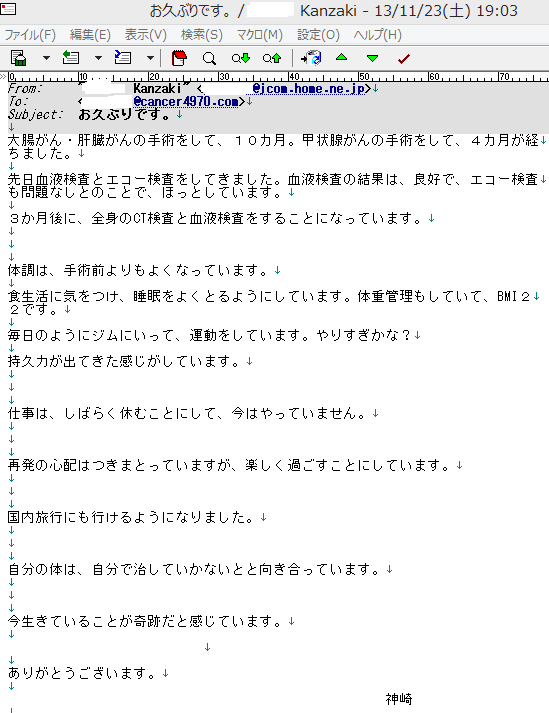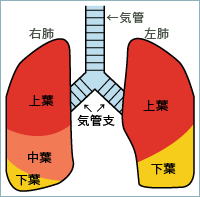
大腸がん肺転移とは
大腸がんは日本人のがん死因第2位を占める重要な疾患であり、進行すると他の臓器に転移する可能性があります。中でも肺転移は大腸がん患者さんにとって重要な問題の一つです。
大腸がんの肺転移は、原発巣である大腸から血液の流れに乗ってがん細胞が肺に到達し、そこで増殖することで発生します。大腸がんの手術を受けた患者さんの約15~20%に肺転移が認められ、多くの場合は手術後2~3年以内に発見されます。しかし、10年以上経過してから突然肺に影が見つかるケースもあり、長期間にわたる経過観察が必要となります。
大腸がん肺転移の症状と早期発見
大腸がんの肺転移は、初期段階では症状が現れないことが多く、定期的な画像検査により発見されるケースがほとんどです。症状が現れる場合には以下のようなものがあります。
呼吸困難や息切れが最も多い症状で、特に階段の上り下りや軽い運動時に感じることが多いです。持続的な咳や痰が出る場合もあり、時として血痰を伴うことがあります。胸痛も重要な症状の一つで、深呼吸や咳をする際に痛みが強くなる特徴があります。
早期発見のためには、大腸がん手術後の定期的なフォローアップが欠かせません。通常、術後は3~6ヶ月ごとにCT検査や胸部レントゲン検査が実施されます。血液検査では腫瘍マーカーであるCEAやCA19-9の測定も重要な指標となります。
大腸がん肺転移の診断方法
大腸がん肺転移の診断には、複数の画像診断と病理学的検査が組み合わせて使用されます。
胸部CT検査は最も重要な検査で、転移の個数、大きさ、位置を正確に把握できます。造影剤を使用することで、転移巣の血流や周囲組織との関係もより詳細に評価できます。PET-CT検査は全身の転移状況を一度に評価でき、他臓器への転移の有無も同時に確認できる優れた検査法です。
確定診断のためには病理学的検査が必要で、気管支鏡検査や経皮的肺生検により組織を採取します。これにより、転移性肺がんか原発性肺がんかの鑑別が可能になります。
大腸がん肺転移の治療選択基準
大腸がん肺転移の治療法選択には、いくつかの重要な判断基準があります。
手術治療の適応条件として、患者さんが手術に耐えられる全身状態であることが前提となります。大腸の原発巣が適切に治療されており、肺以外に遠隔転移がないことも重要です。転移の個数については、従来は片側の肺に限局した1~3個程度の転移が手術適応とされていましたが、近年では両側肺転移でも条件が揃えば手術が検討されます。
2025年現在では、転移の個数よりも完全切除の可能性と患者さんの術後肺機能の温存が重視される傾向にあります。
| 治療法 | 適応条件 | 5年生存率 |
|---|---|---|
| 外科手術 | 転移個数が少ない、完全切除可能 | 40~50% |
| 化学療法 | 切除不能、全身状態良好 | 15~25% |
| 放射線治療 | 局所制御目的、症状緩和 | 20~30% |
外科的治療法の進歩
大腸がん肺転移に対する外科治療は近年大きく進歩しています。
従来の開胸手術に代わり、胸腔鏡下手術が標準的な治療法として確立されました。胸腔鏡手術では、数センチの小さな切開創から内視鏡を挿入し、モニターを見ながら転移巣を切除します。この手術法により、患者さんの身体的負担が大幅に軽減され、術後の回復も早くなりました。多くの場合、術後3~5日で退院が可能となります。
ロボット支援下手術も導入されており、より精密な手術が可能になっています。3次元画像と精密な器具操作により、重要な血管や神経を温存しながら確実な切除が行えます。
片側肺転移の場合の5年生存率は47.5%と報告されていますが、近年では両側肺転移でも積極的な切除により30~45%の5年生存率が得られています。
薬物療法の最新動向
切除不能な大腸がん肺転移に対する薬物療法も大きく進歩しています。
従来の5-FUやマイトマイシンCを基本とした化学療法に加え、分子標的薬の登場により治療効果が向上しました。ベバシズマブ(アバスチン)は血管新生を阻害することで腫瘍の増殖を抑制し、セツキシマブ(アービタックス)やパニツムマブ(ベクティビックス)はEGFR阻害により抗腫瘍効果を発揮します。
近年注目されているのは免疫チェックポイント阻害剤です。マイクロサテライト不安定性(MSI-H)を有する大腸がんに対してペムブロリズマブ(キイトルーダ)が高い効果を示しており、適応患者では劇的な効果が期待できます。
個別化医療の観点から、遺伝子検査により患者さん一人ひとりに最適な治療法を選択する時代になっています。KRAS、NRAS、BRAFなどの遺伝子変異の有無により、使用する薬剤が決定されます。
放射線治療の役割
大腸がん肺転移に対する放射線治療は、主に症状緩和や局所制御を目的として実施されます。
定位放射線治療(SBRT)は、高精度で高線量の放射線を腫瘍に集中照射する治療法です。手術が困難な部位の転移や、手術を希望されない患者さんに対して有効な選択肢となります。通常、1~5回の短期間治療で完了し、外来通院での治療が可能です。
症状がある転移に対しては緩和的放射線治療が実施され、咳や胸痛、呼吸困難などの症状改善に効果があります。
予後と生存率
大腸がん肺転移の予後は、転移の状況や治療法により大きく異なります。
手術可能な症例では5年生存率は40~50%と比較的良好ですが、切除不能例では15~25%程度となります。予後に影響する因子として、転移個数、大きさ、発症時期、患者さんの全身状態、腫瘍マーカー値などがあります。
近年の治療法の進歩により、以前は治療困難とされた症例でも長期生存が期待できるようになりました。多学科チームによる集学的治療により、個々の患者さんに最適な治療計画が立てられます。
生活の質の向上と支持療法
大腸がん肺転移の治療では、生存期間の延長だけでなく、生活の質(QOL)の維持・向上も重要な目標となります。
呼吸リハビリテーションは、呼吸機能の維持・改善に有効で、理学療法士の指導のもと適切な呼吸法や運動療法が実施されます。栄養管理も重要で、管理栄養士による個別の栄養指導により、治療効果の向上と副作用の軽減を図ります。
心理的サポートも欠かせません。がん専門の心理士やソーシャルワーカーが、患者さんや家族の不安や悩みに対応し、療養生活をサポートします。
今後の治療展望
大腸がん肺転移の治療は今後さらなる発展が期待されています。
がん免疫療法の分野では、新しい免疫チェックポイント阻害剤や細胞治療の開発が進んでいます。CAR-T細胞療法や腫瘍浸潤リンパ球(TIL)療法など、患者さん自身の免疫系を活用した治療法の臨床試験が実施されています。
精密医療の分野では、液体生検による循環腫瘍DNA(ctDNA)の解析により、より早期の再発診断や治療効果判定が可能になることが期待されます。人工知能を活用した画像診断や治療計画の最適化も研究が進んでいます。
患者さんへのアドバイス
大腸がん肺転移の診断を受けた患者さんにとって、正確な情報の理解と適切な治療選択が重要です。
定期的な検査を欠かさず受けることで、早期発見・早期治療が可能になります。症状がある場合は遠慮なく医療チームに相談し、適切な対症療法を受けることが大切です。
参考文献・出典情報
4. NCCN Guidelines: Colon Cancer
5. ESMO Clinical Practice Guidelines: Colon Cancer
6. New England Journal of Medicine: Metastatic Colorectal Cancer
7. The Lancet: Colorectal Cancer Treatment
8. Journal of Clinical Oncology: Pulmonary Metastasectomy
9. American Cancer Society: Colorectal Cancer Surgery
10. 厚生労働省:がん対策情報