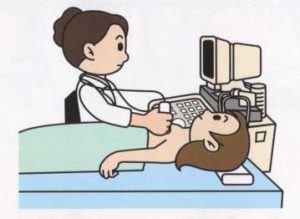
【サイト内 特設ページ】

こんにちは。17年間の活動実績を持つ、
「プロのがん治療専門アドバイザー」本村ユウジです。
がんを治すために必要なことは、たった1つです。
詳しくはこちらのページでお伝えさせてください。
→がんを治すための「たった1つの条件」とは?
乳房温存療法における放射線治療の基本方針
乳房温存療法は、乳房温存手術と術後の放射線治療、そして全身的な補助療法から構成される標準的な治療法です。乳がんの大きさや位置によって治療の適応が決まりますが、一般的に直径3センチメートル以内の乳がんが1個だけであれば、乳房温存療法の適用が検討されます。
最新の診療ガイドラインによると、乳房温存療法の根底にあるのは「乳腺内の目で見える病巣を乳房温存手術で切り取る」「詳細な病理検査で取り残しがないことを確認する」「細胞レベルで取り残した可能性のある病巣は放射線治療で根絶する」という考え方です。
放射線治療の実施時期と治療開始のタイミング
乳房温存手術後の放射線治療は、手術後約2週間から2か月の間で開始されます。傷が治癒し、腕を挙げることが可能になった時点で治療を開始することが重要です。術後薬物療法を行う場合は、それを終えてから放射線治療を開始します。
放射線治療の開始が遅すぎると、微小ながん細胞が増殖する恐れがあるため、手術後5か月以上間をあけないのが原則とされています。分子標的薬やホルモン療法薬の場合は、放射線療法と一緒に行うことができますが、副作用のリスクを避けるためには照射後が望ましいとされています。
【サイト内 特設ページ】

こんにちは。17年間の活動実績を持つ、
「プロのがん治療専門アドバイザー」本村ユウジです。
がんを治すために必要なことは、たった1つです。
詳しくはこちらのページでお伝えさせてください。
→がんを治すための「たった1つの条件」とは?
最新の放射線照射方法と線量設定
現在の標準的な放射線治療では、4から6メガボルトのX線を用いて接線対向2門照射法で実施されます。低いX線エネルギーを使用することが重要なポイントです。患者さんは両手を頭の上に挙げた体位で治療を受けます。
照射線量については、従来の通常分割法では全乳房に50グレイを25回(週5日間、5週間)で照射することが標準的でした。さらに、手術標本の病理検査結果によっては、腫瘍床に電子線を10グレイ追加照射することがあります。
短期照射法(寡分割照射)の最新動向
近年、治療期間の短縮を目的とした寡分割照射が注目されています。これは1回あたりの線量を少し増加させて、全体の回数を減らす方法です。具体的には、16から20回(3から4週間)で治療を完了させる方法が普及しています。
2025年現在、寡分割照射は副作用や治療効果が通常分割法と同等であることが確認されており、標準治療として位置づけられています。特に50歳以上で、乳房部分切除術後のpT1-2N0、全身化学療法を行っていない患者さんには強く推奨されています。
欧米の研究では、カナダで2.66グレイ×15から16回(総線量40から42グレイ)、イギリスで2.5グレイ×15回(総線量40グレイ)の短期照射法が、従来の方法と比較して術後10年間の局所再発率と生存率、副作用に差がないことが確認されています。
【サイト内 特設ページ】

こんにちは。17年間の活動実績を持つ、
「プロのがん治療専門アドバイザー」本村ユウジです。
がんを治すために必要なことは、たった1つです。
詳しくはこちらのページでお伝えさせてください。
→がんを治すための「たった1つの条件」とは?
領域リンパ節への照射について
腋窩リンパ節への転移が4個以上あった場合には、鎖骨上窩などへのリンパ節転移が多いと報告されており、このような場合は鎖骨上窩への放射線療法が有用とされています。腋窩リンパ節への転移が1から3個の場合には、病理学的悪性度、腫瘍の大きさ、リンパ節転移の個数などのリスク因子によって、照射を検討する場合があります。
ただし、腋窩リンパ節郭清後に腋窩に放射線照射を行っても生存率は改善せず、かえって腕のむくみや肩の副作用が増えるため、腋窩リンパ節郭清後の腋窩への放射線療法は推奨されていません。
新しい照射技術の発展
最新の放射線治療技術として、左乳がんの患者さんに対しては深吸気息止め照射が導入されています。これは大きく息を吸って息を止めた状態で照射することで、心臓が胸壁から離れ、照射範囲から外れるようにする方法です。この技術により、心臓への放射線被曝を大幅に減らすことができます。
また、一部の施設では、SAVI(Strut-Adjusted Volume Implant)という新しい放射線療法も導入されています。これは手術時または手術後にカテーテルを挿入し、1回3.4グレイの放射線照射を1日2回、5日間(計34グレイ)行う方法です。
放射線治療の副作用と対策
放射線治療による副作用は、照射した部位にのみ現れるため、髪の毛が抜けたり、めまいや吐き気が起こることはありません。主な副作用として以下があります。
急性期の副作用
治療開始から2から3週間後に放射線皮膚炎が起こり、照射部位の皮膚が日焼けのように赤くなったり、かゆみやひりひり感を生じることがあります。これらの症状は治療終了後2週間ほどで徐々に回復します。また、汗腺の機能低下により皮膚が乾燥することもあります。
晩期の副作用
治療終了後数か月から数年経ってから現れる副作用として、乳房の萎縮・硬化、治療した側の上肢の浮腫などがあります。また、乳房背側の肺の一部に放射線が当たるため、放射線治療終了2から6か月後に放射線肺炎が100人の中で1から2人の頻度で発症することがあります。
症状が強い場合はステロイド服用が必要になることがありますが、重篤な副作用の発生頻度は比較的少ないとされています。
治療効果と再発予防
乳房温存療法における放射線治療の効果は明確に証明されています。欧米の研究では、乳房温存手術後10年での乳房内再発率は、放射線治療を行った場合約8%であるのに対し、行わなかった場合約25%に達することが知られています。
放射線治療により局所再発を約3分の1に減少させることが可能であることがわかっており、そのため乳房を温存した場合でも放射線治療を行えば、乳房切除術を受けた場合と予後は変わりありません。
治療計画の立案と品質管理
放射線治療を行う際は、放射線腫瘍医が手術の内容や切除したがんの大きさなどをもとにコンピュータを使って適切な放射線量と照射範囲を決定します。医学物理士が品質管理の面から細かくチェックし、正確性を確保します。
患者さんには放射線療法をするときと同じ体位で、平坦なベッドに横になってもらい、CT撮影を行って、その画像に照射すべき範囲をマークしていきます。治療は外来で行い、1回あたりの照射時間は約15分程度です。
最新のガイドラインに基づく推奨事項
2025年現在、日本乳癌学会の乳がん診療ガイドライン2022年版(2024年3月WEB改訂版)では、早期乳がんに対する乳房温存手術後の放射線治療を強く推奨しています。特に寡分割照射については、通常分割照射と同等の治療として推奨されており、患者さんの負担軽減と治療効果の両立が図られています。
治療の選択については、患者さんの年齢、腫瘍の特徴、リンパ節転移の状況、全身状態などを総合的に判断して決定されます。治療を担当する医師とよく相談し、納得できる判断をするためには正しい知識が必要です。
参考文献・出典情報
- 日本乳癌学会「乳癌診療ガイドライン2022年版」
- 国立がん研究センター がん情報サービス「乳がんの治療」
- 京都大学医学部附属病院 放射線治療科「乳房温存療法」
- がんプラス「乳がんの放射線療法 治療の進め方は?治療後の経過は?」
- 日経メディカル「乳癌術後の寡分割照射(3週間)によるリンパ浮腫リスクは通常照射(5週間)に非劣性を示す【ESMO 2024】」
- 患者さんのための乳がん診療ガイドライン2023年版「放射線療法の副作用について」
- 日本呼吸器学会「放射線肺臓炎」
- 広島大学大学院医系学研究科 放射線腫瘍学「乳がん放射線治療」
- 総合東京病院「乳腺温存療法手術後の全乳房寡分割照射」
- 横浜栄共済病院「乳房温存療法の術後放射線治療について」













