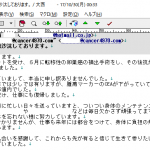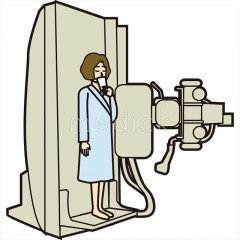
卵巣がんの再発率と再発時期の実態
卵巣がんの再発について理解するため、まずは統計的なデータから見ていきます。卵巣がんでは、初回治療が奏効して画像上にがんがなくなっても、半数以上の症例で再発・転移が起こります。この数字は、卵巣がんの特性を表す重要なデータです。
再発のめやすとして5年が挙げられることが多いですが、これはあくまで一つの指標に過ぎません。実際には5年経過後でも再発する可能性があるため、長期的な経過観察が必要とされています。
進行期別に見た生存率では以下のような数値が報告されています。ステージ1では92~96%、ステージ2は64%、ステージ3は30~41%、ステージ4は12~28.9%となっており、進行期によって予後に差が生じていることがわかります。
卵巣がん再発時に現れる症状
卵巣がんの再発症状は、初発時と似ている場合が多く見られます。以下のような症状が現れることがあります。
腹部症状
統計的には腹部膨満(お腹が張る)、腹痛、胃腸障害、頻尿(尿が近い)、体重減少などが多い症状として報告されています。これらの症状は他の疾患でも見られるため、卵巣がん特有の症状ではありませんが、既往歴のある患者さんでは注意深く観察する必要があります。
腹膜に転移して腹水がたまるとお腹が張った感じ(腹部膨満感)や、下腹痛の症状が現れます。腹水の蓄積は、がんが腹膜に播種(散らばって転移)することで引き起こされる代表的な症状の一つです。
全身症状
再発時には、食欲不振、易疲労感、体重減少といった全身症状も現れることがあります。がんが大きくなると、膀胱や直腸を圧迫することにより、頻尿や便秘が起きたり、脚がむくんだりすることもあります。
また、進行して腹水がたまると、おなかが大きく前に突き出てくることもあります。これは腹水により腹部が圧迫され、呼吸困難を伴う場合もあります。
再発発見のための検査方法と検査時期
治療後の定期検診は、再発の早期発見において極めて重要な役割を果たします。初回治療後の定期検診では、患者さんの状態や初回治療の内容に応じて、適切な検査スケジュールが組まれます。
基本的な検査項目
定期検診では、以下のような基本的な検査が実施されます:
- 触診、内診、直腸診による身体診察
- 細胞診
- 胸部単純X線検査
- 血液・生化学検査
- 腫瘍マーカー測定
これらの検査に加えて、手術や放射線療法、化学療法に伴う合併症の確認も重要な検査項目となります。
腫瘍マーカー検査の重要性
血液検査による腫瘍マーカーの測定も重要な検査の1つです。この検査は、体の中にがんが潜んでいると大量につくられる物質が血液中にどれだけ含まれているかを調べるものです。
卵巣がんの代表的な腫瘍マーカーは「CA125」と呼ばれるもので、再発すると多くの場合、数値が上昇してきます。CA125は卵巣がんの経過観察において最も重要な指標の一つとされています。
| 腫瘍マーカー | 特徴 | 測定頻度 |
|---|---|---|
| CA125 | 卵巣がんで最も重要なマーカー | 定期検診毎 |
| CEA | 消化器系がんでも上昇 | 必要に応じて |
| CA19-9 | 膵臓がんなどでも上昇 | 必要に応じて |
画像診断の役割
さらに画像診断としてCT検査も行われますが、毎回ではなく半年~1年に1回、必要に応じて行われることが多いとされています。
CT検査で何らかの所見が得られた場合に、追加の検査としてMRIやPET-CTによる検査が行われることもあります。これらの画像診断は、腫瘍マーカーの上昇や症状の出現と合わせて、総合的な判断に使用されます。
骨シンチグラフィー検査
骨転移を調べるための骨シンチグラフィーは、放射線同位元素を体内に投与し、その分布パターンを画像化する検査方法です。注射した薬剤が骨の代謝が活発な部位に集積する性質を利用しており、がんの経過観察のほか、骨折や炎症の確認にも使用されます。
再発時における最新治療法
卵巣がんが再発した場合の治療選択は、再発までの期間、がんの広がり方、これまでに行われた治療内容などを総合的に判断して決定されます。
プラチナ感受性による治療分類
卵巣がんの再発治療において重要な概念が「プラチナ感受性」です。世界的ながん治療ガイドラインである「NCCNガイドライン」では、再発卵巣がんの手術をする条件として、初回治療と再発との間隔が少なくとも6か月あることとしているため、プラチナ感受性の患者さんが主な対象と考えられます。
初回治療終了から再発までの期間が6か月以上の場合を「プラチナ感受性再発」、6か月未満の場合を「プラチナ抵抗性再発」として分類し、それぞれに適した治療法が選択されます。
局所再発に対する治療
がん病巣が初回に発生した場所に限定されている局所再発の場合は、以下の治療法が検討されます:
- 外科手術による腫瘍摘出
- 放射線治療
例えば、手術の対象となるのは、転移がリンパ節だけに留まっている場合や、遠隔転移があっても肝臓に1か所だけ病巣がある場合です。つまり、転移がさまざまな箇所に広がらないで、単発で再発しているケースでは手術によって治療効果を上げることが可能となります。
遠隔転移に対する治療
がんが複数箇所に転移している場合は、手術による完全摘出や放射線療法が困難となるため、主に薬物療法が選択されます。
腹膜播種の場合
再発は、がんが腹腔内に散らばって増殖する播種が圧倒的に多くとされており、この場合は化学療法が中心となります。
脳転移の場合
脳への転移が確認された場合は、放射線療法が主な治療選択肢となります。全脳照射や定位放射線治療が症例に応じて選択されます。
最新の薬物療法
2018年1月、プラチナ製剤感受性の再発卵巣がんの治療薬として承認された新薬がオラパリブ(製品名:リムパーザ)です。この薬剤は分子標的治療薬として注目されています。
オラパリブは経口薬であるため、自宅での服用が可能です。通院による点滴が必要なほかの薬と比べると、時間的制約などの患者さんの負担がかなり軽減される可能性があります。
現時点(2025年)では、卵巣癌に対する免疫チェックポイント阻害薬などの新規薬剤は、標準治療として広く確立されてはいませんが、特定の遺伝子変異(MSI-Highなど)を持つ場合や、臨床試験の枠組みで検討されることがあります。
| 薬剤分類 | 代表的薬剤 | 投与方法 | 対象患者 |
|---|---|---|---|
| プラチナ系 | カルボプラチン | 静脈点滴 | プラチナ感受性再発 |
| タキサン系 | パクリタキセル | 静脈点滴 | 併用療法として |
| PARP阻害薬 | オラパリブ | 経口薬 | BRCA変異例など |
| その他 | イリノテカン、エトポシド | 静脈点滴 | プラチナ抵抗性再発 |
遺伝学的検査の活用
卵巣がん・卵管がんでは、BRCA1遺伝子あるいはBRCA2遺伝子に異常がある場合などに、対応する薬物療法を検討します。これらの遺伝子変異がある場合、PARP阻害薬による治療効果が期待できるとされています。
治療方針決定における重要な要因
再発がんの治療法選択は、以下の要因を総合的に評価して決定されます:
- 再発までの期間(プラチナ感受性の判定)
- がんの広がり方(局所再発か遠隔転移か)
- これまでの治療歴
- 患者さんの全身状態
- 年齢や併存疾患
- 本人の希望や価値観
治療効果の判定と経過観察
治療効果の判定には、画像診断による腫瘍サイズの変化、腫瘍マーカーの推移、症状の改善度などが総合的に評価されます。定期的な検査により、治療継続の可否や治療変更の必要性が判断されます。
生活の質を重視した治療アプローチ
再発がんの治療においては、根治を目指すだけでなく、患者さんの生活の質(QOL)を維持・改善することも重要な目標となります。症状緩和のための支持療法や緩和ケアも、治療の重要な構成要素として位置づけられています。
副作用管理
化学療法による副作用として、嘔気・嘔吐、食欲不振、脱毛、末梢神経障害、血液毒性などが挙げられます。これらの副作用に対する適切な予防・治療により、治療継続性の向上と生活の質の維持が図られます。
栄養管理と運動療法
治療中の栄養状態の維持は、治療効果の向上と副作用軽減につながります。また、適度な運動は体力維持や心理的な安定にも寄与するとされています。
定期検診の重要性と継続の必要性
卵巣がんの治療後は、再発の早期発見を目的として、長期にわたる定期検診の継続が重要です。自覚症状が現れる前に再発を発見できることも多く、検診を欠かさないことが治療成績の向上につながります。
検診間隔は、初回治療の内容、病期、組織型などに応じて個別に設定されますが、一般的には治療直後は頻回に、時間経過とともに間隔を延長していく方式が採用されています。
患者さんと医療チームとの連携
再発の早期発見と適切な治療のためには、患者さん自身による症状の自己観察と、気になる症状がある場合の早期受診が重要です。医療チームとの良好なコミュニケーションを維持し、不安や疑問がある場合は積極的に相談することが推奨されます。
最新の研究動向と今後の展望
5年ぶりの改訂となる2025年版では、最新のエビデンスをもとに、薬物療法のCQが大幅にアップデートされたとされており、卵巣がん治療ガイドラインも継続的に更新されています。
卵巣がんはsilent killerとも呼ばれ早期発見の難しいがんですが、研究の進展により、より効果的な治療法や診断方法の開発が期待されています。
参考文献・出典情報
- 国立がん研究センター がん情報サービス「卵巣がん・卵管がん 患者数(がん統計)」
- 国立がん研究センター がん情報サービス「卵巣がん・卵管がん 検査」
- 国立がん研究センター がん情報サービス「卵巣がん・卵管がん 治療」
- がんプラス「卵巣がん、初回治療後の経過観察と再発・転移したときの治療」
- 日本婦人科腫瘍学会「卵巣がん・卵管癌・腹膜癌治療ガイドライン2020年版」
- 再発がんの情報サイト「卵巣癌が再発しやすい部位や5年生存率」
- 独立行政法人国立病院機構 大阪医療センター「卵巣がん(婦人科)」
- 京都済生会病院「卵巣がん・悪性卵巣腫瘍」
- がんメディ「卵巣がんのステージ別生存率と平均余命」
- 国立がん研究センター「院内がん登録2012年10年生存率集計 公表」