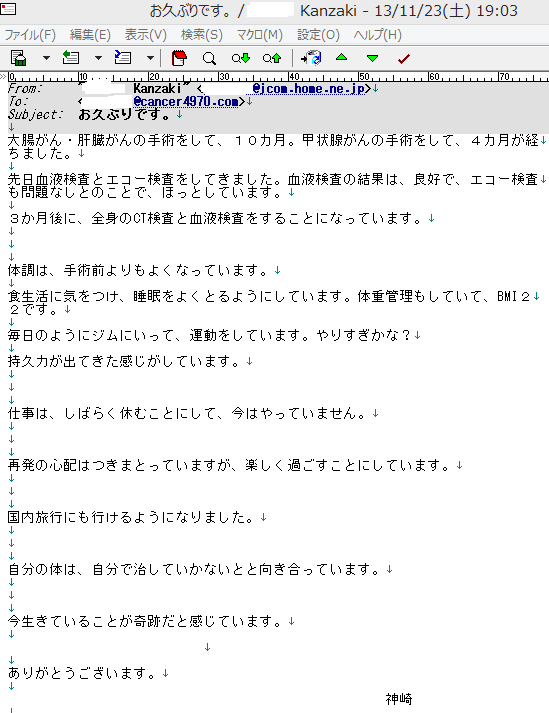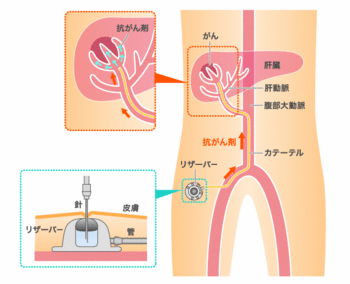
肝動注療法(動注化学療法)とは
こんにちは。がん治療専門アドバイザー、本村ユウジです。
肝臓がん治療の選択肢の1つとして「肝動注療法(動注化学療法)」があります。この治療法は、がんに栄養を供給している血管(肝動脈)に抗がん剤を直接注ぎ込む方法です。「経カテーテル動脈注入療法(TAI)」とも呼ばれます。
肝細胞がんは肝動脈から豊富に血液を受け取っています。この特性を利用して、肝動脈に抗がん剤を注入することで、より多くの抗がん剤ががんに流れ込み、効果的にがん細胞を攻撃できます。
また、肝臓で抗がん剤が分解されることで、全身を流れる血液中の抗がん剤濃度が低くなるため、副作用を抑えることができます。正常な肝臓細胞は肝動脈だけでなく門脈からも血液を受け取っているため、抗がん剤の濃度がそれだけ低くなるという利点もあります。
治療には、1回のみ実施する方法と、スケジュールに従って繰り返し注入を行う反復動注療法があります。反復動注療法では通常、リザーバーという装置を体内に埋め込んで治療を行います。
1回のみの方法では、一般的に肝動脈塞栓療法などの他の治療と組み合わせます。肝動脈塞栓療法と組み合わせる場合は、「化学塞栓療法」と呼ばれます。反復動注療法は単独で実施する場合と、他の治療の前後に補助的に行う場合があります。
肝動注療法が選択される患者さん
動注療法は、がんが進行している人や他の治療法が選択できない患者さんに対して実施されることが多い治療法です。がんが進行しているときは治療法が制限されることが多いですが、動注療法はがんの進行状態によって制限されることがあまりないためです。
ただし、動注療法は効果が得られる人が約50パーセント前後とされており、抗がん剤の副作用で肝臓の働きが悪化したり、全身状態が悪くなる可能性もあります。そのため、他の治療を選択できる場合はそちらを優先します。
近年では、抗がん剤の副作用を小さくする様々な方法があるため、他の治療法を行う前後に補助療法として動注療法を行うことも少なくありません。
動注療法の治療選択順位
肝細胞がんに対しては、まず外科治療(肝切除)やラジオ波焼灼療法、マイクロ波凝固法などの局所的で完治の可能性が比較的高い手法による治療を考えます。次に、肝動脈塞栓療法(TACE)による治療を検討します。これらの治療が難しいときに、動注療法(主に反復動注療法)を実施することになります。
動注療法が優先的に用いられない理由は、現時点では肝細胞がんに対して治療効果の高い抗がん剤が存在しないためです。現在用いられている抗がん剤は、高濃度で肝臓の腫瘍に送り込んでも、がんの進行が止まらないこともあります。
肝動注療法に適した状況
以下のような場合には、動注療法が選択されます。
肝臓内部に4個以上の腫瘍(がん)がある場合
腫瘍が4個以上発生しているときに局所的治療法を行うことはまれです。その理由の1つは、すべての腫瘍に局所的治療を施すには時間がかかり、体に大きな負担がかかるためです。
もう1つの理由は、4個以上の腫瘍が存在するときには、画像診断などで確認できるもの以外にも小さな腫瘍が存在する可能性があるからです。このような場合には、肝臓全体を治療対象とする肝動脈塞栓療法、または動注療法で治療を行います。腫瘍に被膜がないなどの理由で肝動脈塞栓療法の効果が低いと予測されるときには、動注療法を選択します。
腫瘍が門脈をふさいでいる/門脈に浸潤している場合
腫瘍が成長して主な門脈をふさいでいるときには、肝動脈塞栓療法では治療できないことがあります。門脈の血流が肝臓の広範囲に行きわたらないときに肝動脈もふさげば、肝臓が大きな損傷を受けるためです。
また、腫瘍が門脈をふさいでいるときには、門脈を通してがんが肝臓内部に転移していることが少なくありません。そのため、たとえラジオ波焼灼療法やマイクロ波凝固法などの局所的治療法で治療を行ったとしても、転移した微小ながんから再発する可能性が高くなります。
このため、腫瘍が門脈に浸潤している、あるいは門脈をふさいでいるときには、しばしば動注療法が選択されます。また、動注療法と局所的手法を組み合わせて治療を行うこともあります。
がんの悪性度が高い場合
肝細胞がんでも、中分化がんあるいは低分化がんと呼ばれるものは悪性度が高いとされます。これらのがんは、腫瘍の被膜の外側にがん細胞が浸潤したり、肝臓の内部に転移しやすい性質を持ちます。
そのため、肝切除やマイクロ波凝固療法などの局所的治療法だけでは、十分な治療効果を期待できないことが少なくありません。
このため、悪性度の高いがんに対しては、補助療法として局所的治療法の前後に動注療法を行う医療機関もあります。ただし、その有効性については議論が分かれているのが現状です。
肝動注療法に適さない状況
動注療法は多くの場合、がんが進行した人に対して行う治療法の1つです。しかし、大きな副作用が生じる危険もあるため、動注療法を行うかどうかは慎重に検討すべきとされます。以下は、動注療法による治療が禁止される場合です。
肝臓の障害度が高い(肝機能が低下している)場合
動注療法は肝臓に損傷を与える可能性があるため、肝臓の障害度が高い人は治療を受けることができません。
具体的には、黄疸が強い(総ビリルビンが血液100ミリリットルあたり3ミリグラム以上)、治療をしても腹水が治らない、肝性脳症(意識障害)を起こしているなどの場合は、動注療法は禁止されます。これはChild-Pugh分類でいうとクラスCに相当する状態です。
また、検査結果は治療可能とされた場合でも、肝硬変を起こしている人に対しては、注意深く病状を見て動注療法を行うかどうかを決めます。動注療法で使用される薬には肝臓に障害を起こしやすいものもあるため、肝硬変の人は選択できる薬が限られることもあります。
Child-Pugh分類による肝機能評価
肝細胞がんの治療法を選択する際には、Child-Pugh分類による肝機能評価が重要です。この分類では以下の5項目を評価します。
| 評価項目 | 1点 | 2点 | 3点 |
|---|---|---|---|
| 肝性脳症 | なし | 軽度 | ときどき昏睡 |
| 腹水 | なし | 少量 | 中等量 |
| 血清ビリルビン値(mg/dL) | 2.0未満 | 2.0~3.0 | 3.0超 |
| 血清アルブミン値(g/dL) | 3.5超 | 2.8~3.5 | 2.8未満 |
| プロトロンビン活性値(%) | 70超 | 40~70 | 40未満 |
合計点数により以下のように分類されます。
| 分類 | 合計点数 | 肝機能の状態 |
|---|---|---|
| クラスA | 5~6点 | 良好な状態。様々な治療法が選択可能 |
| クラスB | 7~9点 | 中程度の障害。治療法に制限あり |
| クラスC | 10~15点 | 重度の障害。多くの治療が困難 |
Child-Pugh分類クラスCの患者さんでは、動注療法を含む多くの積極的治療が困難とされ、肝移植や緩和ケアが検討されます。
造血能力が低下している場合
ほとんどの抗がん剤は、がん細胞だけでなく活発に増殖する正常な細胞も攻撃します。たとえば、血球をつくる骨髄や、胃や口の中の粘膜などの細胞です。
そのため、血球をつくる能力が落ちているときに抗がん剤を使用すると、骨髄の働きがさらに下がり、赤血球や白血球、血小板の数が減って著しい貧血に陥ったり、深刻な感染症にかかる、出血が止まらないなどの恐れが高くなります。これを「骨髄抑制」と呼びます。
具体的には、血液1マイクロリットルあたり白血球が2000個以下、血小板が5万個以下の場合は、この治療は行いません(医療機関によって多少異なります)。血小板輸血や血球の生産を促す薬の投与によってこれらの値が回復すれば、治療を開始できます。
その他の禁忌事項
心臓や腎臓に異常がある場合、薬によってはこれらの臓器を悪化させる可能性があります。そのため、使用できる薬の種類が限られたり、動注療法を受けることができなくなったりすることがあります。
肝動注療法の実施方法
肝動注療法では、事前に肝動脈の中にカテーテルを挿入し、リザーバーという器具を足のつけ根の皮下に埋め込む必要があります。
カテーテルは細く軟らかい管で、先端部分が少し細くなっている太さ2.7ミリメートル程度のものを使います。リザーバーは500円硬貨ほどの大きさで、肝動脈に入れたカテーテルと携帯用の薬液ポンプから出ている管を連結します。
抗がん薬の入ったポンプから薬液を肝動脈に注入するときは、リザーバーに針を刺し込んで接続します。
使用される抗がん剤
注入する抗がん剤は、フルオロウラシル(5-FU)が主に使われます。全身化学療法で用いる量をそのまま注入すると肝臓がダメージを受けてしまうため、投与量を調整しています。
ただし、その量では十分な効果が得られにくいため、フルオロウラシルの作用を増強する別の薬を併用します。併用する薬は、シスプラチンやインターフェロンなどです。
シスプラチンは抗がん剤の1つで、インターフェロンは肝炎の治療薬ですが、肝臓がんに対する作用や免疫力を高める作用があることがわかっています。
なお、低用量シスプラチン併用5-FU肝動注療法は健康保険が認められていますが、インターフェロン併用5-FU肝動注は現時点では保険適用外の場合があり、医療機関によって臨床試験として実施されることもあります。
治療の効果と成績
肝動注化学療法の治療効果については、がんの大きさが変わらない状態も含めた増殖抑制効果は約52パーセントとされています。そのうちがんが完全に消えたり、一部小さくなったりした割合は約32パーセント程度です。
生存率は治療後1年で約30パーセント前後、3年で約6パーセント前後とされていますが、肝機能が良い患者さんほど高い結果が得られています。
治療が効きやすい条件下であれば、生存期間中央値は12カ月程度に上るとの報告もあります。
副作用について
副作用については、大きく分けて抗がん薬による副作用とインターフェロン(使用する場合)による副作用があります。
抗がん薬では味覚異常や食欲不振、吐き気、口内炎、下痢、白血球減少などが起こります。インターフェロンでは発熱や倦怠感、白血球減少などがみられます。
食欲がないときは無理をせず、食べたいと思うもの、好きなものを少しずつ口にすることが推奨されます。冷たいものやあっさりしたもののほうが食べやすいとされています。
骨髄抑制で免疫力が低下し、感染症にかかりやすくなるため、帰宅時や食事の前などは手洗い、うがいを必ず行うことが重要です。
まれにカテーテルが肝動脈から抜けて他の臓器に抗がん薬が回ってしまうトラブルが起こることがあります。そうならないために、抗がん薬を入れる前は必ずX線検査でカテーテルの状態を確認します。
また、体内に異物が入ったことによってできる血栓が脳に飛んで脳梗塞を起こすことがあります。これは鎖骨からカテーテルを入れる場合に起こりやすく、足のつけ根の血管からカテーテルを入れることでこうしたリスクを回避する医療機関もあります。
最新の治療動向(2026年更新)
2025年には肝細胞がん診療ガイドライン2025年版が公開され、治療選択のアルゴリズムが更新されました。
現在の標準治療では、Child-Pugh分類AまたはBで、がんが肝臓内にとどまっている場合は、肝切除、ラジオ波焼灼療法(RFA)、肝動脈化学塞栓療法(TACE)が中心となっています。肝外転移がある場合には薬物療法を選択します。
薬物療法においては、免疫チェックポイント阻害薬と分子標的薬を組み合わせた治療が一次治療として用いられるようになっています。代表的なものとして、アテゾリズマブ(抗PD-L1抗体)とベバシズマブ(抗VEGF抗体)の併用療法や、ペムブロリズマブ(キイトルーダ)とレンバチニブ(レンビマ)の併用療法があります。
これらの免疫療法薬が使用できない場合には、ソラフェニブやレンバチニブなどの分子標的薬が用いられます。二次治療としては、レゴラフェニブ、ラムシルマブ、カボザンチニブなどが使用可能です。
肝動注化学療法は、これらの全身薬物療法が行えない場合や、全身化学療法の副作用が強くて続けられない場合、全身化学療法の効果が見られなかった場合などに選択されることがあります。
また、2025年にはレンバチニブとペムブロリズマブに肝動脈化学塞栓療法(TACE)を加えた併用療法の臨床試験(LEAP-012試験)についても報告されており、今後の治療選択肢がさらに広がる可能性があります。
治療選択における重要なポイント
肝細胞がんの治療法を選択する際には、以下の5つの因子が重要となります。
| 評価因子 | 内容 |
|---|---|
| 肝予備能(Child-Pugh分類) | 肝臓の機能がどのくらい保たれているか |
| 肝外転移 | 肝臓以外の臓器への転移の有無 |
| 脈管侵襲 | がんが肝臓内の血管や胆管に侵入しているか |
| 腫瘍数 | がんの個数 |
| 腫瘍径 | がんの大きさ |
これらの因子を総合的に評価して、最適な治療法が選択されます。
肝動注療法が選択される典型的なケースは、Child-Pugh分類AまたはB、肝外転移なし、腫瘍数4個以上の場合などです。この場合、一般的には肝動脈塞栓療法が第一選択となりますが、塞栓療法の効果が低いと予測される場合や、門脈腫瘍栓がある場合などに肝動注療法が選択されます。
治療を受ける際の注意点
肝動注療法を受ける際には、以下の点に注意が必要です。
まず、治療前に十分な検査を行い、肝機能や全身状態を正確に評価することが重要です。特にChild-Pugh分類や血液検査の結果は、治療の可否を判断する上で欠かせません。
治療中は定期的な検査が必要です。カテーテルの位置確認のためのX線検査、血液検査による肝機能や骨髄機能のチェックなどが行われます。
副作用が現れた場合は、速やかに医療チームに報告することが大切です。適切な対症療法により、副作用を軽減できる場合があります。
また、治療効果の判定も重要です。定期的な画像検査(CTやMRIなど)により、がんの大きさや数の変化を確認します。治療効果が不十分な場合は、他の治療法への変更が検討されます。
肝動注療法は長期にわたる治療となることが多いため、体調管理や栄養管理も重要です。バランスの取れた食事、適度な休息、感染予防のための衛生管理などを心がけることが推奨されます。
なお、肝動注療法を実施できる医療機関は限られており、特にリザーバーを留置する技術を有する医師がいる施設で行われます。治療を希望する場合は、担当医に相談し、適切な医療機関を紹介してもらうことが必要です。
参考文献・出典情報
- 国立がん研究センター がん情報サービス「肝臓がん(肝細胞がん)治療」
- 国立がん研究センター「肝がんの治療について」
- 日本肝臓学会「肝細胞癌診療ガイドライン2025年版」
- がんプラス「肝臓がんの薬物療法 肝動注化学療法と分子標的治療をどう選択するか」
- がんプラス「肝臓がんの肝動注化学療法 治療の進め方は?治療後の経過は?」
- がんプラス「肝臓がんの状態と肝機能を考慮した最新の治療選択とは」
- エーザイ株式会社「切除不能な非転移性肝細胞がんを対象とした臨床第Ⅲ相LEAP-012試験の状況について」
- 武田薬品工業「肝細胞がん(HCC)の評価」
- 日本臨床外科学会「治療計画に影響を与える肝機能分類」
- エーザイ「肝がんはどうやって治療する?」