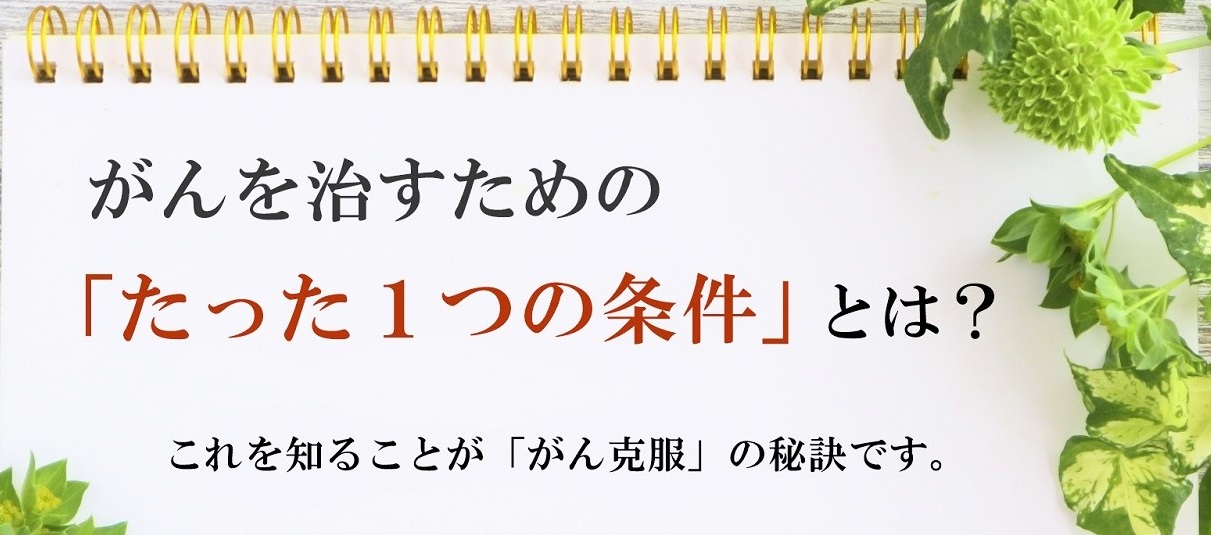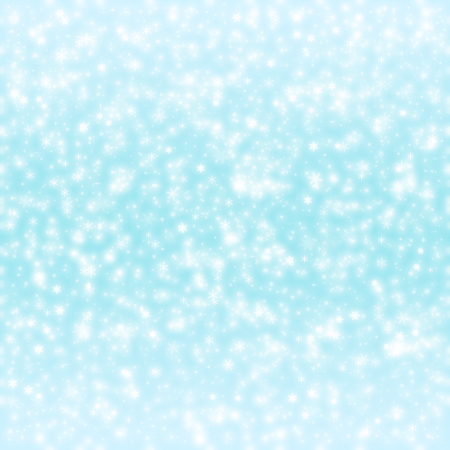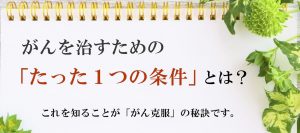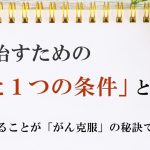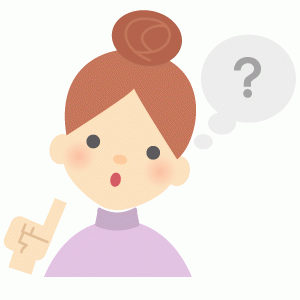
乳がん治療で使われるホルモン剤は、からだの中で作られる女性ホルモンであるエストロゲンを減らしたり、乳がん細胞内のエストロゲン受容体とエストロゲンとの結合を邪魔することで、がん細胞の分裂増殖を防ぐ作用があります。
ホルモン療法の作用
乳がんには、エストロゲン(女性ホルモン)をエサとして増殖するものと、そうでないものがあります。ホルモン剤は、エサである体内のエス卜口ゲンの量を減らしたり、がん細胞がエストロゲンを取り込むのを邪魔したりすることで、がんの増殖を抑えます。
ホルモン療法の効果が期待できるのは、エストロゲンを取り込んで増殖する性質をもった乳がんで、乳がん患者さん全体の60~70%です。エストロゲンをエサにして増殖する細胞は、「エサを取り込む口」である「ホルモン受容体」をもっています。
したがって、ホルモン療法が効くかどうかは、ホルモン受容体(エス卜口ゲン受容体とプロゲステ口ン受容体)の有無を調べればわかります。
手術で切除した乳がん組織を調べて、エストロゲン受容体かプロゲステロン受容体(エス卜口ゲンの働きによってつくられる受容体)の少なくともどちらか一方があれば、ホルモン受容体「+」、または「陽性」あるいはホルモン感受性「あり」といい、ホルモン療法が有効です。どちらもなければ、ホルモン受容体「-」、または「陰性」あるいはホルモン感受性「なし」といいます。
ホルモン受容体が陰性の場合は、ホルモン療法の効果は期待できないため行われません。
ホルモン療法は、手術後の初期治療として使用することで、転移や再発の確率が減少し、また進行・再発乳がんでは、がんの進行を抑える効果が証明されています。
ホルモン剤の種類
ホルモン療法には作用の異なる2つの方法、すなわち、体内のエストロゲンの量を減らす方法と、がん細胞がエストロゲンを取り込むのを邪魔する方法があります。体内のエストロゲンを減らす方法としては、①LH-RHアゴ二スト製剤、②アロマターゼ阻害薬があります。
がん細胞がエストロゲンを取り込むのを邪魔する方法としては、抗エストロゲン薬があります。体内でのホルモンの分泌は、閉経前と閉経後で大きく異なるので、薬剤もそれにあったものを使用します。
(1)体内のエストロゲンの量を減らす方法
エストロゲンは、閉経前の女性では主に卵巣でつくられ、卵巣機能が低下した閉経後は副腎や脂肪組織でつくられます。
閉経前の女性では、脳の「視床下部」というところから「下垂体」に、「性腺刺激ホルモン(LH)」を出す指令(性腺刺激ホルモン放出ホルモン、LH-RH)が出されると、下垂体は性腺刺激ホルモンを出して卵巣を刺激し、卵巣はエストロゲンを作ります。
LH-RHアゴ二ス卜製剤はLH-RHとよく似た構造をもつ物質で、LH-RHの働きを邪魔するため下垂体から卵巣への指令が出なくなり、その結果エストロゲンがつくられなくなります。
一方、閉経後は卵巣の機能力が低下するので、卵巣ではエストロゲンがつくられなくなります。その代わりに、副腎(腎臓のすぐ上にある組織)皮質から分泌される、アンドロゲンという男性ホルモンからエストロゲンがつくられるようになります。
アンドロゲンがエストロゲンにつくりかえられる過程で働いているのが、脂肪組織などにある「アロマターゼ」という酵素です。したがってアロマターゼの働きを阻害する薬(アロマターゼ阻害薬)を使用することでエストロゲンがつくられなくなります。
(2)がん細胞がエストロゲンを取り込むのを邪魔する方法
エストロゲンをエサにして増殖する細胞は、「エサを取り込む口」であるホルモン受容体をもっています。抗エストロゲン薬はこのホルモン受容体にくっつき、エス卜口ゲンを取り込むのを邪魔しますので、がん細胞の増殖が抑えられます。抗エストロゲン薬にはタモキシフェン(ノルバデックス)、トレミフェン(フェアストン)などがあります。
(3)その他のホルモン剤
上記以外にも間接的に体内のエス卜口ゲンの量を調節することで、がんの増殖を抑える薬として、酢酸メド口キシプロゲステロン(ヒスロンH)があります。進行・再発乳がんで、他のホルモン療法が効かなくなったときに使用します。
ホルモン療法は何をどれくらい行えばよいのか?
手術後のホルモン療法としては、閉経前ではLH-RHアゴ二ス卜製剤(2年以上)と抗エストロゲン剤(5年)、閉経後ではアロマターゼ阻害薬(5年)と抗エストロゲン剤を用います。進行・再発乳がんでは、原則として効果がある間は続けます。
ホルモン療法は、エス卜口ゲンを取り込んで増殖する性質がある乳がんに効果がありますので、手術後に実施することで再発を予防する効果が期待でき、進行・再発乳がんでは進行を抑える効果が期待できます。
抗エストロゲン薬のタモキシフェン(ノルバデックス)は、閉経前・後に関係なく用いますが、LH-RHアゴ二スト製剤は閉経前に、アロマターゼ阻害薬は閉経後に使用します。
閉経とは、年齢が60歳以上か45歳以上で、過去1年以上月経がない場合か、あるいは両側の卵巣を摘出している場合のことです。そうでなく、閉経しているかどうか分からない場合は、血液中のエストロゲンと卵胞刺激ホルモンを測定して判断します。
・閉経前
卵巣でのエストロゲン合成を抑えるために、LH-RHアゴ二ス卜製剤を1カ月に1回、または3カ月に1回、皮下に注射します。治療は2~5年間継続するのが一般的です。再発を抑制する効果は、抗がん剤と併用しない場合に比べて20~30%くらいです。これは、仮に再発する人が100人いたとしたら、全員がこの治療を受けることで70~80人に減らせるという意味です。
抗がん剤CMFを6力月間投与する治療と、LH-RHアゴ二ス卜製剤を2年間使用する治療を比べると、再発抑制効果はほぼ同等です。LH-RHアゴ二スト製剤とタモキシフェンを併用する治療は、ACやCAFの再発抑制効果とほぼ同等です。LH-RHアゴ二スト製剤に加えて、タモキシフェンを1日1回、5年間服用します。
・閉経後
アンドロゲンからエストロゲンを作る過程で働く、アロマターゼを阻害するアロマターゼ阻害薬を使います。アロマターゼ阻害薬は新薬が相次いで出されており、2009年現在でアナストロゾール(アリミデックス)、レトロゾール(フェマーラ)、エキセメスタン(アロマシン)の3種類(いずれも内服薬)があります。この3種類の薬の効果は、ほとんど同じとされています。
アロマターゼ阻害薬を手術後早期から5年間服用すると、タモキシフェンを5年間服用するのと比べて、再発する可能性を5年間で17~19%改善することが報告されています。また、タモキシフェンを2~3年間服用している患者さんが、途中でアロマターゼ阻害薬に変更し合計5年間服用する方法や、タモキシフェンを5年間服用後にアロマターゼ阻害薬に変更して、2~5年服用する方法も有効であることがわかってきています。
・転移・再発後
転移・再発した患者さんには、閉経前では、LH-RHアゴ二ス卜製剤をタモキシフェンの内服と同時に行うことが、最も効果が高いと報告されています。効果が続いているかぎり同じ治療を続けます。
一方、閉経後では、アロマターゼ阻害薬がタモキシフェンと同等か優れていると考えられます。タモキシフェンの代わりにアロマターゼ阻害薬を使うこともあり、タモキシフェンの効果がなくなったときにはアロマターゼ阻害薬に、アロマターゼ阻害薬の効果がなくなったときにはタモキシフェンに切り替えて使用します。
アロマターゼ阻害薬やタモキシフェンの効果がなくなってきたときには、酢酸メドロキシプロゲステロン(ヒスロンH)を使用します。
ホルモン剤にはどのような副作用があるのか?その対処法は?
ホルモン剤の副作用としてホットフラッシュ、生殖器の症状、関節や骨・筋肉の症状などが出ることがあります。それぞれの対処法を参考にし、担当医や看護師、薬剤師に相談しましょう。
・ホットフラッシュ(ほてり、のぼせ)
ホットフラッシュは血液中のエストロゲン(=女性ホルモン)が少なくなり、体温調節がうまくできなくなるために起こります。更年期の症状としてよく知られていますが、ホルモン療法はエストロゲンを抑える作用がありますので、同じ症状が出ます。
ホットフラッシュの症状は突然かっと暑くなったり、汗をかいたり、胸から顔面にかけて赤くなったりすることなどです。動悸や不安、睡眠障害などを伴うこともあります。
ホルモン療法によるホットフラッシュは軽いものも含めると、50%以上の患者さんに出現しますが、症状は次第に軽減しますので、しばらく経過をみるのがよいでしょう。
<対処法>
服装の工夫や運動などを日常生活に取り入れてみましょう。頻繁にホットフラッシュが起こったり、夜眠れなかったりして、仕事や日常生活に支障を起こす場合は、薬によって症状を和らげることもできます。
ビタミンE、セロト二ン作動性抗うつ薬であるパロキセチン(パキシル)やvenlafaxine(未承認)、抗てんかん薬であるガバペンチン(ガバペン)、降圧薬であるク口ニジン(力タプレス)等によって、ホットフラッシユの頻度が3~6割低下するという報告があります。ただし、上記の薬は保険適応外であり副作用もありますので、担当医と相談しましょう。
パロキセチンはタモキシフェン(ノルバデックス)の効果を弱めてしまうため、タモキシフェンと一緒に内服することはできません。
更年期症状としてホットフラッシュが出たときには、その対処方法として、エストロゲン補充療法を行うことがありますが、乳がん患者さんには、再発を増加させる危険性があるので行うべきではないといえます。アロマターゼ阻害薬は、ホットフラッシュの発生する頻度がタモキシフェンより低いことがわかっていますので、閉経後の患者さんではアロマターゼ阻害薬に変更するのも検討すべきといえます。
・生殖器の症状
性器出血、膣分泌物の増加、膣の乾燥、膣炎などの症状が現れることがあります。また、タモキシフェンにより、子宮体がんになる危険性が2~3倍増えるといわれています。しかし、もともと800人に1人くらいの割合で子宮体がんになる可能性が、800人に2~3人に増えるくらいで頻度は非常に低く、タモキシフェンによる再発予防効果の利益のほうが大きいと考えられています。
<対処法>
定期的な検診により、早期に子宮体がんを発見できる可能性が高くなりますので、タモキシフェン内服中は1年に1回くらい婦人科検診を受けましょう。不規則な性器出血や下腹部の痛みなどがある場合には婦人科を受診し、経膣超音波検査などを受けるとよいでしょう。
・血液系への影響
タモキシフェンや酢酸メドロキシプ口ゲステロン(ヒスロンH)では、血液が固まりやすくなるため、下肢の静脈に血栓(血の塊)ができたり、血栓が肺に流れていき、血管がつまる「肺動脈塞栓症」を起こしたりすることが非常にまれにあります。そのため、静脈血栓症の既往のある患者さんではこれらの薬は使えません。
・関節や骨・筋肉の症状
エストロゲンは骨を健康的に保つように働いています。アロマターゼ阻害薬やLH-RHアゴ二スト製剤はエストロゲンを減らすため、骨密度が低下し、骨折を起こす可能性があります。
また、アロマターゼ阻害薬では、関節のこわばりや関節の痛みなどの症状が出現することがありますが、特に何も対処しなくても、ほとんどの患者さんで症状は改善します。一方、タモキシフェンは骨に対して保護的に働きますので、骨が丈夫になります。
<対処法>
アロマターゼ阻害薬を内服している場合や、抗がん剤治療等によって早い時期に閉経となった場合には、年に1回の骨密度測定を行い、骨密度をチェックしましょう。
骨を強くするためにカルシウムやビタミンDを多く含む食品の摂取や、定期的な運動を心がけるとよいようです。骨密度が低下している場合には、ビスフォスフォネー卜という薬を内服したり、タモキシフェンに変更したりすることで、骨密度の低下や骨折を予防できます。
・精神・神経の症状
ホルモン療法により、頭痛、気分が落ち込む、イライラする、やる気が起きない、眠れないなどの症状が現れることがあります。睡眠薬や気分を安定させる薬が処方されることがあります。カウンセリングという方法もありますので、担当医と相談しましょう。
以上、乳がんで使われるホルモン療法についての解説でした。
私がサポートしている患者さんでもホルモン療法を受けている方は多くいます。抗がん剤に比べて副作用が少なく、長く使える場合もありますが、体にダメージはありますし、「がんを治す薬」ではありません。
乳がんを克服するためには総合的なアプローチが必要です。