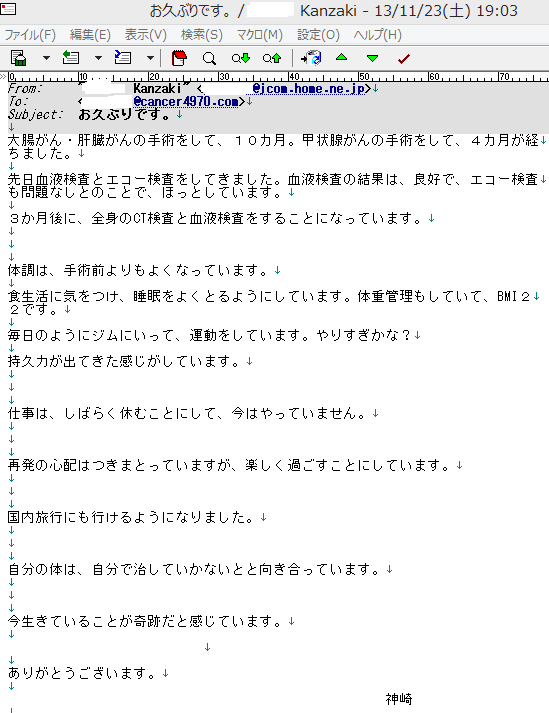人工肛門(ストーマ)を造設することになったとき、多くの方が「これからの生活はどうなるのだろう」と不安を感じることでしょう。しかし、2025年現在、ストーマ装具の技術向上と充実した支援制度により、ストーマがあっても以前とほぼ変わらない生活を送ることが可能です。この記事では、人工肛門術後の生活について、最新の情報を交えながら詳しく解説します。
人工肛門(ストーマ)とは何か
ストーマの基本的な構造
人工肛門(ストーマ)とは、腸の一部をお腹の壁を通して体の外に出し、肛門に代わる便の出口としたものです。ストーマは1~2cm程度皮膚から腸が突き出た形になっており、腸の内側部分(粘膜)が表面に出るように裏返して皮膚と縫い合わせています。
ストーマの表面は口の中と同じような粘膜でできており、皮膚と比べて柔らかく、赤い色をしています。粘膜には痛みを感じる神経がないため、軽く触れたり装具を装着する際に接触しても痛みを感じることはありません。ただし、強くこすると出血することがあるため、取り扱いには注意が必要です。出血した場合は、軽く押さえておくと止まります。
人工肛門の種類と特徴
人工肛門には大きく分けて以下の種類があります:
造設期間による分類
- 永久人工肛門:直腸切断術などで永続的に使用するもの
- 一時的人工肛門:腸閉塞や縫合不全の治療のため一時的に造設するもの
構造による分類
- 単孔式:腸管の一端を外に出したもの(永久人工肛門に多い)
- 双孔式:腸管を二つの孔として外に出したもの(一時的人工肛門に多い)
部位による分類
- 結腸ストーマ(コロストミー):結腸を用いて造設
- 回腸ストーマ(イレオストミー):回腸を用いて造設
2025年現在、日本では永久的なストーマを造設された方が22万人を超えており、多くの方がストーマとともに充実した生活を送っています。
人工肛門術後の生活における基本的な管理
オストメイトとしての新しい生活
人工肛門を造設した人のことを「オストメイト」と呼びます。オストメイトになると、従来の肛門からの排便とは全く異なる新しい排便習慣に慣れる必要があります。これは大きな変化ですが、適切な知識と技術を身につけることで、快適な生活を送ることができます。
人工肛門には肛門括約筋がないため、本来の肛門のように意識的に「締める・緩める」ことによる排便コントロールができません。そのため、便やガスがいつ出るかわからない状態になります。
ストーマ装具による管理
排便管理のために、常に専用の袋状の装具(パウチ)を人工肛門に装着します。この装具により、便の受け皿として機能し、日常生活を安全に送ることができます。
ストーマ装具は以下の部品で構成されています:
- 面板(皮膚保護剤):ストーマ周囲の皮膚に直接貼り付ける板状の部品
- ストーマ袋(パウチ):排泄物を受け止める袋
装具には以下の重要な機能があります:
- 皮膚保護作用:排泄物から皮膚を守る
- 水分吸収作用:汗や排泄物の水分を吸収
- 密着作用:皮膚にしっかりと密着
- 防臭・防水効果:においの発生や漏れを防ぐ
排便パターンと管理方法
ストーマからの排便は常にだらだらと出続けるわけではありません。S状結腸人工肛門の場合、排便は通常1日2~3回程度で、食事の2時間後程度に排泄されることが多いです。イレオストミー(回腸ストーマ)の場合は、より頻繁で液状の排泄物となります。
ガスや便がたまったら、パウチの下部にある排出口からトイレに捨てます。パウチ自体は数日に1回(一般的に週2回程度)交換します。
人工肛門術後の生活における日常生活の工夫
生活制限のない自由な暮らし
2025年現在、人工肛門があることによる日常生活の制限はほとんどありません。以下のような活動も問題なく行えます:
- うつぶせ寝:ストーマを圧迫しない程度であれば可能
- 入浴:装具を装着したまま湯船に浸かることができる
- スポーツ:激しい接触を避ければ多くのスポーツが可能
- 旅行:事前の準備により快適に旅行を楽しめる
- 仕事:職種により配慮が必要な場合もあるが、多くの職業で継続が可能
入浴時の注意点と工夫
入浴については、以下の方法があります:
装具を装着したままの入浴
- 装具には防水効果があるため、そのまま湯船に浸かることができる
- ストーマ内側から外に向かって常に圧力がかかっているため、お湯が体内に入ることはない
- 入浴前にストーマ袋の排泄物を空にしておく
- 入浴後は装具の水分をタオルでよく拭き取る
装具を外しての入浴
- S状結腸ストーマの方で便が出ない時間帯に可能
- 排便のタイミングを把握してから実施することが重要
- 万が一の場合に備えて、専用のキャップを用意しておく
温泉や銭湯での配慮
公共の入浴施設を利用する際には、以下の工夫をする方が多いです:
- 肌色のパッチでストーマを目立たなくする
- 入浴用の小さな装具やキャップを使用する
- オストメイト対応の施設を事前に調べる
外出時の準備と注意点
外出時には以下の用品を携帯することをお勧めします:
- 予備の装具(面板とパウチ)
- 清拭用品(ウェットティッシュなど)
- ビニール袋(使用済み装具の処理用)
- はさみ(面板のサイズ調整用)
- オストメイトマーク(必要に応じて)
2025年現在、オストメイト対応トイレの設置が全国的に進んでおり、外出先でも安心して装具の交換や処理ができる環境が整いつつあります。
最新のストーマ装具技術と種類
装具の種類と選択
2025年現在のストーマ装具は大幅に改良され、以下の種類があります:
構造による分類
- ワンピース型:面板と袋が一体化したタイプ
- ツーピース型:面板と袋が分離できるタイプ
機能による分類
- クローズド型:使い捨てタイプ
- ドレーナブル型:排出口があり、内容物を排出できるタイプ
- ウロストミー用:尿路系ストーマ専用
最新装具の優れた機能
現在の装具には以下のような優れた機能が搭載されています:
- 高密着性:皮膚との密着性が向上し、漏れのリスクが大幅に軽減
- 脱臭フィルター:活性炭を内蔵したフィルターによりにおいを抑制
- 防水・防臭効果:完全防水で臭いの漏れを防止
- 肌に優しい素材:アレルギーのリスクを軽減する素材を使用
- 目立ちにくいデザイン:肌色で薄型、衣服の下でも目立たない
専用アクセサリーの充実
装具の使い勝手を向上させる専用アクセサリーも豊富に開発されています:
- 皮膚保護ペースト:ストーマ周囲の隙間を埋める
- 皮膚保護パウダー:軽度の皮膚トラブルに対応
- 剥離剤:装具を優しく剥がすための溶剤
- 消臭剤:パウチ内のにおいを抑える
- 固定具:装具の密着性を高める補助具
- ベルト類:装具を固定するサポートベルト
ストーマケアの専門サポート体制
ストーマ外来による専門ケア
2025年現在、多くの大規模病院で「ストーマ外来」が設置されています。ここでは、日本看護協会が認定したストーマ管理の専門資格を持った看護師(皮膚・排泄ケア認定看護師、WOCナース)が、患者さん一人ひとりのストーマの状態に合わせた個別指導を行います。
ストーマ外来で受けられるサービス
- 装具の選択と調整に関するアドバイス
- スキントラブルの予防と対処法の指導
- 日常生活における具体的な工夫の提案
- 心理的サポートとカウンセリング
- 最新装具の情報提供と試用
自分が通院している病院にストーマ外来がない場合でも、他の医療機関のストーマ外来を受診することが可能です。積極的に専門的なサポートを求めることをお勧めします。
ストーマ・トラブルの予防と対処
よくあるストーマトラブルには以下があります:
皮膚トラブル
- 接触性皮膚炎:便の漏れによる皮膚の炎症
- 機械的皮膚炎:装具の圧迫や摩擦による皮膚トラブル
- アレルギー性皮膚炎:装具の材質による皮膚反応
ストーマの合併症
- ストーマヘルニア:腸が必要以上に飛び出す状態
- ストーマ脱出:ストーマが過度に突出する
- ストーマ狭窄:ストーマの開口部が狭くなる
これらのトラブルは、適切な装具の選択とケア技術の習得により多くの場合で予防・改善が可能です。
人工肛門術後の生活における食事と栄養管理
基本的な食事の注意点
ストーマがあっても、基本的には従来通りの食事を楽しむことができます。ただし、以下の点に注意が必要です:
水分摂取の重要性
排尿・排便量を抑えるために水分摂取を控えることは避けましょう。十分な水分摂取は、脱水予防と感染症予防に重要です。特に回腸ストーマの方は、水分と電解質の喪失が多いため、より注意深い水分管理が必要です。
食物繊維の摂取について
食物繊維を多く含む食品を一度に大量摂取すると、繊維がストーマに引っかかって便の排出が滞る「フードブロッケージ」が起こる可能性があります。以下の食品は注意が必要です:
- きのこ類(えのき、しめじなど)
- 海藻類(わかめ、昆布など)
- 果物の皮や筋(りんごの皮、オレンジの筋など)
- 野菜の繊維質な部分(セロリ、ごぼうなど)
これらの食品を完全に避ける必要はありませんが、よく噛んで少量ずつ摂取することが大切です。
ガス産生を抑える食事の工夫
ガスの発生を抑えるための食事の工夫:
ガスを発生しやすい食品
- 炭酸飲料
- 豆類(大豆、小豆など)
- 芋類(さつまいも、じゃがいもなど)
- アブラナ科野菜(キャベツ、ブロッコリーなど)
- 乳製品(乳糖不耐症の場合)
食事の方法
- ゆっくりと良く噛んで食べる
- 早食いや大食いを避ける
- 食事中の会話を控えめにして空気の摂取を減らす
- 規則正しい食事時間を心がける
身体障害者手帳の申請と福祉制度
身体障害者手帳の申請プロセス
永久人工肛門を造設した方は、通常「膀胱・直腸機能障害」として身体障害者手帳の対象となります。2025年現在の申請プロセスは以下の通りです:
申請の準備
- お住まいの市区町村の福祉担当窓口(福祉課、福祉事務所)で申請書類を入手
- 必要書類:
- 身体障害者手帳交付申請書
- 身体障害者診断書・意見書(膀胱・直腸用)
- 写真(縦4cm×横3cm)
- 印鑑
- マイナンバーカードまたは通知カード
診断書の作成
膀胱・直腸機能障害の指定医に診断書の作成を依頼します。手術を行った病院の医師が指定医でない場合は、福祉担当窓口で指定医を紹介してもらえます。
申請から交付まで
申請から手帳交付まで1~2か月程度かかります。永久ストーマの場合、通常は4級の手帳が交付されますが、造設から6か月経過後の状態によっては1級や3級への変更申請も可能です。
ストーマ装具の給付制度
身体障害者手帳が交付されると、「日常生活用具給付制度」によりストーマ装具の給付を受けることができます。
給付内容(2025年現在)
- 消化管系ストーマ:月額約8,858円
- 尿路系ストーマ:月額約11,639円
- 給付対象:ストーマ装具、皮膚保護用品、洗腸用具など
- 自己負担:原則として購入費の1割(所得に応じて減免あり)
申請手続き
- 身体障害者手帳と印鑑を持参し、日常生活用具費支給申請書に記入
- 指定販売業者に見積書を発行してもらい提出
- 自治体から支給決定通知書と給付券が送付される
- 給付券と引き換えに装具を受け取り、自己負担額を支払う
その他の福祉サービス
身体障害者手帳により以下のサービスを受けることができます:
交通機関の運賃割引
- JR・私鉄:普通乗車券5割引(片道100km超)
- バス・タクシー:運賃割引
- 国内航空運賃:割引
- 有料道路通行料:割引
税制上の優遇
- 所得税・住民税:障害者控除
- 自動車税・軽自動車税:減免
- 相続税・贈与税:特別控除
その他のサービス
- 公共施設入場料の割引
- 携帯電話使用料の割引
- NHK受信料の減免
- 郵便料金の減額
医療費控除と障害年金
医療費控除の活用
ストーマ装具の購入費は医療費控除の対象となります:
- 医師発行の「ストーマ装具使用証明書」が必要
- 年間10万円(所得200万円未満の場合は所得の5%)を超える医療費が対象
- 5年間遡及して申告可能
- 確定申告により税金の還付を受けられる
障害年金の受給
ストーマを造設した方は、以下の条件で障害年金を受給できる場合があります:
- 国民年金加入者:障害基礎年金
- 厚生年金加入者:障害厚生年金
- 受給額は障害等級と加入期間により決定
- 詳細は年金事務所または市区町村の年金担当窓口で確認
オストメイト支援団体と情報ネットワーク
日本オストミー協会の活動
公益社団法人日本オストミー協会は、オストメイトとその家族を支援する全国組織です。2025年現在、全国に支部があり、以下のような活動を行っています:
- オストメイト同士の交流会・勉強会の開催
- 最新の装具情報や生活の工夫に関する情報提供
- 医療機関や行政への要望活動
- オストメイト対応トイレの普及促進
- 若い世代の交流グループ「20/40フォーカスグループ」の運営
専門的な相談窓口
ストーマに関する相談は以下の窓口で受けることができます:
- ストーマ外来がある医療機関
- がん診療連携拠点病院の相談支援センター
- 日本オストミー協会の各支部
- 一般社団法人日本創傷・オストミー・失禁管理学会
- 市区町村の障害福祉担当窓口
若い女性オストメイト向けサポート
若い女性オストメイト向けには「ブーケ(若い女性オストメイトの会)」があり、結婚、出産、育児、就職といった女性特有の悩みについて情報交換や相談ができる場を提供しています。
仕事復帰と社会参加
職場復帰への準備
ストーマ造設後の職場復帰は多くの場合可能ですが、以下の準備が重要です:
復帰前の準備
- ストーマケアの技術習得と安定
- 装具交換のタイミングと所要時間の把握
- 職場での装具交換場所の確認
- 緊急時の対応策の準備
- 必要に応じて産業医との相談
職場での配慮事項
- トイレ使用時間の延長への理解
- 重量物取り扱いの制限(ストーマヘルニア予防)
- 定期通院のための時間調整
- ストレス軽減への配慮
就職支援制度
身体障害者手帳を持つオストメイトは、以下の就職支援を受けることができます:
- ハローワークでの専門相談
- 障害者雇用枠での就職
- 就職困難者として失業給付期間の延長
- 職業訓練の優先受講
- 就労移行支援事業の利用
災害時の備えと対策
災害時用の備蓄
2025年現在、自然災害への備えがより重要視されています。オストメイトの方は以下の災害用備蓄を準備しておくことをお勧めします:
必需品の備蓄(最低7日分)
- ストーマ装具(面板・パウチ)
- 皮膚保護用品(ペースト、パウダーなど)
- 清拭用品(ウェットティッシュ、タオル)
- はさみ(装具カット用)
- ビニール袋(廃棄用)
- 常用薬
- 身体障害者手帳のコピー
- オストメイト携帯カード
避難時の注意点
避難所生活では以下の点に注意が必要です:
- プライバシーを確保できる場所での装具交換
- 避難所担当者への状況説明
- 医療従事者との連携
- ストーマ用品の補給ルートの確保
スポーツと趣味活動
参加可能なスポーツ
ストーマがあっても多くのスポーツを楽しむことができます:
推奨されるスポーツ
- ウォーキング・ジョギング
- 水泳(防水装具使用)
- サイクリング
- ゴルフ
- テニス(非接触スポーツ)
- ヨガ・ピラティス
注意が必要なスポーツ
- 格闘技(接触により装具が外れるリスク)
- 重量挙げ(ストーマヘルニアのリスク)
- 激しい接触を伴う球技
スポーツ時の装具選択
スポーツを行う際は以下の装具を選択することをお勧めします:
- 密着性の高い装具
- 防水性に優れた装具
- 動きを妨げない柔軟な素材
- 必要に応じて固定ベルトの併用
旅行と外出の楽しみ方
旅行の事前準備
ストーマがあっても安心して旅行を楽しむための準備:
国内旅行
- 普段使用している装具の十分な持参
- 旅行先のオストメイト対応施設の確認
- 医療機関の場所の把握
- 保険証・身体障害者手帳の携帯
海外旅行
- 英文の診断書・携帯カードの準備
- 装具の十分な持参(手荷物と預け荷物に分散)
- 現地での装具入手先の確認
- 海外旅行保険の加入
- 税関での説明用英文書類
航空機利用時の注意点
飛行機を利用する際の特別な配慮:
- 事前にカットした面板の機内持ち込み(刃物持ち込み制限のため)
- 気圧変化によるパウチの膨張への対応
- 長時間フライト時の装具交換タイミング
- 必要に応じて航空会社への事前連絡
家族・パートナーとの関係
家族への説明と理解促進
ストーマ造設後の家族関係を良好に保つために:
- ストーマの基本的な知識の共有
- 日常ケアの方法の説明
- 緊急時の対応方法の指導
- 心理的サポートの重要性の理解
- 必要に応じて家族向け勉強会への参加
パートナーシップの維持
夫婦・パートナー関係において重要な点:
- オープンなコミュニケーション
- 外見的変化への相互理解
- 性生活に関する十分な話し合い
- 必要に応じて専門カウンセラーへの相談
- 新しい生活スタイルへの適応
心理的サポートとメンタルケア
ストーマ造設による心理的影響
ストーマ造設は患者さんに大きな心理的影響を与えることがあります:
一般的な心理的反応
- ボディイメージの変化への戸惑い
- 将来への不安
- 社会復帰への心配
- 自尊心の低下
- 孤立感や疎外感
心理的サポートの重要性
適切な心理的サポートにより、多くの方が前向きな生活を取り戻すことができます:
- 専門カウンセラーによるカウンセリング
- 同じ経験を持つピアサポーター との交流
- 家族・友人からの理解と支援
- 段階的な社会復帰プログラム
- 生きがいや目標の再発見
最新の研究と今後の展望
装具技術の進歩
2025年現在も装具技術の研究開発が続いており、以下のような進歩が期待されています:
- より高性能な皮膚保護剤の開発
- 長期装着可能な装具
- IoT技術を活用したスマート装具
- 環境に優しい生分解性素材の採用
- 個人の体型に完全にフィットするオーダーメイド装具
再建手術の進歩
一時的ストーマの方向けに、腸管再建手術の技術も向上しています:
- 腹腔鏡下での低侵襲再建手術
- ロボット支援手術の普及
- 術後合併症の軽減
- 機能温存技術の向上
まとめ
人工肛門術後の生活は、適切な知識と技術、そして充実した支援制度により、以前とほぼ変わらない充実した日々を送ることが可能です。2025年現在、ストーマ装具の技術は大幅に向上し、様々な生活場面に対応できるようになっています。
重要なのは以下の点です:
- 正しいストーマケア技術の習得
- 自分に適した装具の選択
- 専門医療スタッフとの連携
- 身体障害者手帳による支援制度の活用
- オストメイト同士の情報交換
- 家族・友人の理解と協力
- 前向きな生活態度の維持
現在日本では22万人を超える方がストーマとともに生活しており、多くの方が仕事、趣味、旅行、スポーツなどを楽しんでいます。医療技術の進歩と社会的理解の向上により、オストメイトを取り巻く環境は確実に改善されています。
ストーマ造設直後は不安が大きいかもしれませんが、適切なサポートを受けながら段階的に慣れていけば、必ず快適な生活を送ることができます。一人で悩まず、医療スタッフ、患者会、家族などの支援を積極的に活用し、新しい生活に向けて歩んでいくことが大切です。
参考文献・出典情報
- ストーマ(人工肛門)について|WOC支援室|がん研有明病院
- 【コラム】人工肛門(ストーマ)のある生活
- 大腸がんの術後生活とケア ストーマと上手に付き合うコツ – がんプラス
- 【はじめての方へ】ストーマ(人工肛門・人工膀胱)のケアと生活上の注意点 - LIFULL 介護
- 身体機能の喪失~66歳男性 直腸がんの場合~ | 小野薬品 がん情報 一般向け
- ストーマ(人工肛門‧人工膀胱)のケア方法と日常生活の工夫|アピアランスケア|がんになっても
- 手術後のストーマケアはどう進めるか | メディカルノート
- 社会福祉制度について|ストーマ装具販売。給付券の申請から利用までサポートします。株式会社ザイタック
- 利用者向けページ(日常生活用具) 横浜市
- ストマ装具等の代金と治療費がかかり大変だ。
- 日常生活用具の給付券申請 | ストーマ・ライフ
- 身体障害者手帳 | ストーマ・ライフ
- 主な福祉制度 | 日本オストミー協会
- 人工肛門を作ったのですが、ストマ用装具は給付されますか|金沢市公式ホームページ
- MPI - 社会福祉制度について