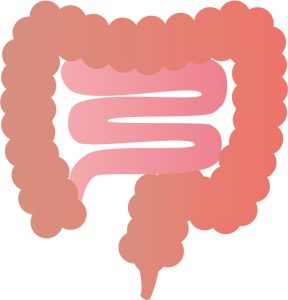
大腸がんは結腸から発生する結腸がんと、直腸から発生する直腸がんに分けられ、これらを総称して大腸がんと呼ばれています。現在、大腸がんは日本で最も多いがんとなっており、早期発見・早期治療により完治可能な病気として知られています。
大腸がんの進行は他のがんと比較すると比較的緩やかで、早期に発見して適切な治療を受ければ、再発するリスクを大幅に減らすことができます。しかし近年、日本での大腸がんの患者数は急激に増加しており、2020年の統計では年間約15万人が新たに大腸がんと診断されています。
2022年の最新統計によると、大腸がんによる年間死亡者数は5万3,088人(男性28,099人、女性24,989人)に達しており、女性では大腸がんがすべてのがんによる死亡原因の第1位、男性では第2位となっています。この数字は1950年の男性1,819人、女性1,909人と比較すると、70年余りで約28倍という驚異的な増加を示しています。
大腸がんの主な原因と危険因子
大腸がんの原因は多岐にわたりますが、最も大きな要因として食生活の欧米化が挙げられています。特に高脂肪、高カロリー、そして食物繊維の少ない食事が大腸がんのリスクを高めることが分かっています。
食生活に関わる原因
食生活の変化は大腸がん増加の最大の要因です。牛肉や豚肉などの赤肉、ハムやソーセージなどの加工肉の摂取量増加により、大腸がんのリスクが高まることが科学的に証明されています。また、アルコールの大量摂取も確実な危険因子として認識されています。
反対に、食物繊維を多く含む野菜や果物の摂取、適度な身体活動は大腸がんのリスクを下げる効果があります。バランスの取れた食事と健康的な生活習慣を心がけることが予防につながります。
年齢と遺伝的要因
大腸がんの発症リスクは50歳以上から急激に高まり、発症のピークは60歳代となっています。高齢化社会の進展により、この年代の人口が増加していることも、大腸がん患者数増加の一因となっています。
家族に大腸がんの既往歴がある場合、遺伝的要因によりリスクが高くなりますが、家族性大腸がんの割合は全体の5%以下とわずかです。むしろ生活習慣や環境要因の影響が大きいことが分かっています。
その他のリスク要因
過去に大腸ポリープを経験したことがある人は、再発のリスクが高くなります。また、肥満、運動不足、慢性的な便秘も大腸がんのリスクを高める要因として知られています。
喫煙は大腸がんを含むすべてのがんの重大な危険因子であり、禁煙は大腸がん予防の重要な取り組みです。
最新の研究から分かった原因
最近の研究により、リトコール酸という物質が新たな大腸がんの原因として注目されています。胆汁酸が腸内細菌により変化したリトコール酸は発がん性物質であり、腸の粘膜を刺激してがん化を促進します。
この現象を防ぐには、ビタミンDとビタミンCの摂取が効果的であることが分かってきました。これらのビタミンは大腸粘膜を保護し、リトコール酸の有害な作用を抑制する働きがあります。
大腸がんが発生する仕組みと進行パターン
大腸がんは、大腸の内側の表面にある粘膜の細胞から発生します。正常な粘膜細胞が何らかの原因でがん細胞に変化し、それが分裂・増殖を繰り返すことで目に見える腫瘍となります。
大腸がん発生の2つの経路
現在、大腸がんの発生には主に2つの経路があると考えられています。
第一の経路は「腺腫~がん連関」と呼ばれるもので、良性の大腸ポリープ(腺腫)が発がん刺激を受けてがん化する過程です。この経路による大腸がんが全体の大部分を占めています。
第二の経路は、正常な粘膜から直接がんが発生する「デノボがん」です。この発生メカニズムについては、まだ完全には解明されていませんが、研究が進められています。
大腸がんができやすい部位
大腸は全長約1.5~2メートルの長い臓器ですが、がんの発生には明確な傾向があります。最新のデータによると、直腸に35%、S状結腸に34%と、肛門から30センチメートル以内の部位に約70%の大腸がんが集中しています。
その他の部位では、上行結腸11%、横行結腸9%、盲腸6%、下行結腸5%の順となっています。この傾向は世界共通であり、便が長時間滞留する部位ほど発がん物質にさらされる時間が長いためと考えられています。
大腸ポリープと大腸がんの関係
大腸ポリープは粘膜にできるイボ状の病変の総称です。このうち、がん化する可能性があるのは腺腫と呼ばれるタイプです。
腺腫のサイズが1センチメートルを超えるとがん化の可能性が高くなり、2センチメートルを超えると更にリスクが増加します。ただし、1センチメートル以下の小さな腺腫でもがん化することがあるため、発見された場合は定期的な経過観察が必要です。
内視鏡検査で切除したポリープに一部がん化した部分が見つかることがあり、これを「腺腫内がん」と呼びます。この段階で発見・治療できれば、再発リスクは非常に低くなります。
大腸がんの自覚症状 - 部位別の違いと進行度による変化
大腸がんの最も重要な特徴は、早期段階ではほとんど自覚症状がないことです。症状が現れた時には既にある程度進行していることが多いため、定期的な検診による早期発見が極めて重要です。
大腸がんの代表的な症状
大腸がんが進行すると、主に「出血」「便通異常」「腸閉塞」という3つの症状が現れます。
出血による症状
がんによる潰瘍が形成されると出血が始まります。初期は微小な出血のため肉眼では確認できませんが、進行すると明らかな血便として認識できるようになります。
便が通過する際にがんの表面がこすられることで出血が起こりますが、一度に大量出血することは稀です。そのため気づかないうちに慢性的な出血が続き、貧血症状で発見されることもあります。
便通異常
がんが大きくなると大腸の内腔が狭くなり、便の通過障害が生じます。その結果、便秘や便が細くなる症状が現れます。
硬い便は狭い部分を通過できないため、軟らかい便のみが少しずつ出るようになり、下痢と感じることもあります。また、狭窄部位より上流に便が溜まることで腹部膨満感や腹痛を生じることがあります。
腸閉塞
がんが大腸内腔を完全に塞ぐと腸閉塞(イレウス)という緊急事態となります。便やガスが排出されず、腸管内に蓄積することで激しい腹痛や嘔吐を引き起こします。
腸閉塞は緊急手術が必要な状態であり、腸管穿孔などの重篤な合併症を防ぐため迅速な対応が求められます。
部位別の症状の特徴
右側結腸(盲腸・上行結腸・横行結腸)のがん
右側の結腸にできたがんは、症状が現れにくいという特徴があります。この部位では便がまだ液状であり、腸管も太いため、がんによる狭窄があっても通過障害を起こしにくいからです。
また、出血があっても肛門までの距離が長いため、血液成分が分解されてしまい、血便として認識しにくくなります。そのため、原因不明の貧血や腹部腫瘤として発見されることが多く、診断時には既に進行していることがあります。
代表的な症状は、腹部の鈍痛、慢性貧血、黒色便です。これらの症状は軽微なことが多く、見落とされがちなため注意が必要です。
左側結腸(下行結腸・S状結腸)と直腸のがん
左側の結腸や直腸にできたがんは、比較的症状が現れやすい傾向があります。この部位では便が固形化しており、腸管も細いため、がんによる影響が現れやすいからです。
代表的な症状は、鮮血便や血液・粘液が付着した便、便の狭小化、便秘と下痢の交代などです。特に直腸がんでは、排便後の残便感や頻回の便意も特徴的な症状です。
進行した大腸がんの全身症状
がんが進行すると、局所症状に加えて全身症状も現れます。慢性的な出血による貧血症状(動悸、息切れ、めまい、易疲労感)、食欲不振、体重減少、発熱などが代表的です。
また、肝臓や肺への転移により、これらの臓器に腫瘤が発見されることで大腸がんが見つかることもあります。転移性大腸がんの場合、原発巣よりも転移巣の症状が先に現れることがあります。
便の状態から読み取る大腸がんのサイン
大腸がんによる出血は、血便の状態から発生部位をある程度推測することが可能です。日常的な便の観察は、早期発見につながる重要な手がかりとなります。
部位別の血便の特徴
1. 黒色便(タール様便):右側結腸からの出血を示唆します。便が肛門まで到達する時間が長いため、血液が酸化・変性して黒くなります。
2. 便に混じった血液:S状結腸からの出血で見られます。肉眼でも血液の混入が確認できる状態です。
3. 便の表面に付着した鮮血:直腸からの出血の特徴です。血液が新鮮なため赤い色を保っています。
4. 便と血液が分離:下部直腸や肛門近くからの出血で見られます。
血便以外の便の変化
血便以外にも、便の形状や排便習慣の変化は重要なサインです。便が細くなる、排便回数の変化、便秘と下痢の交代、残便感、排便時の腹痛などがあれば、早めに医療機関を受診することをお勧めします。
ただし、これらの症状は痔疾患や炎症性腸疾患でも見られるため、自己判断せずに専門医による診断を受けることが大切です。
大腸がんの早期発見に向けた検診と検査法
大腸がんは早期発見により治療成績が大幅に改善するがんです。40歳代から罹患者が増加するため、40歳以上の方は年1回の大腸がん検診を受けることが推奨されています。
対策型検診(便潜血検査)
現在、日本の対策型大腸がん検診では便潜血検査(免疫法)が実施されています。2日分の便を採取し、目に見えない微量の血液を検出する検査です。
最新の研究により、現在使用されている便潜血検査の感度は84%、特異度は92%と、以前と比較して大幅に向上していることが明らかになりました。定期的に受診し、陽性の場合に精密検査を受けることで、大腸がん死亡率の更なる減少が期待されています。
精密検査
便潜血検査陽性の場合や症状がある場合は、精密検査として大腸内視鏡検査が行われます。肛門から内視鏡を挿入し、直腸から盲腸まで全大腸を観察する検査で、病変の早期発見と同時に組織採取や治療も可能です。
内視鏡検査が困難な場合は、大腸X線検査(注腸検査)や大腸CT検査が選択されることもあります。
任意型検診
人間ドックなどでは、PET-CT検査や腫瘍マーカー(CEA、CA19-9)測定も行われています。これらは補完的な検査として位置づけられており、便潜血検査と組み合わせることでより精度の高い診断が可能になります。
2025年最新の大腸がん治療情報
2025年現在、大腸がんの治療は個別化医療の時代に入っており、遺伝子検査の結果に基づいた治療選択が行われています。特に進行大腸がんでは、MSI-High/dMMRの場合に免疫チェックポイント阻害薬が第一選択として使用されるようになりました。
免疫療法の進歩
2024年9月には、MSI-High/dMMRの大腸がんに対してニボルマブ(オプジーボ)とイピリムマブ(ヤーボイ)の併用療法が一次治療として承認されました。これにより、従来の化学療法では効果が限定的だった症例でも良好な治療成績が期待できるようになっています。
分子標的薬の新展開
2024年には新たな分子標的薬「ルマケラス」がKRAS G12C変異陽性の大腸がんに対して承認され、個別化治療の選択肢が更に広がりました。遺伝子変異に応じた治療戦略により、より効果的ながん治療が可能になっています。
大腸がん予防のための生活習慣
大腸がんの予防には、生活習慣の改善が最も重要です。以下の点に注意することで、発症リスクを大幅に下げることができます。
食生活の改善
食物繊維を多く含む野菜、果物、全粒穀物の摂取を増やし、赤肉や加工肉の摂取を控えめにしましょう。また、適度な飲酒に留め、禁煙を心がけることが重要です。
身体活動の維持
定期的な運動は大腸がんリスクを下げる最も効果的な方法の一つです。週150分以上の中強度の身体活動を目標に、日常生活に運動を取り入れましょう。
適正体重の維持
肥満は大腸がんのリスク要因であるため、適正体重の維持が重要です。バランスの取れた食事と規則的な運動により、健康的な体重を保ちましょう。
まとめ - 早期発見が救う命
大腸がんは現在日本で最も多いがんですが、早期発見により完治が期待できる疾患でもあります。初期段階では自覚症状がほとんどないため、40歳以上の方は定期的な検診受診が極めて重要です。
日常生活では便の状態や排便習慣の変化に注意を払い、気になる症状があれば早めに医療機関を受診しましょう。また、生活習慣の改善により発症リスクを下げることも可能です。
最新の治療法の進歩により、進行がんであっても治療選択肢が広がっています。正しい知識を持ち、適切な予防と早期発見に努めることで、大腸がんは十分に対応可能な疾患です。
初期段階で発見された大腸がんの5年生存率は約99%と非常に良好な成績を示しており、早期発見の重要性が改めて確認されています。定期検診を受診し、自分の健康を守りましょう。
参考文献・出典情報
- 日本生活習慣病予防協会. 「大腸がんによる年間死亡者数は、5万3,088人 令和4年(2022)「人口動態統計(確定数)の概況」より」. https://seikatsusyukanbyo.com/statistics/2024/010804.php
- 国立がん研究センター がん情報サービス. 「大腸がん(結腸がん・直腸がん) 治療」. https://ganjoho.jp/public/cancer/colon/treatment.html
- 国立がん研究センター がん情報サービス. 「大腸がん検診について」. https://ganjoho.jp/public/pre_scr/screening/colon.html
- オリンパス おなかの健康ドットコム. 「大腸がん検診」. https://www.onaka-kenko.com/early-detection/colorectal-cancer-screening.html
- 国立がん研究センター. 「科学的根拠に基づくわが国の大腸がん検診を提言「有効性評価に基づく大腸がん検診ガイドライン」2024年度版公開」. https://www.ncc.go.jp/jp/information/pr_release/2024/1127/index.html
- 国立がん研究センター. 「大腸がんファクトシート 2024」. https://www.ncc.go.jp/jp/icc/crcfactsheet/index.html
- 大阪市. 「大腸がん検診を受けましょう」. https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000017891.html
※本記事は2025年7月に最新情報を基に更新されました。医療情報は日々更新されるため、診断や治療については必ず医療機関で専門医にご相談ください。



