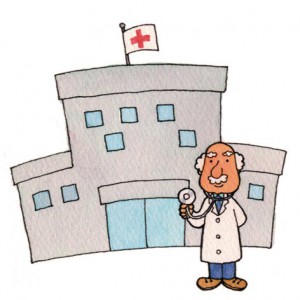【サイト内 特設ページ】

がんを治すために必要なことは、たった1つです。
詳しくはこちらのページで。
→がんを治すための「たった1つの条件」とは?
がん治療でセカンドオピニオンが必要な理由
病気になったとき、「他の病院にも行って、意見を聞きたい」と思った経験を持つ方は多いのではないでしょうか。診察結果は正しいのか、他に治療法はないのか、という疑問が浮かんだとき、別の医療機関で意見を聞きたいという気持ちが出てくるものです。
がん治療においては、医療の標準化が進み病院ごとの格差は縮小してきました。しかし、診察結果や治療法の提案については、医師の経験や専門性によって差が生じることがあります。命に関わる病気だからこそ、確かな診断と納得性のある治療法の選択が重要になります。
特に疑問点がない場合でも、複数の医師の見解を聞いたうえで納得するというステップを踏むことで、より安心して治療に臨めるようになります。患者さんご自身が主体的に治療を選択するためにも、セカンドオピニオンは有効な手段です。
セカンドオピニオンを受けるべきタイミングとは
セカンドオピニオンを受けるタイミングについて、迷う方も多いでしょう。以下のような状況では、セカンドオピニオンを検討する価値があります。
がんと診断されたとき
がんの告知を受けた直後は、心理的にも動揺している状態です。診断内容が正確かどうか、他の可能性はないかを確認するために、セカンドオピニオンを受けることは合理的な選択です。特に早期がんと進行がんでは治療方針が大きく変わるため、病期の判断について別の専門医の意見を聞くことは意義があります。
治療方針に納得できないとき
提案された治療法について、なぜその治療が選ばれたのか理解できない場合や、他に選択肢がないのか疑問に思う場合には、セカンドオピニオンを受けることで治療の必要性や妥当性を確認できます。治療法の選択は患者さんの生活の質や今後の人生設計に関わるため、納得したうえで決定することが大切です。
希少ながんや難治性のがんと診断されたとき
患者数が少ないがんや、治療が難しいとされるがんの場合、専門的な知識や経験を持つ医師の意見を聞くことが重要です。専門施設や症例数の多い医療機関でセカンドオピニオンを受けることで、最新の治療法や臨床試験の情報を得られる可能性があります。
再発や転移が見つかったとき
再発や転移が見つかった場合、初回治療とは異なる治療戦略が必要になることがあります。治療の選択肢を広げるためにも、専門医の意見を聞くことは有用です。
【サイト内 特設ページ】

がんを治すために必要なことは、たった1つです。
詳しくはこちらのページで。
→がんを治すための「たった1つの条件」とは?
セカンドオピニオンの具体的な進め方(手順)
がん治療におけるセカンドオピニオンは、以下の4つのステップで進めていきます。順を追って説明します。
ステップ1:現在の担当医に診療情報提供書の準備を依頼する
セカンドオピニオンを受ける際には、これまでの診断や治療の経過を正確に伝える必要があります。そのために必要なのが「診療情報提供書」です。
診断についてのセカンドオピニオンを聞く場合、どのような検査に基づいて診断されたのか、治療に関する場合にはどのような検査結果(がんの性格、病期、経過、病状など)に基づき、どのような治療が提案されているのかを伝える必要があります。転移や再発の場合には、それまでの治療内容も重要な情報です。
診療情報提供書には、以下のような情報が含まれます。
- 病名と診断日
- 実施した検査の種類と結果(血液検査、画像検査、病理検査など)
- がんの進行度(ステージ)
- これまでに受けた治療とその経過
- 現在の病状
- 提案されている治療方針
診療情報提供書の作成を依頼しにくいと感じる方もいるかもしれませんが、セカンドオピニオンは患者さんの権利として認められています。担当医に率直に相談してみましょう。ほとんどの医師は快く対応してくれます。
もし診療情報提供書の作成を依頼できない状況であっても、患者さんご自身が正しく説明できれば、セカンドオピニオンを聞くことは可能です。ただし、検査データや画像診断の結果など、具体的な情報があるほうが正確な意見を得られるため、できる限り資料を準備することをお勧めします。
ステップ2:セカンドオピニオンを提供してくれる医療機関を探す
セカンドオピニオンを提供している医療機関は、全国に数多くあります。探し方にはいくつかの方法があります。
インターネットで検索する方法が最も手軽です。「がん セカンドオピニオン」や「がん種名 セカンドオピニオン」などのキーワードで検索すると、多くの医療機関が見つかります。各医療機関のホームページで、セカンドオピニオン外来の有無、対応可能ながんの種類、費用、予約方法などを確認できます。
患者団体や患者支援組織の相談窓口に問い合わせる方法もあります。がん種ごとの患者会では、セカンドオピニオンを受けられる医療機関の情報を持っていることがあります。
また、現在の担当医や看護師に相談するのも一つの方法です。医療従事者は他の医療機関の情報を持っていることが多く、適切な医療機関を紹介してくれる場合があります。
がん診療連携拠点病院や地域がん診療病院では、がん相談支援センターが設置されており、セカンドオピニオンに関する相談に応じています。どこに相談すればよいか分からない場合は、このような窓口を利用するのも有効です。
医療機関を選ぶ際のポイント
セカンドオピニオンを受ける医療機関を選ぶ際には、以下の点を考慮するとよいでしょう。
| 選択基準 | 確認ポイント |
|---|---|
| 専門性 | ご自身のがん種を専門とする医師がいるか、症例数は多いか |
| 施設の規模と設備 | 最新の検査機器や治療設備があるか、臨床試験を実施しているか |
| アクセス | 通院可能な距離か、交通の便はよいか |
| 費用 | セカンドオピニオンの費用はいくらか、支払い方法は |
| 予約の取りやすさ | 予約から受診までどのくらいかかるか |
ステップ3:セカンドオピニオン外来を受診する
セカンドオピニオン外来の多くは完全予約制です。突然訪問するのではなく、事前にホームページなどで受診方法を確認し、電話やインターネットで予約を取りましょう。予約の際には、がんの種類、相談したい内容、希望する日時などを伝えます。
受診当日には、以下のものを持参します。
- 診療情報提供書
- 検査結果のコピー(血液検査、画像検査、病理検査など)
- 画像データ(CD-ROMなど)
- お薬手帳(服用中の薬がある場合)
- 質問事項をまとめたメモ
セカンドオピニオンの面談時間は、30分から1時間程度が一般的です。限られた時間を有効に使うために、聞きたいことを事前に整理しておくことが大切です。質問事項を箇条書きにしたメモを準備しておくとよいでしょう。
また、1人で受診するよりも、家族や友人に同行してもらうことをお勧めします。複数の人が聞くことで、聞き漏らしを減らすことができますし、後で内容を確認し合うこともできます。緊張していると医師の説明を十分に理解できないこともあるため、同行者がいると安心です。
面談後、セカンドオピニオンを提供した医師から担当医宛に情報提供書が出される場合があります。可能であれば、この書類に目を通しておくことも、今後の治療方針を考えるうえで役立ちます。
ステップ4:現在の担当医と相談する
セカンドオピニオンを聞いたあとは、現在の担当医に会い、得られた意見や今後についてどうしたいかという考えを伝えます。セカンドオピニオンはあくまで「意見を聞く」ことが目的であり、自動的に転院や転医になるわけではありません。
セカンドオピニオンの結果、現在の治療方針に納得できた場合は、そのまま現在の医療機関で治療を続けることができます。もし別の治療法を希望する場合や、セカンドオピニオンを提供した医療機関での治療を希望する場合は、その旨を担当医に伝えましょう。
転院や転医を希望する際は、担当医との関係が悪化することを心配する方もいますが、患者さんには医療機関や医師を選ぶ権利があります。誠実に自分の考えを伝えれば、ほとんどの医師は理解してくれます。
セカンドオピニオンの費用について
セカンドオピニオンの費用は、医療機関によって異なります。一部の医療機関では保険診療で実施していますが、多くの場合は自由診療(保険外診療)として独自の料金を設定しています。
自由診療の場合、費用は2万円から3万円程度が一般的です。面談時間や必要な資料の量によって、費用が変動することもあります。高額な場合は5万円以上かかることもあるため、事前に確認しておくことをお勧めします。
費用の支払い方法も医療機関によって異なります。当日現金払いのところもあれば、クレジットカードが使えるところもあります。予約の際に、費用と支払い方法を確認しておきましょう。
【サイト内 特設ページ】

がんを治すために必要なことは、たった1つです。
詳しくはこちらのページで。
→がんを治すための「たった1つの条件」とは?
セカンドオピニオンを受ける際の注意点
客観的な意見を求めることが大切
自分の病気に関して正しい情報を得ることは大切です。そして、正しい診断や標準治療を理解して、納得できる医療を受けることが重要です。
しかし、自分の希望に合った意見を言ってくれる医師に出会うまで、何か所もの医療機関を受診する患者さんもいます。これは「ドクターショッピング」と呼ばれる状態で、適切な治療のタイミングを逃す危険性があります。
例えば、抗がん剤治療を受けたくないと思っていても、科学的根拠に基づけば抗がん剤治療を行ったほうがよい経過をもたらす場合があります。このような場合、抗がん剤治療の専門家から効果と副作用のバランスについて正確な情報を得ることが大切です。
患者さんの希望をそのまま受け入れる医師がよい医師とは限りません。患者さんご自身がどのような治療を選択するかの判断材料として、具体的で客観的な意見を伝えることができる医師が優れた医師だといえます。
治療開始のタイミングを逃さない
セカンドオピニオンを受けること自体は有意義ですが、複数の医療機関を回っているうちに時間が経過し、治療開始が遅れてしまうことがあります。がんの種類や進行度によっては、治療の遅れが予後に影響することもあるため、適切なタイミングで決断することが必要です。
セカンドオピニオンは新たな検査や治療ではない
セカンドオピニオンは、既存の検査結果や診断に基づいて意見を提供するものです。新たな検査や治療を受けるためのものではありません。もし追加の検査や治療が必要と判断された場合は、改めて通常の診療として受けることになります。
セカンドオピニオンと転院・転医の違い
セカンドオピニオンは「意見を聞く」ことが目的であり、転院や転医とは異なります。セカンドオピニオンを受けたあとも、現在の医療機関で治療を続けることができます。
一方、転院や転医は、治療を受ける医療機関や医師を変更することを意味します。セカンドオピニオンの結果、別の医療機関での治療を希望する場合は、転院や転医の手続きを進めることになります。
オンラインでのセカンドオピニオン
2025年現在、オンライン診療の普及に伴い、オンラインでセカンドオピニオンを提供する医療機関も増えています。遠方の専門医の意見を聞きたい場合や、移動が困難な場合には、オンラインでのセカンドオピニオンが便利です。
オンラインセカンドオピニオンでは、事前に診療情報や検査データを送付し、ビデオ通話などで医師と面談します。対面での受診と同様に、質問事項を準備し、家族と一緒に参加することをお勧めします。
セカンドオピニオンを活用して納得できる治療選択を
がん治療は長期にわたることが多く、患者さんご自身が納得して治療を選択することが、治療を続けるうえでの支えになります。セカンドオピニオンは、納得できる治療選択をするための有効な手段です。
医師との信頼関係を大切にしながら、必要に応じてセカンドオピニオンを活用し、ご自身にとって最善の治療法を選んでください。セカンドオピニオンを受けることは、決して現在の担当医に対する不信感の表れではなく、より良い医療を受けるための前向きな行動です。