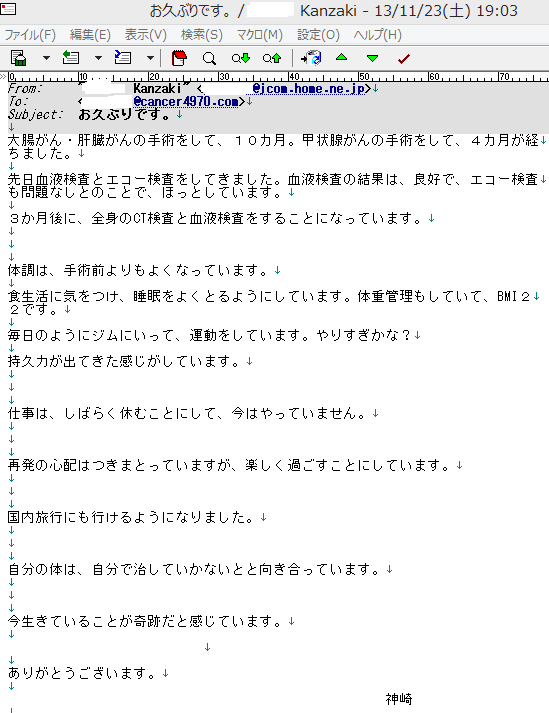【サイト内 特設ページ】

こんにちは。17年間の活動実績を持つ、
「プロのがん治療専門アドバイザー」本村ユウジです。
がんを治すために必要なことは、たった1つです。
詳しくはこちらのページでお伝えさせてください。
→がんを治すための「たった1つの条件」とは?
大腸がん・直腸がんの抗がん剤治療とは
大腸がん・直腸がんの抗がん剤治療(化学療法)は、患者さんの病期や身体状況に応じて様々な薬剤を組み合わせて実施されます。現在のがんの化学療法は、複数の薬を用いる「多剤併用療法」が主流で、大腸がんでも、やはりいくつかの薬を組み合わせて治療します。
大腸がんの抗がん剤治療は主に以下の場面で用いられます。
手術後の再発予防を目的とした「術後補助化学療法」では、大腸がんは手術で完全にがんを取りきれるがんですが、見えないがん細胞が残っていて、それが一定の期間をおいて再発することがあります。こうした見えないがん細胞を薬で攻撃し、再発率を下げることが治療の目的です。
進行・転移大腸がんに対しては、がんの増殖を抑えて生存期間の延長を図る治療が行われます。大腸がんにおいて、化学療法は進歩しています。15年ほど前までは全身化学療法による延命効果は半年ほどで、使える薬は限られてもいましたが、ここ10年余りの間にさまざまな薬が登場しています。
術後補助化学療法の主要な抗がん剤治療コース
術後補助化学療法は、手術でがんを取り除いた後に、目に見えない微小ながん細胞を根絶することを目的とした治療です。治療は手術のあと十分に体力が回復してから行い、およそ手術後4~8週の間に始めるのが一般的です。
FOLFOX療法(2週間ごと12回)
FOLFOX4とFOLFOX6は、オキサリプラチンを含む標準的な治療法です。
| 治療法 | 薬剤 | 投与量 | 投与方法 |
|---|---|---|---|
| FOLFOX4 | ロイコボリン | 200mg/m²(L-ロイコボリンでは100mg/m²) | 2時間点滴静注(1日目・2日目) |
| フルオロウラシル(急速投与) | 400mg/m² | ボーラス静注(1日目・2日目) | |
| フルオロウラシル(持続投与) | 600mg/m² | 22時間持続点滴静注(1日目・2日目) | |
| オキサリプラチン | 85mg/m² | 2時間点滴静注(1日目) | |
| FOLFOX6 | ロイコボリン | 400mg/m²(L-ロイコボリンでは200mg/m²) | 2時間点滴静注(1日目) |
| フルオロウラシル(急速投与) | 400mg/m² | ボーラス静注(1日目) | |
| フルオロウラシル(持続投与) | 2400mg/m² | 46時間持続点滴静注 | |
| オキサリプラチン | 85mg/m² | 2時間点滴静注(1日目) |
XELOX(CAPOX)療法(3週間ごと8回)
内服薬のカペシタビンとオキサリプラチンを組み合わせた治療法です。
| 薬剤 | 投与量 | 投与方法 |
|---|---|---|
| カペシタビン | 1000mg/m² | 1日2回、14日間内服後7日間休薬 |
| オキサリプラチン | 130mg/m² | 2時間点滴静注(1日目) |
術後補助化学療法の目標は、治療の完遂、つまり決められた用量、回数をすべて終えることです。FOLFOX療法、XELOX療法ともに、治療期間は6カ月です。
【サイト内 特設ページ】

こんにちは。17年間の活動実績を持つ、
「プロのがん治療専門アドバイザー」本村ユウジです。
がんを治すために必要なことは、たった1つです。
詳しくはこちらのページでお伝えさせてください。
→がんを治すための「たった1つの条件」とは?
転移性大腸がんの主要な抗がん剤治療コース
転移性大腸がんでは、細胞障害性抗がん剤に分子標的薬を組み合わせた治療が標準的に行われます。大腸がんの薬物療法で使う薬は、作用の仕方によって、細胞障害性抗がん薬、分子標的薬、免疫チェックポイント阻害薬という種類に大きく分けられます。
ベバシズマブ併用療法
血管新生阻害薬のベバシズマブをFOLFOXやXELOXに追加します。
| 薬剤 | 投与量 | 投与方法 |
|---|---|---|
| ベバシズマブ | 5mg/kgまたは10mg/kg | 初回90分点滴静注(1日目)、FOLFOXやXELOXに併用 |
FOLFIRI療法(2週間ごと)
イリノテカンを含む治療レジメンです。
| 薬剤 | 投与量 | 投与方法 |
|---|---|---|
| イリノテカン | 180mg/m²(日本承認量150mg/m²) | 30~90分点滴静注(1日目) |
| ロイコボリン | 400mg/m²(L-ロイコボリンでは200mg/m²) | 2時間点滴静注(1日目) |
| フルオロウラシル(急速投与) | 400mg/m² | ボーラス静注(1日目) |
| フルオロウラシル(持続投与) | 2400mg/m² | 46時間持続点滴静注 |
SOX療法(21日ごと)
日本で開発されたS-1とオキサリプラチンの組み合わせです。
| 薬剤 | 投与量 | 投与方法 |
|---|---|---|
| S-1 | 40mg/m²(日本承認量120mg/日まで) | 1日2回、14日間内服後7日間休薬 |
| オキサリプラチン | 130mg/m² | 2時間点滴静注(1日目) |
IRIS療法
イリノテカンとS-1の組み合わせによる治療法です。
| 薬剤 | 投与量 | 投与方法 |
|---|---|---|
| イリノテカン | 125mg/m² | 30~90分点滴静注(1日目、15日目)4週ごと |
| S-1 | 40~60mg(体表面積により調整) | 1日2回(80~120mg/日)1~14日投与後、2週間休薬 |
分子標的薬を用いた最新の抗がん剤治療
分子標的薬は、がん細胞の特定の分子を標的として攻撃する新しいタイプの薬です。分子標的薬は、がん細胞の特定の遺伝子やタンパク質を標的とすることで、がんの増殖を抑制する薬剤です。
EGFR阻害薬
セツキシマブとパニツムマブは、特定の遺伝子条件を満たす患者さんに使用されます。
| 薬剤 | 投与量 | 投与方法 |
|---|---|---|
| セツキシマブ | 初回400mg/m²、2回目以降250mg/m² | 初回2時間、2回目以降1時間点滴静注(毎週) |
| パニツムマブ | 6mg/kg | 1時間点滴静注 |
RAS変異やBRAF変異がない場合には、真ん中の矢印に進みます。左側(下行結腸から直腸)の大腸がんの場合には、EGFR阻害薬であるアービタックスやベクティビックスを抗がん剤治療と併用します。
レゴラフェニブによる治療
| 薬剤 | 投与量 | 投与方法 |
|---|---|---|
| レゴラフェニブ | 160mg/日 | 1日1回食後内服、21日間投与後7日間休薬(4週ごと) |
【サイト内 特設ページ】

こんにちは。17年間の活動実績を持つ、
「プロのがん治療専門アドバイザー」本村ユウジです。
がんを治すために必要なことは、たった1つです。
詳しくはこちらのページでお伝えさせてください。
→がんを治すための「たった1つの条件」とは?
免疫チェックポイント阻害剤を用いた最新治療
2025年3月現在、大腸がんの治療に効果があると証明されている免疫療法は、MSI-High/dMMR(遺伝子に入った傷を修復する機能が働きにくい状態)の場合と、腫瘍遺伝子変異量高スコア(TMB-High:がん細胞中の遺伝子変異の量が多い状態)の場合に免疫チェックポイント阻害薬を使用する方法のみです。
免疫チェックポイント阻害剤は、がん細胞が免疫細胞の攻撃を逃れる仕組みをブロックすることで、免疫システムを活性化し、がん細胞を排除する治療法です。
大腸がんにおいてはほとんどの患者さんに免疫チェックポイント阻害薬は効果がありません。ただし、特定の遺伝子異常を持つ一部のタイプでは効果が認められています。そのタイプとは「MSI-High(高頻度マイクロサテライト不安定性)」や「dMMR(ミスマッチ修復機能欠損)」と呼ばれる特徴を持つがんで、これらは大腸がんにおいては全体の5%程度と限られた割合にとどまります。
主要な免疫チェックポイント阻害薬
MSI-Hやdmmrの大腸がん患者さんには以下の薬剤が使用されます。
| 薬剤分類 | 代表的薬剤 | 適応条件 |
|---|---|---|
| 抗PD-1抗体 | ニボルマブ(オプジーボ) ペムブロリズマブ(キイトルーダ) |
MSI-H/dMMRまたはTMB-High |
| 抗CTLA-4抗体 | イピリムマブ(ヤーボイ) | 他の免疫チェックポイント阻害薬との併用 |
治療期間と投与スケジュール
大腸がんの抗がん剤治療では、治療の目的や患者さんの状況により期間が決まります。
術後補助化学療法の期間
手術後の再発予防治療では決められた期間の完遂が重要です。
| 治療法 | 投与間隔 | 総回数 | 治療期間 |
|---|---|---|---|
| FOLFOX4/FOLFOX6 | 2週ごと | 12回 | 6カ月 |
| XELOX(CAPOX) | 3週ごと | 8回 | 6カ月 |
転移性大腸がんの治療期間
転移性大腸がんでは、病気の進行や副作用の状況を見ながら治療を継続します。一次治療、二次治療と段階的に進められることが一般的です。
進行・再発がんに対する化学療法の場合、最初に行われる治療を一次治療(ファーストライン)、一次治療の次に試みられる治療を二次治療(セカンドライン)といいます。
副作用と安全性管理
副作用は、使用する薬によって異なり、その程度も個人差があります。最近では副作用を予防する薬なども開発され、特に吐き気や嘔吐については、以前と比べて予防(コントロール)することができるようになってきました。
主要な副作用
| 薬剤 | 主な副作用 | 注意点 |
|---|---|---|
| オキサリプラチン | 末梢神経障害、アレルギー反応 | 冷たいものに触れるとしびれが増悪 |
| イリノテカン | 下痢、骨髄抑制、脱毛 | 下痢は早期型と遅発型がある |
| フルオロウラシル | 口内炎、手足症候群、骨髄抑制 | 持続点滴により副作用軽減 |
| ベバシズマブ | 高血圧、出血、血栓症 | 手術前後の休薬期間が必要 |
| 免疫チェックポイント阻害薬 | 自己免疫反応、肝機能障害 | 免疫関連副作用の早期発見が重要 |
遺伝子検査と個別化治療
手術で取り切ることが難しい大腸がんで、薬物療法の適応があり、標準的な治療が終了する場合には、がん遺伝子パネル検査を検討することがあります。がん遺伝子パネル検査では、多数の遺伝子について異常がないかを同時に調べ、治療方針を検討します。
重要な遺伝子マーカー
| 遺伝子マーカー | 検査意義 | 治療選択への影響 |
|---|---|---|
| RAS変異 | EGFR阻害薬の効果予測 | 変異ありの場合、EGFR阻害薬無効 |
| BRAF変異 | 予後予測と治療選択 | 予後不良因子、特別な治療戦略が必要 |
| MSI-H/dMMR | 免疫チェックポイント阻害薬の効果予測 | 免疫療法の適応決定 |
| TMB-High | 免疫チェックポイント阻害薬の効果予測 | 免疫療法の適応決定 |
外来化学療法と生活の質
大腸癌の薬物療法はほとんど全てを外来で行うことができます。
現在の大腸がん治療では、中心静脈ポート(CVポート)を使用することで、46時間の持続点滴を自宅で行うことが可能になっています。
外来化学療法のメリット
- 入院期間の短縮により日常生活への影響を最小限に抑制
- 家族との時間を大切にしながら治療継続
- 感染リスクの低減
- 医療費の抑制
- 社会復帰の促進
最新の治療動向と今後の展望
2025年現在、大腸がん治療は個別化医療の時代に入っています。患者さんごとの遺伝子プロファイルに基づいた治療選択により、より効果的で副作用の少ない治療が可能になってきています。
例えば、国立がん研究センター東病院では大腸がんにおいて免疫チェックポイント阻害薬が効きにくいと言われているマイクロサテライト不安定性がない(MSS)患者さんと免疫チェックポイント阻害薬が効きやすいと言われているマイクロサテライト不安定性のある(MSI-H)患者さん、それぞれの直腸がん患者さんに対して、化学放射線療法(放射線治療と抗がん剤の併用治療)のあとにニボルマブという免疫チェックポイント阻害薬を行い、その後に手術を行う新しい治療の有効性・安全性を評価する医師主導治験(VOLTAGE試験)を実施しました。
今後期待される治療法
- 新規分子標的薬の開発
- 免疫チェックポイント阻害薬の適応拡大
- CAR-T細胞療法などの細胞治療
- がんワクチン療法
- 放射線治療との併用療法