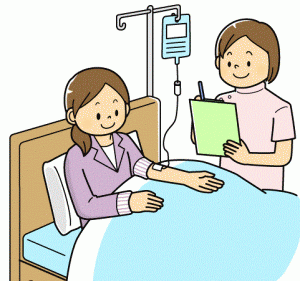
糖尿病患者さんの死因第1位はがん
日本での2011年から2020年における糖尿病患者さんの死因調査によると、最も多い死因はがん(38.9%)となっています。
これは2位の感染症(17.0%)、3位の血管障害(10.9%)を大きく上回る数値です。
従来、糖尿病の進行による主な合併症として注目されていたのは血管系の障害でした。高血糖状態が長期間続くことで、細い血管や太い血管が損傷を受け、様々な問題を引き起こします。細い血管の障害では、糖尿病網膜症、糖尿病腎症、神経障害などが起こり、太い血管の障害では動脈硬化が進行し、脳梗塞、心筋梗塞、狭心症などの生命に関わる疾患につながります。
しかし現在では、これらの血管系合併症が重篤化する前に、がんによって亡くなる患者さんの方が多くなっているのが実情です。
糖尿病の患者さんががんを併発した際の治療は、単純ながんの治療以上に複雑で困難になります。手術を行う場合、麻酔や血管の処置は避けられませんし、抗がん剤治療は血管に直接影響を与えます。リスクが重なる状況での治療選択を迫られることになるのです。
糖尿病とがんの関係性について
糖尿病がある人では、がん死リスクは1.3倍、がん発症リスクは1.2倍増加することが研究で示されています。特に注意が必要ながんの種類について見てみましょう。
海外のデータによると、糖尿病患者さんで発症リスクが高いのは、肝がん(2.2倍)、膵がん(2.1倍)、子宮がん(1.6倍)、胆嚢がん(1.6倍)、腎がん(1.3倍)、大腸がん(1.3倍)などです。日本国内のデータでは、肝がん(2.0倍)、膵がん(1.9倍)、大腸がん(1.4倍)となっており、主に消化器系のがん発症リスクが有意に高いことが判明しています。
興味深い点として、糖尿病の男性では前立腺がんの発症率が通常の0.8倍と低くなっており、前立腺がんになりにくいことが報告されています。これは糖尿病によってテストステロンが低下することと関連していると考えられています。
糖尿病とがんの共通危険因子
糖尿病もがんも、多くの場合生活習慣病のカテゴリに含まれます。両疾患には以下のような共通の危険因子があります:
- 加齢
- 肥満
- 運動不足
- 食生活の乱れ(赤肉や加工肉の過剰摂取、高GI食品の摂取など)
- 過剰な飲酒
- 喫煙
つまり、異なる病気でありながら、発症の原因は非常に似通っているのです。
糖尿病ががん発症リスクを高める機序
現在想定されている糖尿病により発がんリスクが高まる機序について、高血糖と高インスリン血症という主な2つの因子が、正常細胞をがん化し、がん細胞を増殖させていくと考えられています。
2型糖尿病では、血糖を調整するホルモンであるインスリンがうまく働かない「インスリン抵抗性」の状態になります。この状態に対処するため、膵臓から大量のインスリンが分泌され、血液中のインスリン濃度が高くなる「高インスリン血症」を引き起こします。
高血糖により血中酸化ストレスが増加すると、染色体にダメージを与え、正常細胞ががん化します。さらに、高血糖自体が細胞増殖のエネルギーとなり、がん化した細胞の増殖が促進されます。
インスリンは直接的に発がんプロモーションに関与し、IGF-1という成長因子を介して間接的にも発がんを促進すると考えられています。また、最近の研究では、インスリンが正常細胞の発がん抑制機能を阻害することで、がん細胞の増殖を助長する可能性も明らかになっています。
さらに、慢性的な高血糖状態は血液の酸化を促し、炎症を起こしやすくするため、これらもがん発生の原因となります。
「自分の判断は正しいのか?」と不安な方へ

がん治療。
何を信じれば?
不安と恐怖で苦しい。
がん治療を左右するのは
治療法より“たった1つの条件”です。
まず、それを知ってください。
がん専門アドバイザー 本村ユウジ
糖尿病患者さんのがん治療予後が悪い理由
糖尿病を有するがん患者さんは生命予後・術後予後が不良であることがメタ解析で示されています。最近の研究では、糖尿病の患者さんは糖尿病でない人と比較して、がん手術後の短期死亡率が約50%高くなるとされています。
予後が悪化する主な理由は以下の通りです:
- 高血糖のため手術創や血管損傷の治癒が遅い
- 感染症などの合併症を起こしやすい
- 心血管系への影響により突然死のリスクが高い
- 血糖コントロールが困難な状況では抗がん剤の効果が低下する可能性がある
糖尿病患者さんに対するがん治療の留意点
手術の場合
がん治療で手術を前提とする場合、最も重要なのは血糖値のコントロールです。高血糖の状態では、血糖値が適正範囲まで低下するまで手術は延期されることが一般的です。
手術前の血糖値のコントロール目標について統一された見解はありませんが、尿ケトン体陰性、空腹時血糖値110~140mg/dL、または食後血糖値160~200mg/dLなどといわれています。
外科や麻酔科では、手術や全身麻酔を安全に行える条件として「尿糖10%以下」を重視します。
術前評価では、糖尿病特有の合併症についても注意深く検査します。糖尿病網膜症がある場合、急激な血糖コントロールによって眼底出血が悪化する可能性があるため、慎重な管理が必要です。また、神経障害がある患者さんでは、術後に立ちくらみや転倒のリスクが高くなるため、これらの点も考慮した対策を立てます。
がんの治療のため速やかに血糖値を調整することが必要な場合や、検査や手術で食事の摂取が不規則になる場合は、インスリン治療を行うこともあります。インスリン治療のよいところは、手術という身体に大きなストレスがかかるときでも安全に使用できること、投与する量が少量ずつそのつど変えられるため、きめ細やかな調整ができるところです。
化学療法(薬物治療)の場合
化学療法では、使用する薬剤によって血糖値に影響を与えるものがあるため、特別な注意が必要です。
腎臓にダメージを与えやすいシスプラチンなどの薬剤は、糖尿病患者さんには慎重に投与されます。また、化学療法の副作用(炎症や吐き気)を抑制するために使用されるステロイド薬にも注意が必要です。
ステロイド薬を糖尿病患者さんに使用すると、血糖コントロールが悪化するリスクがあります。そのため、ステロイド使用時には、既に糖尿病と診断されている人はもちろん、糖尿病の有無を確認する検査が行われることもあります。
その他、一部の分子標的薬では、インスリンの働きを阻害して高血糖を引き起こすことがあります。乳がんや前立腺がんで使用されるホルモン療法も血糖値に影響を与えるため、注意深い監視が必要です。
血糖値上昇に注意が必要な薬剤一覧
| 薬剤分類 | 具体的な薬剤名 |
|---|---|
| 副腎皮質ステロイド | プレドニン、デカドロン、ベタメタゾン、メドロール |
| 分子標的薬 | アフィニトール、トーリセル、タシグナ、スーテント |
| ホルモン治療薬 | リュープリン、ゾラデックス、プロスタール、カソデックス |
| 抗がん剤 | ロイナーゼ |
| 抗精神薬 | ジプレキサ、セロクエル、リスパダール、ルーラン、エビリファイ |
| その他 | インターフェロン、高カロリー輸液 |
食事・栄養管理の難しさ
がん治療で手術や化学療法を実施した場合、食欲の低下や減退が顕著になることがあります。食事量が少ないと低血糖状態になりやすく、糖尿病患者さんは高血糖だけでなく低血糖のリスクも考慮する必要があります。
食欲低下時には、血糖降下作用があるスルホニル尿素薬やインスリン製剤の投与量を調整する必要があります。
また、糖尿病治療薬の一つであるビグアナイド系薬剤は、体調不良時に服用すると乳酸アシドーシスという生命に関わる副作用を引き起こす可能性があります。そのため、手術後や抗がん剤の副作用による体調不良時には、一時的に薬剤を中止するなどの配慮が必要です。
糖尿病とがんの予防策
がんと糖尿病に共通してリスクを下げる食事例として、野菜、果物、食物繊維、全粒(未精白)穀物、魚をカロリーやバランスの管理をしたうえで摂取することが挙げられます。
一方で、リスクを上昇させる食品として、赤肉・加工肉の過剰摂取や高GI食品の摂取が指摘されています。
運動に関しても、日本の観察研究によると、運動量が多いグループほどがんリスクが低下することがわかっているため、運動ががんの予防につながる可能性があります。
体重管理も重要で、肥満の解消は糖尿病とがんの両方のリスクを減少させることが知られています。
早期発見の重要性
糖尿病患者さんは定期的に血液検査や画像検査を受けるため、がんが早期に発見される場合があります。しかし、すべてのがんを発見できるわけではないため、糖尿病の定期通院とは別に、がん検診を受けることが重要です。
厚生労働省では、胃がん、子宮頸がん、乳がん、肺がん、大腸がんについて、がん検診の受診を推奨しています。これらの検診は糖尿病の有無に関わらず推奨されているものです。
特に肝炎ウイルス(B型・C型)に感染している糖尿病患者さんは、肝臓がんのリスクが特に高いため、定期的な腫瘍マーカー検査や腹部超音波検査の受診が推奨されます。
治療における医療連携の重要性
糖尿病を合併するがん患者さんの数は増えているので、今後はがん診療に携わる多くの医師がインスリンの導入に積極的に取り組むことが期待されます。
糖尿病とがんの両方を抱える患者さんの治療には、がん専門医、糖尿病専門医、看護師、薬剤師、栄養士などによるチーム医療が不可欠です。各専門職が連携することで、より安全で効果的な治療が可能になります。
患者さんとご家族へのメッセージ
糖尿病の患者さんががんを併発することは決して珍しいことではありませんが、適切な血糖管理と専門医による治療により、がん治療を安全に行うことが可能です。
重要なのは、糖尿病とがんの両方の治療を並行して行うことです。「がん治療を優先して糖尿病は後回し」や「血糖値を下げてからがん治療」といった考え方ではなく、両方の病気に対する包括的なアプローチが必要です。
治療中は、医療チームとの密接なコミュニケーションを保ち、体調の変化や気になることがあれば遠慮なく相談してください。また、定期的ながん検診の受診も欠かさず行いましょう。
最新の治療動向と今後の展望
近年、糖尿病治療薬とがんリスクの関係についても研究が進められています。メトホルミンはがんリスクを低下させる可能性があることが示されていますが、ピオグリタゾンについては膀胱がんの発生リスクが増加する可能性が完全には否定できないため、膀胱がん治療中の患者さんには投与を避けることが推奨されています。
また、インスリン注射により発がんが増えることは否定されており、インスリン治療による血糖コントロールががんリスクに悪影響を与えることはありません。
参考文献・出典情報
- 糖尿病とがんの相互関連性、最新の知見は?/日本糖尿病学会|医師向け医療ニュースはケアネット
- がん | 糖尿病情報センター
- 糖尿病だとなぜ、がんが増えるのか? | せいてつLab | 社会医療法人 製鉄記念八幡病院
- 【医師監修】糖尿病とがんの意外な関係性について|千葉市若葉区の都賀駅の内科病院でおすすめの板谷...
- 糖尿病とがん | 2021年 | コラム | ニュース一覧 | 一般財団法人 浜松光医学財団 浜松PET診断センター
- 糖尿病とその後のがん罹患との関連について | 現在までの成果 | 多目的コホート研究 | 国立研究開発法人 国立がん研究センター がん対策研究所 予防関連プロジェクト
- 膵臓(すいぞう)がんになりやすい人とは?リスク因子10項目を解説
- 【特集記事】糖尿病と「共に生きる」ために | 再発転移がん治療情報
- 他に病気があっても安心・安全ながん治療を受けるために
- 糖尿病とがん、2つの治療をされる方へ | 糖尿病情報センター



