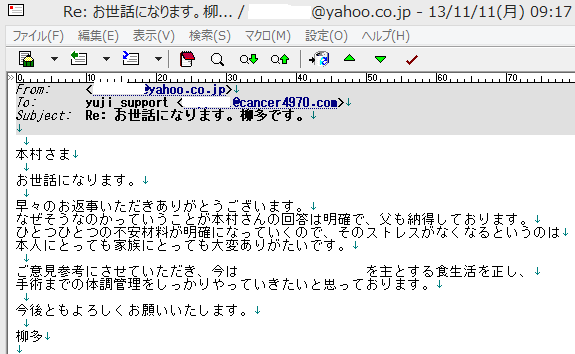【サイト内 特設ページ】

がんを治すために必要なことは、たった1つです。
詳しくはこちらのページで。
→がんを治すための「たった1つの条件」とは?
膵臓がんと放射線治療の基礎知識
膵臓がんは早期発見が難しく、治療選択に悩まれる患者さんが多いがんの一つです。がん専門アドバイザーの本村ユウジが、膵臓がんにおける放射線治療について、最新の情報を交えながら詳しく解説します。
膵臓がんの主な症状には、食欲不振、腹部の不快感、体重減少、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、背中の痛みなどがあります。これらの症状が現れた時点で、すでに膵臓以外の臓器にがんが広がっているケースが少なくありません。
膵臓がんの放射線治療が適応となる条件
膵臓がんの治療では、手術によるがんの切除が最も優先される治療法です。しかし、切除が可能な患者さんの割合は、多く見積もっても全体の約20パーセント程度にとどまります。つまり、膵臓がんの患者さんの約80パーセントは、発見時にすでに手術でがんを完全に取り除くことが難しい状態にあるということです。
このような切除不能な膵臓がんの患者さんに対して、放射線治療は重要な治療選択肢となります。特に、抗がん剤と放射線を組み合わせた「化学放射線治療」が第1選択の治療法として選ばれることが多くなっています。
放射線治療の適応となる主なケース
膵臓がんにおいて放射線治療が検討されるのは、以下のような状況です。
まず、局所進行がんで手術ができない場合です。がんが周囲の主要な血管に巻き込んでいるなど、技術的に切除が困難な状態の患者さんが対象となります。
次に、手術後の再発予防や補助療法として用いられることがあります。手術で切除できた患者さんでも、再発リスクを減らすために放射線治療を追加することがあります。
また、痛みなどの症状を和らげる目的(緩和照射)でも放射線治療が活用されます。骨転移による痛みや、がんによる圧迫症状の軽減に効果が期待できます。
【サイト内 特設ページ】

がんを治すために必要なことは、たった1つです。
詳しくはこちらのページで。
→がんを治すための「たった1つの条件」とは?
膵臓がんへの放射線治療の具体的な進め方
標準的な外部照射の方法
膵臓がんの放射線治療では、10メガボルト(MV)のエックス線を使用するのが一般的です。照射方法としては、多門照射法や4門照射法という技術が用いられます。これらの方法は、複数の方向から放射線を当てることで、がん病巣に効率よく線量を集中させながら、周囲の正常組織へのダメージを最小限に抑える工夫がされています。
膵臓がんは放射線に対する感受性(効きやすさ)があまり高くない特徴があります。さらに膵臓の周囲には、放射線に弱い肝臓、腎臓、脊髄といった重要な臓器が隣接しているため、照射できる線量には制限があります。
そのため、一般的な治療では総線量は50グレイ(Gy)程度とされ、1回あたりの線量は1.8から2グレイで照射を行います。これを週に5回、約5週間から6週間かけて実施するのが標準的な治療期間となります。
術中照射という選択肢
切除不能な局所進行がんの患者さんに対しては、開腹手術の際に「術中照射」が行われることがあります。これは、お腹を開いた状態で直接がん病巣に放射線を当てる方法です。
術中照射では10から20メガエレクトロンボルト(MeV)の電子線が使用されます。膵臓を切除した場合には20から25グレイを1回で照射し、切除できない膵臓がんの場合には25から30グレイの1回照射が行われます。
ただし、術中照射単独では十分な治療効果が得られないため、通常は外部照射と併用して実施されます。
放射線治療と化学療法の併用について
現在の膵臓がん治療では、放射線治療単独ではなく、抗がん剤との併用(化学放射線治療)が主流となっています。放射線と抗がん剤を組み合わせることで、相乗効果が期待できるためです。
よく用いられる抗がん剤には、ゲムシタビン(ジェムザール)やS-1(ティーエスワン)などがあります。これらの薬剤は放射線の効果を高める作用(放射線増感作用)を持っているとされています。
治療スケジュールは、放射線照射と並行して抗がん剤を投与する方法や、先に抗がん剤治療を行ってから放射線治療に移行する方法など、患者さんの状態や医療機関の方針によって異なります。
【サイト内 特設ページ】

がんを治すために必要なことは、たった1つです。
詳しくはこちらのページで。
→がんを治すための「たった1つの条件」とは?
膵臓がん放射線治療の効果について
膵臓がんの放射線治療の効果については、正直に申し上げて限定的であるというのが現状です。膵臓がん全体の5年生存率は約5パーセント程度とされており、切除不能な局所進行がんの患者さんの5年生存率は1から2パーセント程度にとどまります。
しかし、化学放射線治療によって以下のような効果が報告されています。
腫瘍の進行を遅らせることができる場合があります。完全にがんを消失させることは難しくても、がんの成長を一定期間抑えることで、生存期間の延長につながる可能性があります。
また、痛みなどの症状を軽減する効果も期待できます。膵臓がんによる背中の痛みや腹痛は患者さんのQOL(生活の質)を大きく低下させますが、放射線治療によってこれらの症状が和らぐことがあります。
さらに、手術後の補助療法として用いた場合、再発リスクを減らせる可能性も指摘されています。
放射線治療による副作用と対策
急性期の副作用
放射線治療中から治療終了後数週間以内に現れる副作用を急性期副作用といいます。膵臓がんの放射線治療では、以下のような症状が出ることがあります。
食欲の低下は比較的多くの患者さんが経験される症状です。食事の量が減ってしまうことで、体力の低下や体重減少につながることがあります。少量ずつ複数回に分けて食事を摂る、栄養価の高い食品を選ぶなどの工夫が必要です。
吐き気や嘔吐も起こりやすい副作用です。制吐剤(吐き気止め)の処方によって、ある程度コントロールできることが多いです。
また、全身のだるさや疲労感を感じる患者さんもいらっしゃいます。治療期間中は無理をせず、十分な休息を取ることが大切です。
照射部位の皮膚に軽い炎症(発赤やひりひり感)が生じることもありますが、通常は軽度で、治療終了後には回復します。
晩期の副作用
治療終了から数か月、時には数年後に現れる副作用を晩期副作用といいます。膵臓がんの放射線治療では、照射範囲に含まれる胃や十二指腸に影響が出ることがあります。
具体的には、胃潰瘍や十二指腸潰瘍が発生する可能性があります。また、出血、穿孔(穴があくこと)、狭窄(狭くなること)といった合併症がみられることもあります。
これらの晩期副作用は重篤になることもあるため、治療終了後も定期的な経過観察が重要です。胃カメラなどの検査で早期に発見し、適切な治療を行うことで対処できる場合があります。
陽子線治療と重粒子線治療について
新しい放射線治療の特徴
従来のエックス線による放射線治療に加えて、近年では陽子線治療や重粒子線治療といった、より精密な放射線治療が開発されています。
これらの治療法は、粒子線と呼ばれる特殊な放射線を使用します。陽子線や重粒子線(炭素イオン線)は、体内の特定の深さで最大のエネルギーを放出する性質(ブラッグピーク)を持っているため、がん病巣にピンポイントで線量を集中させることができます。
その結果、周囲の正常組織へのダメージを従来の放射線治療よりも少なくできる可能性があります。また、より高い線量をがん病巣に届けることができるため、治療効果の向上も期待されています。
膵臓がんへの陽子線・重粒子線治療の現状
膵臓がんに対する陽子線治療や重粒子線治療は、研究段階から臨床応用の段階に移行しつつあります。いくつかの医療機関で臨床試験や先進医療として実施されており、従来の治療法と比較した効果や安全性が検証されています。
2025年現在、膵臓がんに対する粒子線治療の研究は進んでいますが、標準治療として確立されるには、さらなるデータの蓄積が必要とされています。
膵臓がん放射線治療の保険適応について
標準的な放射線治療の保険適応
従来のエックス線を用いた外部照射による放射線治療は、膵臓がんに対して保険適応となっています。化学放射線治療として抗がん剤と併用する場合も、保険診療の範囲内で治療を受けることができます。
陽子線・重粒子線治療の保険適応
陽子線治療や重粒子線治療については、保険適応の状況が複雑です。2025年時点での状況を確認する必要がありますが、一部のがん種では保険適応となっている一方、膵臓がんについては条件付きでの先進医療や、自由診療として実施されているケースがあります。
粒子線治療を検討される場合は、実施医療機関に保険適応の有無、治療費用について事前に確認することをお勧めします。保険適応外の場合、治療費は数百万円に及ぶこともあるため、経済的な負担も考慮する必要があります。
放射線治療の期間とスケジュール
標準的な外部照射による放射線治療の期間は、通常5週間から6週間程度です。週に5日(月曜日から金曜日)照射を行い、土日は休みというスケジュールが一般的です。
1回の照射自体にかかる時間は10分から15分程度ですが、準備や位置合わせの時間を含めると、1回の通院で30分から1時間程度かかることが多いです。
治療開始前には、CT撮影などを行って詳細な治療計画を立てる必要があります。この治療計画の作成には1週間から2週間程度かかることもあります。
化学放射線治療の場合は、抗がん剤の投与スケジュールも組み合わせるため、全体の治療期間はさらに長くなることがあります。
放射線治療を受ける際の注意点
放射線治療を受けられる患者さんには、いくつか注意していただきたい点があります。
まず、治療中は栄養状態の維持が重要です。副作用で食欲が落ちても、できるだけ食事を摂るように心がけてください。必要に応じて栄養補助食品の利用も検討しましょう。
照射部位の皮膚ケアも大切です。照射部位を強くこすったり、刺激の強い石鹸を使ったりすることは避けてください。また、直射日光を避け、入浴時は熱すぎないお湯を使用することをお勧めします。
体調の変化があれば、すぐに医療スタッフに相談しましょう。副作用は適切に対処することで軽減できることが多いです。我慢せずに伝えることが大切です。
また、他の医療機関を受診する際には、放射線治療を受けていることを必ず伝えましょう。薬の飲み合わせなどで注意が必要な場合があります。
治療選択における大切な考え方
膵臓がんは予後が厳しいがんであることは事実です。しかし、治療法は日々進歩しており、新しい抗がん剤や治療法の組み合わせによって、少しずつではありますが治療成績は改善してきています。
放射線治療は、膵臓がん治療における重要な選択肢の一つです。手術ができない患者さんにとっては、化学放射線治療が生存期間を延ばし、症状を和らげる可能性のある治療法となります。
治療を選択する際には、担当医からしっかりと説明を受け、治療の目的(根治を目指すのか、症状緩和を目的とするのか)、期待される効果、起こりうる副作用、治療にかかる期間や費用などを十分に理解した上で、ご自身やご家族が納得できる選択をすることが大切です。
| 治療法 | 特徴 | 保険適応 |
|---|---|---|
| 標準的な外部照射 | 10MVのエックス線を使用。総線量50Gy程度を5-6週間で照射 | 適応あり |
| 術中照射 | 開腹時に直接照射。20-30Gyを1回で照射 | 適応あり |
| 陽子線治療 | 精密な照射が可能。周囲組織へのダメージが少ない | 条件により異なる |
| 重粒子線治療 | 陽子線よりさらに高い生物学的効果 | 条件により異なる |