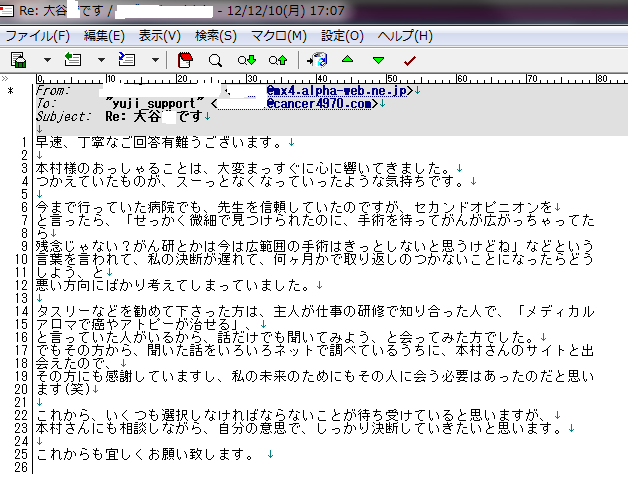ステージ4および再発子宮頸がんの治療方針について
子宮頸がんがステージ4に進行した場合、あるいは再発した場合、治療の選択肢は限られてきます。このステージでは、がん細胞が子宮頸部を超えて骨盤外へ広がっていたり、膀胱や直腸の粘膜にまで浸潤していたり、遠隔転移が認められたりします。
このような進行した状態では、局所的な治療法である手術や放射線治療を単独で適応することは難しくなります。根治を目指すことは困難であり、治療の目的はがんの進行を遅らせることや、痛みなどの症状を緩和してQOL(生活の質)を維持・向上させることが中心となります。
ただし、治療方針は患者さん一人ひとりの状態によって異なります。がんの広がり方、転移の有無、これまでの治療歴、年齢、全身状態などを総合的に評価した上で、最適な治療法を選択していくことになります。
ステージ4の子宮頸がんに対する化学療法(抗がん剤治療)の選択肢
手術や放射線治療が適応とならない進行期の子宮頸がんや再発子宮頸がんでは、化学療法(抗がん剤治療)が主な治療法となります。全身に薬剤を行き渡らせることで、体内のどこにあるがん細胞にも作用することを期待する治療法です。
シスプラチンを用いた化学療法の歴史
子宮頸がんに対する化学療法は、1980年代からシスプラチンという白金製剤を中心に行われてきました。シスプラチンは子宮頸がんに対して一定の効果を示す薬剤として長年使用されてきた実績があります。
1990年代に入ると、卵巣がんで有効性が認められていた「シスプラチン+パクリタキセル(タキソール)併用治療」、いわゆるTP療法が子宮頸がんにも応用されるようになりました。臨床試験の結果、シスプラチン単独治療よりもTP療法のほうが効果が高いことが確認され、以降は子宮頸がんの化学療法における標準治療の一つとして位置づけられました。
TP療法の特徴と課題
TP療法はシスプラチンとパクリタキセルを組み合わせた治療法です。がん細胞に対する効果は認められていますが、シスプラチンには腎毒性や消化器毒性が強いという特徴があります。
具体的には、吐き気や嘔吐、腎機能の低下などの副作用が現れやすく、患者さんによっては副作用の症状が厳しいため、予定していた治療を完遂できずに途中で中断せざるを得ないケースも少なくありませんでした。
TC療法の登場と特徴
TP療法の副作用の問題を受けて、シスプラチンの代わりに同じ白金製剤であるカルボプラチンを使用するTC療法(カルボプラチン+パクリタキセル併用治療)が試みられるようになりました。
カルボプラチンはシスプラチンと比較して腎毒性が低いため、腎臓への負担が少なく、通院での治療も可能になります。入院の必要性が減ることで、患者さんの日常生活への影響を抑えることができるという利点があります。
ただし、カルボプラチンにも副作用があります。特に手足のしびれなどの末梢神経障害が現れやすいという特徴があり、この点には注意が必要です。
TP療法とTC療法の効果比較
TP療法とTC療法を比較する臨床試験が複数行われ、TC療法の有効性も裏付けられました。効果の面では両者に大きな差はないとされており、副作用のプロフィールや患者さんの状態に応じて選択されます。
2016年以降の標準的な治療では、TC療法が第一選択として考慮されることが多く、患者さんの腎機能や既往歴、全身状態などを考慮して、場合によってはTP療法も活用されています。現在では医師と患者さんが相談しながら、個々の状況に最も適した治療法を選んでいくことが一般的です。
| 治療法 | 使用薬剤 | 主な特徴 | 主な副作用 |
|---|---|---|---|
| TP療法 | シスプラチン+パクリタキセル | 効果が確認されている標準的な治療 | 腎毒性、消化器毒性(吐き気、嘔吐) |
| TC療法 | カルボプラチン+パクリタキセル | 腎毒性が低く通院治療も可能 | 末梢神経障害(手足のしびれ) |
分子標的薬アバスチンを追加する化学療法
アバスチンとは
アバスチン(ベバシズマブ)は、2013年に卵巣がんで適応となった分子標的薬です。従来の抗がん剤のように直接がん細胞を攻撃するのではなく、血管新生阻害薬として作用します。
がん細胞は成長するために新しい血管を作り出し、そこから栄養や酸素を得ています。アバスチンはこの新しい血管が作られるのを阻害することで、がん細胞への栄養補給を遮断し、がんの増殖を抑える働きをします。
進行再発子宮頸がんにおけるアバスチンの効果
進行または再発した子宮頸がんの患者さんを対象とした臨床試験(GOG240試験)が行われました。この試験では、化学療法単独で治療を行ったグループと、化学療法にアバスチンを追加したグループを比較しました。
その結果、アバスチンを追加したグループでは、全生存期間(OS)の中央値が17.0カ月、無増悪生存期間(PFS)の中央値が8.2カ月、奏効率(RR)が48%となり、いずれの項目においても化学療法単独のグループよりも良好な結果が得られました。
この試験結果を受けて、進行・再発子宮頸がんに対してアバスチンを化学療法に追加することが、治療選択肢の一つとして認められるようになりました。
アバスチンの副作用について
アバスチンには特有の副作用があります。化学療法にアバスチンを追加すると、それぞれの薬剤の副作用が重なることになるため、注意深い管理が必要です。
アバスチンの副作用として報告されているものには、出血、血栓塞栓症、消化管穿孔(消化管に穴が開くこと)、泌尿生殖器瘻(尿路系に穴が開くこと)などがあります。
これらの重篤な副作用は発生頻度としては1%前後と稀ですが、臨床試験では尿管や膀胱に瘻孔(穴)ができる副作用が約10.6%に認められ、アバスチンを使用しなかったグループと比較すると約5倍高い頻度でした。
ステージ4や再発の子宮頸がんの患者さんは、すでに放射線治療や化学療法を受けている方が多く、骨盤内の臓器が治療によるダメージを受けている場合があります。このような状態でアバスチンを使用すると、尿管や膀胱に瘻孔が生じるリスクが高まり、尿漏れなどの症状が現れて日常生活に影響を及ぼす可能性があります。
アバスチン使用における治療費の課題
分子標的薬は一般的に高額な薬剤であり、アバスチンも例外ではありません。治療を継続する場合、患者さんの経済的負担は相当なものになります。
日本では公的医療保険制度により高額療養費制度が適用されますが、それでも患者さんの自己負担額は決して少なくありません。また、医療費全体としても国の財政に与える影響は小さくありません。
そのため、アバスチンを使用する際には、期待される効果と副作用のリスク、経済的な負担を総合的に評価し、本当にこの治療が必要な患者さんに対して慎重に適応を判断していくことが求められています。
その他の化学療法の選択肢
TP療法やTC療法、アバスチンの追加以外にも、子宮頸がんに対していくつかの化学療法の選択肢が研究されています。
例えば、TS-1(テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤)とシスプラチンの併用療法や、ネダプラチンとイリノテカンの併用療法などが、有効な治療法となる可能性があるとして臨床試験が行われてきました。
これらの治療法は、既存の標準治療が効果を示さなくなった場合や、副作用により標準治療が継続できない場合などに、代替案として検討されることがあります。ただし、いずれの治療法も個々の患者さんの状態に応じて慎重に選択される必要があります。
免疫チェックポイント阻害薬の登場
近年、がん治療の分野では免疫チェックポイント阻害薬が注目を集めています。子宮頸がんにおいても、PD-1阻害薬であるペムブロリズマブ(キイトルーダ)が、特定の条件を満たす患者さんに対して使用可能となっています。
免疫チェックポイント阻害薬は、患者さん自身の免疫システムを活性化させてがん細胞を攻撃する治療法です。従来の化学療法とは異なる作用機序を持つため、新たな治療選択肢として期待されています。
ただし、すべての患者さんに効果があるわけではなく、バイオマーカー検査などで適応を判断する必要があります。また、免疫関連の特有な副作用(免疫関連有害事象)にも注意が必要です。
治療選択における重要なポイント
ステージ4や再発した子宮頸がんの治療では、以下のような点を考慮して治療方針を決定していきます。
患者さんの全身状態と治療歴
これまでにどのような治療を受けてきたか、現在の体力や臓器機能はどうか、合併症はあるかなど、総合的な評価が必要です。以前の治療で副作用が強く出た経験がある場合は、それを踏まえた薬剤選択が求められます。
がんの広がりと症状
がんがどこまで広がっているか、どのような症状が出ているかによって、治療の目的や方法が変わってきます。痛みなどの症状が強い場合は、まず症状を和らげることを優先することもあります。
患者さんの希望と価値観
治療を受ける本人である患者さんが、どのような治療を望むか、何を大切にしたいかという価値観も重要な要素です。積極的な治療を希望する方もいれば、副作用を最小限にしてQOLを保つことを優先したい方もいます。
医師から提示される治療選択肢について十分な説明を受け、疑問点や不安なことがあれば遠慮なく質問し、納得した上で治療方針を決めることが大切です。
治療中の支持療法とケア
化学療法を行う際には、主な治療と並行して支持療法が重要になります。支持療法とは、治療に伴う副作用を予防したり軽減したりするための治療のことです。
吐き気や嘔吐に対しては制吐剤を使用し、白血球が減少した場合には感染予防のための対策を講じます。貧血が進行すれば輸血を検討することもあります。痛みに対しては鎮痛薬を適切に使用し、患者さんができるだけ快適に過ごせるよう配慮します。
また、栄養状態を良好に保つことも治療を続ける上で重要です。食欲不振や味覚の変化などで食事が摂りにくくなることがありますが、管理栄養士などの専門家に相談しながら、食べやすい工夫をしていくことができます。
緩和ケアの重要性
進行したがんの治療において、緩和ケアは欠かせない要素です。緩和ケアは終末期だけのものではなく、診断の早い段階から並行して受けることが推奨されています。
痛みやその他の身体的な症状を和らげることはもちろん、精神的なサポートや社会的な支援も緩和ケアの一部です。患者さん本人だけでなく、ご家族に対するケアも含まれます。
緩和ケアチームや緩和ケア専門医、緩和ケア認定看護師などの専門家と連携しながら、治療を進めていくことが推奨されます。
最新の治療開発状況
子宮頸がんの治療は日々進歩しており、新しい薬剤や治療法の開発が続けられています。特に分子標的薬や免疫チェックポイント阻害薬の分野では、新たな薬剤の臨床試験が進行中です。
また、がんのゲノム情報を解析して個々の患者さんに最適な治療を選択する「がんゲノム医療」も徐々に広がってきています。特定のがん遺伝子変異が見つかった場合には、それに対応した分子標的薬を使用できる可能性があります。
これらの最新治療については、がんゲノム医療中核拠点病院やがん診療連携拠点病院などで情報を得ることができます。臨床試験への参加も選択肢の一つとなる場合があります。
セカンドオピニオンの活用
進行したがんの治療では、さまざまな選択肢がある一方で、どの治療を選ぶべきか迷うこともあります。そのような場合、セカンドオピニオンを受けることは有効な手段です。
セカンドオピニオンとは、現在診療を受けている医師とは別の医師に意見を求めることです。異なる専門家の視点から意見を聞くことで、治療の選択肢について理解が深まり、より納得して治療方針を決定できるようになります。
参考文献・出典情報
NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology: Cervical Cancer
GOG 240試験:進行子宮頸がんにおけるベバシズマブの効果(PubMed)