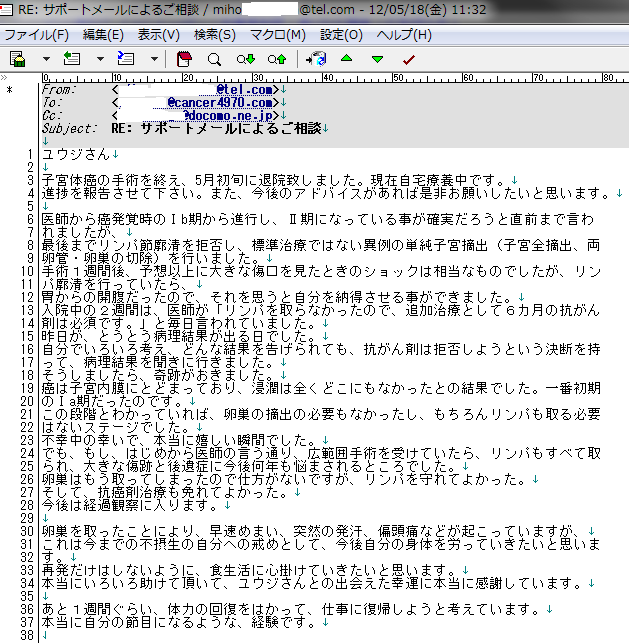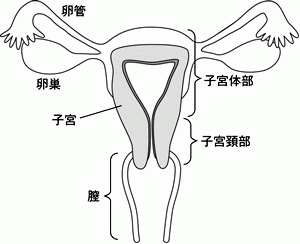
子宮体がんと診断された際に受け取る組織診断結果は、今後の治療方針を決める重要な情報です。この記事では、組織診断の結果をどのように理解すれば良いかを、一般の方にも分かりやすく説明します。
【サイト内 特設ページ】

こんにちは。17年間の活動実績を持つ、
「プロのがん治療専門アドバイザー」本村ユウジです。
がんを治すために必要なことは、たった1つです。
詳しくはこちらのページでお伝えさせてください。
→がんを治すための「たった1つの条件」とは?
組織診断とは何か
組織診断は、子宮体がんの確定診断を目的とした検査です。細いスプーンやチューブ状の専用器具を挿入し、がんが疑われる子宮内膜から小さな組織を切り取り、顕微鏡で組織の状態を調べます。この検査により、がんかどうかを確定するとともに、子宮体がんの組織型と悪性度も調べることができます。
がん細胞は、発生した組織・器官の性質や構造などにより異なります。がん細胞の分類は、病理学の専門医が顕微鏡で見て、基本的にはその形態(組織型)により行います。2025年現在、この組織診断の精度は向上しており、より正確な分類が可能になっています。
子宮体がんの主要な組織型について
子宮体がんは、組織型によっていくつかの種類に分けられます。それぞれの組織型によって、治療方針や予後が異なるため、正確な理解が重要です。
類内膜腺がん(るいないまくせんがん)
がん細胞の形態が子宮内膜細胞に似ているタイプで、子宮体がんの約80%以上を占める最も多い組織型です。分化度の高低により、以下のように分類されます。
- 高分化型(グレード1、G1):悪性度が低く、予後が比較的良好
- 中分化型(グレード2、G2):中程度の悪性度
- 低分化型(グレード3、G3):悪性度が高く、増殖・転移が速い
類内膜腺がんの患者さんは、他の組織型と比較して予後が良好とされています。特に高分化型(G1)の場合、5年生存率は95%と報告されています。
漿液性腺がん(しょうえきせいせんがん)
卵巣にできる漿液性腺がんと似たタイプで、がん細胞は漿液を産生します。漿液は、無色から薄黄色の透明な液体です。この組織型は、類内膜腺がんと比較して悪性度が高く、化学療法に抵抗性を示すことが多いとされています。
2025年現在の治療成績では、漿液性腺がんと明細胞腺がんをあわせた5年生存率は60~65%と報告されており、類内膜腺がんと比較すると予後は厳しいものとなります。
明細胞腺がん(めいざいぼうせんがん)
卵巣にできる明細胞腺がんと似たタイプで、顕微鏡で見ると、明るい色調の細胞質、あるいは釘頭(ホブネイル)型の細胞から構成されるがんです。漿液性腺がんと同様に、化学療法に抵抗性を示すことが多く、手術による完全摘出が困難な場合は予後が厳しいとされています。
その他の組織型
上記以外にも、粘液性腺がんやがん肉腫などの組織型がありますが、これらはまれな組織型です。それぞれの組織型に応じた専門的な治療が必要となります。
【サイト内 特設ページ】

こんにちは。17年間の活動実績を持つ、
「プロのがん治療専門アドバイザー」本村ユウジです。
がんを治すために必要なことは、たった1つです。
詳しくはこちらのページでお伝えさせてください。
→がんを治すための「たった1つの条件」とは?
組織診断結果の見方と重要性
組織診断結果を受け取った際に確認すべき点は以下の通りです。
| 項目 | 内容 | 治療への影響 |
|---|---|---|
| 組織型 | 類内膜腺がん、漿液性腺がん、明細胞腺がんなど | 治療方針の決定に重要 |
| 悪性度(グレード) | G1(高分化型)からG3(低分化型) | 予後予測と術後治療の選択 |
| 浸潤の深さ | 筋層浸潤の程度 | 手術範囲とリンパ節郭清の必要性 |
| リンパ管侵襲 | がん細胞がリンパ管に入っているか | 転移リスクの評価 |
2025年の最新治療動向
2025年現在、子宮体がん治療において注目すべき進展があります。特に免疫チェックポイント阻害薬の導入により、治療選択肢が広がっています。
免疫チェックポイント阻害薬の導入
2024年以降、進行・再発子宮体がんに対する免疫チェックポイント阻害薬の使用が承認されています。特にミスマッチ修復機能異常(dMMR)やマイクロサテライト不安定性高値(MSI-High)を示す子宮体がんでは、これらの薬剤が効果的とされています。
組織診断の結果、dMMRやMSI-Highが確認された場合、従来の化学療法に加えて免疫チェックポイント阻害薬による治療が選択肢となります。これにより、患者さんの治療成績向上が期待されています。
個別化医療の進歩
組織診断結果に基づいた個別化医療が進歩しています。2025年現在、がん遺伝子パネル検査により、患者さん一人ひとりのがんの特性に応じた治療法の選択が可能になっています。組織型や分子生物学的特徴を詳細に分析することで、より適切な治療選択ができるようになりました。
【サイト内 特設ページ】

こんにちは。17年間の活動実績を持つ、
「プロのがん治療専門アドバイザー」本村ユウジです。
がんを治すために必要なことは、たった1つです。
詳しくはこちらのページでお伝えさせてください。
→がんを治すための「たった1つの条件」とは?
術後再発リスク分類について
手術後の治療方針は、組織診断結果とがんの広がりによって決定される再発リスク分類に基づいて決められます。
低リスク群
以下の条件を満たす患者さんは低リスク群に分類されます。
- IA期の類内膜腺がんでグレード1または2
- 筋層浸潤が1/2未満
- リンパ管侵襲陰性
低リスク群の患者さんでは、手術のみで追加治療を行わないことが一般的です。
中・高リスク群
以下のような場合は中・高リスク群に分類されます。
- 類内膜腺がんでグレード3
- 漿液性腺がんや明細胞腺がん
- 筋層浸潤が深い場合
- リンパ節転移がある場合
中・高リスク群の患者さんでは、手術後に化学療法や放射線治療などの追加治療が検討されます。
患者さんが知っておくべきポイント
組織診断結果を理解する上で、患者さんが知っておくべき重要なポイントをまとめます。
セカンドオピニオンの重要性
組織診断は専門的な判断を要するため、特に悪性度の高い組織型と診断された場合や、治療方針に迷いがある場合は、セカンドオピニオンを求めることも重要です。病理診断の専門医による再検討により、より正確な診断や適切な治療方針の決定につながることがあります。
定期的な経過観察の必要性
組織型や悪性度によって、術後の経過観察の間隔や検査内容が異なります。特に漿液性腺がんや明細胞腺がんの患者さんでは、より頻繁な経過観察が必要となることがあります。主治医と相談して、適切な経過観察スケジュールを確認しましょう。
生活習慣の改善
組織診断結果に関わらず、再発予防のために生活習慣の改善は重要です。適度な運動、バランスの取れた食事、禁煙などは、がんの再発リスクを下げる可能性があります。また、肥満は子宮体がんのリスク因子でもあるため、適正体重の維持が推奨されます。
医師とのコミュニケーションのコツ
組織診断結果について医師と話す際のポイントをご紹介します。
質問リストの準備
診察前に質問リストを準備しておくことをお勧めします。以下のような質問が参考になります。
- 私のがんはどのタイプで、悪性度はどの程度ですか?
- この結果から、どのような治療が必要でしょうか?
- 再発のリスクはどの程度ありますか?
- 定期検査はどの程度の頻度で必要ですか?
- 生活上で気をつけることはありますか?
家族の同席
重要な診察には家族に同席してもらうことをお勧めします。組織診断結果の説明は複雑で、一人では聞き漏らしがちな情報もあります。家族が同席することで、より正確に情報を理解し、治療に関する意思決定を適切に行うことができます。
今後の研究動向と展望
2025年現在、子宮体がんの組織診断と治療に関して、以下のような研究が進められています。
バイオマーカーの開発
より精密な予後予測のためのバイオマーカーの研究が進んでいます。従来の組織型や悪性度に加えて、分子生物学的特徴を詳細に分析することで、個々の患者さんに最適な治療法を選択できるようになることが期待されています。
新規治療薬の開発
免疫チェックポイント阻害薬以外にも、新しいメカニズムを持つ治療薬の開発が進んでいます。特に分子標的治療薬や抗体薬物複合体(ADC)などの新しい治療選択肢が臨床試験で検討されています。
人工知能を活用した診断支援
病理診断の精度向上を目的として、人工知能(AI)を活用した診断支援システムの開発が進められています。これにより、より客観的で一貫した診断が可能になることが期待されています。
まとめ
子宮体がんの組織診断結果は、治療方針決定において極めて重要な情報です。主要な組織型である類内膜腺がん、漿液性腺がん、明細胞腺がんにはそれぞれ異なる特徴があり、悪性度や予後も大きく異なります。
2025年現在、免疫チェックポイント阻害薬の導入により治療選択肢が広がり、個別化医療の進歩により患者さん一人ひとりに最適な治療が選択できるようになっています。組織診断結果を正しく理解し、医師との十分な話し合いを通じて、最適な治療方針を決定することが重要です。