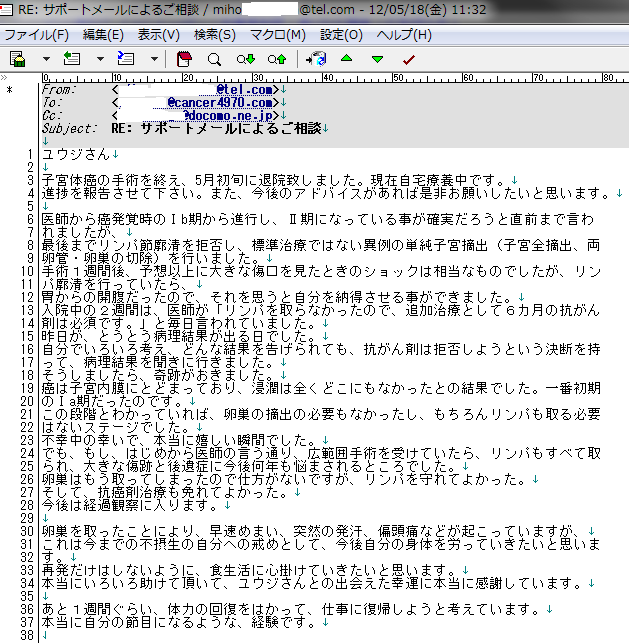子宮体がんと診断されたものの、将来の妊娠を諦めたくないという方にとって、高単位黄体ホルモン療法(MPA療法)は重要な選択肢の一つです。
この治療法は、子宮を温存しながらがん細胞の治療を目指す方法として、2025年現在でも多くの医療機関で実施されています。
子宮体がんの黄体ホルモン療法とは何か
黄体ホルモン療法は、メドロキシプロゲステロンアセテート(MPA)という人工的な黄体ホルモンを用いた治療法です。この療法は、通常40歳未満の患者さんで、子宮体がんの0期またはⅠA期G1と診断され、子宮を温存して妊娠を希望する場合に適用されます。
MPAを400mg/日という高用量で内服することにより、子宮内膜の細胞に変化を促し、がん細胞の性質を変化させていきます。この治療は「高単位黄体ホルモン療法」とも呼ばれ、子宮摘出手術を避けながら治療効果を期待できる方法として位置づけられています。
実際の臨床現場では、40歳以上の患者さんや組織分化度がG2の場合でも、患者さんの強い希望がある場合に実施されることがありますが、これらはイレギュラーなケースとして慎重に検討されます。
MPA療法の具体的な治療プロセス
治療の流れは以下のようになります。まず、MPAを400mg/日で約8週間内服します。この期間中、子宮内膜細胞は徐々に「顔つき」を変化させ、粘液を分泌する正常な細胞へと変貌していきます。
8週間経過後、静脈麻酔下で子宮内膜全面掻爬術を行います。これは子宮内腔の全面を覆う子宮内膜をかき出す手術です。掻爬する層は、子宮内膜の機能層と基底層の間で実施されます。
掻爬術後、再びMPAを400mg/日で8週間内服し、2度目の全面掻爬術を行います。この過程を6か月間(3~4回の掻爬術を含む)繰り返すことで、がん細胞の消失を目指します。
治療の作用機序
がん細胞が基底層に存在していても、子宮筋層に達していない段階であれば、治療期間中に基底層から機能層へとがん細胞が移動し、掻爬術によって除去される可能性が高くなります。この理論に基づいて、子宮内膜がんの消失を目指すのがMPA療法の基本的な考え方です。
MPA療法の効果と成功率
2025年現在までの研究データによると、適切な適応基準を満たした患者さんにおけるMPA療法の完全奏効率は約70~80%とされています。ただし、この効果は組織型や進行度によって大きく左右されます。
| 組織型・進行度 | 完全奏効率 | 再発率 |
|---|---|---|
| 0期・ⅠA期G1 | 約75~85% | 約20~30% |
| ⅠA期G2 | 約60~70% | 約30~40% |
| その他の組織型 | 約40%以下 | 約50%以上 |
治療が成功した場合でも、再発のリスクが存在するため、治療完了後は速やかに排卵性月経の誘導を行い、できるだけ早期の妊娠を目指すことが推奨されています。
MPA療法の副作用とリスク
高用量の黄体ホルモンを長期間使用するため、様々な副作用が報告されています。軽度の副作用から重篤なものまで、患者さんは治療前に十分理解しておく必要があります。
軽度から中等度の副作用
比較的頻度の高い副作用として、以下のようなものが挙げられます:
・体重増加(月1~2kg程度の増加が一般的)
・頭痛や片頭痛
・抑うつ気分や気分の変調
・肝機能数値の上昇
・むくみや体液貯留
・乳房の張りや痛み
・消化器症状(吐き気、食欲不振など)
重篤な副作用
最も注意すべき副作用は血栓症のリスク増加です。具体的には以下のような疾患のリスクが高まります:
・下肢深部静脈血栓症
・肺血栓塞栓症
・脳梗塞
・心筋梗塞
・網膜血管閉塞症
これらのリスクは、40歳以上の患者さん、肥満度の高い方、喫煙者において特に高くなるため、これらの条件に該当する場合は原則として治療禁忌とされています。
治療の適応と禁忌
MPA療法を安全に実施するためには、厳格な適応基準と禁忌事項があります。2025年現在のガイドラインでは、以下の条件が設定されています。
適応条件
・40歳未満(例外的に40歳以上でも検討される場合あり)
・子宮体がん0期またはⅠA期G1
・強い妊娠希望がある
・十分な説明と同意が得られている
・定期的な経過観察が可能
禁忌事項
・血栓症の既往歴がある
・重度の肝機能障害
・重篤な心疾患
・コントロール不良の糖尿病
・重度の肥満(BMI 35以上)
・禁煙できない場合
リスクが高い患者さんでも治療を希望する場合は、血栓予防目的でバイアスピリンの併用や、より頻繁な血液検査による監視が必要となります。
治療失敗時や再発時の対応
MPA療法が失敗した場合や、治療後に再発した場合の対応は、患者さんの年齢、全身状態、がんの性質などを総合的に判断して決定されます。
治療失敗のリスクファクター
G1の高分化型であれば、MPA療法による病勢の抑制効果は期待できますが、完全な治癒に至らない場合があります。また、治療過程で実施される複数回の子宮内膜掻爬術により、子宮内容物が卵管を通って逆流し、腹腔内にがん細胞が拡散するリスクも指摘されています。
このような場合、Ⅰ期の子宮体がんが腹膜播種を伴うⅢA期に進展する可能性があり、予後に大きな影響を与える可能性があります。
危険な組織型での注意点
G3の低分化がん、漿液性腺がん、明細胞腺がん、がん肉腫などの危険な組織型の場合、MPA療法によってⅢA期への進展リスクが高くなることが知られています。これらの組織型に対するMPA療法は、より慎重な適応判断が必要です。
治療成績と予後
国内外の多くの医療機関から、MPA療法の治療成績が報告されています。10~20例の小規模な症例集積研究が中心ですが、いずれの報告でも1~2例の進行例や死亡例が含まれており、決してリスクの低い治療ではないことが示されています。
長期的な予後については、治療成功例での5年生存率は95%以上と良好ですが、再発例や治療失敗例では予後が悪化する傾向があります。そのため、6か月の治療期間で効果が認められない場合や、治療後に再発した場合は、速やかに根治手術への移行を検討することが重要です。
2025年における最新の動向
近年、MPA療法の効果を高めるための様々な工夫が検討されています。子宮鏡下での局所治療の併用や、分子標的薬との組み合わせ療法などの研究が進められており、将来的により効果的で安全な治療法の開発が期待されています。
また、がん遺伝子検査の普及により、MPA療法の効果を予測できる可能性も示唆されており、個別化医療の観点からも注目されています。
患者さんが知っておくべきポイント
MPA療法を検討する際は、以下の点を十分理解しておくことが重要です:
・完全治癒が保証される治療ではない
・再発のリスクが存在する
・重篤な副作用のリスクがある
・治療失敗時は根治手術が必要
・定期的な経過観察が不可欠
・治療成功後は早期の妊娠が推奨される
これらの点を踏まえ、主治医とよく相談の上、治療方針を決定することが大切です。
参考文献・出典情報
1. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology: Uterine Neoplasms
3. Fertility-sparing management of endometrial cancer: A systematic review - PubMed
6. European Journal of Gynaecological Oncology
7. Gynecologic Oncology Research and Practice
8. International Journal of Clinical Oncology