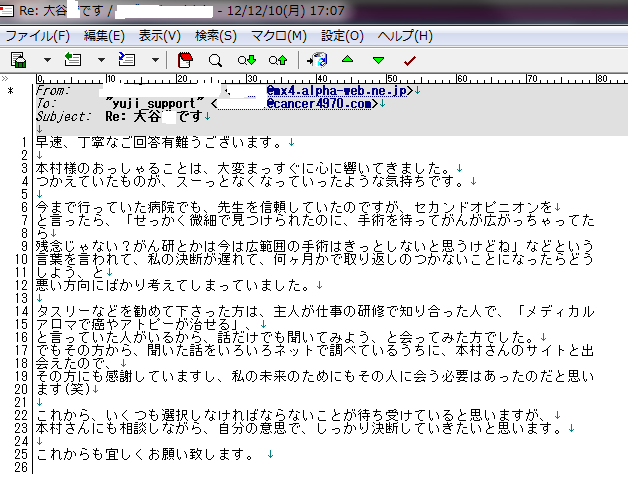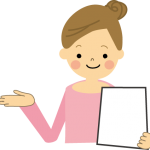
妊娠が分かって産婦人科を受診した際に、定期検診で子宮頸部の異常が見つかることがあります。特に子宮頸部上皮内がん(0期がん)の診断を受けた場合、「赤ちゃんに影響はないのか」「今すぐ治療が必要なのか」など、多くの不安を抱えることになるでしょう。
今回は、妊娠中に子宮頸がんが発見された場合の適切な対応方法と治療の選択肢について、最新の医学情報をもとに分かりやすく解説します。
【サイト内 特設ページ】

こんにちは。17年間の活動実績を持つ、
「プロのがん治療専門アドバイザー」本村ユウジです。
がんを治すために必要なことは、たった1つです。
詳しくはこちらのページでお伝えさせてください。
→がんを治すための「たった1つの条件」とは?
妊娠中の子宮頸がん発見率と基本的な対応方針
日本では妊娠中の子宮頸がん検診により、年間約1,000~1,500人の妊婦さんに子宮頸部の異常が見つかっています。このうち、上皮内がん(0期)が約70%を占め、浸潤がんは約30%となっています。
妊娠中に子宮頸がんが発見された場合の基本的な対応方針は、母体の安全と胎児の健康を両立させることです。多くの場合、出産を優先し、がんの治療は産後に延期されます。これは、妊娠初期から中期にかけての治療が流産や早産のリスクを高める可能性があるためです。
子宮頸部上皮内がん(0期がん)の場合の治療選択
妊娠中の経過観察方法
0期がんと診断された場合、基本的には出産まで経過観察を行います。定期的な検査スケジュールは以下の通りです:
| 妊娠週数 | 検査内容 | 目的 |
|---|---|---|
| 12週 | 細胞診・コルポスコピー | 進行の有無を確認 |
| 20週 | 細胞診・コルポスコピー | 浸潤がんへの進行チェック |
| 28週 | 細胞診・コルポスコピー | 出産前最終確認 |
これらの検査により、がんの進行状況を継続的に監視します。多くの場合、妊娠中に上皮内がんが浸潤がんに進行することは稀で、安全に出産まで経過観察が可能です。
妊娠中の円錐切除術について
妊娠20週までの期間において、浸潤がんが強く疑われる場合を除いて、円錐切除術は原則として行いません。その理由は以下の通りです:
・出血多量のリスク
・流産の危険性
・早産の可能性
・子宮頸管無力症の発症リスク
これらのリスクを回避するため、浸潤がんの明確な証拠がない限り、治療は産後まで延期されます。
【サイト内 特設ページ】

こんにちは。17年間の活動実績を持つ、
「プロのがん治療専門アドバイザー」本村ユウジです。
がんを治すために必要なことは、たった1つです。
詳しくはこちらのページでお伝えさせてください。
→がんを治すための「たった1つの条件」とは?
浸潤がんが疑われる場合の対応
妊娠中期での治療判断
妊娠20週以降に浸潤がんが強く疑われる場合、母体の生命に関わるリスクを考慮して、治療方針の見直しが必要になります。この場合の選択肢は以下の通りです:
1. 妊娠継続と同時治療
2. 妊娠中断と根治的治療
3. 帝王切開による早期分娩後の治療
どの選択肢を取るかは、がんの進行度、妊娠週数、患者さんの希望を総合的に判断して決定されます。
進行期別の治療戦略
浸潤がんの場合、進行期(ステージ)に応じて治療方針が異なります:
IA1期(微小浸潤がん):円錐切除術または単純子宮全摘術
IA2期以上:広汎子宮全摘術または放射線治療
妊娠中の場合、これらの治療は胎児への影響を最小限に抑えるタイミングで実施されます。
産後の治療計画と経過観察
出産後の検査スケジュール
出産後の治療計画は、妊娠中の経過観察結果に基づいて策定されます。一般的なスケジュールは以下の通りです:
産後6~8週:初回検査(悪露終了後)
産後3か月:詳細検査(細胞診・コルポスコピー・生検)
産後6か月:治療方針の最終決定
授乳と治療の両立
産後3か月の検査で浸潤がんが疑われる場合、治療のために断乳が必要になることがあります。これは、手術や放射線治療が授乳中の女性に与える影響を避けるためです。
円錐切除術を受ける場合、月経の回帰を確認してから実施することが一般的です。これは、妊娠・出産による子宮頸部の変化が安定するのを待つためです。
【サイト内 特設ページ】

こんにちは。17年間の活動実績を持つ、
「プロのがん治療専門アドバイザー」本村ユウジです。
がんを治すために必要なことは、たった1つです。
詳しくはこちらのページでお伝えさせてください。
→がんを治すための「たった1つの条件」とは?
妊娠中の子宮頸がん治療における最新の動向
センチネルリンパ節生検の活用
2024年から2025年にかけて、妊娠中の子宮頸がん治療においてセンチネルリンパ節生検の応用が検討されています。この技術により、リンパ節転移の有無をより正確に評価し、過度な手術を避けることが可能になっています。
分子標的治療薬の研究進展
HPV(ヒトパピローマウイルス)に対する分子標的治療薬の研究が進んでおり、将来的には妊娠中でも安全に使用できる治療選択肢が増える可能性があります。
次回妊娠を希望する場合の注意点
治療後の妊娠可能性
円錐切除術を受けた後でも、多くの場合で妊娠は可能です。ただし、以下の点に注意が必要です:
・子宮頸管無力症のリスク
・早産の可能性
・帝王切開が必要になる場合
妊娠前の準備
次回妊娠を希望する場合、以下の準備が重要です:
・定期的な子宮頸がん検診の継続
・HPVワクチンの接種(該当する場合)
・産婦人科医との十分な相談
家族へのサポートと心理的ケア
パートナーとの情報共有
妊娠中の子宮頸がん診断は、患者さんだけでなくパートナーにとっても大きな不安要因となります。正確な情報を共有し、一緒に治療方針を検討することが重要です。
セカンドオピニオンの活用
治療方針について不安がある場合、セカンドオピニオンを求めることも有効です。特に浸潤がんが疑われる場合は、複数の専門医の意見を聞くことで、より適切な治療選択ができます。
予防と早期発見の重要性
定期検診の徹底
子宮頸がんの多くはHPV感染が原因であり、定期的な検診により早期発見が可能です。妊娠を希望する女性は、妊娠前から定期的な子宮頸がん検診を受けることが推奨されます。
HPVワクチンの効果
HPVワクチンの接種により、子宮頸がんの発症リスクを約70~90%減少させることができます。既に妊娠している場合はワクチン接種はできませんが、出産後の接種を検討することができます。
妊娠中に子宮頸がんが見つかった場合、多くは出産を優先し、産後に治療を行うことが可能です。重要なのは、医療チームと密に連携し、定期的な経過観察を怠らないことです。