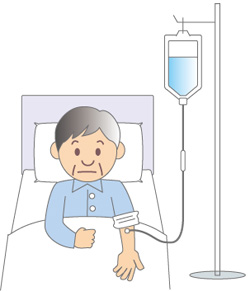
がん放射線治療における晩期障害とは
晩期障害とは、がんの放射線治療の照射が終了してから数か月から数年後に発生する有害事象です。この障害は、放射線治療中や直後に現れる急性期副作用とは明確に区別されます。
晩期障害は、放射線照射による組織の修復過程で血流が低下し、間質結合組織の増殖によって組織が硬くなることで発症します。主な特徴として、放射線照射による直腸炎、放射線脊髄炎、肺繊維症、白内障などがあり、一般的に症状は重く、元の状態に戻ることはありません。
晩期障害の発生頻度は比較的まれですが、一度発症すると回復が困難であることが多いため、放射線治療では医師が晩期障害を起こさないよう線量と照射野に細心の注意を払う必要があります。事前にリスクを理解したうえで治療法を選択することが重要です。
急性期副作用と晩期障害の違い
放射線治療の副作用は、発症時期によって急性期副作用と晩期障害の2種類に分類されます。これらの違いを理解することで、適切な対処ができるようになります。
急性期副作用の特徴
急性期副作用は、治療開始後から照射後数週間までに生じる反応です。多くの人に発生する可能性がありますが、治療が終われば徐々に回復することが多いという特徴があります。主な症状には以下があります:
- 皮膚の発赤や色素沈着
- 脱毛
- 口内炎や粘膜炎
- 疲労感
- 消化器症状(吐き気、下痢など)
これらの症状は時間の経過とともに改善され、適切な対症療法により症状を軽減することが可能です。
晩期障害の特徴
一方、晩期障害は照射後数か月から数年で生じる反応で、発生することはまれですが、生じると回復困難、あるいは回復に長時間を要することが多い傾向にあります。2025年現在の研究では、晩期障害の発症メカニズムがより詳しく解明されており、予防策も向上しています。
| 項目 | 急性期副作用 | 晩期障害 |
|---|---|---|
| 発症時期 | 治療開始後から数週間以内 | 治療終了後数か月から数年後 |
| 発生頻度 | 比較的多い | まれ |
| 回復性 | 治療終了後に改善 | 回復困難 |
| 重症度 | 軽度から中等度 | 重篤になることが多い |
「自分の判断は正しいのか?」と不安な方へ

がん治療。
何を信じれば?
不安と恐怖で苦しい。
がん治療を左右するのは
治療法より“たった1つの条件”です。
まず、それを知ってください。
がん専門アドバイザー 本村ユウジ
部位別の晩期障害について
晩期障害は放射線を照射した部位によって異なる症状が現れます。以下、主要な部位別に詳しく解説します。
頭部への照射による晩期障害
脳に耐容線量を超える照射が行われた場合、脳や脳神経が障害を受け、以下の症状が発生することがあります:
- 難聴
- 顔面神経麻痺
- 脳障害
- 下垂体機能低下
- 認知機能の低下
- 記憶障害
また、眼球に放射線が照射された場合には、白内障や網膜症が発生し、視力障害の原因となります。2024年の最新の研究では、強度変調放射線治療(IMRT)の活用により、これらの重要な器官への放射線量を最小限に抑える技術が向上しています。
口腔・頸部への照射による晩期障害
口腔や頸部への過剰線量照射により、以下の障害が発生する可能性があります:
- 皮膚潰瘍や皮下組織の硬化
- 唾液腺機能低下による口腔乾燥や味覚異常
- 軟骨や下顎骨の壊死
- 放射線脊髄症による四肢の麻痺やしびれ
- 甲状腺機能低下
口腔がんなどの治療では、唾液腺に耐容線量以上の線量が照射されることがあるため、唾液の減少により口の乾きや味覚異常が生じることがあります。重篤な場合、軟骨や下顎骨が壊死し、手術が必要になることもあります。
肺・縦隔への照射による晩期障害
肺がんへの照射では、以下の晩期障害が発生する可能性があります:
- 放射線性肺炎
- 肺線維症による肺機能低下
- 食道狭窄
- 心外膜炎
- 心不全
- 放射線脊髄症
肺の線維化が起こり、肺機能が低下します。線維化した肺の体積が大きくなれば、患者さんは息苦しさを感じるようになります。食道に過剰な線量が照射された場合、食道が細くなり、食事の通過が困難になることもあります。
乳房・胸壁への照射による晩期障害
乳房温存療法後の放射線治療では、以下の障害が生じる可能性があります:
- 乳房の硬化
- 肺の部分的線維化
- リンパ浮腫
- 上腕神経障害による手のしびれや筋力低下
- 肋骨骨折のリスク増加
特に腋窩照射後のリンパ浮腫は患者さんの日常生活に大きな影響を与える可能性があります。
腹部・骨盤への照射による晩期障害
腹部や骨盤への照射により、以下の晩期障害が発生することがあります:
- 放射線性直腸炎・結腸炎
- 膀胱壁の硬化や萎縮
- 血尿
- 下肢浮腫
- 不妊
- 肝機能障害
- 腎機能低下
直腸や結腸が過剰照射を受けた場合、潰瘍ができ出血することがあります。膀胱では、膀胱壁が硬くなり萎縮が起こったり、血尿が出現することもあります。
2025年における最新の予防策と治療技術
晩期障害の予防には、最新の放射線治療技術の活用が重要です。2024年から2025年にかけて、以下の技術がさらに発展しています。
強度変調放射線治療(IMRT)の進歩
IMRTは、がんに放射線を集中させ、周辺臓器への放射線量を最小限に抑える技術です。2024年に更新された日本放射線腫瘍学会の強度変調放射線治療(IMRT)臨床的ガイドラインでは、より精密な照射技術の標準化が進んでいます。
最新のIMRT技術には以下の特徴があります:
- マルチリーフコリメーター(MLC)の高精度化
- 回転型IMRT(VMAT)による治療時間の短縮
- リアルタイム画像誘導による位置精度の向上
画像誘導放射線治療(IGRT)の活用
IGRTは、治療日ごとに画像を撮影し、照射位置を正確に調整する技術です。2022年のIGRTガイドラインに基づき、より安全で正確な治療が可能になっています。
トモセラピーによる高精度治療
トモセラピーは、IMRT専用の治療装置として、広範囲かつ線量集中度の高い照射を可能にします。特に以下のような特徴があります:
- CT撮影機能を内蔵した正確な位置合わせ
- 広範囲照射への対応
- 複雑な形状の腫瘍への最適化された線量分布
晩期障害の早期発見と対処法
晩期障害は一度発症すると回復が困難なため、早期発見と適切な対処が重要です。
定期的な経過観察の重要性
放射線治療後は、定期的な診察により慎重に経過を観察していくことが必要です。医師は以下の点に注意して経過を追います:
- 照射部位の皮膚や粘膜の変化
- 臓器機能の評価
- 新たな症状の出現
- 画像検査による構造的変化の確認
患者さん自身ができること
患者さん自身も以下の点に注意し、異常を感じた場合は早めに医療機関に相談することが大切です:
- 照射部位の変化や症状の観察
- 定期的な検診の受診
- 生活習慣の改善(禁煙・禁酒など)
- 口腔ケアの徹底(頭頸部照射の場合)
晩期障害を最小限に抑えるための生活上の注意点
晩期障害のリスクを減らすためには、治療中および治療後の生活習慣も重要です。
禁煙・禁酒の重要性
喫煙や飲酒は放射線による組織への影響を悪化させる可能性があります。特に頭頸部の放射線治療を受けた患者さんでは、禁煙・禁酒が晩期障害の予防に極めて重要です。
口腔ケアの徹底
頭頸部への放射線治療を受けた患者さんでは、唾液分泌の低下により虫歯や歯周病のリスクが高まります。定期的な歯科受診と適切な口腔ケアが必要です。
栄養管理と運動
適切な栄養管理と適度な運動は、組織の修復能力を高め、晩期障害のリスクを軽減する可能性があります。
まとめ
がんの放射線治療における晩期障害は、治療終了後に発生する重要な合併症です。急性期副作用とは異なり、一度発症すると回復が困難なため、予防が最も重要です。
2025年現在、IMRT、IGRT、トモセラピーなどの最新技術により、晩期障害のリスクは大幅に軽減されています。しかし、完全に予防することは困難であり、治療前のリスク評価と治療後の継続的な経過観察が不可欠です。放射線治療を検討している患者さんは、晩期障害のリスクも含めて医師とよく相談し、最適な治療法を選択することをお勧めします。
参考文献・出典情報
- SURVIVORSHIP.JP - 放射線治療の副作用(有害事象)とは
- 新松戸中央総合病院 - 放射線治療による副作用について
- 国立がん研究センター がん情報サービス - 晩期合併症/長期フォローアップ
- 国立がん研究センター がん情報サービス - 放射線治療の実際
- 日本放射線腫瘍学会 - 強度変調放射線治療(IMRT)臨床的ガイドライン2024
- 虎の門病院 - トモセラピーによるオーダーメイド放射線治療
- 国立がん研究センター がん情報サービス - 放射線治療の種類と方法
- 東京大学医学部附属病院 放射線科 - IMRT
- がん研有明病院 - 強度変調放射線治療(IMRT)
- MSDマニュアル家庭版 - 放射線療法による神経系の損傷



