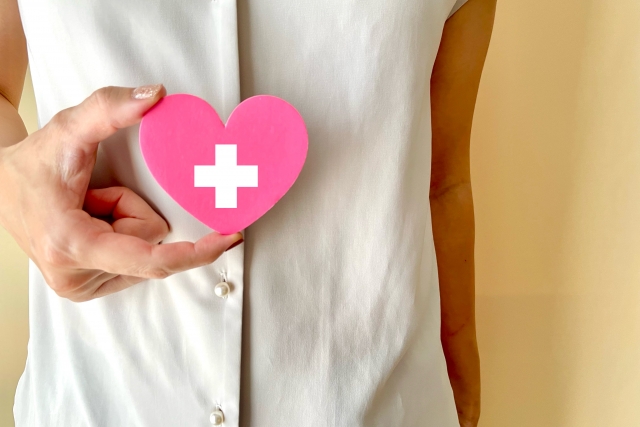
【サイト内 特設ページ】

こんにちは。17年間の活動実績を持つ、
「プロのがん治療専門アドバイザー」本村ユウジです。
がんを治すために必要なことは、たった1つです。
詳しくはこちらのページでお伝えさせてください。
→がんを治すための「たった1つの条件」とは?
2025年胃がん治療の特徴:
胃がんの治療戦略は、従来、原発腫瘍の深達度(T因子)、リンパ節転移の有無と範囲(N因子)、遠隔臓器への転移(M因子)を組み合わせたTNM病期分類に基づいて決定されてきました。
この解剖学的な進行度分類は、依然として予後予測と治療方針(手術適応の有無など)の根幹をなす重要な指標です。しかし、2025年を迎えた現在、この伝統的なパラダイムは大きな転換点を迎えています。切除不能・再発胃がんの領域では、TNM分類のみで治療法を決定することはもはや十分ではなく、がん細胞が持つ分子生物学的な特性、すなわち「バイオマーカー」の評価が治療選択に不可欠となっています。
この変化を主導しているのが、日本胃癌学会が2025年3月に改訂した「胃癌治療ガイドライン第7版」です。
この最新ガイドラインでは、切除不能・進行再発胃がんにおけるバイオマーカーの重要性が強調され、治療アルゴリズムが大幅に更新されました。特に、以下の4つのバイオマーカーは、治療方針を決定する上で極めて重要な役割を担っています。
- HER2(Human Epidermal Growth Factor Receptor 2): ヒト上皮増殖因子受容体2型。以前から標的治療薬が存在しますが、治療薬の選択肢が拡大しています。
- PD-L1(Programmed Death-Ligand 1): 免疫チェックポイント分子。CPS(Combined Positive Score)という指標で評価され、免疫チェックポイント阻害薬の効果を予測します。
- MSI-H/dMMR(Microsatellite Instability-High/Mismatch Repair Deficient): 高頻度マイクロサテライト不安定性/ミスマッチ修復機構欠損。免疫チェックポイント阻害薬が著効する可能性が高いことを示します。
- Claudin 18.2(CLDN18.2): クローディン18.2。正常な胃粘膜細胞にも存在しますが、胃がん細胞で高発現することがあり、2024年に承認された新規分子標的薬のターゲットとなります。
これらのバイオマーカーに基づく治療選択は、日本胃癌学会が策定した「切除不能進行・再発胃癌バイオマーカー検査の手引き」にも詳述されており、臨床現場での標準的な実践として定着しつつあります。
このパラダイムシフトがもたらす最も重要な臨床的帰結は、診断時における網羅的なバイオマーカー検査の必須化です。
従来はHER2検査が先行し、その結果に応じて他の検査が追加される逐次的なアプローチが取られることもありました。
しかし、2025年現在、HER2陰性症例に対する一次治療の選択肢が、CLDN18.2陽性であればゾルベツキシマブ併用化学療法、PD-L1 CPSが高値であればニボルマブ併用化学療法といった形で複数存在するため、治療開始前にこれらのバイオマーカー情報をすべて把握しておくことが、患者さんにとって最適な初回治療を決定する上で不可欠となります。
したがって、切除不能・再発胃がんの診断が確定した際には、HER2、PD-L1、MSI、CLDN18.2の4項目を同時に検査する「Upfront Quad-Panel」が新たな標準診断プロセスとなりつつあります。これは、病理診断部門のワークフローや検査結果の報告体制にも変革を迫る、胃がん個別化医療時代の幕開けを象徴する動きです。
| バイオマーカー | 定義・臨床的意義 | 主な検査方法 | 2025年時点での主要な関連治療薬 |
| HER2 | がん細胞の増殖に関わるタンパク質の過剰発現または遺伝子増幅 | IHC法、ISH法 | トラスツズマブ、トラスツズマブ デルクステカン |
| PD-L1 (CPS) | 腫瘍細胞および免疫細胞におけるPD-L1タンパクの発現レベル | IHC法 (CPSスコア) | ニボルマブ、ペムブロリズマブ |
| MSI-H/dMMR | DNAミスマッチ修復機能の欠損 | PCR法、IHC法 | ペムブロリズマブ |
| Claudin 18.2 | 胃粘膜由来のがん細胞に高発現する膜タンパク質 | IHC法 | ゾルベツキシマブ |
切除不能・再発胃がんに対する薬物療法の新時代
バイオマーカー主導の治療選択が標準となったことで、切除不能・再発胃がんの薬物療法は新たな時代に突入しました。
特定の分子標的を持つ患者群に対して、従来よりも高い効果が期待できる薬剤が次々と登場し、治療アルゴリズムはより複雑かつ個別化されています。
Claudin 18.2標的治療の登場:ゾルベツキシマブの臨床的意義
2024年3月に日本で承認されたゾルベツキシマブ(販売名:ビロイ)は、胃がん治療における画期的な新薬です。
本剤は、胃がん細胞の約3~4割で高発現が認められる膜タンパク質「Claudin 18.2(CLDN18.2)」を標的とする世界初の抗体薬です。その作用機序は、がん細胞表面のCLDN18.2に結合し、抗体依存性細胞傷害(ADCC)および補体依存性細胞傷害(CDC)を介して免疫系を活性化させ、がん細胞を攻撃するというものです。
この薬剤の承認の根拠となったのは、2つの国際共同第III相臨床試験、SPOTLIGHT試験とGLOW試験です。
SPOTLIGHT試験では、化学療法(mFOLFOX6)にゾルベツキシマブを上乗せすることで、プラセボ群と比較して病勢進行または死亡のリスクが約25%有意に低下し(PFSハザード比 0.751)、全生存期間(OS)も中央値で約2.7カ月延長しました(OSハザード比 0.750)。同様に、GLOW試験でも化学療法(CAPOX)への上乗せにより、PFSとOSの有意な延長が示されました。これらの結果は、CLDN18.2陽性という新たなバイオマーカーで定義される大規模な患者群(スクリーニングされた患者の約38%)に対して、新たな一次治療の標準選択肢が確立されたことを意味します。
ゾルベツキシマブの投与には、コンパニオン診断薬である「ベンタナ OptiView CLDN18(43-14A)」を用いた免疫組織化学染色(IHC)検査が必須であり、腫瘍細胞の75%以上で中等度から強度の染色が認められた場合に「陽性」と判定されます。
一方で、本剤は特徴的な有害事象プロファイルを持っています。
特に、悪心(80%以上)と嘔吐(60%以上)が高頻度に認められます。
これらは本剤の標的であるCLDN18.2が正常な胃粘膜にも発現していることによるオンターゲット作用と考えられており、特に初回投与時に強く現れる傾向があります。そのため、日本癌治療学会は「制吐薬適正使用ガイドライン速報」を発出し、NK1受容体拮抗薬、5-HT3受容体拮抗薬、デキサメタゾン、オランザピンなどを含む強力な予防的制吐療法の実施を推奨しています。
適切な有害事象管理を行うことで、多くの患者さんが治療を継続することが可能で、2025年以降、本剤はCLDN18.2陽性胃がん治療の根幹を担う薬剤となります。
HER2陽性胃がん治療の進化:トラスツズマブ デルクステカンの役割拡大
HER2陽性胃がんの治療は、抗体薬物複合体(ADC)であるトラスツズマブ デルクステカン(T-DXd、販売名:エンハーツ)の登場により、二次治療以降の戦略が大きく進化しました。
2025年6月に結果が公表された国際共同第III相試験(DESTINY-Gastric04)は、トラスツズマブを含む一次治療後に増悪したHER2陽性の治癒切除不能な進行・再発胃がん患者さんを対象に、T-DXdと従来の標準治療であったラムシルマブ+パクリタキセル併用療法を比較したものです。
この試験において、T-DXd群は主要評価項目である全生存期間(OS)を有意に延長し、死亡リスクを30%減少させました(OS中央値:14.7カ月 vs 11.4カ月、ハザード比 0.70)。
無増悪生存期間(PFS)や奏効割合(ORR)といった副次評価項目においても、T-DXd群が有意に良好な結果を示しました。
この結果は、HER2陽性胃がんの二次治療におけるT-DXdの優位性を確立し、新たな標準治療としての地位を不動のものとしました。これにより、HER2陽性胃がん患者さんに対しては、「一次治療:トラスツズマブ+化学療法(+PD-L1陽性であればペムブロリズマブ)」から「二次治療:T-DXd」という明確でエビデンスに基づいた治療シークエンスが初めて構築されました。
ただし、T-DXdの投与においては、重篤な有害事象である間質性肺疾患(ILD)に最大限の注意が必要です。
DESTINY-Gastricシリーズの試験では、約10-14%の患者さんにILDが報告されており、死亡に至った症例も存在します。
そのため、投与中は定期的な胸部画像検査や動脈血酸素飽和度(SpO2)のモニタリングが必須であり、呼吸困難、咳嗽、発熱などの初期症状を見逃さず、疑わしい場合は速やかに投与を中止し、呼吸器専門医と連携してステロイド投与などの適切な処置を行うことが極めて重要です。T-DXdの有効性は、このような徹底したリスク管理体制のもとで初めて最大限に活かされます。
一次治療における免疫療法の確立と課題
HER2陰性胃がんの一次治療においては、免疫チェックポイント阻害薬と化学療法の併用が標準治療の一つとして確立されました。
この流れを決定づけたのが、CheckMate-649試験(グローバル)とATTRACTION-4試験(アジア)です。
CheckMate-649試験では、ニボルマブ+化学療法が化学療法単独と比較して、主要評価項目であるOSとPFSの両方を統計学的に有意に延長しました。
この効果は特にPD-L1 CPSが5以上の集団で顕著であり、CPSスコアが免疫療法の効果を予測する重要なバイオマーカーであることが示されました。一方、ATTRACTION-4試験では、PFSの有意な延長は認められたものの、もう一つの主要評価項目であるOSは達成されませんでした。
この両試験におけるOSの結果の乖離は、臨床現場に重要な示唆を与えます。その一因として、ATTRACTION-4試験の化学療法単独群において、後治療として免疫チェックポイント阻害薬が投与された患者さんの割合が比較的高かったことが挙げられます。
これにより、対照群の生存期間が延長し、両群間のOSの差が統計学的に検出しにくくなった可能性があります。このことは、免疫療法の恩恵を最大化するためには、二次治療以降ではなく、一次治療の段階から導入することの重要性を示唆しています。したがって、2025年時点での最適な戦略は、診断時にPD-L1 CPSを評価し、特に高値の患者さんに対しては初回治療から積極的に免疫チェックポイント阻害薬を併用することです。
免疫療法の導入に伴い、免疫関連有害事象(irAE)の管理も必須となります。
間質性肺疾患、大腸炎、肝機能障害、内分泌障害など、その症状は多岐にわたるため、非特異的な症状であっても常にirAEを鑑別に挙げ、早期発見と専門医との連携による迅速な対応が求められます。
| 試験名 | 対象集団 | 介入群 | 対照群 | 主要評価項目 | OSハザード比 (95% CI) | PFSハザード比 (95% CI) |
| SPOTLIGHT | CLDN18.2陽性, HER2陰性 1次治療 | ゾルベツキシマブ + mFOLFOX6 | プラセボ + mFOLFOX6 | PFS, OS | 0.750 (0.601−0.936) | 0.751 (0.598−0.942) |
| GLOW | CLDN18.2陽性, HER2陰性 1次治療 | ゾルベツキシマブ + CAPOX | プラセボ + CAPOX | PFS, OS | 0.771 (0.615−0.965) | 0.687 (0.544−0.866) |
| DESTINY-Gastric04 | HER2陽性 2次治療 | T-DXd | ラムシルマブ + パクリタキセル | OS | 0.70 | (PFS) 0.75 |
| CheckMate 649 | HER2陰性 1次治療 (PD-L1 CPS≥5) | ニボルマブ + 化学療法 | 化学療法 | OS, PFS | 0.71 (0.61−0.83) | 0.68 (0.56−0.81) |
| JACCRO GC-07 | Stage III 治癒切除後 術後補助 | S-1 + ドセタキセル | S-1 | 3年無再発生存率 | - | 0.632 (0.489−0.816) |
【サイト内 特設ページ】

こんにちは。17年間の活動実績を持つ、
「プロのがん治療専門アドバイザー」本村ユウジです。
がんを治すために必要なことは、たった1つです。
詳しくはこちらのページでお伝えさせてください。
→がんを治すための「たった1つの条件」とは?
周術期および外科的治療における最新動向
切除可能な局所進行胃がんに対する治療戦略もまた、薬物療法と外科手技の両面で進化を続けています。
手術と化学療法をいかに最適に組み合わせるか、そして手術自体の低侵襲化をいかに進めるかが主要なテーマとなっています。
周術期化学療法の最適化:FLOTとDOSレジメンの比較
長らく、切除可能胃がんの補助化学療法は、アジアでは術後に行うのが標準、欧米では術前・術後に行う周術期化学療法が標準と、地域差が存在しました。
しかし近年、アジアでも周術期化学療法の有効性を示すエビデンスが蓄積され、その流れが変わりつつあります。
その代表例が、韓国で行われたPRODIGY試験です。この試験では、術前化学療法としてDOS療法(ドセタキセル、オキサリプラチン、S-1)を行うことで、手術単独先行群に比べて無増悪生存期間の有意な延長が示されました。
欧米の標準であるFLOT療法(5-FU、ロイコボリン、オキサリプラチン、ドセタキセル)と並び、DOS療法はアジアにおける有力な周術期化学療法の選択肢として注目されています。
2025年版の日本胃癌学会ガイドラインでも、周術期化学療法が新たなクリニカルクエスチョンとして取り上げられており、日本国内でもその導入が本格的に議論されています。
さらに、次世代の治療法として、周術期化学療法に免疫チェックポイント阻害薬を組み合わせる試みも進んでいます。
MATTERHORN試験では、FLOT療法にデュルバルマブを併用することで、イベントフリー生存率の改善傾向が報告されており、今後の標準治療を塗り替える可能性を秘めています。
術後補助化学療法の進展:JACCRO GC-07試験のインパクト
術後補助化学療法においても、より強力なレジメンが標準治療の地位を確立しました。
Stage IIIの治癒切除胃がん患者さんを対象とした日本の臨床試験JACCRO GC-07(START-2)では、従来の標準治療であったS-1単独療法と、S-1にドセタキセルを併用する治療法が比較されました。
この試験は、中間解析の段階で、S-1+ドセタキセル併用群がS-1単独群に比べて3年無再発生存率を有意に改善した(66% vs 50%)ことから、有効中止となりました。
この結果に基づき、Stage IIIの治癒切除胃がんに対する術後補助化学療法として、S-1+ドセタキセル併用療法が新たな標準治療として推奨されることになりました。
低侵襲手術の進化:ロボット支援下胃切除術と単孔式手術
外科的治療の分野では、低侵襲化が大きな潮流となっています。従来の腹腔鏡下手術の限界を超える技術として、ロボット支援下手術が急速に普及しています。手術支援ロボット「ダヴィンチ」は、高精細な3D画像、手ぶれ補正機能、そして人間の手首以上の可動域を持つ多関節鉗子を特徴とし、腹腔鏡下手術よりも精密で安全なリンパ節郭清や吻合を可能にします。
2025年には、この技術がさらに進化し、「ダヴィンチSP」を用いた単孔式手術が胃がん治療に導入されました。
これは、臍部など1カ所の小さな切開創から手術器具を挿入し、胃切除と再建を完遂する究極の低侵襲手術です。傷が一つであるため、術後の痛みが少なく、整容性にも優れ、患者さんの早期回復に大きく貢献することが期待されます。
これらの低侵襲手術の進歩は、周術期化学療法の発展と相乗効果を生みます。効果的な術前化学療法によって腫瘍が縮小すれば、ロボット支援下手術のような精密な手技がより安全かつ確実に行えるようになります。そして、低侵襲手術によって患者さんの術後回復が早まれば、体力が落ちないうちに術後補助化学療法を開始・完遂することが可能となり、治療全体の成績向上につながります。
このように、薬物療法と外科治療の進歩が相互に作用し合い、治癒を目指す治療の質を全体として高めているのが2025年の胃がん治療の姿です。
未来への展望:個別化医療を加速する先端技術
2025年の胃がん治療はバイオマーカー主導の個別化医療へと大きく舵を切りました。血液検体を用いた遺伝子解析技術や、AIの活用など、さらなる先端技術が臨床応用に向けて研究されており、未来の治療を大きく変える可能性を秘めています。
リキッドバイオプシーの臨床応用への期待
リキッドバイオプシーは、血液中にごく微量に存在するがん細胞由来のDNA(circulating tumor DNA; ctDNA)を解析する技術です。患者さんにとっては採血のみで済むため、繰り返し行うことが可能な低侵襲な検査であり、大きく期待されています。
日本では、産学連携の全国がんゲノムスクリーニング事業「SCRUM-Japan」がこの分野の研究を牽引しています。消化器がんを対象としたMONSTAR-SCREENやGOZILAといったプロジェクトでは、数千人規模の患者さんから収集した血液検体を用いて、リキッドバイオプシーによる網羅的ゲノム解析の有用性が検証されています。
これらの研究により、リキッドバイオプシーは組織生検に比べて迅速に結果が得られ、より多くの患者さんを適切な臨床試験につなげられる可能性が示されています。
将来的に期待される臨床応用は主に二つあります。一つは、術後の再発モニタリングです。
手術後にctDNAを検出することで、画像検査では捉えられない微小な残存病変(Minimal Residual Disease; MRD)を特定し、再発リスクを層別化します。これにより、再発リスクが高い患者さんにはより強力な術後補助化学療法を行い、リスクが低い患者さんには不要な治療を回避するといった、真の個別化治療が可能になります。このコンセプトは、大腸がん領域で進行中の「CIRCULATE-Japan」プロジェクトで検証されています。
もう一つは、薬物療法中の効果モニタリングと耐性機序の解明です。治療中にctDNAを経時的に測定することで、治療効果を早期に判定したり、治療が効かなくなった際に耐性に関わる遺伝子変異の出現をリアルタイムで捉えたりすることが可能になります。これにより、CTスキャンで腫瘍の増大が確認されるよりも早く、次の治療戦略へと移行できるようになります。
2025年時点では、胃がん領域におけるリキッドバイオプシーはまだ研究段階が中心ですが、SCRUM-Japanのような大規模プロジェクトから得られるエビデンスは、近い将来、胃がん治療を現在の「静的な治療計画」から、リアルタイムの分子情報に基づいて治療法を最適化し続ける「動的な治療戦略」へと変貌させるでしょう。
統合的治療戦略と今後の研究開発の方向性
2025年の胃がん治療は、バイオマーカーに基づく薬物療法の進展、周術期治療の最適化、そして低侵襲外科手術の進化という三つの潮流が融合し、より効果的で個別化された統合的治療戦略へと発展しています。
今後の研究開発は、これらの流れをさらに加速させる方向へ進みます。薬物療法では、エンハーツに続く新規ADCの開発や、複数の免疫チェックポイント阻害薬を組み合わせる複合免疫療法などが期待されます。
また、MONSTAR-SCREENなどで得られる膨大なゲノム情報や臨床情報をAIで解析し、新たな治療標的やバイオマーカーを同定する研究も活発化すると思われます。














