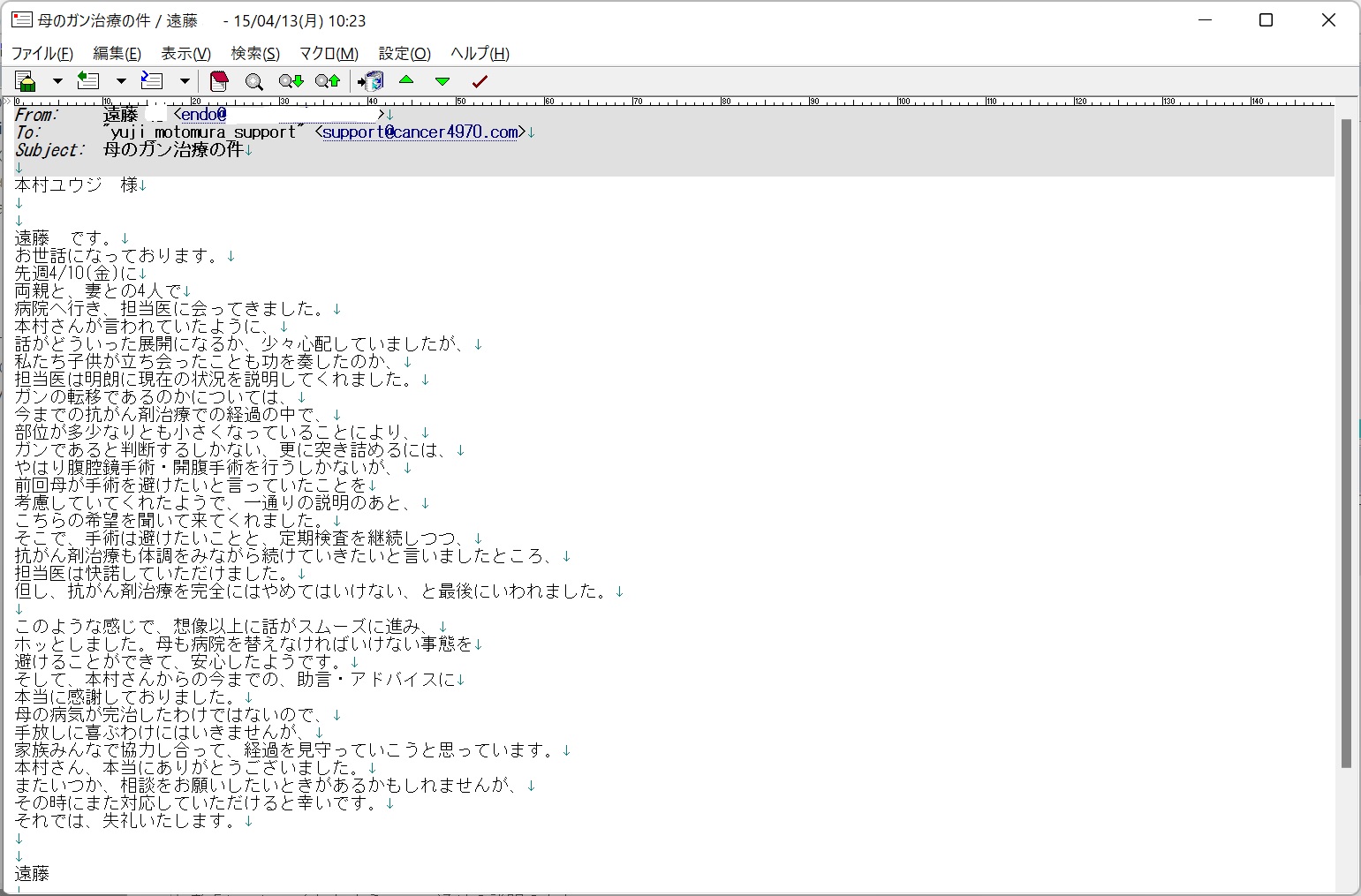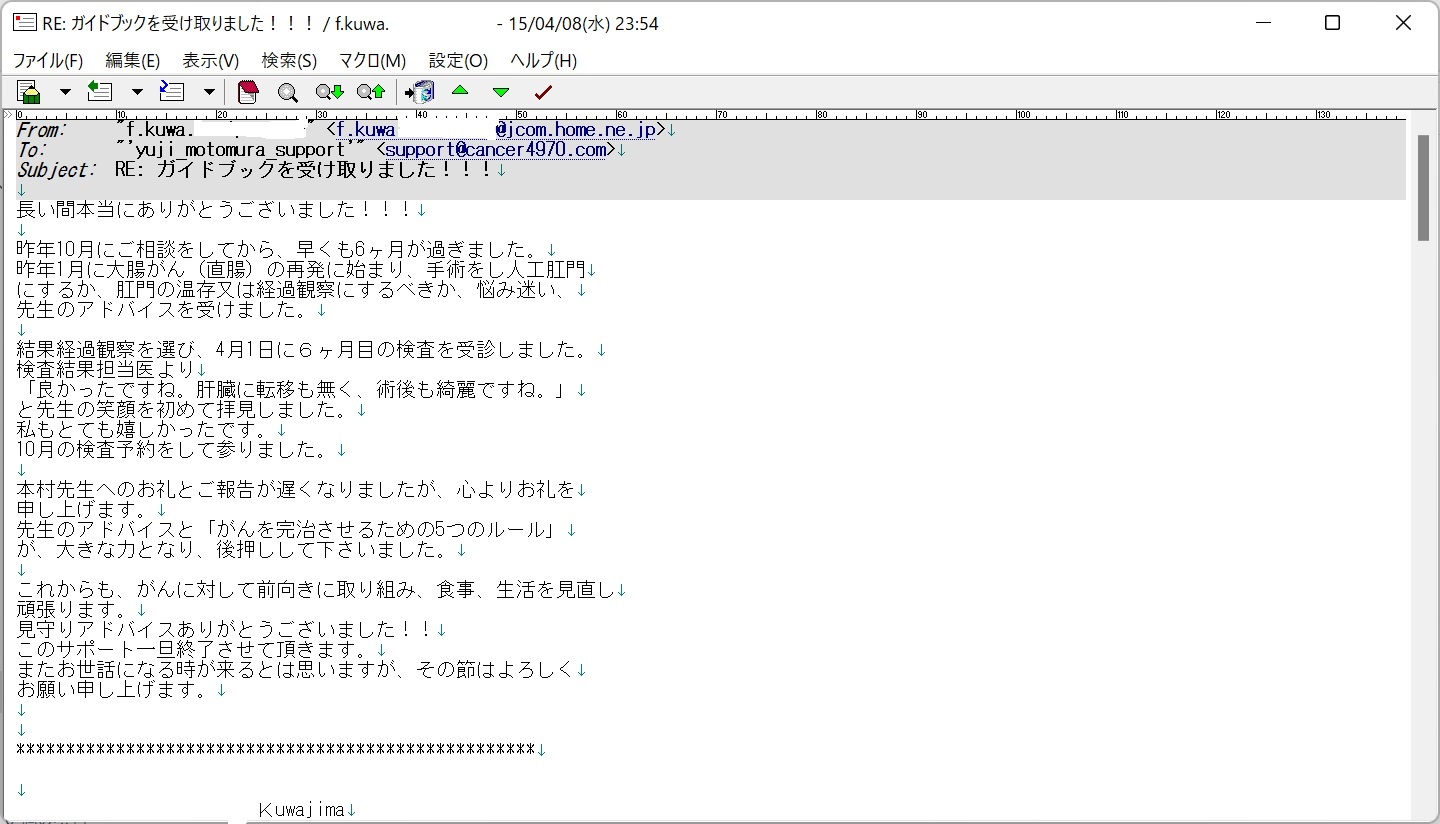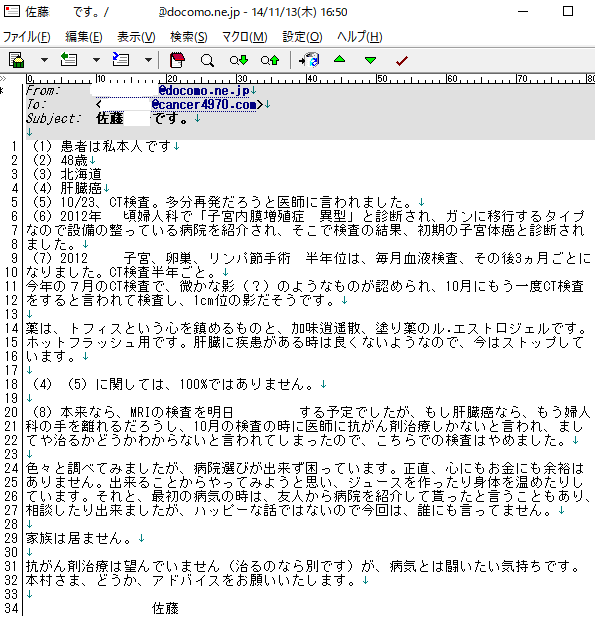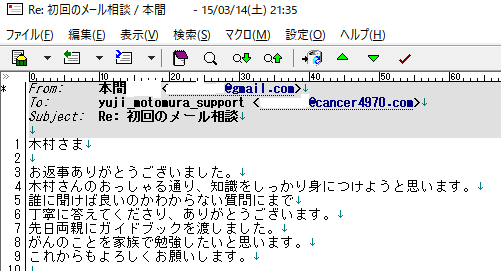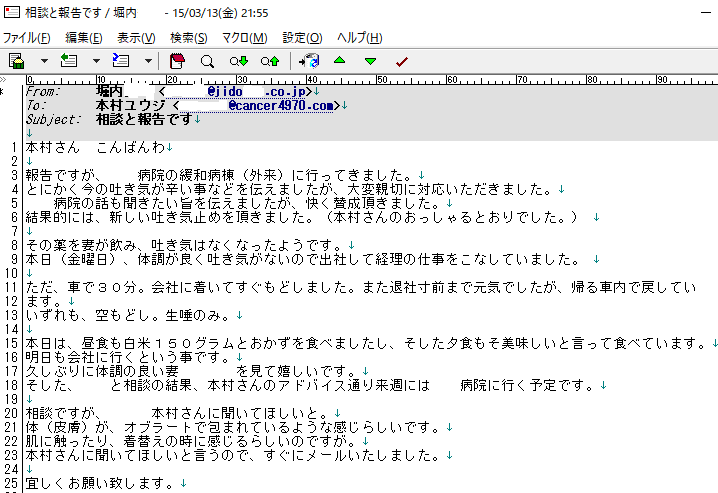こんにちは。がん専門のアドバイザー、本村ユウジです。
免疫チェックポイント阻害剤は、2014年にオプジーボ(ニボルマブ)が日本で初めて承認されて以降、がん治療に革命をもたらしました。
ノーベル賞を受賞した本庶佑教授の研究成果として注目を集め、「夢の新薬」として期待されてきました。従来の抗がん剤とは異なる作用機序により、効果が持続する可能性があることから、多くの患者さんが治療の選択肢として検討しています。
しかし、実際の医療現場では、免疫チェックポイント阻害剤特有の副作用への対応が大きな課題となっています。従来の抗がん剤とは全く異なる副作用のパターンが見られるため、医療従事者でさえ対応に苦慮するケースがあります。
この記事では、免疫チェックポイント阻害剤で起こりうる副作用について、2026年時点の最新情報をもとに詳しく解説します。
免疫チェックポイント阻害剤とは
免疫チェックポイント阻害剤は、がん細胞が免疫細胞にかけている「ブレーキ」を解除することで、免疫細胞ががん細胞を攻撃できるようにする薬です。
人間の体には、免疫細胞が自分の正常な細胞を攻撃しないよう、「免疫チェックポイント」という仕組みが備わっています。がん細胞はこの仕組みを悪用して、免疫細胞からの攻撃を逃れています。
免疫チェックポイント阻害剤は、このブレーキを解除して、免疫細胞ががん細胞を攻撃できるようにします。ただし、この「ブレーキを解除する」という作用が、独特の副作用を引き起こす原因となっています。
現在使用されている主な免疫チェックポイント阻害剤
2026年現在、日本で承認されている主な免疫チェックポイント阻害剤は以下のとおりです。
| 分類 | 一般名 | 商品名 |
|---|---|---|
| PD-1阻害薬 | ニボルマブ | オプジーボ |
| ペムブロリズマブ | キイトルーダ | |
| PD-L1阻害薬 | アテゾリズマブ | テセントリク |
| デュルバルマブ | イミフィンジ | |
| アベルマブ | バベンチオ | |
| CTLA-4阻害薬 | イピリムマブ | ヤーボイ |
これらの薬剤は、メラノーマ(悪性黒色腫)、非小細胞肺がん、腎細胞がん、胃がん、食道がん、頭頸部がんなど、多くのがん種に対して承認されています。2025年には、限局型小細胞肺がんに対する維持療法としてPD-L1阻害薬が新たに保険適用となり、治療の選択肢が広がっています。
免疫関連有害事象(irAE)とは
免疫チェックポイント阻害剤による副作用は、「免疫関連有害事象」(irAE:immune-related Adverse Events、アイアールエーイー)と呼ばれています。
従来の抗がん剤では、吐き気、脱毛、白血球減少などの副作用が投与直後から現れることが一般的でした。しかし、irAEは全く異なる特徴を持っています。
irAEの特徴は以下のとおりです。
まず、発現する臓器が多岐にわたります。皮膚、消化管、肝臓、肺、内分泌器官、腎臓、神経、筋肉、眼など、全身のあらゆる臓器に症状が現れる可能性があります。
次に、発現時期が予測しにくいという点です。投与開始後2か月以内に起こることが多いとされていますが、投与開始直後に現れることもあれば、投与終了後数か月経ってから発現することもあります。国立がん研究センターの報告によると、投与終了後から遅発性irAE発現までの期間中央値は6か月とされています。
さらに、投薬を中止しても症状が持続することがあります。従来の抗がん剤では、投薬を中止すれば多くの副作用は改善しますが、irAEは投薬中止後も症状が続くケースがあります。
主な副作用の種類と症状
厚生労働省が2022年に公開した「免疫チェックポイント阻害薬による免疫関連有害事象対策マニュアル」では、以下の副作用が重要な特定されたリスクとして挙げられています。
| 臓器・部位 | 主な症状 | 注意すべき初期症状 |
|---|---|---|
| 肺 | 間質性肺炎 | 息切れ、空咳、発熱、呼吸困難 |
| 消化器 | 大腸炎、重度の下痢 | 下痢、腹痛、血便、黒い便 |
| 肝臓・胆道 | 肝機能障害、肝炎、硬化性胆管炎 | 倦怠感、黄疸、食欲不振 |
| 内分泌 | 甲状腺機能障害、1型糖尿病、副腎障害 | 動悸、体重変化、口の渇き、多尿、倦怠感 |
| 皮膚 | 重度の皮膚障害 | 発疹、かゆみ、水疱、皮膚の剥離 |
| 神経・筋肉 | 重症筋無力症、筋炎、横紋筋融解症、脳炎、ギランバレー症候群 | まぶたが下がる、手足の力が入らない、筋肉痛、しびれ、意識障害 |
| 腎臓 | 腎機能障害、腎不全 | 尿量の変化、むくみ、倦怠感 |
| 血液 | 免疫性血小板減少性紫斑病 | 出血しやすい、あざができやすい |
| 眼 | ぶどう膜炎 | 視力低下、眼の痛み、充血 |
| その他 | 心筋炎、膵炎、静脈血栓塞栓症 | 胸の痛み、動悸、腹痛、脚の腫れや痛み |
このように症状は非常に多岐にわたります。そのため、「いつもと違う体調の変化」に気づくことが重要です。
重篤な副作用の発生頻度
重篤な副作用(グレード3以上)が発現する確率は、単独投与の場合、全体として比較的低いとされています。
具体的には、間質性肺炎で約3パーセント、重症筋無力症、心筋炎、大腸炎、重度の下痢、肝機能障害、腎障害、副腎障害などは各1パーセント程度と報告されています。
ただし、CTLA-4阻害薬であるヤーボイ(イピリムマブ)は、他の免疫チェックポイント阻害剤と比較して副作用が強く現れる傾向があります。臨床試験では、グレード3から4の有害事象が30から40パーセント程度の確率で発生しています。
また、PD-1阻害薬やPD-L1阻害薬とCTLA-4阻害薬を併用する場合、副作用の発現頻度は高くなります。例えば、皮膚障害の発現率は、PD-1またはPD-L1阻害薬単独使用で18パーセントですが、併用療法では51.1パーセントに上昇すると報告されています。
副作用の発現時期
副作用の種類によって、発現しやすい時期に違いがあります。
| 発現時期 | 主な副作用 |
|---|---|
| 比較的早期(2から8週間以内) | 皮膚障害、下痢・大腸炎、肝機能障害 |
| 中期(数か月以内) | 間質性肺炎、甲状腺機能障害 |
| 遅発性(数か月以上) | 1型糖尿病、神経系障害、副腎障害 |
重要なのは、治療終了後も副作用が発現する可能性があるという点です。投与終了後、数週間から数か月経過してから症状が現れることがあるため、治療が終わったからといって安心はできません。
医療現場での対応の難しさ
免疫チェックポイント阻害剤の副作用対応が難しい理由として、以下の点が挙げられます。
第一に、症状が多臓器にわたるため、診断が困難であることです。現代の病院は臓器別、診療科別に分かれており、横断的に起きる症状への対応がスムーズにいかないことがあります。
例えば、肺がんの治療中に下痢が続いた場合、患者さんが消化器科を受診しても、「免疫チェックポイント阻害剤の副作用」と気づかれず、整腸剤を処方されるだけで終わってしまうことがあります。実際には大腸炎が進行していて、対処が遅れると腸に穴があく(消化管穿孔)という重篤な状態になる可能性があります。
第二に、経験値が比較的浅い薬であることです。2014年の承認から10年以上が経過していますが、長期的な副作用のデータはまだ蓄積途中です。実際、オプジーボでは承認後5年経ってから「結核」が重大な副作用として追加されました。
第三に、主治医の知識がアップデートされていない可能性があることです。免疫チェックポイント阻害剤の副作用に関する情報は日々更新されています。主治医が最新の情報を把握していない場合、「この症状は投薬とは関係ない」と判断されてしまうリスクがあります。
副作用の治療方法
irAEが発現した場合の基本的な対応は、重症度に応じて以下のように行われます。
グレード1(軽症)の場合、慎重な経過観察のもと、治療を継続できることがあります。ただし、肺障害などでは一時的な休薬が必要になる場合があります。
グレード2(中等症)以上では、免疫チェックポイント阻害剤の投与を休止または中止し、ステロイド薬による治療が検討されます。ステロイド内服で改善しない場合は、ステロイドパルス療法などの高用量ステロイド投与が行われます。
グレード3(重症)以上になると、高用量の副腎皮質ステロイドが投与されます。ステロイドで効果が不十分な場合は、インフリキシマブやミコフェノール酸モフェチルなどの免疫抑制剤の使用も検討されます。
ただし、内分泌系のirAEについては対応が異なります。甲状腺機能障害や劇症1型糖尿病に対しては、ステロイドは使用せず、ホルモン補充療法が行われます。
患者さんが気をつけるべきこと
免疫チェックポイント阻害剤を使用する際、患者さん自身が注意すべき点をまとめます。
まず、体調の変化を記録することです。毎日の体調をメモし、いつもと違う症状が現れたら、すぐに主治医に報告しましょう。製薬会社が提供している治療日誌を活用することも有効です。
次に、異変があれば必ず主治医に報告することです。目に異常が起きて眼科を受診したり、下痢が続いて消化器科を受診したりしても、それが薬の副作用と判断できない可能性があります。まずは投薬を管理している主治医に報告し、必要に応じて専門科を紹介してもらうことが重要です。
また、総合的な診療体制が整った病院で治療を受けることが望ましいです。様々な症状に対応するには、複数の診療科の連携が必要になります。小規模なクリニックや診療科が限定的な病院では、irAEへの適切な対応が難しい場合があります。大学病院や総合病院のように、様々な診療科が揃っている病院での治療が推奨されます。
さらに、治療終了後も注意を続けることです。投与終了後、数か月経ってから副作用が現れることがあります。治療が終わったからといって油断せず、体調の変化に気を配りましょう。
免疫チェックポイント阻害剤の効果について
副作用についての説明が中心となりましたが、効果についても触れておきます。
免疫チェックポイント阻害剤の特徴は、「効果が出る確率はそれほど高くないが、効果が出れば長期間持続する」という点です。
単剤での奏効率(腫瘍が縮小する割合)は20から30パーセント程度とされています。しかし、効果が現れた場合、その効果が長期間続く可能性があります。
また、irAEが発現した患者さんの一部では、副作用のために治療を中止した後も、長期にわたって病勢がコントロールされているという研究報告もあります。これは、免疫が適切に活性化された証拠である可能性が示唆されています。
まとめ
免疫チェックポイント阻害剤は、がん治療に新たな可能性をもたらした画期的な薬です。しかし、従来の抗がん剤とは全く異なる副作用プロファイルを持っており、適切な管理が必要です。
副作用は全身のあらゆる臓器に現れる可能性があり、発現時期も予測しにくいという特徴があります。そのため、患者さん自身が体調の変化に注意を払い、異変があれば速やかに主治医に報告することが重要です。
また、総合的な診療体制が整った病院で治療を受けること、治療終了後も継続的に体調を確認することが大切です。
irAEの多くは、早期に発見して適切に対処すれば、コントロール可能です。正しい知識を持ち、医療チームと協力しながら治療に臨むことで、より安全に免疫チェックポイント阻害剤の治療を受けることができます。
参考文献・出典情報
- 厚生労働省「免疫チェックポイント阻害薬による免疫関連有害事象対策マニュアル」
- 国立がん研究センター中央病院「薬薬連携を充実させるための研修会 開催報告」
- 日本肺癌学会「患者さんと家族のための肺がんガイドブック2024年版」
- 中外製薬「おしえて 肺がんのコト」
- 岡山済生会総合病院「がん治療の免疫チェックポイント阻害薬ってどんな薬?」
- 「肺がんとともに生きる」肺がんの免疫療法と免疫チェックポイント阻害薬
- 大阪大学大学院医学系研究科「免疫チェックポイント阻害剤による免疫関連有害事象」
- 消化器癌治療の広場「免疫関連有害事象(irAE)」
- 6種複合免疫療法「免疫チェックポイント阻害薬のirAE治療と対策」
- がん情報サイト「副作用で免疫療法薬中止後も、一部の患者で病勢コントロール持続の可能性」