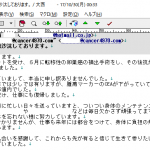卵巣がんは自覚症状がほとんど出ない病気として知られています。
そのため、「silent disease」(沈黙の病気)「silent killer」(沈黙の殺人者)などと呼ばれ、気がついたときには、進行がんになっている例が少なくありません。
卵巣は2つあるので、片方にがんが発生しても、もう一方の卵巣が正常に機能していれば、年齢相応の性機能は保たれるため、症状が出にくいのです。
子宮のように不正性器出血が起こることもありません。ですので生理、おりもの、月経不順はまず関係ありません。
人によっては、不定愁訴(原因不明の身体症状が出たり消えたりする状態)が上・下腹部に現れることがあります。そのあたりの不快な症状が卵巣がんのチェック項目といえます。
ただ、おなかが張るとか、重いといった程度ですから、この時点で卵巣がんを疑って婦人科を受診する人はほとんどいないのです。
【サイト内 特設ページ】
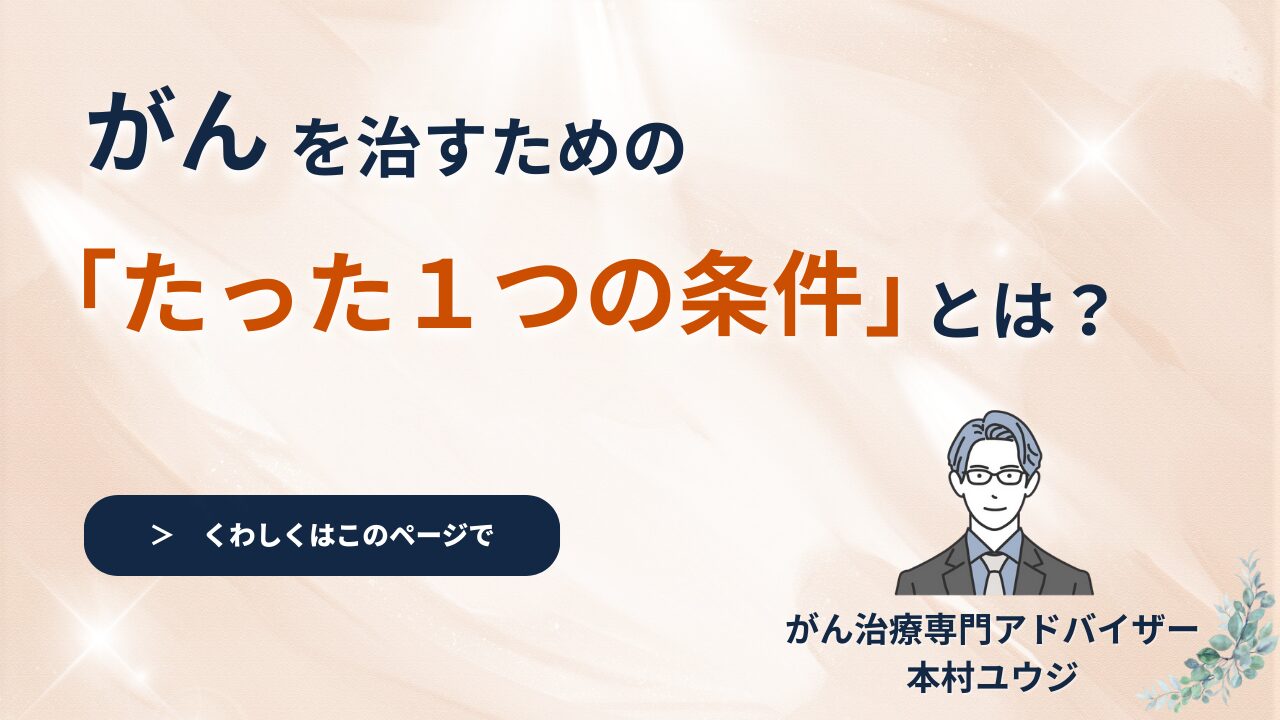
こんにちは。17年間の活動実績を持つ、
「プロのがん治療専門アドバイザー」本村ユウジです。
がんを治すために必要なことは、たった1つです。
詳しくはこちらのページでお伝えさせてください。
→がんを治すための「たった1つの条件」とは?
卵巣がんのわずかな自覚症状
卵巣がんが大きくなって、はじめて下腹部にしこりを感じたり、腹部膨満感(おなかがふくれた感じ)を覚えるようになります。
卵巣が腫れているということに気がつかず、「最近太った」とか「スカートのウエストがきつくなった」という人がいます。
これは、卵巣が腫れているためだけでなく、腹腔内にがんが播種(がん細胞が種をばらまくような状態で転移すること)した結果、腹膜の機能が低下し、多量の腹水がたまっていることも考えられます。
卵巣がんの中で、漿液性や移行上皮は腹水が貯留するタイプです。
類内膜、明細胞、粘液性では、腹水が多量にたまることはまれです。
がん病巣がさらに大きくなると、腹部膨満感が強くなったり、あお向けに寝られないほど苦しくなることもあります。
卵巣がんの初期にはほとんど症状がない
卵巣がんは、卵巣内にとどまっているⅠ期で発見できれば8割ほどは改善しやすいですがこの段階で発見できるのは約30%に過ぎません。
6割以上がⅢ期、Ⅳ期の進行がんに至ってから発見され、5年生存率はⅢ期で約30%、Ⅳ期で約10%となります。
早期発見が難しい理由は、卵巣がんの初期段階にはほとんど症状がなく、ある程度大きくならないと画像診断でもとらえられないがんであるからです。
卵巣は骨盤内(腹腔内)に、固定がゆるいフリーな状態で存在しているため、大きくなっても周囲の臓器を圧迫しません。
腹水が溜まって腹部が膨れても、本人には少々太ったという認識しかないことも多いのです。
卵巣がんの茎捻転
卵巣に腫瘍ができ、それ自体で重みを増してくると、卵巣を支える靭帯が引き伸ばされて、靭帯のつけ根部分が茎のようになります。
その部分がなんらかのきっかけで、ねじれてしまうことがありますが、これを「茎捻転」といいます。
茎捻転を起こすような腫瘍は、一般的には良性のものが多いのですが、捻転がひどくなると、靭帯を通る血管が圧迫され、炎症を起こし、下腹部の激痛、吐き気、発熱などの症状が現れます。
捻転が徐々に起こる場合には、痛みもだんだん強くなってきます。
茎捻転を放っておくと、組織が壊死して、周囲と癒着したり、場合によっては破裂や出血を起こして命にかかわります。
【サイト内 特設ページ】
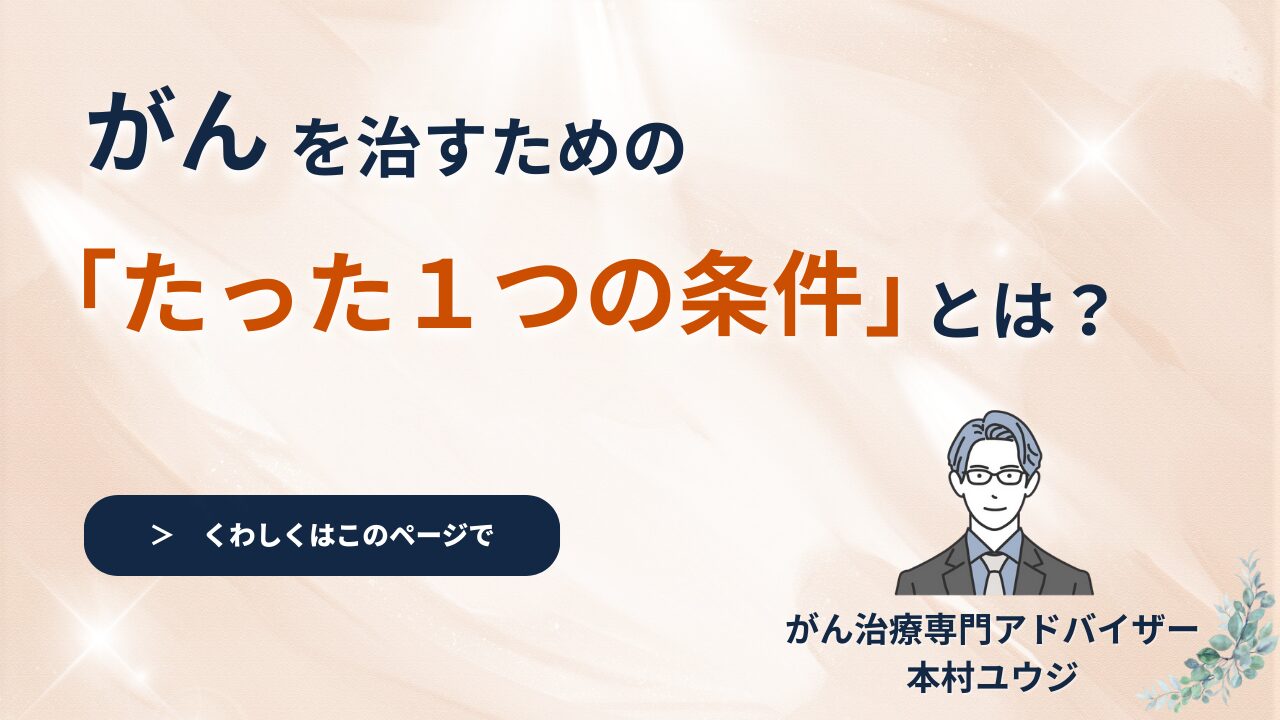
こんにちは。17年間の活動実績を持つ、
「プロのがん治療専門アドバイザー」本村ユウジです。
がんを治すために必要なことは、たった1つです。
詳しくはこちらのページでお伝えさせてください。
→がんを治すための「たった1つの条件」とは?
似た症状が起きる卵管炎とは?
分娩、流産、人工妊娠中絶、性感染症のクラミジア、その他(ブドウ球菌、大腸菌など)の細菌感染によって、卵管で炎症を起こすものです。
放置すると、卵管内や周囲に癒着が生じ、卵子が通過できなくなって不妊になったり、卵管の輸送機能が低下して子宮外妊娠を起こしたりします。
急性期の症状は、部位がはっきりしない腹痛(下腹部とは限らない)、不定期に起こる腹痛、腹部膨満感、発熱、水様性のおりものの増加などです。
進行すると腹水がたまって腹部膨満感がさらに強まり、歩行困難になって入院が必要になる場合もあります。慢性化すると、激烈な症状は治まりますが、下腹部の重み、痛み、張り、ひきつり、腰の痛みなどが続きます。
治療法としては、抗生物質(クラリス、ジスロマック内服、ミノマイシン点滴)で、90%以上がほぼ完治します。
卵管閉塞や癒着を起こした場合は、手術が必要になることもあります。炎症がひどくなると、卵管閉塞が起こり、閉塞部の一部に浸出液がたまる卵管留水腫や、うみがたまる卵管留膿腫ができることがあります。
また、炎症が卵巣にまで及んだ場合、卵巣炎を併発することがあります。さらに骨盤まで広がると、骨盤腹膜炎を起こします。