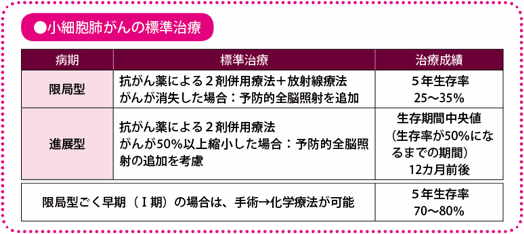
こんにちは。がん専門のアドバイザー、本村ユウジです。
小細胞肺がんは肺がん全体の約10~15%を占める特殊なタイプのがんです。増殖速度が速く、早期から転移しやすいという特徴がありますが、その一方で化学療法や放射線療法への反応が良好という側面も持っています。
この記事では、小細胞肺がんの基本的な特徴から、2026年時点での最新治療法まで、患者さんやご家族が治療方針を考える際に役立つ情報を整理してお伝えします。
小細胞肺がんとは|基本的な特徴と発症状況
小細胞肺がんは、日本における年間肺がん死亡者数(約73,000人)の中で一定の割合を占める疾患です。発生頻度は年齢とともに増加し、男性が女性の約5倍と多く、喫煙との関連が強いことが分かっています。
小細胞肺がんの主な特徴として、以下の点が挙げられます。
腫瘍の増殖速度が非常に速いこと、リンパ節を巻き込んだ腫瘤を形成しやすいこと、気管支や血管に沿って進展する傾向があること、遠隔転移の頻度が高いことなどです。また、腫瘍随伴症候群という特有の症状を伴うケースも少なくありません。
ただし、化学療法や放射線療法に対する感受性が高いという特性があり、この点が非小細胞肺がんとは異なる治療アプローチにつながっています。
小細胞肺がんの病期分類と予後因子
小細胞肺がんでは、1969年に提唱された分類法が現在も広く使われています。これは「限局型(LD)」と「進展型(ED)」という2つの病期に大きく分ける方法です。
| 病期分類 | 定義 | 特徴 |
|---|---|---|
| 限局型(LD) | 病巣が一側胸郭内に限局 | 同側肺門リンパ節、両側縦隔リンパ節、両側鎖骨上窩リンパ節転移まで。悪性胸水や心嚢水を認めない |
| 進展型(ED) | 限局型を超える範囲 | 遠隔転移がある、または広範囲の胸水・心嚢水を認める |
最も重要な予後因子は病期(LDかEDか)とパフォーマンスステータス(PS)です。それ以外にも、年齢、喫煙歴、LDH値、ALP値、転移部位などが予後に関連することが明らかになっています。
パフォーマンスステータス(PS)の評価基準
| PS | 状態 |
|---|---|
| 0 | まったく問題なく活動できる。発症前と同じ日常生活が制限なく行える |
| 1 | 肉体的に激しい活動は制限されるが、歩行可能で、軽作業や座っての作業は行える |
| 2 | 歩行可能で自分の身のまわりのことはすべて可能だが、作業はできない。日中の50%以上はベッド外で過ごす |
| 3 | 限られた自分の身のまわりのことしかできない。日中の50%以上をベッドか椅子で過ごす |
| 4 | まったく動けない。完全にベッドか椅子で過ごす |
「自分の判断は正しいのか?」と不安な方へ

がん治療。
何を信じれば?
不安と恐怖で苦しい。
がん治療を左右するのは
治療法より“たった1つの条件”です。
まず、それを知ってください。
がん専門アドバイザー 本村ユウジ
小細胞肺がん治療の歴史的変遷
第二次世界大戦後、がん治療の中心は手術でした。しかし1969年に報告された英国の比較試験で、小細胞肺がんに対する手術の5年生存率が1%だったのに対し、放射線治療では4%と上回る結果が示されました。
同時期に、シクロフォスファミド(CPA)を用いた化学療法と緩和医療のみ(BSC)を比較した試験では、化学療法群の生存期間中央値が8か月、BSC群が4か月と、化学療法の有用性が明確になりました。
その後、CAV療法(シクロフォスファミド、ドキソルビシン、ビンクリスチンの3剤併用)が開発され、1980年代にはEP療法(エトポシドとシスプラチンの併用)が登場しました。これらの化学療法と放射線治療を組み合わせた化学放射線療法の研究が積み重ねられ、治療成績の向上につながっていきました。
限局型(LD)小細胞肺がんの標準治療
手術の位置づけ
1960年代以降、小細胞肺がんにおける手術の役割は限定的とされてきました。しかし、病期1期の末梢型小細胞肺がんで完全切除が可能な場合には、手術後にEP療法を行うことで5年生存率66%という良好な成績が得られています。
一方、リンパ節転移を伴う病期3a期では5年生存率が13%と不良であり、病期1期の症例に限って手術が選択肢となります。それ以外の限局型小細胞肺がんでは、化学放射線療法が標準治療となっています。
化学放射線療法の進化
限局型小細胞肺がんに対する化学放射線療法と化学療法単独の比較試験では、放射線を併用することで死亡の相対リスクが0.86に低下し、3年生存率が改善することが示されました。
放射線と化学療法の実施時期については、早期同時併用、後期同時併用、交替併用、逐次併用などが検討されてきました。その結果、EP療法と放射線療法の早期同時併用が、生存期間中央値27か月、5年生存率24%と最も良好な成績を示しました。
放射線の照射方法については、1日2回照射(AH-TRT)が1日1回照射と比較され、食道炎の頻度は高いものの、生存期間中央値23か月、5年生存率26%とAH-TRTが優れた結果となりました。
これらの臨床試験の結果から、2026年時点での限局型小細胞肺がんの標準治療は、EP療法とAH-TRTの早期同時併用となっています。ただし、パフォーマンスステータスが不良な患者さんや病変範囲が広い場合には、化学療法を先行させ、放射線を後から組み合わせる方法も行われています。
進展型(ED)小細胞肺がんの最新治療
初回化学療法の標準と新たな選択肢
進展型小細胞肺がんの治療は、長年にわたってEP療法またはIP療法(イリノテカンとシスプラチンの併用)が標準とされてきました。
日本で行われた臨床試験では、パフォーマンスステータス0~2、70歳以下の患者さんを対象にIP療法とEP療法を比較し、IP療法で生存期間中央値12.8か月、2年生存率19.5%と良好な結果が得られました。一方、欧米での試験では同様の差は認められませんでした。
| 治療法 | 使用薬剤 | 特徴 |
|---|---|---|
| EP療法 | エトポシド+シスプラチン | 世界的な標準治療。有害事象が比較的軽微 |
| IP療法 | イリノテカン+シスプラチン | 日本での標準治療の一つ。一部の患者さんで良好な成績 |
免疫チェックポイント阻害剤の併用療法
2018年以降、進展型小細胞肺がんの治療において画期的な進展がありました。免疫チェックポイント阻害剤と化学療法を組み合わせる治療法です。
アテゾリズマブ(商品名:テセントリク)とEP療法を併用するIMpower133試験では、EP療法単独と比較して生存期間の延長が認められ、進展型小細胞肺がんの一次治療として承認されました。
同様に、デュルバルマブ(商品名:イミフィンジ)とEP療法を併用するCASPIAN試験でも良好な結果が示され、こちらも標準治療の選択肢となっています。
| 免疫療法併用 | 対象 | 治療内容 |
|---|---|---|
| アテゾリズマブ+EP療法 | 進展型小細胞肺がん初回治療 | 化学療法と免疫療法の同時併用。維持療法も含む |
| デュルバルマブ+EP療法 | 進展型小細胞肺がん初回治療 | 化学療法と免疫療法の同時併用。維持療法も含む |
これらの免疫療法併用は、従来の化学療法のみと比べて生存期間を数か月延長させることが分かっており、2026年時点での進展型小細胞肺がんの標準治療として位置づけられています。
高用量化学療法と投与スケジュール
抗がん剤の投与量を増やす高用量化学療法は、骨髄移植の併用も含めて検討されてきました。しかし、ほとんどの試験で腫瘍縮小効果は向上するものの、延命効果は得られず、むしろ重篤な副作用が増加する結果となりました。
治療期間については、プラチナ製剤を中心とした併用療法では4~6サイクル(多くは4サイクル)が最も効果的で副作用も抑えられることが明らかになっています。
再発小細胞肺がんの治療選択肢
小細胞肺がんは初回治療での奏効率が高い一方で、局所再発や中枢神経への転移が起こりやすいという特徴があります。
再発のタイプによる治療方針
再発小細胞肺がんは、初回治療終了から再発までの期間によって分類されます。
| 再発タイプ | 定義 | 治療アプローチ |
|---|---|---|
| Sensitive relapse | 初回治療終了から2~3か月以上経過後の再発で、初回治療で腫瘍縮小が得られた場合 | ノギテカン(トポテカン)などの化学療法が選択される |
| Refractory relapse | 上記以外の再発(早期再発や初回治療無効例) | アムルビシンなどの化学療法が標準的 |
再発時の新しい治療選択肢
ニボルマブ(商品名:オプジーボ)は、再発小細胞肺がんに対して一定の効果が示されています。単剤での奏効率は約10%、イピリムマブ(商品名:ヤーボイ)との併用では19~23%でした。ただし、副作用による治療中止例が6~11%あることも報告されています。
また、ルルビネクテジン(Zepzelca)という新しい薬剤が、再発小細胞肺がんの治療薬として海外で承認されており、今後日本でも使用できる可能性があります。
分子標的薬と新規治療薬の開発状況
非小細胞肺がんでは多くの分子標的薬が開発されていますが、小細胞肺がんでは長らく有効な分子標的薬が見つかっていませんでした。
抗体薬物複合体(ADC)であるrovalpituzumab tesirine(Rova-T)は、DLL3という小細胞肺がんで高発現する物質を標的とした薬剤として期待されていました。初期の臨床試験では高発現例で39%の奏効率が得られましたが、その後の試験で期待された効果が得られず、開発は中止となりました。
現在も、新たなバイオマーカーに基づく治療薬の開発が続けられており、タルラタマブ(Imdelltra)などの新薬が臨床試験段階にあります。
予防的全脳照射(PCI)について
小細胞肺がんは脳転移を起こしやすいため、初回治療で良好な効果が得られた患者さんに対して、予防的に脳全体に放射線を照射する予防的全脳照射(PCI)が検討されてきました。
限局型小細胞肺がんでは、PCIによって脳転移の発生率が低下し、生存期間の延長効果も示されています。一方、進展型小細胞肺がんにおけるPCIの有用性については議論があり、患者さんの状態や希望を考慮して実施を判断することになります。
小細胞肺がん治療における課題と展望
小細胞肺がんの治療は、約20年にわたって大きな変化がない時期が続きましたが、2018年以降、免疫チェックポイント阻害剤の併用療法という新しい選択肢が加わり、治療成績の改善が見られています。
現在も、新たなバイオマーカーの探索、新規薬剤の開発、既存薬の最適な組み合わせの検討など、様々な臨床試験が進行中です。特に、免疫療法と化学療法の組み合わせ方、治療期間の最適化、副作用のマネジメント向上などが重要な研究テーマとなっています。
また、個々の患者さんの腫瘍の特性に応じた個別化医療の実現に向けて、遺伝子検査やバイオマーカーの研究も進められています。
治療方針を考える際のポイント
小細胞肺がんの治療方針を考える際には、以下のような点が重要になります。
まず、病期が限局型か進展型かによって、標準的な治療アプローチが異なります。限局型では化学放射線療法が中心となり、進展型では化学療法(免疫療法併用を含む)が主体となります。
次に、患者さんの全身状態(パフォーマンスステータス)が治療選択に大きく影響します。積極的な治療が可能な状態か、より負担の少ない治療を選択すべきかを判断する必要があります。
また、年齢、合併症の有無、臓器機能なども考慮要素となります。高齢の患者さんや腎機能が低下している患者さんでは、薬剤の選択や投与量の調整が必要になることがあります。
免疫チェックポイント阻害剤の使用については、特有の副作用(免疫関連有害事象)のリスクと効果のバランスを考える必要があります。
治療を受ける医療機関の選択も大切です。小細胞肺がんの治療経験が豊富で、放射線治療の設備が整い、副作用への対応体制が充実している施設を選ぶことが望ましいでしょう。
まとめ|小細胞肺がん治療の現状と今後
小細胞肺がんは増殖速度が速く転移しやすい一方で、化学療法や放射線療法への反応が良好という特性を持つがんです。
限局型では化学放射線療法の早期同時併用が標準治療となっており、進展型では従来の化学療法に加えて、免疫チェックポイント阻害剤を併用する治療が新たな標準として確立されています。
再発時には、再発までの期間や初回治療の効果によって治療方針が異なり、様々な薬剤が選択肢となります。
2026年時点では、さらなる治療成績の向上を目指して、新規薬剤の開発や既存治療の最適化に関する研究が活発に進められています。個々の患者さんに最適な治療を提供するための個別化医療の実現も、今後の重要な課題となっています。



