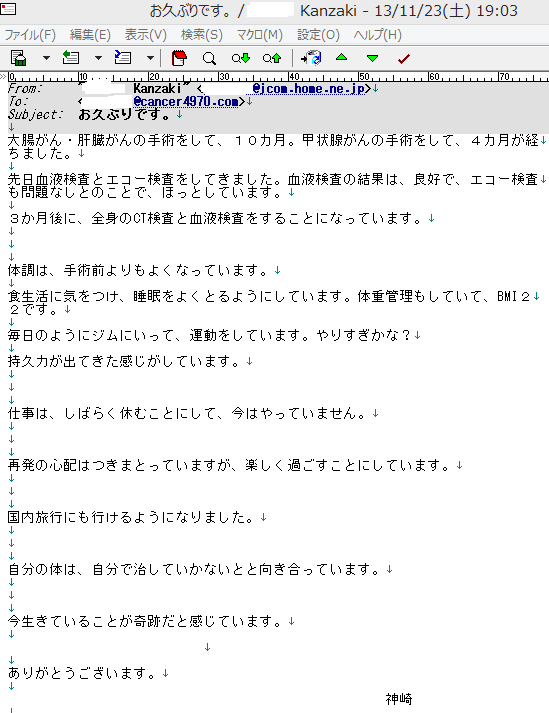大腸がんは早期発見・治療で高い治癒率が期待できる一方、がん細胞が血管やリンパ管を通じて他の臓器へ広がる「転移」は依然として大きな課題です。
ここでは最新のガイドライン(2024年改訂)と2024〜2025年に承認・報告された新薬や診断技術を踏まえ、大腸がんが転移したらどうなるのか、そして治療の選択肢や再発を防ぐための取り組みを、一般の方にも分かりやすく解説します。
大腸がんが転移したらどうなる?再発と転移の仕組み
1. 再発とは
手術で原発巣(大腸にできたがん)を完全に取り除いても、顕微鏡レベルのがん細胞が体内に残っている可能性があります。これらが時間をかけて増殖し、画像検査で確認できる大きさになった状態を「再発」と呼びます。
2. 転移のメカニズム
がん細胞は次の3経路で広がります。
- リンパ行性転移:リンパ管からリンパ節へ広がる
- 血行性転移:血管を通じて肝臓・肺・骨・脳などに到達
- 播種(腹膜播種):腹腔内に散らばるように転移
進行度別に見る転移・再発リスク
大腸がんの進行度(ステージ)が上がるほど再発・転移リスクは高くなります。ステージ0〜Iでは5年生存率が90%以上ですが、ステージIIIでは30%前後に再発、ステージIVでは遠隔転移を有するため治癒が難しくなります。
よく転移する臓器と症状
1. 肝転移
大腸の静脈血が門脈を通じて最初に流れ込む肝臓は転移の好発部位です。初期は無症状ですが、進行すると腹部の張りや黄疸、腹水がみられます。
2. 肺転移
呼吸器症状がないまま進行し、血痰・胸痛・咳嗽が出現することがあります。CTで偶発的に発見されるケースも多いです。
3. 腹膜・卵巣への播種
腹部膨満感や腸閉塞症状をきたすことがあり、女性では卵巣腫大が見つかる場合があります。
最新ガイドライン(2024年改訂)と治療戦略
1. 手術療法
転移が1臓器かつ切除可能であれば、手術が第一選択となります。近年はロボット支援下手術や腹腔鏡下肝切除が保険適用となり、低侵襲手術の選択肢が拡大しました。
2. 化学療法のアップデート
2024年9月に承認されたVEGFR阻害薬フルキンチニブ(フリュザクラ)は、既治療の進行・再発大腸がんに対し生存期間を延長することが示されています。従来のFOLFOX/FOLFIRIレジメンに加え、レゴラフェニブ・トリフルリジン/チピラシルなど多剤併用が標準的になりました。
3. 分子標的薬・抗体薬
- RAS野生型:抗EGFR抗体(セツキシマブ、パニツムマブ)
- HER2陽性:抗体薬物複合体トラスツズマブ デルクステカンが第II相DESTINY-CRC02試験で奏効率37%を達成
- BRAF V600E変異:エンコラフェニブ+セツキシマブ併用が推奨
4. 免疫チェックポイント阻害薬
MSI-H/dMMRの大腸がんではペンブロリズマブ単剤が一次治療として承認済みです。さらに2025年のCheckMate-8HW試験でニボルマブ+イピリムマブ併用がPFSを有意に延長し、欧州医薬品庁で承認申請が受理されました。
5. 局所療法の進歩
- Y-90経動脈放射線塞栓療法(TARE):EPOCH試験の追加解析では化学療法抵抗性の肝転移に対しPFSの延長が報告
- HIPEC(腹腔内温熱化学療法):HIPECT4試験で局所制御率向上が示された一方、全生存期間への上乗せ効果は限定的と報告されています
転移・再発を早期に見つける最新検査
2025年4月にスペインで開発された血液検査TAV16(ctDNA解析)は、手術後2〜4週間で微小転移を検出し、再発を高精度で予測できるとNature Cancer誌に報告されました。日本でも多施設共同研究が進行中です。
術後フォローアップと生活の注意点
JSCCRガイドラインでは、ステージII以上で術後5年間は3〜6か月ごとの血液検査(CEA・CA19-9)と年1回のCT、内視鏡検査を推奨しています。禁煙・適正体重の維持・定期的な運動は再発リスク低減に寄与すると報告されています。
まとめ
大腸がんが転移した場合でも、手術・薬物療法・局所療法の選択肢は年々広がっています。病理型・遺伝子変異・転移部位に応じた個別化治療が鍵であり、専門医と相談しながら最適な治療計画を立てることが重要です。