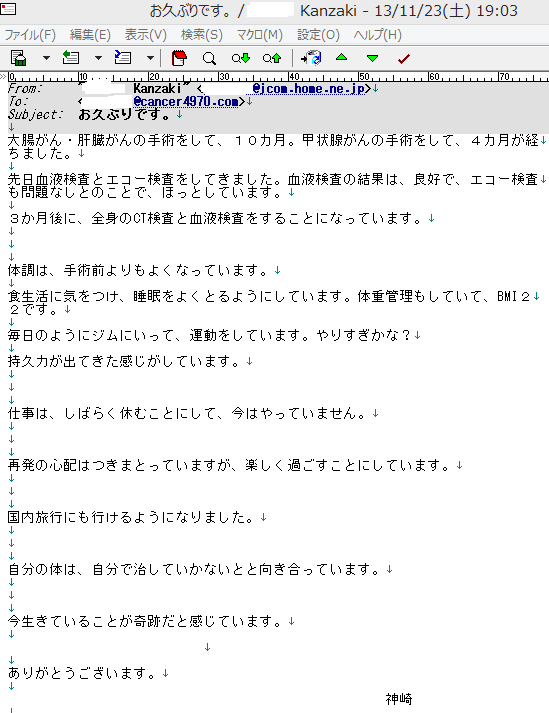【サイト内 特設ページ】

こんにちは。17年間の活動実績を持つ、
「プロのがん治療専門アドバイザー」本村ユウジです。
がんを治すために必要なことは、たった1つです。
詳しくはこちらのページでお伝えさせてください。
→がんを治すための「たった1つの条件」とは?
肝臓がんにおける手術適応の歴史的変遷
2000年以前の肝臓がん治療においては、肝機能が低下している患者さんに対しても広く手術が実施されていました。当時は根治性を重視する治療方針が主流でしたが、手術自体は成功しても、術後の肝不全や合併症により患者さんが亡くなるケースが問題となっていました。
このような状況を受けて、現在では肝機能評価に対してより厳密な基準が設けられるようになりました。特に肝機能が悪化している患者さんについては、手術適応から除外されることが多くなり、代替治療法の選択が重要視されています。
現在の手術適応判断における基本原則
肝臓がんにおける手術適応の判断は、単にがんの状態だけでなく、残存肝機能の評価が最も重要な要素となります。肝機能が良好であることが手術適応条件の基本となっており、これにより肝機能の悪い患者さんの手術ケースは以前と比較して減少傾向にあります。
肝臓がんの発生原因として肝硬変が重要な位置を占めており、肝細胞が破壊され組織が硬化して機能が低下した状態の程度が、手術適応の有無や切除範囲の決定に直結します。このような背景から、肝機能評価は治療選択において欠かせない要素となっています。
【サイト内 特設ページ】

こんにちは。17年間の活動実績を持つ、
「プロのがん治療専門アドバイザー」本村ユウジです。
がんを治すために必要なことは、たった1つです。
詳しくはこちらのページでお伝えさせてください。
→がんを治すための「たった1つの条件」とは?
肝機能評価における分類システム
Child-Pugh分類による評価
現在の肝臓がん治療では、Child-Pugh(チャイルド・ピュー)分類が肝予備能評価の標準的な指標として使用されています。この分類は以下の5項目を総合的に評価します:
| 評価項目 | 1点 | 2点 | 3点 |
|---|---|---|---|
| 肝性脳症 | なし | 軽度(I-II度) | 高度(III-IV度) |
| 腹水 | なし | 軽度 | 中等度以上 |
| 血清ビリルビン値(mg/dl) | 2.0未満 | 2.0-3.0 | 3.0超 |
| 血清アルブミン値(g/dl) | 3.5超 | 2.8-3.5 | 2.8未満 |
| プロトロンビン時間(%) | 70超 | 40-70 | 40未満 |
合計点数により以下の分類が行われます:
- Child-Pugh分類A(5-6点):肝機能良好、代償性肝硬変
- Child-Pugh分類B(7-9点):肝機能中等度低下、代償性から非代償性への移行期
- Child-Pugh分類C(10-15点):肝機能著明低下、非代償性肝硬変
肝障害度分類とICG検査
日本では、Child-Pugh分類に加えて肝障害度分類も用いられます。この分類にはICG(インドシアニングリーン)検査が含まれており、より詳細な肝機能評価が可能です。ICG検査では、肝臓の解毒機能を緑色色素の処理能力で評価し、15分後の血中残存率(ICGR15)により肝機能を数値化します。
正常な肝機能では15分で注入量の90%以上が処理されICGR15は10%未満となりますが、ICGR15が10%以下なら肝臓の約70%まで、10-20%なら約33%まで、20-30%なら約17%まで安全に切除可能とされています。
手術適応の具体的基準
基本的な適応条件
2025年現在の標準的な手術適応基準は以下の通りです:
- 肝予備能:Child-Pugh分類AまたはB
- 肝障害度:A、BまたはBに近いレベル
- 肝外転移:なし
- 脈管侵襲:なし、または限定的
- 腫瘍数:3個以下が望ましい
- 腫瘍径:特に制限なし(10cm超でも切除可能な場合あり)
詳細な適応判断
Child-Pugh分類がAまたはBであっても、総ビリルビン値が2.0mg/dlを超える場合は手術適応にならないことが多く、肝障害度がBの場合でもAに近いレベルでなければ手術は困難とされています。
腫瘍が1個で3cm以上の場合は手術の安全性が高まりますが、2-3個の多発例では手術を行っても治療成績が低下する傾向があります。このため、可能な限り単発病変での手術が推奨されています。
【サイト内 特設ページ】

こんにちは。17年間の活動実績を持つ、
「プロのがん治療専門アドバイザー」本村ユウジです。
がんを治すために必要なことは、たった1つです。
詳しくはこちらのページでお伝えさせてください。
→がんを治すための「たった1つの条件」とは?
手術できない場合の治療選択
穿刺局所療法(ラジオ波焼灼療法)
Child-Pugh分類AまたはBで、腫瘍径3cm以下、3個以下の場合にはラジオ波焼灼療法(RFA)が選択されます。体への負担が少なく、手術に比べて低侵襲な治療法として位置づけられています。
肝動脈化学塞栓療法(TACE)
腫瘍径が3cmを超える1-3個の病変、または4個以上の多発病変で手術やRFAの適応とならない場合に実施されます。カテーテルを用いてがんに栄養を供給する血管を塞栓し、同時に抗がん薬を投与する治療法です。
薬物療法
肝外転移がある進行例では、分子標的薬と免疫チェックポイント阻害薬を組み合わせた全身薬物療法が標準治療となっています。Child-Pugh分類Aの患者さんで、他の治療が適応とならない場合に選択されます。
肝移植
Child-Pugh分類Cの患者さんで、ミラノ基準(腫瘍1個で5cm以下、または3個以下で各3cm以内)または5-5-500基準(腫瘍5cm以内、5個以内、AFP500ng/ml以下)を満たす場合に肝移植が検討されます。
腫瘍マーカーの役割と意義
AFP(αフェトプロテイン)
AFPは肝細胞がんの代表的な腫瘍マーカーで、基準値は10-20ng/ml以下です。200ng/ml以上の持続的上昇や400ng/mlを超える場合は肝細胞がんの可能性が極めて高くなります。ただし、肝炎や肝硬変でも上昇するため、診断には画像検査との組み合わせが必要です。
その他の腫瘍マーカー
PIVKA-II、AFP-L3分画も肝細胞がんの診断や経過観察に用いられ、小さながんの発見には2種類以上のマーカーを組み合わせた検査が推奨されています。
最新の治療アルゴリズム
2025年現在の肝細胞がん治療アルゴリズムでは、以下の5因子を総合的に評価して治療方針を決定します:
- 肝予備能(Child-Pugh分類)
- 肝外転移の有無
- 脈管侵襲の有無
- 腫瘍数
- 腫瘍径
これらの因子に基づき、患者さん個々の状態に最適な治療法が選択されます。
定期的なサーベイランスの重要性
B型・C型肝炎ウイルス感染による慢性肝炎や肝硬変の患者さんには、3-6か月ごとの定期的な超音波検査と腫瘍マーカー検査が推奨されています。早期発見により、より根治的な治療選択が可能となります。
手術以外の最新治療法
定位放射線治療
腫瘍径5cm以下、3個以内の病変に対しては、定位放射線治療も選択肢の一つとなっています。正常肝組織への影響を最小限に抑えながら、高線量の放射線を精密に照射する治療法です。
免疫チェックポイント阻害薬
進行肝細胞がんに対する一次治療として、免疫チェックポイント阻害薬と分子標的薬の併用療法が標準治療となっており、治療成績の向上が期待されています。
治療方針決定における多職種連携
肝臓がんの治療方針決定には、消化器内科、肝胆膵外科、放射線科、病理診断科などの専門家が連携し、患者さんの病状、肝機能、年齢、併存疾患などを総合的に評価して最適な治療法を選択します。
今後の展望
肝臓がん治療は年々進歩しており、新たな分子標的薬や免疫療法の開発、低侵襲治療技術の向上により、より多くの患者さんに治療選択肢を提供できるようになってきています。また定期的な診療ガイドラインの更新により、最新のエビデンスに基づいた治療が提供されています。
患者さんにとって重要なのは、自身の肝機能や腫瘍の状態を正確に把握し、専門医との十分な相談のもと、最適な治療方針を決定することです。
参考文献・出典情報
国立がん研究センター がん情報サービス 肝臓がん(肝細胞がん)治療