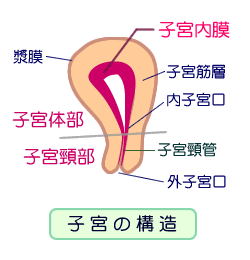
子宮体がんの現状と患者数の推移
こんにちは。がん専門のアドバイザー、本村ユウジです。
子宮体がんは子宮の内側を覆う子宮内膜から発生するがんで、子宮頸部で発生する子宮頸がんとは全く別の疾患です。発生する部位、特徴、治療法も大きく異なるため、両者を区別して理解することが重要です。
日本における子宮体がんの罹患者数は年々増加しており、2022年の統計では年間約18,500人の女性が新たに子宮体がんと診断されています。死亡数は年間約2,700人で、罹患数、死亡数ともに増加傾向が続いています。
年齢別では40歳代から患者数が増え始め、50歳代から60歳代がピークとなります。閉経を迎える時期以降の発症が多いという特徴があります。
国立がん研究センターの統計によると、1975年ころには子宮がん全体の内訳は8対2の割合で子宮頸がんが多かったのですが、子宮体がんが1990年代から増え始め、2010年代には子宮頸がんを上回るようになりました。現在では子宮がん全体の約60%を子宮体がんが占めています。
子宮体がんが増加している理由
生活習慣の変化とホルモンバランス
子宮体がんが増加した原因として最も影響が大きいとされているのは生活習慣の変化です。
特に食生活の欧米化や運動不足による肥満の増加により、ホルモンのバランスが崩れやすくなっています。肥満になると脂肪組織で女性ホルモンのエストロゲンが産生され、エストロゲンの作用が過剰になります。子宮内膜に対するエストロゲンの持続的な刺激があると、細胞の異常増殖によりがん化につながります。
実際に、肥満の女性は標準体重の女性と比較して、子宮体がんのリスクが2倍から4倍高いという研究結果が報告されています。
社会環境の変化と女性のライフスタイル
女性の社会進出に伴う労働環境の変化も、子宮体がん増加の一因と考えられています。
仕事によるストレスは体調悪化や生理不順を引き起こす可能性があります。また、晩婚化や出産年齢の高齢化、出産経験のない女性の増加も子宮体がんのリスク要因です。妊娠中や授乳期はエストロゲンの影響が抑えられるため、出産経験が子宮体がんの予防因子となることが知られています。
出産経験のない女性は、出産経験のある女性と比較して子宮体がんのリスクが約2倍高いとされています。
高齢化と特定の組織型の増加
日本社会の高齢化も子宮体がん増加の背景にあります。
高齢者に多く見られる悪性度の高い漿液性腺がん(しょうえきせいせんがん)という組織型が増えています。この組織型はホルモンの影響を受けにくく、一般的な子宮体がんとは発生メカニズムが異なります。加齢によってがんを発症しやすくなり、子宮体部に発生した場合に漿液性腺がんとなることが多いのです。
「自分の判断は正しいのか?」と不安な方へ

がん治療。
何を信じれば?
不安と恐怖で苦しい。
がん治療を左右するのは
治療法より“たった1つの条件”です。
まず、それを知ってください。
がん専門アドバイザー 本村ユウジ
世界と日本における子宮体がんの状況
欧米諸国での発生状況
アメリカでは、肉食中心の食生活、高カロリー、高脂肪、糖質過多の食事、肥満などが以前から社会問題となっており、子宮体がんの罹患率は日本より高い状況が続いています。2024年のデータでは、アメリカにおける子宮体がんの新規患者数は年間約67,000人、死亡数は約13,000人と報告されています。
ヨーロッパ諸国でも同様の傾向があり、特に西ヨーロッパや北ヨーロッパで子宮体がんの発生率が高くなっています。
アジア諸国との比較
アジア諸国の中では、日本は子宮体がんの罹患率が比較的高い国の一つです。韓国や中国などの東アジア諸国でも、経済発展に伴う生活習慣の欧米化により、子宮体がんの増加傾向が見られます。
一方、東南アジアや南アジアの国々では、まだ子宮頸がんの方が子宮体がんより多い状況が続いていますが、都市部を中心に子宮体がんが増加しつつあります。
子宮体がんの標準的な治療法
手術療法が治療の中心
子宮体がんの治療では手術が第一選択となります。
標準的な手術は、子宮全摘出術に加えて両側の卵巣と卵管を切除する手術です。多くの場合、骨盤リンパ節や傍大動脈リンパ節の摘出(リンパ節郭清)も行われます。リンパ節転移の有無を確認することで、術後の追加治療の必要性を判断します。
近年では、腹腔鏡手術やロボット支援手術が普及してきました。これらの低侵襲手術は従来の開腹手術と比較して、術後の回復が早く、入院期間も短縮できる利点があります。2024年現在、ロボット支援下子宮悪性腫瘍手術は保険適用となっており、多くの施設で実施可能となっています。
放射線治療の位置づけ
子宮体がんでは、子宮体部に放射線が効きにくいという特性があるため、放射線治療は手術の代替治療としてはあまり行われません。
ただし、手術後に再発リスクが高いと判断された場合や、手術ができない進行がんに対して、症状緩和を目的として放射線治療が選択されることがあります。また、骨盤内への再発に対しては、放射線治療が有効な場合もあります。
化学療法の役割
化学療法(抗がん剤治療)は、以下のような状況で実施されます。
まず、手術後に再発リスクを減らす目的で行われる術後補助化学療法があります。進行期やリンパ節転移の有無、組織型などから再発リスクを評価し、高リスクと判断された患者さんに対して実施されます。
次に、手術ができないほど進行した場合の治療として化学療法が選択されます。がんの縮小を目指す治療や、症状を和らげて生活の質を保つための治療が行われます。
さらに、手術後に再発した場合にも化学療法が実施されます。再発の部位や範囲によって治療方針は異なりますが、症状緩和と生活の質の維持を目的とした治療が中心となります。
子宮体がんで使用できる化学療法薬
従来から使用されている抗がん剤
2026年現在、子宮体がんで標準的に使用されている抗がん剤には以下のものがあります。
| 薬剤名(一般名) | 商品名例 | 特徴 |
|---|---|---|
| パクリタキセル | タキソール | 微小管阻害薬。第一選択として広く使用 |
| ドセタキセル | タキソテール | 微小管阻害薬。パクリタキセルと類似 |
| ドキソルビシン | アドリアマイシン | アントラサイクリン系抗がん剤 |
| シスプラチン | ランダ、ブリプラチン | 白金製剤。他剤との併用が多い |
| カルボプラチン | パラプラチン | 白金製剤。シスプラチンより副作用が軽い |
標準的な治療レジメンとしては、パクリタキセルとカルボプラチンの併用療法(TC療法)や、ドキソルビシンとシスプラチンの併用療法(AP療法)などが用いられています。
卵巣がん治療薬との関連性
子宮体がんと卵巣がんは、同じ女性生殖器のがんであり、組織学的な類似性があります。そのため、卵巣がんで使用されている薬剤を子宮体がんでも使用できないかという議論が以前からありました。
現在、卵巣がんで承認されているが子宮体がんでは未承認という薬剤には、イリノテカン(トポテシン、カンプト)、リポソーム化ドキソルビシン(ドキシル)、ノギテカン(ハイカムチン)、ゲムシタビン(ジェムザール)などがあります。
これらの薬剤についても、今後の臨床試験の結果によっては子宮体がんでの使用が可能になる可能性があります。
最新の分子標的薬と免疫療法
血管新生阻害薬ベバシズマブ
ベバシズマブ(アバスチン)は、がんの血管新生を阻害する分子標的薬です。卵巣がんでは2013年から使用可能となっていましたが、子宮体がんでの承認は遅れていました。
2023年に子宮体がんに対するベバシズマブの承認が拡大され、パクリタキセルとカルボプラチンとの併用療法として使用できるようになりました。進行または再発子宮体がんに対する治療選択肢として、期待されています。
免疫チェックポイント阻害剤の登場
近年、がん治療において大きな注目を集めているのが免疫チェックポイント阻害剤です。
子宮体がんの一部では、DNA修復機能に異常があるマイクロサテライト不安定性(MSI-High)やミスマッチ修復機能欠損(dMMR)という特徴を持つものがあります。このような特徴を持つがんに対して、免疫チェックポイント阻害剤が有効であることが明らかになっています。
2024年現在、ペムブロリズマブ(キイトルーダ)が、MSI-HighまたはdMMRの進行・再発子宮体がんに対して承認されています。従来の化学療法と比較して、副作用のプロファイルが異なり、一部の患者さんでは長期間の効果が期待できます。
さらに、2023年からはドスタルリマブ(ジェムペルリ)とカルボプラチン・パクリタキセルの併用療法が、dMMRの子宮体がんに対する一次治療として承認されました。免疫療法と化学療法を組み合わせることで、より高い治療効果が期待されています。
PARP阻害薬への期待
PARP阻害薬は、遺伝性乳がん・卵巣がん症候群の原因となるBRCA1/2遺伝子の変異がある患者さんに対して効果を発揮する分子標的薬です。
欧米では2014年末から卵巣がんに対してPARP阻害薬の使用が承認されており、日本でも2018年以降、オラパリブ(リムパーザ)、ニラパリブ(ゼジューラ)などが卵巣がんの治療薬として承認されています。
子宮体がんの中でも予後不良な漿液性腺がんは、卵巣がんと組織学的な類似性が高く、BRCA変異を持つ患者さんが一定数存在します。そのため、PARP阻害薬が子宮体がんにも有効ではないかと期待されています。
現時点では子宮体がんに対するPARP阻害薬の承認はまだ得られていませんが、臨床試験が進行中であり、将来的には新たな治療選択肢となる可能性があります。
PI3K/AKT/mTOR経路を標的とした治療
子宮体がんの多くでは、PI3K/AKT/mTOR経路と呼ばれる細胞増殖に関わるシグナル伝達経路に異常が見られます。特に類内膜腺がんでは、PTEN遺伝子の変異やPIK3CA遺伝子の変異が高頻度で認められます。
この経路を標的とした分子標的薬として、mTOR阻害薬のエベロリムス(アフィニトール)やテムシロリムス(トーリセル)、PI3K阻害薬などが研究されています。
これまでの臨床試験では単剤での効果は限定的でしたが、他の薬剤との併用により効果を高める試みが続けられています。ホルモン療法剤との併用や、免疫チェックポイント阻害剤との併用など、様々な組み合わせが検討されています。
最新の手術技術とその進歩
ロボット支援手術の普及
ロボット支援手術は、従来の腹腔鏡手術よりもさらに精密な操作が可能な低侵襲手術です。
da Vinciサージカルシステムと呼ばれるロボット手術システムを使用し、術者は3D画像を見ながら、多関節を持つ鉗子を自在に操作できます。手振れ補正機能や拡大視野により、より繊細な手術が可能となっています。
2018年に子宮体がんに対するロボット支援下子宮悪性腫瘍手術が保険適用となり、2024年現在では全国の多くの施設で実施されています。特にリンパ節郭清を伴う手術において、出血量の減少や術後回復の早さといった利点が報告されています。
センチネルリンパ節生検の導入
従来は、リンパ節転移の有無を調べるために広範囲のリンパ節郭清が行われていましたが、これには下肢のリンパ浮腫などの合併症のリスクがありました。
センチネルリンパ節生検は、がん細胞が最初に到達するリンパ節(センチネルリンパ節)のみを調べる方法です。このリンパ節に転移がなければ、他のリンパ節への転移の可能性は低いと判断し、広範囲のリンパ節郭清を省略できます。
子宮体がんにおいても、早期がんの患者さんを対象としたセンチネルリンパ節生検の臨床試験が進められており、将来的には標準治療となる可能性があります。リンパ浮腫などの術後合併症を減らしながら、必要な情報を得ることができる技術として期待されています。
妊孕性温存療法の進歩
ホルモン療法による子宮温存治療
若年で妊娠を強く希望する患者さんに対しては、条件を満たす場合に限り、子宮を温存するホルモン療法が選択肢となります。
適応となるのは、類内膜腺がんのグレード1(高分化型)で、筋層浸潤がなく、リンパ節転移や遠隔転移がないごく早期のがんです。さらに、ホルモン受容体(エストロゲン受容体、プロゲステロン受容体)が陽性であることが条件となります。
治療には高用量の黄体ホルモン製剤であるメドロキシプロゲステロン酢酸エステル(MPA)が使用されます。通常、6ヶ月から1年程度の投与を行い、3ヶ月ごとに子宮内膜の組織検査を実施して効果を確認します。
ホルモン療法により完全奏効(がん細胞が消失)が得られた場合、速やかに妊娠を試みることが推奨されます。妊娠・出産後は、再発予防のため子宮摘出術を検討する必要があります。
妊孕性温存療法のリスク
ホルモン療法による子宮温存治療は、あくまで妊娠・出産までの時間を稼ぐための治療であり、がんを完全に治すことを目的とした治療ではありません。
治療中にがんが進行するリスクや、治療終了後に再発するリスクがあります。また、がんの進行により、最終的に手術という選択肢さえ取れなくなる可能性もあります。これらのリスクを十分に理解した上で、慎重に検討する必要があります。
実際、ホルモン療法の完全奏効率は約70~80%と報告されていますが、その後の再発率も30~40%と高く、長期的な予後については不明な点が多いのが現状です。
今後の展望と課題
個別化医療の推進
今後の子宮体がん治療では、患者さん一人ひとりのがんの特性に応じた個別化医療がさらに進むと期待されています。
がん組織の遺伝子検査により、MSI-HighやdMMR、BRCA変異、その他の遺伝子変異の有無を調べ、それぞれに適した治療法を選択する時代になってきています。従来の組織型や進行期だけでなく、分子生物学的な特徴に基づいた治療選択が標準となっていくでしょう。
新規薬剤の開発
現在も様々な新規薬剤の臨床試験が進行中です。
特に注目されているのは、抗体薬物複合体(ADC)と呼ばれる新しいタイプの抗がん剤です。がん細胞に特異的に結合する抗体に、強力な抗がん剤を結合させたもので、がん細胞を選択的に攻撃できる可能性があります。HER2陽性の子宮体がんに対するトラスツズマブ デルクステカン(エンハーツ)などが臨床試験で評価されています。
また、新たな免疫チェックポイント阻害剤や、異なる作用機序を持つ分子標的薬の開発も続けられています。
予防と早期発見の重要性
治療法の進歩とともに、予防と早期発見の重要性も増しています。
肥満の予防、適切な体重管理、バランスの取れた食生活、定期的な運動などの生活習慣改善が、子宮体がんのリスク低減につながります。また、不正出血などの症状がある場合は速やかに婦人科を受診し、必要に応じて子宮内膜の検査を受けることが早期発見につながります。
特に閉経後の不正出血は、子宮体がんの可能性を考慮すべき重要なサインです。少量の出血であっても、放置せずに医療機関を受診することが大切です。
参考文献・出典情報
1. 国立がん研究センターがん情報サービス「子宮体がん(子宮内膜がん)」
https://ganjoho.jp/public/cancer/corpus_uteri/index.html
2. 日本婦人科腫瘍学会「子宮体がん治療ガイドライン2023年版」
https://jsgo.or.jp/guideline/taigan2023.html
3. 日本産科婦人科学会「子宮体癌取扱い規約 病理編 第5版」
http://www.jsog.or.jp/
4. 国立がん研究センター「がん統計」(全国がん登録)
https://ganjoho.jp/reg_stat/statistics/stat/summary.html
5. アメリカがん協会(American Cancer Society)「Endometrial Cancer Statistics」
https://www.cancer.org/cancer/endometrial-cancer/about/key-statistics.html
6. 日本癌治療学会「がん診療ガイドライン」
https://www.jsco-cpg.jp/
7. 医薬品医療機器総合機構(PMDA)「添付文書情報」
https://www.pmda.go.jp/
8. 日本臨床腫瘍学会「がん免疫療法ガイドライン」
https://www.jsmo.or.jp/about/guideline.html
9. 国立がん研究センター中央病院「子宮体がんの治療」
https://www.ncc.go.jp/jp/ncch/clinic/gynecology/110/index.html
10. 厚生労働省「がん対策情報」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/gan/index.html



