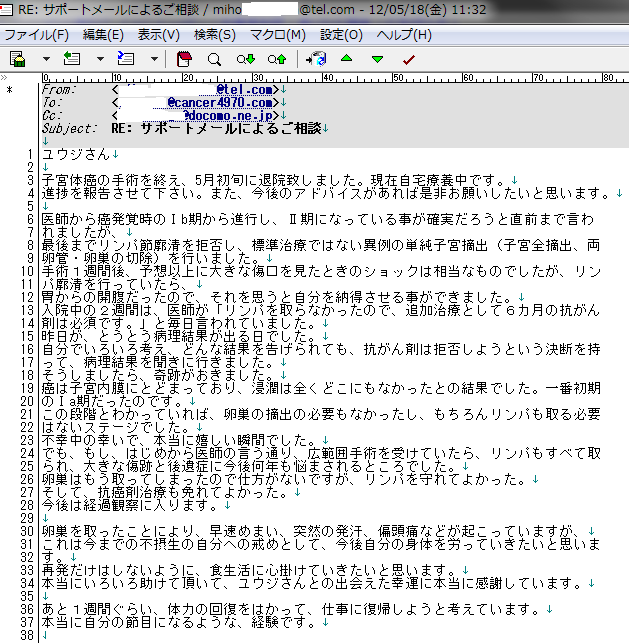子宮体がんと診断された患者さんにとって、放射線治療に関する詳しい情報を知ることは、治療計画を理解し適切に準備を進める上で重要です。
ここでは子宮体がんに対する放射線治療について、最新の医療情報に基づいて詳しく解説します。
【サイト内 特設ページ】

がんを治すために必要なことは、たった1つです。
詳しくはこちらのページで。
→がんを治すための「たった1つの条件」とは?
子宮体がんの放射線治療とは
子宮体がんの放射線治療は、エックス線やガンマ線を使ってがん細胞にダメージを与え、がんを小さくしたり治療する方法です。手術後の再発予防や、手術が困難な場合の根治治療として用いられます。
日本では、手術でリンパ節の処理が適切に行われていることが多く、骨盤内の再発が少ないとされています。そのため術後の治療は化学療法が主流となっており、放射線治療は選択肢の一つとして位置づけられています。
放射線治療が適応される症例
子宮体がんにおける放射線治療の適応は、以下のような場合に検討されます。
術後放射線治療
手術で摘出した病理結果において、術後の再発リスクが中等度以上と判断された場合に行われます。特に、手術で病理組織を調べた結果、がんの進行度や組織型から再発リスクが高いと評価された患者さんに対して実施されます。
根治的放射線治療
手術前の推定進行期がⅠ期またはⅡ期で、がんを手術で取り切れると考えられるが、他の病気や高齢、肥満などの理由で手術ができない時に、治癒を目的とした根治的放射線治療が検討されます。
再発に対する治療
手術で切除した腟の断端に再発した場合には放射線治療が行われます。また、腟やリンパ節の再発、少数個の遠隔転移を生じた場合に、薬物療法に加えて救済的な放射線治療が選択されることもあります。
緩和的放射線治療
がんの進行や転移による痛みなどの症状を和らげることを目的とした緩和的放射線治療も行われます。
【サイト内 特設ページ】

がんを治すために必要なことは、たった1つです。
詳しくはこちらのページで。
→がんを治すための「たった1つの条件」とは?
子宮体がん放射線治療のスケジュール
子宮体がんの放射線治療スケジュールは、治療の目的や患者さんの状態によって異なりますが、一般的な治療の流れをご紹介します。
治療前の準備期間
放射線治療を開始する前には、治療計画の策定が必要です。強度変調回転照射(VMAT)で治療を行う場合、放射線治療計画用CTを撮影後、10から14日間程度で治療開始となります。また、膀胱容量を一定に保つために蓄尿時間の管理を行い、ヨード造影剤を用いた放射線治療計画用CTを撮影します。
手術日から概ね2か月以内には治療を開始することが推奨されています。
外照射の治療スケジュール
外照射は通常、月曜日から金曜日まで週5回行われます。1回の治療時間は約10分で、平日毎日通院していただく形になります。治療中に痛みや熱さを感じることはありません。
総線量は一般的に50から50.4グレイで、25から28回に分けて照射されます。これは約5から6週間の治療期間に相当します。
腔内照射を併用する場合
症例によっては、外照射と併用して腔内照射が行われることがあります。腔内照射は、子宮や膣など人体の空洞部分に専用の器具を挿入し、その器具内を線源が通過することで治療を行います。体の内部から放射線を照射するため、効率的に腫瘍へ放射線を照射することが可能です。
子宮体がん放射線治療の副作用
放射線治療の副作用は、治療開始後から照射後数週間までに生じる「急性反応」と、照射後数カ月から数年で生じる「晩期合併症」に分けられます。
急性反応
治療開始後数週間以内に起こる急性反応には、以下のような症状があります。
| 症状 | 詳細 |
|---|---|
| 全身症状 | だるさ、疲労感、食欲低下 |
| 消化器症状 | 吐き気、下痢、直腸炎 |
| 泌尿器症状 | 膀胱炎、頻尿、排尿時痛 |
| 皮膚症状 | 照射部位の皮膚炎、発赤 |
| 粘膜症状 | 粘膜炎、口内炎(照射範囲による) |
これらの急性反応は、治療終了後には通常自然に治っていきます。症状の程度には個人差があり、適切な対症療法で症状を軽減することが可能です。
晩期合併症
治療後数カ月から数年たってから起こる晩期合併症には、以下のようなものがあります。
消化器系の合併症
放射線治療による晩期副作用の多くは直腸、膀胱または小腸に起こります。重篤な消化管副作用の多くは治療後3年以内に発生しますが、数十年経過した後に発生することもあります。
主な症状には、小腸閉塞、直腸出血、小腸炎などがあります。小腸閉塞のリスクは患者さんの特徴や治療法と強く関連しており、放射線治療前に腹部の手術歴がある患者さんではリスクが3から4倍に増加すると報告されています。
泌尿器系の合併症
尿路系副作用の発生までの平均期間は、腸管副作用の発生期間と比較して長い傾向があります。最もよく認められる重篤な晩期副作用は膀胱出血で、発生率は2から5パーセント程度です。
婦人科特有の合併症
放射線治療を行うと、卵巣の機能はほぼ失われてしまいます。これにより女性ホルモンが減少し、更年期障害と同様の症状が起こることがあります。具体的には、ほてり、発汗、食欲低下、だるさ、イライラ、頭痛、肩こりなどの症状があらわれます。
副作用の予防と対策
現在では、強度変調回転放射線治療(VMAT)などの高精度な治療技術を用いることで、晩期的な腸閉塞などの副作用の発症率を軽減できるようになっています。
また、副作用を予防する薬なども開発されており、特に吐き気や嘔吐については予防することができるようになってきました。
【サイト内 特設ページ】

がんを治すために必要なことは、たった1つです。
詳しくはこちらのページで。
→がんを治すための「たった1つの条件」とは?
子宮体がん放射線治療の入院期間
子宮体がんの放射線治療における入院の必要性は、治療の種類と組み合わせによって決まります。
通院での治療
放射線治療単独の場合は、基本的に通院での治療が可能です。外照射は1回約10分の治療で、月曜日から金曜日まで週5回、約5から6週間継続します。患者さんは毎日通院していただく必要がありますが、入院の必要はありません。
入院が必要な場合
化学療法と併用する場合(同時化学放射線療法)は入院で行われることが一般的です。これは、抗がん剤の投与と管理、副作用のモニタリングを適切に行うためです。
腔内照射を行う場合にも、処置の性質上、短期間の入院や日帰り入院が必要になることがあります。腔内照射は専用の器具を挿入する処置のため、鎮静剤を使用し、処置後はリカバリー室で休息いただいた後、当日中に帰宅できることが多いです。
入院期間の目安
化学療法と放射線治療を併用する場合の入院期間は、治療プロトコルや患者さんの状態によって異なりますが、通常は数日から1週間程度の短期入院を複数回行うことが多いです。
緊急的な副作用管理が必要な場合や、全身状態の管理が必要な場合には、より長期の入院が必要になることもあります。
温熱療法の併用について
一部の医療機関では、子宮体がんに対して放射線治療や抗がん剤の治療効果を高める温熱療法を取り入れています。がんの存在する領域の皮膚表面を2方向からパットで挟み込み高周波電流を流して加温します。
1回の加温時間は40から60分程度で、週に1から2回、放射線治療を行っている期間中に総5回程度行います。この治療により、放射線治療や抗がん剤の効果を高めることが期待されています。
治療後の経過観察
放射線治療が終了した後は、定期的な経過観察が必要です。経過観察の目的は、治療効果の確認、再発の早期発見、副作用の管理です。
通院スケジュール
経過観察は、再発のリスクに応じて、治療終了から2年までは3から6か月ごと、その後5年までは6から12か月ごとを目安に定期的に行うことが勧められています。
検査内容
定期的な診察では、症状の確認、内診、血液検査、画像検査(CTやMRIなど)が行われます。必要に応じて追加の検査が実施されることもあります。
患者さんへの生活指導
治療中の注意点
放射線治療中は、照射部位の皮膚を清潔に保ち、刺激を避けることが重要です。また、十分な休息と栄養摂取を心がけ、体力の維持に努めることが大切です。
副作用への対処
急性反応が起こった場合は、担当医や医療スタッフに相談し、適切な対症療法を受けることが重要です。症状を我慢せず、早めに相談することで、治療を継続しながら症状を管理できます。
長期的な健康管理
治療後は、定期的な検査を受けるとともに、健康的な生活習慣を維持することが大切です。バランスの取れた食事、適度な運動、禁煙などが推奨されます。
最新の治療技術について
近年、放射線治療の技術は大きく進歩しています。強度変調放射線治療(IMRT)や体積変調回転放射線治療(VMAT)などの高精度治療により、正常組織への照射を最小限に抑えながら、がん組織に十分な線量を照射することが可能になっています。
また、画像誘導放射線治療(IGRT)により、治療の精度が向上し、副作用の軽減が期待できます。
セカンドオピニオンの重要性
子宮体がんの治療方針決定においては、複数の治療選択肢がある場合が多いため、セカンドオピニオンを求めることも重要です。放射線治療の適応や治療方法について、別の専門医の意見を聞くことで、より適切な治療選択ができる場合があります。
チーム医療の重要性
子宮体がんの放射線治療は、放射線腫瘍医、婦人科医、看護師、放射線技師、薬剤師などの多職種によるチーム医療で行われます。患者さんが安心して治療を受けられるよう、医療チーム全体でサポートします。
経済的な側面について
放射線治療は健康保険の適用となり、高額療養費制度の対象にもなります。治療費については、医療ソーシャルワーカーや医事課に相談することで、経済的な負担軽減の方法について詳しい説明を受けることができます。
また、重粒子線治療など一部の先進的な治療については、限られた施設で保険適用となっている場合があります。
子宮体がんの放射線治療は、適切に実施されることで高い治療効果が期待できる治療法です。治療スケジュール、副作用、入院期間について正しく理解し、医療チームと密接に連携を取りながら治療を進めることが重要です。