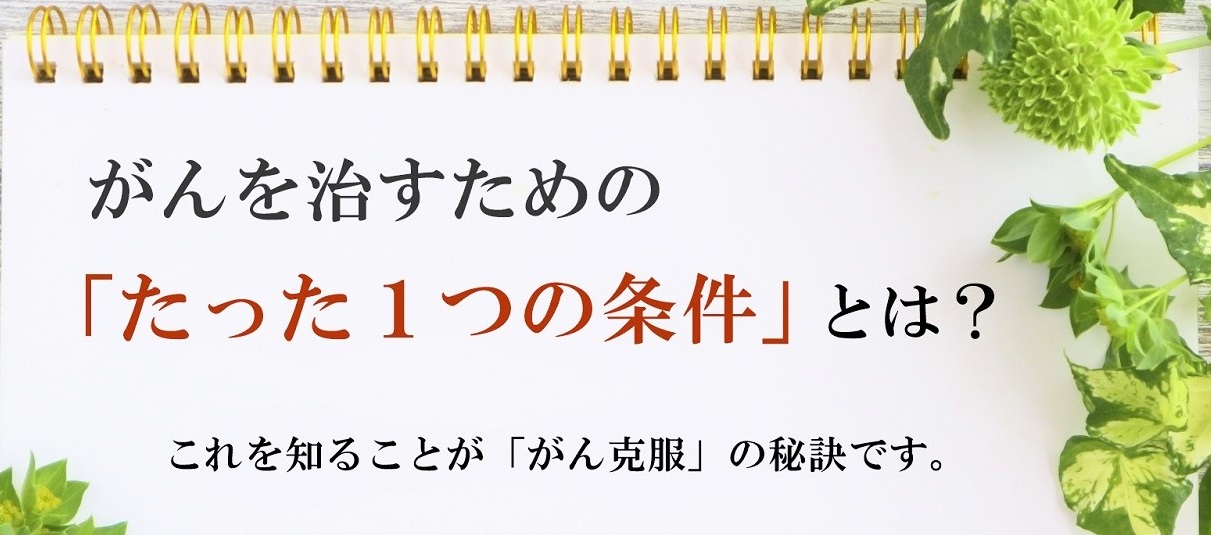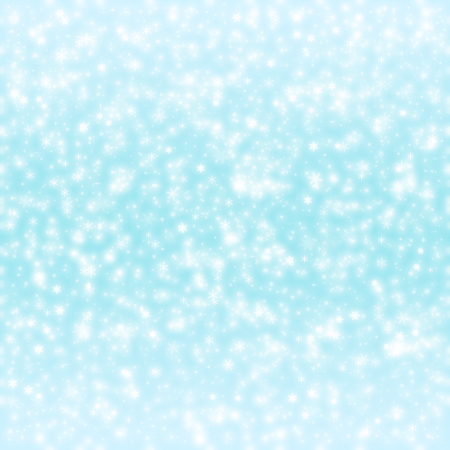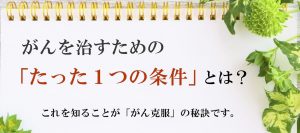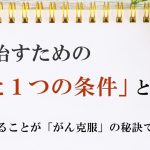抗がん剤は乳がんの状況に応じて、①術前化学療法、②術後化学療法、③転移・再発後抗がん剤の3つの場合に用いられます。なぜ、どういう目的で手術の前後に使われるのでしょうか。
化学療法(抗がん剤など薬を使った治療)は、作用の仕方が異なる抗がん剤を同時に、または順番に組み合わせることで、より高い治療効果を目指します。
また、投与の間隔や1回の投与量なども重要です。
乳がん手術後の化学療法
術後化学療法は「術後補助化学療法」とも言います。しかし、今やそれを「補助」とは認識されていません。
乳がんはシコリとして見えるまでに10年くらいはかかると考えられています。シコリになる前から、あるいはシコリが大きくなるにつれて、微小ながん細胞が全身に転移していきます。これは、最新の画像検査でも見えないようながん細胞の微小な転移です。術後化学療法は、このがん細胞を攻撃して再発を防ぐことが目的です。
術後化学療法は、病理検査で浸潤性乳がんの大きさが2㎝を超えたり、組織異型度や核異型度(悪性度)が高かったり、リンパ節に転移があったり、ホルモン受容体(エストロゲン受容体、プロゲステロン受容体)がなかったり、血管やリンパ管の中にがん細胞(脈管侵襲)があったり、HER2陽性だったりした場合に適応となります。
術後化学療法の意義は、臨床試験において再発した人や、死亡した患者さんの人数を標準治療と研究治療との間で比べて、どのくらい再発や死亡が軽減されたか医学的に「確率」を計算して検証します。術後化学療法が導入されたこの30年間で、化学療法を全くしない時代に再発していた患者さんの約半数の再発を防げるようになったといわれています。
しかし副作用がある抗がん剤治療を受けるか、受けないかは難しい判断です。副作用の怖さから拒絶反応を示す人もいます。
抗がん剤治療を行うことで再発のリスクがなくなるわけではありませんが、乳房以外の他の臓器に転移・再発した場合の平均的な生命の予後は3年から5年位であることは事実です。抗がん剤を使う、使わないを問わず、乳がんにおいて「再発・転移を防ぐこと」は最も重要なテーマであるといえます。
乳がん手術前の化学療法
がん細胞は腫瘍状態になってからは、どんどん増殖していきます。そのため腫瘍が小さいうちに抗がん剤で攻撃すれば体の中に隠れているがん細胞も少ないことから、効果が高いと考えられていました。
ところが、いくつかの臨床試験の結果、術前化学療法の方が術後化学療法より、統計学的に再発や死亡をより抑えることができるという結果は出ていません。
つまり、化学療法として術前でも術後でも「再発の予防」としての効果は同じです。この結果は、当時の腫瘍学の仮説から予測できないものでした。
その理由として、がん細胞が最初から抗がん剤に抵抗性を持っていることや、「がん幹細胞」から新たながん細胞の増殖が始まることなどが考えられます。
ただ、術前化学療法によって多くのケースでは腫瘍が小さくなります。手術が実施しやすくなる、薬の効果を確認できるといったメリットはあるといえます。
術前化学療法の対象となる乳がん
術前化学療法は1980年代にまず「局所進行乳がん」の患者さんを対象に行われました。
局所進行乳がんは、がんが皮膚表面に露出したり、胸の筋肉や肋骨など胸壁まで達していたり、脇や鎖骨の下のリンパ節へたくさん転移したりするⅢ期の乳がんです。理由は、すぐに手術をしても十分に局所治療ができない病状だからです。
しかし、近年では比較的早期の乳がんの患者さんを対象に、手術の前に化学療法を行う「術前化学療法」が急速に広まり「標準治療」となりました。
「術前化学療法」は手術の前に抗がん剤を使ってシコリを小さくし、乳房を温存するために行われています。
乳房温存術が可能とされる患者さんは、シコリの大きさが3cm以下の人で、広範な石灰化(マンモグラフィで広い範囲に石灰沈着があること)がない、乳がんが限られた範囲にある、というような条件を満たす場合です。
以上、乳がんの化学療法についての解説でした。
がんと診断されたあと、どのような治療を選び、日常生活でどんなケアをしていくのかで、その後の人生は大きく変わります。
納得できる判断をするためには正しい知識が必要です。