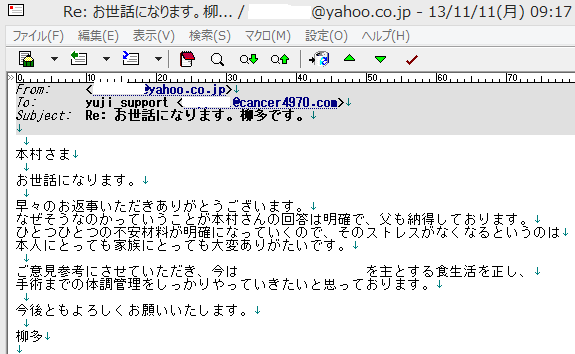【サイト内 特設ページ】

こんにちは。17年間の活動実績を持つ、
「プロのがん治療専門アドバイザー」本村ユウジです。
がんを治すために必要なことは、たった1つです。
詳しくはこちらのページでお伝えさせてください。
→がんを治すための「たった1つの条件」とは?
膵臓がんの検査が困難な理由
膵臓は人体の奥深くに位置する臓器であるため、一般的な画像診断では発見が非常に困難です。膵臓がんを疑って詳細な検査を行わない限り、早期発見は極めて難しいとされています。
膵臓がんの患者さんの多くは、初期症状として胃腸の不調を訴えます。しかし、このような症状は他の消化器疾患でも見られるため、膵臓がんの可能性を考慮せずに検査を行うと、異常なしと判断されてしまうケースが少なくありません。
2025年現在、膵臓がんの5年生存率は約12%と依然として低い水準にありますが、早期発見により治療成績は大幅に改善することが分かっています。そのため、適切な検査方法を理解することは非常に重要です。
膵臓がん診断方法の基本的な流れ
初期検査:腹部超音波検査と血液検査
患者さんが異常を感じて病院を受診した場合、まず実施される検査は腹部超音波検査と血液検査です。これらは非侵襲的で比較的簡単に行える検査として、多くの医療機関で実施されています。
腹部超音波検査では、熟練した技師が綿密に検査を行うことで、早期がんの段階でも胆管や膵管の拡張、腫瘍そのものを発見できる可能性があります。しかし、膵臓がんを疑わない段階では見落とされることも多いのが現状です。
血液検査については、早期がんでは膵臓が分泌する酵素の値がわずかに上昇することがありますが、明確な異常値を示すことは少ないとされています。
腫瘍マーカー検査の特徴と限界
膵臓がんの診断において重要な腫瘍マーカーには、CA19-9とDUPAN2があります。これらのマーカーは進行がんでは高い確率で上昇しますが、早期がんでは上昇しないケースが多く見られます。
| 腫瘍マーカー | 基準値 | 早期がんでの陽性率 | 進行がんでの陽性率 |
|---|---|---|---|
| CA19-9 | 37 U/ml以下 | 約30% | 約80% |
| DUPAN2 | 150 U/ml以下 | 約25% | 約70% |
このため、初期症状で受診しても膵臓がんが発見される確率は低く、早期発見の難しさを物語っています。
【サイト内 特設ページ】

こんにちは。17年間の活動実績を持つ、
「プロのがん治療専門アドバイザー」本村ユウジです。
がんを治すために必要なことは、たった1つです。
詳しくはこちらのページでお伝えさせてください。
→がんを治すための「たった1つの条件」とは?
膵臓がん検査の進歩した診断技術
CT検査による詳細な画像診断
超音波検査や血液検査で異常が認められた場合、次に行われるのが腹部CT検査です。近年のマルチスライスCT技術の向上により、膵臓の微細な変化まで捉えることが可能になっています。
CT検査では造影剤を使用することで、膵臓の血流状況や周囲臓器との関係を詳細に観察できます。2025年の最新技術では、0.5mm以下の薄いスライス厚での撮影が可能となり、小さな腫瘍の発見率も向上しています。
ERCP検査:膵管の直接観察
膵臓がんが疑われる場合に実施される専門的な検査がERCP(内視鏡的逆行性胆管膵管造影)です。この検査では、十二指腸にある膵管と胆管の出口まで細い内視鏡を挿入し、造影剤を注入してX線撮影を行います。
ERCP検査の利点は以下の通りです:
- 膵管の内壁の詳細な観察が可能
- 胆汁や膵液の採取によるがん細胞の検出
- 必要に応じて組織採取も実施可能
- 治療的処置(ステント留置など)も同時に行える
胆管が閉塞して黄疸が生じている場合には、PTC(経皮経肝胆管造影)も併用されることがあります。
MRCP検査:非侵襲的な膵管観察
最近では、ERCPの代替またはERCPに先立ってMRCP(MR胆管膵管造影)が実施されることが増えています。この検査は、MRIを膵液や胆汁を見やすく設定して膵管と胆管を撮影する方法です。
MRCP検査の特徴:
- 非侵襲的で安全性が高い
- 造影剤の使用が不要な場合が多い
- 膵管全体の形態を一度に観察可能
- 繰り返し検査が容易
最新の膵臓がん検査技術
超音波内視鏡(EUS)による精密診断
2025年現在、多くの専門医療機関で導入されている超音波内視鏡は、内視鏡の先端に超音波発生装置を搭載した検査機器です。胃や十二指腸から膵臓に近接して超音波検査を行えるため、非常に詳細な観察が可能です。
超音波内視鏡の優れた点:
- 腫瘍の大きさと広がりの正確な把握
- 周囲血管への浸潤の評価
- リンパ節転移の検出
- 組織採取(EUS-FNA)も可能
血管造影検査による手術適応の判定
膵臓がんの治療方針を決定する上で重要なのが、周囲の重要な血管への浸潤の有無です。血管造影検査により、腫瘍が血管を侵している場合は外科手術の適応外と判断されます。
近年では、CTアンギオグラフィーやMRアンギオグラフィーなど、より低侵襲な血管画像診断技術も発達しており、患者さんの負担軽減に貢献しています。
【サイト内 特設ページ】

こんにちは。17年間の活動実績を持つ、
「プロのがん治療専門アドバイザー」本村ユウジです。
がんを治すために必要なことは、たった1つです。
詳しくはこちらのページでお伝えさせてください。
→がんを治すための「たった1つの条件」とは?
膵臓がんの早期発見に向けた最新動向
液体生検(リキッドバイオプシー)の可能性
2025年の医学界では、血液中に含まれる循環腫瘍DNA(ctDNA)を検出する液体生検技術が注目されています。この技術により、従来の検査では発見困難な早期膵臓がんの診断が期待されています。
液体生検の利点:
- 簡単な血液検査で実施可能
- 非侵襲的で患者負担が少ない
- 遺伝子変異の詳細な解析が可能
- 治療効果の監視にも応用可能
AI画像診断技術の導入
人工知能(AI)を活用した画像診断システムの開発も進んでいます。膵臓がんの画像を学習したAIが、医師の診断を補助することで、見落としの減少や診断精度の向上が期待されています。
膵臓がん検査における注意点と限界
現在のスクリーニング検査の課題
胃がんのバリウム検査のような簡便なスクリーニング検査は、膵臓がんについてはまだ確立されていません。これは膵臓の解剖学的特徴と、早期がんでも症状が現れにくいことが主な理由です。
また、膵臓がんの明確な危険因子も完全には解明されていないため、高リスク群に対する定期的な検査体制の構築も課題となっています。
早期発見の重要性と治療成績
膵臓がんは治療が極めて困難ながんですが、早期に発見できれば根治(完全にがんを取り除くこと)の可能性は60%以上に向上します。この数値は、進行がんの治療成績と比較すると大幅な改善を示しています。
| 発見時期 | 5年生存率 | 根治切除率 |
|---|---|---|
| 早期がん(ステージI) | 約60% | 約90% |
| 進行がん(ステージII-III) | 約20% | 約40% |
| 転移がん(ステージIV) | 約5% | 適応なし |
膵臓がんの検査を受ける際の心構え
症状があれば早めの受診を
膵臓がんの初期症状には以下のようなものがあります:
- 上腹部の鈍い痛みや不快感
- 食欲不振や体重減少
- 背中の痛み
- 糖尿病の新規発症または悪化
- 脂肪便(便が脂っこくなる)
これらの症状が持続する場合は、積極的に医療機関を受診することが重要です。
セカンドオピニオンの活用
膵臓がんの診断は専門性が高いため、診断に不安がある場合はセカンドオピニオンを求めることも大切です。膵臓がんに精通した専門医による詳細な検査により、より正確な診断が期待できます。
まとめ
膵臓がんの検査と診断は、その解剖学的特徴により困難な側面がありますが、医療技術の進歩により診断精度は着実に向上しています。早期発見により治療成績が大幅に改善するため、適切な検査を適切なタイミングで受けることが重要です。
2025年現在も新しい検査技術の開発が続いており、将来的にはより簡便で正確なスクリーニング検査の実用化が期待されています。
参考文献・出典
American Society of Clinical Oncology「Pancreatic Cancer Guidelines」
European Society for Medical Oncology「Pancreatic Cancer Guidelines」
Nature Medicine「Advances in Pancreatic Cancer Detection 2025」
The Lancet Oncology「Early Detection Strategies for Pancreatic Cancer」