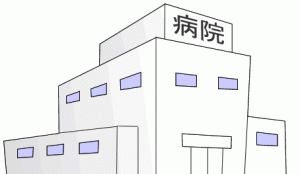
食道がんの治療(内視鏡治療、手術、化学放射線療法)を受けて、がんが体内からなくなったと判断された場合でも、再発のリスクはゼロではありません。治療のときに目に見えない小さながん細胞が残っていて、時間をかけて大きくなることがあるからです。
さらに、食道がんは重複がんといって、他の臓器にがんが新たに発生することがあります。食道がんにかかられた患者さんは約23%程度の頻度で他の臓器にもがんができることがわかっており、咽頭を中心とする頭頸部がん、胃がん、大腸がんの順で多いと報告されています。このため、定期的な検査による早期発見・早期治療が重要になります。
食道がん治療後の定期検査で調べる5つのポイント
食道がんの治療後に行う定期検査には、明確な目的があります。ただ漠然と検査を受けるのではなく、何をチェックしているのかを理解することで、より安心して検査を受けることができます。
局所再発の早期発見
治療した食道の同じ場所やその周辺に、がんが再び現れていないかを調べます。手術で食道を切除した部分の周辺や、内視鏡治療を行った部位に再発がないかを確認します。
リンパ節転移の有無
首、胸、お腹のリンパ節にがんが転移していないかを調べます。食道がんの再発は80%以上が手術後2年以内に起こることが分かっていますため、特に治療後の最初の2年間は重点的にチェックが行われます。
他の臓器への転移
肺、肝臓、骨などの離れた臓器に転移していないかを調べます。これらの臓器は食道がんが転移しやすい場所として知られています。
播種再発のチェック
がん細胞が腹腔内や胸腔内に散らばって増殖していないかを確認します。これは「播種(はしゅ)」と呼ばれる特殊な再発パターンです。
重複がんの早期発見
食道以外の臓器に新しくがんが発生していないかを調べます。食道がんでは、約20%に重複がんが発生するといわれています。特に頭頸部がん(のどのがん)、胃がん、大腸がんが多く見つかります。
食道がん治療後に行われる6つの主要検査
定期検査では、患者さんの病状や治療法に応じて複数の検査を組み合わせて行います。それぞれの検査には明確な役割があります。
| 検査名 | 目的 | 頻度 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 身体診察 | 触診による再発チェック | 毎回 | 首のリンパ節の腫れなどを確認 |
| 血液検査 | 栄養状態、腫瘍マーカー測定 | 毎回 | 貧血や栄養状態も評価 |
| 上部消化管内視鏡検査 | 局所再発、重複がんの発見 | 年1回 | 食道、胃、十二指腸を詳細に観察 |
| CT検査 | 全身の転移チェック | 3~6か月毎 | リンパ節、肺、肝臓などを確認 |
| 超音波検査 | 腹部臓器、リンパ節の観察 | 適宜 | 体に負担をかけずに検査可能 |
| PET検査 | 全身のがん細胞検出 | 必要時 | 骨転移なども発見可能 |
身体診察での視診・触診
医師が直接体を診察し、首のリンパ節の腫れや皮膚の変化、声の変化などを確認します。簡単な検査ですが、再発の兆候を早期に発見する重要な役割があります。
血液生化学検査と腫瘍マーカー
血液検査では、治療後の栄養状態や貧血の有無を調べると同時に、腫瘍マーカーを測定します。食道がんの腫瘍マーカーは、扁平上皮がんではSCC(扁平上皮がん関連抗原)とCEA(がん胎児性抗原)、腺がんではCEAとなります。
ただし、腫瘍マーカーには限界があることも理解しておく必要があります。進行した食道がんではしばしば腫瘍マーカーが高値となりますが、早期の食道がんでは腫瘍マーカーの値が正常範囲であることがほとんどです。このため、腫瘍マーカーの結果だけでなく、他の検査結果も総合的に判断することが重要です。
上部消化管内視鏡検査(胃カメラ)
食道がん手術後や根治的化学放射線治療後は、1年に1回は上部消化管内視鏡検査(胃カメラ)、半年に1回はCT検査を行い、再発がないかどうか調べます。
内視鏡検査では、食道の局所再発だけでなく、胃や食道の新しい病変も発見できます。前に述べましたが、食道がんに合併する他臓器がんで最も多いものは頭頸部がんと胃がんです。頭頸部がん、胃がんが進行した状態で見つかると食道がんの手術後では手術することができない場合もありますため、年1回の内視鏡検査は欠かせません。
CT検査(コンピュータ断層撮影)
CT検査は食道がん治療後の定期検査の中心となる検査です。手術を受けた患者さんは再発の早期発見のため定期的にCT検査を中心とした検査を行います。このCT検査でリンパ節再発や、肝転移、肺転移などの臓器転移の検索を行います。
CT検査の頻度は治療後の時期によって異なります。そのため最初の1、2年は3~6ヶ月毎など短期間でCT検査を繰り返し、その後期間を延ばしていくのが一般的です。
超音波検査(エコー検査)
超音波検査では、腹部の肝臓や腎臓、リンパ節の状態を調べます。体に負担をかけることなく、繰り返し検査を行うことができる利点があります。
PET検査(陽電子放射断層撮影)
がん細胞がブドウ糖を多く取り込む性質を利用して、全身へのがんの広がりを確認するための検査です。臓器だけでなく骨への転移も調べることができます。CT検査で明らかでない場合に追加で行われることがあります。
定期検査のスケジュールと注意点
定期検査のスケジュールは、初回治療の内容や病期によって決められます。診察や検査の時期や頻度は、初回治療時のがんの進行度、治療の目的や受けた治療、治療の効果、治療後の時間経過によって異なりますが、おおよそ年1~4回程度です。
治療方法別の検査内容
内視鏡的切除(EMR・ESD)後の場合
病理組織検査で粘膜固有層までのがんであったと診断されれば治療後にCT検査などでリンパ節再発を検索する必要は基本的にありません。主に上部消化管内視鏡検査による経過観察が中心となります。
手術・化学放射線療法後の場合
より厳重な経過観察が必要となります。最初の2年間は3~6か月毎のCT検査、年1回の内視鏡検査が標準的です。3年目以降は検査間隔を延ばしていくのが一般的です。
検査で気をつけるべき症状
首のリンパ節に転移すると、首が腫れたり、声がかすれたりします。またお腹や胸のリンパ節に転移すると、背中や腰に痛みを感じることがあります。骨への転移も痛みを伴います。
これらの症状がある場合は、次の定期検査を待たずに早めに担当医に相談することが大切です。
重複がんについて知っておくべきこと
食道がんの患者さんにとって重要なのは、食道がんの再発だけでなく、他の臓器に新しくがんが発生する可能性があることです。
重複がんが起こりやすい理由
食道がんの主な要因である飲酒や喫煙をはじめ、食べ過ぎや肥満といった生活習慣が長く続いている場合、食道だけでなく他の部位にも同じように悪い影響を及ぼしてしまうため、全身にがんが発生しやすい状態となります。
特に注意すべき臓器
特に食道と同じように刺激を受けている、咽頭(いんとう)や喉頭(こうとう)、胃腸や肺では重複がんが多く、これらは同時に発生することもあれば、異なる時期に発生することもあります。
具体的には以下の臓器でがんが発生しやすいことが知られています:
- 頭頸部(咽頭がん、喉頭がん)
- 胃がん
- 大腸がん
- 肺がん
検査結果の見方と医師との相談ポイント
定期検査の結果について、患者さんやご家族が知っておくべきポイントをまとめます。
腫瘍マーカーの数値について
腫瘍マーカーの数値が少し上昇した程度では、過度に心配する必要はありません。定期検査の検査結果で、腫瘍マーカーが少し上昇することがあります。腫瘍マーカが少し上がった程度では、不安に思う必要はありません。
ただし、右肩上がりに上昇する場合は、注意が必要です。たとえ、正常域内であったとしても、右肩上がりに数値が上昇するときは、がんが増殖してきている兆候であることが多いです。
医師に相談すべきタイミング
次のような症状がある場合は、定期検査を待たずに医師に相談しましょう:
- 食べ物がつかえる感じが続く
- 胸や背中の痛み
- 声のかすれ
- 体重の急激な減少
- 血の混じった痰
- 首のリンパ節の腫れ
定期検査を継続することの重要性
手術後の経過観察は治療の一環です。がんが完治しているのか、この先に再発してくるのか、医者が経過を注意深く観察しなければわかりません。
定期検査は単なる確認作業ではなく、治療の継続的な一部と考えることが大切です。がんの再発は治療後3年以内(胃がんの場合は治療後1~2年以内)に起こることが多く、5年以上たってから再発することは少ないことがわかっています。
そのため、最低でも5年間は医師の指示に従って定期的な検査を受け続けることが重要です。
まとめ
食道がん治療後の定期検査は、再発や重複がんの早期発見により、患者さんの予後を大幅に改善する可能性があります。検査の目的と内容を理解し、医師と密に連携を取りながら、継続的な経過観察を受けることが重要です。
検査結果に一喜一憂することなく、長期的な視点で健康管理を行い、気になる症状があれば遠慮なく医療チームに相談しましょう。














