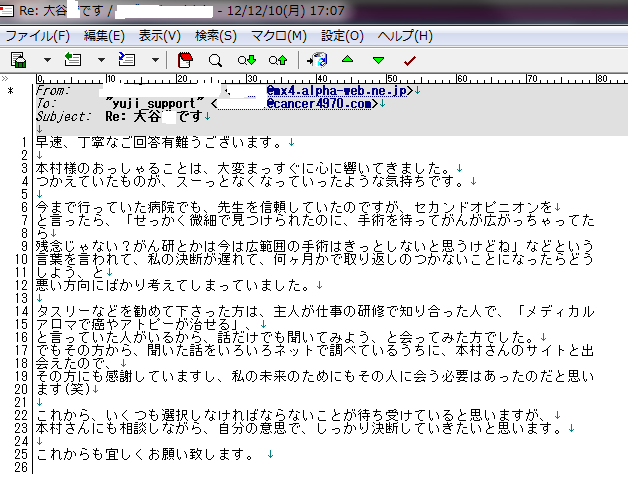子宮頸がん手術後のリンパ浮腫とは
子宮頸がんの手術後に起こる可能性のあるリンパ浮腫について、まず基本的なメカニズムを理解しましょう。リンパ管は血管と同様に全身を巡る管で、その中にはリンパ液が流れています。子宮頸がんの治療でリンパ節郭清(リンパ節の切除)や放射線治療を行うと、リンパ節やリンパ管に障害が起こります。その結果、リンパ液の心臓に向かう流れが滞り、下半身にむくみが生じることがあります。
通常の疲労によるむくみは一晩休むことで改善されますが、リンパ浮腫は改善しません。これがリンパ浮腫の大きな特徴です。
リンパ管は障害を受けても再生する能力があり、再びリンパ液が流れるようになります。そのため、リンパ節郭清を行ったすべての患者さんにリンパ浮腫が起こるわけではありません。ただし、いったん発症すると治りにくく、治療後何年も経ってから突然起こることもあります。
リンパ浮腫は日常生活に支障をきたし、精神的な負担も大きくなります。予防を心がけ、体の変化に注意することが重要です。早期に治療を開始すれば改善しやすく、悪化も防げるため、症状が出たら速やかに対処することが大切です。
子宮頸がん手術後のリンパ浮腫の症状と進行段階
リンパ浮腫の症状は段階的に進行します。むくみは脚からではなく、リンパ節を切除した下腹部や陰部、脚の付け根から始まることが多く、放置するとゆっくりと進行し、足先まで広がっていきます。
第1段階:初期症状
自覚症状はほとんどありませんが、触ると皮膚が厚くなったように感じることがあります。皮膚をつまんだ時に、しわが寄りにくくなるのも特徴的な変化です。
第2段階:軽度のむくみ
目に見えるむくみが現れ、指で押すとへこみます。だるさや疲れやすさなどの症状も出現します。この段階では、脚を高くして休むことで改善が見られることもあります。
第3段階:中等度のむくみ
皮膚が厚くなり、むくみで脚が太くなります。脚を高くしても改善せず、だんだん指で押してもへこまなくなります。
第4段階:重度のリンパ浮腫
皮膚が乾燥し、厚く固くなって角化が目立つようになります。関節を動かしにくくなるなど、機能的な障害も現れます。
リンパ浮腫と一般的なむくみの違い
むくみにはさまざまな原因がありますが、一般的によく見られる脚のむくみは血液循環が悪くなって夕方に現れやすいものです。体を動かしたり、一晩寝ることで改善します。
これに対してリンパ浮腫は、流れなくなったリンパ液が細胞の間にたまって起こるもので、ごく初期の場合を除いては、休むだけで改善することはありません。適切なケアをしないと症状はゆっくりと進行し、ひどくなると皮膚や皮下組織が硬くなる変化も見られます。
また、両脚同時にむくむことはまれで、片方の脚に起こるケースが多いのも特徴です。医療機関でリンパ浮腫の治療を受ける際には、他の原因によるむくみではないかを確認するため、問診、視診、触診をはじめ、必要に応じて画像検査や血液検査も行われます。
子宮頸がん手術後のリンパ浮腫予防のための日常ケア
リンパ浮腫の予防として、まず日常的に家庭でできるケアが基本となります。リンパの流れを助けるために、以下のような生活習慣を心がけましょう。
姿勢と体位の工夫
椅子に座る時や寝る時は、台などを置いて脚を高くするようにします。正座は避けて脚を伸ばして座ることが大切です。寝ている時は膝から下を10センチほど高くしますが、高くしすぎてもよくないので注意が必要です。
運動とリンパ浮腫予防
脚に負担をかけるようなハードな運動は避けるべきですが、水中ウォーキングや自転車こぎなどの軽い運動は予防に効果的です。座っている時に脚を曲げ伸ばしするだけでも効果があります。
スキンケアと清潔の維持
リンパ液の流れが悪い時には炎症も起こりやすく、炎症が起こるとむくみが悪化します。怪我に注意し、清潔と保湿を心がけましょう。肌が乾燥するとバリア機能が低下してしまいます。
具体的なリンパ浮腫予防策一覧
以下に、日常生活で実践できる具体的な予防策をまとめました。
椅子に座る時は脚を下げないように台を置き、その上に足をのせることです。正座は避け、寝ている時は膝から下を10センチほど高くします。立ちっぱなし、座りっぱなしを避け、同じ姿勢を長く続けないようにし、足首や膝、腰などを時々動かすことが重要です。
きつい下着や靴下で体を締めつけないよう注意し、きつい靴や履いていて疲れるような高いヒールの靴は避けましょう。過度の運動は控え、適度な運動を心がけます。足がだるくなったり疲れたりした時には、必ず休憩を取ります。
入浴や岩盤浴、サウナ、ホットカーペットなどで長時間温めないようにし、脚への鍼灸治療やマッサージは受けないことが大切です。太るとリンパ液が流れにくくなり、むくみを起こしやすいので標準体重を保ちましょう。
肌を清潔にしておき、肌が乾燥しないように乳液やクリームなどで保湿を心がけます。日焼けをしないようにし、ちょっとした怪我もしないよう気をつけることが必要です。バランスの良い食事を取ることも重要な予防策の一つです。
早期発見のための注意すべき症状
早い段階でリンパ浮腫の治療を開始できるよう、スキンケアをしながら自分の変化を見逃さないようにしましょう。初期のうちに進行を抑えられるよう、以下のような症状に気づいたら早めに受診することが大切です。
下着や靴下の跡がはっきりとつくようになった場合や、脚が重くだるい感じがする時、皮膚がつっぱった感じがしてつまみづらくなった時は要注意です。それまで見えていた血管が見えなくなったり、片方だけ脚が太くなったり、皮膚がピリピリするような感覚がある時も早期受診の目安となります。
リンパドレナージによる治療法
むくみが起こった時には、スキンケアなどの日常的なケアに加えて、リンパドレナージ、圧迫療法、運動療法を組み合わせた「複合的治療」を行います。
リンパドレナージは、マッサージによって滞ったリンパ液の流れを促す方法です。正しく流れるようにリンパ液を誘導し、むくみを改善します。ただし、筋肉の疲れをもみほぐすような一般的なマッサージとは異なり、強く押したりもんだりすることはありません。美容目的のリンパマッサージとも全く違う治療用のマッサージです。
リンパドレナージの実施方法
リンパドレナージは、リンパ液を流す方向に向かって適切な順序で適切な強さでリンパ液を誘導することが求められます。そのため、リンパ浮腫に関する専門的な知識が必要ですが、資格を持った看護師や専門のセラピストの指導を受けることで、自分でもできるようになります。
皮膚に炎症を起こしている時は避け、ドレナージをする前には皮膚の熱感や傷、発疹がないかよく確認します。皮膚に異常がないことを確認したら、手のひら全体を使ってやさしく、ゆっくりと、リンパ液を流すようにマッサージします。
正しいマッサージの順序
リンパ液を流すためには順番が重要で、むくんでいる所からマッサージを始めるのではありません。わきの下、体の側面から始め、脚の付け根、太もも、膝、すね、ふくらはぎ、足先と進めるのが基本的な手順です。
圧迫療法とその効果
リンパドレナージでリンパ液の流れを促しただけでは、リンパ液は再びたまり始めます。そこで、リンパ液が逆流しないよう、また細胞間にたまらないよう、脚全体を圧迫して圧力をかけるのが圧迫療法です。
圧迫療法ではむくみが軽減し、その状態を維持する効果が期待でき、肌の保護にも役立ちます。弾性ストッキングや弾性包帯が用いられ、いろいろなタイプがあります。サイズはもちろん、圧迫力も自分に適したものでないと十分な効果が得られないため、医師に相談して選ぶことが重要です。
弾性ストッキングの選び方と使用法
正しく履くことも大切で、弾性ストッキングはきつくできているため簡単には履けません。履き方の指導も受けることをお勧めします。弾性包帯は巻き方次第で圧を変えることができ、弾性ストッキングが履けないほどのむくみにも対応できます。専門家の指導を受けて巻くようにしましょう。
運動療法との組み合わせ
筋肉を動かすと、縮んだり緩んだりする筋肉の動きでリンパ液の流れが促されます。圧迫療法で圧力を加えながら動かすと、その効果はさらに大きくなります。
弾性ストッキングや弾性包帯をつけたら、膝や足首など関節の曲げ伸ばしをゆっくり行いましょう。散歩をしたり自転車をこいだりして脚を動かすことは効果的です。弾性ストッキングや弾性包帯は朝起きた時につけ、就寝前に取るのが基本ですが、発疹や傷など皮膚に異常がある時や、圧迫によって痛みやしびれを感じる時などは着用をやめ、主治医に相談しましょう。
医療機関での専門治療
リンパ浮腫の症状が現れたら、まず主治医に相談してみましょう。もしその病院でリンパ浮腫に対する指導や治療をしていなければ、治療できる病院を紹介してくれるはずです。
リンパ浮腫外来を設ける病院も増えており、症状が出ていなくても相談すれば予防法からアドバイスしてくれます。リンパ浮腫に対するケアの指導や治療は健康保険の適用になっているものもありますが、自由診療で行っている施設もあるため、初めに確認することが大切です。
リンパ浮腫外来のある施設は、がん診療連携拠点病院内にある「がん相談支援センター」で確認でき、「がん情報サービス」のサイトでも検索できます。
2025年最新のリンパ浮腫治療動向
近年、リンパ浮腫治療の分野では新しい技術や治療法の開発が進んでいます。リンパ管静脈吻合術やリンパ節移植術などの外科的治療法も選択肢として検討されるようになっています。
また、早期診断のための検査技術も向上し、インドシアニングリーンリンパ管造影などの新しい検査法により、より正確な診断と効果的な治療計画の立案が可能になっています。
予防医学の観点からも、手術前からの予防的なリンパドレナージ指導や、患者さん自身による自己管理プログラムの普及が進んでおり、リンパ浮腫の発症率低下や重症化防止に寄与しています。
生活の質向上のための支援体制
リンパ浮腫は身体的な症状だけでなく、心理的・社会的な影響も大きい疾患です。患者さんの生活の質向上のため、医療機関では多職種チームによる包括的なサポート体制が整備されています。
看護師、理学療法士、作業療法士、医療ソーシャルワーカーなどが連携し、患者さん一人ひとりのライフスタイルに合わせた治療計画を立て、継続的な支援を提供しています。
また、同じ悩みを持つ患者さん同士の交流を促進する患者会やサポートグループの活動も活発になっており、情報共有や相互支援の場として重要な役割を果たしています。
まとめ
子宮頸がん手術後のリンパ浮腫は、適切な予防と早期治療により症状の改善や進行の抑制が可能です。日常生活でのセルフケアを基本とし、症状に気づいたら早めに専門医療機関を受診することが重要です。
リンパドレナージ、圧迫療法、運動療法を組み合わせた複合的治療により、多くの患者さんで症状の改善が期待できます。
参考文献・出典情報
日本リンパ浮腫学会「リンパ浮腫診療ガイドライン2018年版」https://www.jslf.jp/
がん情報サービス「リンパ浮腫」国立がん研究センターhttps://ganjoho.jp/public/support/condition/lymphedema/
厚生労働省「がん対策推進基本計画」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000183313.html
日本婦人科腫瘍学会「子宮頸がん治療ガイドライン」https://jsgo.or.jp/
International Society of Lymphology「The Diagnosis and Treatment of Peripheral Lymphedema」https://www.lymphology.org/
日本がんサポートケア学会「がん治療に伴うリンパ浮腫の予防と管理」https://jascc.jp/
厚生労働省研究班「リンパ浮腫指導管理料に関する研究」https://www.mhlw.go.jp/
日本理学療法士協会「がんのリハビリテーション」https://www.japanpt.or.jp/
World Health Organization「Cancer rehabilitation」https://www.who.int/
日本看護協会「がん看護専門看護師の役割」https://www.nurse.or.jp/