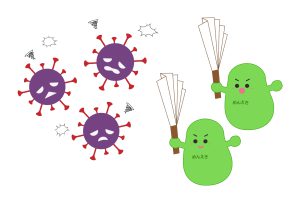
【サイト内 特設ページ】

こんにちは。17年間の活動実績を持つ、
「プロのがん治療専門アドバイザー」本村ユウジです。
がんを治すために必要なことは、たった1つです。
詳しくはこちらのページでお伝えさせてください。
→がんを治すための「たった1つの条件」とは?
がんの免疫療法の歴史と発展
免疫療法と呼ばれる治療法には様々な方法がありますが、長い間、効果が科学的に証明されず、信頼性が不確かな治療法という位置づけでした。
免疫療法の始まりは100年以上前にさかのぼります。
1890年、米ニューヨークでがん治療医をしていたウィリアム・コーリー博士が、高熱を発したがん患者さんのがんが小さくなったり消えたりしていることに気づきました。
高熱の原因は、マラリア、麻疹、インフルエンザ、梅毒などの感染症でした。コーリー博士は翌年、頭部と咽頭にがんのある患者さんに細菌を注射して意図的に高熱を出させたところ、後にがんが消えたと報告されています。
これが「感染によって免疫の仕組みを刺激してがんを治療する」という人類初の免疫療法だったとされています。
しかし、人為的に感染症を起こし、患者さんの命にかかわる恐れがある治療法には問題がありました。コーリー博士はその後、殺した細菌を使う「コーリーワクチン」を開発しましたが、手術や抗がん剤などの効果が確実な治療法が発達したことに加え、コーリーワクチンの再現性に疑問が生じたこともあって使われなくなりました。
サイトカイン療法の登場
1980年代になると、免疫細胞を活発にしたり増やしたりする働きを持つ「サイトカイン」というたんぱく質を患者さんに投与する「サイトカイン療法」が開発されました。
サイトカインは100種類以上が知られていますが、日本では「インターフェロン」と「インターロイキン2」について、腎臓がんに対する保険診療が認められ、標準治療となりました。ただし、その効果や対象となるがんの種類は限定的で、手術、放射線、化学療法の3大療法の補助的な存在にとどまっています。
保険適応外の免疫療法の現状
がん細胞を攻撃するT細胞やNK細胞を体外で培養して投与したり、がんを認識させた樹状細胞を体外で培養して投与したりする「細胞療法」や、がんの目印となる抗原やがん細胞の成分を投与して免疫細胞の活動を刺激する「がんワクチン療法」などがあります。
しかし、これらの治療法はまだ十分な効果が確認されていません。そのため、多くは自費診療として提供されており、保険適応にはなっていません。
モノクローナル抗体療法について
がん細胞を攻撃する抗体を投与する「モノクローナル抗体療法」は、すでに効果が認められ標準治療として使われています。ただし、この抗体はマウスなどで作られたものです。患者さん自身の免疫を利用しているわけではありませんので、他の免疫療法とは少し異なる仕組みといえます。
丸山ワクチンとBCG療法
国内で知られている「丸山ワクチン」は、コーリーワクチンのような考え方で結核菌から開発されたものです。しかし、このワクチンもがんへの治療効果を示す十分な科学的根拠はありません。
毒性を弱めた結核菌(BCG)を使う免疫療法は、特定の免疫細胞に働くわけではありませんが、膀胱がんに対して膀胱内注入する方法だけは治療効果が認められ、標準治療の一つになっています。
【サイト内 特設ページ】

こんにちは。17年間の活動実績を持つ、
「プロのがん治療専門アドバイザー」本村ユウジです。
がんを治すために必要なことは、たった1つです。
詳しくはこちらのページでお伝えさせてください。
→がんを治すための「たった1つの条件」とは?
免疫チェックポイント阻害薬の登場と保険適応
ごく一部のがんでしか効果が認められてこなかった免疫療法ですが、2014年以降、状況が変わりました。オプジーボなどの「免疫チェックポイント阻害薬」の登場です。
それまでの免疫療法は、免疫の「アクセル」を踏む(がんを攻撃する免疫を強化する)ことを目指していたのに対し、免疫チェックポイント阻害薬は、がん細胞が免疫細胞にかけている「ブレーキ」を外す(免疫システムが暴走するのを防ぐ機能を阻害する)ことを目指しました。
免疫チェックポイント阻害薬は、これまで治療が難しかったがん患者さんに効果があるなど十分な治療効果が確認され、次々と保険適応の標準治療となりました。免疫療法は、手術、放射線、抗がん剤の3大療法に続く「第4の治療」となったといえます。
2025年時点での保険適応免疫療法
2025年現在、保険適応となっている主な免疫療法には以下のものがあります。
| 治療法 | 主な適応がん | 保険適応状況 |
| 免疫チェックポイント阻害薬(オプジーボ、キイトルーダなど) | 悪性黒色腫、非小細胞肺がん、腎細胞がん、胃がん、食道がんなど多数 | 保険適応 |
| CAR-T療法 | 再発・難治性の白血病、リンパ腫 | 保険適応 |
| 光免疫療法 | 切除不能な局所進行または局所再発の頭頸部がん | 保険適応 |
| インターフェロン、インターロイキン2 | 腎臓がんなど | 保険適応 |
| BCG膀胱内注入療法 | 膀胱がん | 保険適応 |
その後、がんへの攻撃力を高めた免疫細胞を使う「CAR-T療法」や、がん細胞をピンポイントで攻撃する「光免疫療法」も承認され、免疫療法の選択肢が広がっています。
保険適応の免疫療法と自費の免疫療法の違い
信頼できる治療法が確立する一方で、いまだに免疫療法は玉石混交の状態であることに変わりはありません。保険適応の免疫療法と自費の免疫療法には大きな違いがあります。
効果の証明における違い
保険適応の免疫療法は、厳格な臨床試験を経て治療効果と安全性が科学的に証明されたものです。一方、自費の免疫療法の多くは、治療効果や安全性が科学的に証明されていません。
費用負担の違い
保険適応の免疫療法は、健康保険が適用されるため、患者さんの自己負担は1割から3割程度で済みます。高額療養費制度も利用できます。
自費の免疫療法は、全額を患者さんが負担する必要があります。治療費は数十万円から数百万円に及ぶこともあり、経済的負担が大きくなります。
実施施設の違い
保険適応の免疫療法は、一定の基準を満たした医療機関で実施されます。一方、自費の免疫療法は、主に一部の民間クリニックや病院で自由診療として実施されています。
【サイト内 特設ページ】

こんにちは。17年間の活動実績を持つ、
「プロのがん治療専門アドバイザー」本村ユウジです。
がんを治すために必要なことは、たった1つです。
詳しくはこちらのページでお伝えさせてください。
→がんを治すための「たった1つの条件」とは?
国立がん研究センターによる免疫療法選択の注意点
国立がん研究センターの「がん情報サービス」は、免疫療法を選択する前の注意点として以下を挙げています。
効果が証明された免疫療法と証明されていない免疫療法の区別
現在の免疫療法には、治療効果や安全性が科学的に証明された「効果が証明された免疫療法」と、治療効果や安全性が科学的に証明されていない「効果が証明されていない免疫療法」があります。近年研究開発が進められていますが、「効果が証明された免疫療法」はまだ一部に限られています。
自由診療として行われる免疫療法の注意点
「効果が証明されていない免疫療法」のうち、治療効果や安全性が証明されておらず、保険診療で受けることができない方法は、一部の民間クリニックや病院において「自由診療として行われる免疫療法」として実施されることがあります。
この場合の治療は保険診療で受けることができず、患者さんが全額自費で支払う必要があります。保険診療で受けられないがんに対する治療効果や、薬の量を減らした場合の治療効果は明らかではありません。
「自由診療として行われる免疫療法」を考える場合には、治療効果、安全性、費用について慎重な確認が必要ですので、必ず担当医に話しましょう。また、公的制度に基づく臨床試験、治験などの「研究段階の医療として行われる免疫療法」を熟知した医師にセカンドオピニオンを聞くことを勧めます。
研究段階の医療としての免疫療法
「効果が証明されていない免疫療法」のもう一つが、「研究段階の医療としての免疫療法」です。治療効果や安全性を確かめるために実施する臨床試験や治験などが該当します。
研究段階の医療は、研究内容を審査するための体制や緊急の対応ができる体制が整った医療機関で受けることが大切です。これらは将来、保険適応になる可能性がある治療法ですが、現時点では効果が確立されていません。
治療効果の証明について医師に確認する
免疫療法を提供する医師には、治療の効果が証明されているのかどうか聞きましょう。特に「自由診療として行われる免疫療法」で、治療の効果が期待できるかどうかがわからない場合には、その治療を受けないという選択をすることも大切です。
副作用への理解と対策
効果が証明された方法でも、免疫療法には副作用があります。全身に様々な副作用が起こる可能性があり、いつ、どのように起こるか予測がつかないため注意が必要です。免疫療法を受ける前には、治療を提供する医師に副作用や対策についてよく聞いておきましょう。
自費の免疫療法を選択する際のリスク
免疫療法が画期的な治療法であることに間違いはありません。しかし、保険適応になっていない免疫療法には以下のようなリスクがあります。
効果が得られない可能性
科学的な根拠が不十分な自費の免疫療法では、期待した効果が得られない可能性があります。効果がないだけでなく、その間に病状が進行してしまう恐れもあります。
経済的負担
自費の免疫療法は全額自己負担となるため、数百万円単位の費用がかかることもあります。効果が得られなかった場合、経済的な損失だけが残ることになります。
適切な治療機会の喪失
効果が証明されていない自費の免疫療法に時間を費やすことで、保険適応の標準治療を受ける適切なタイミングを逃してしまう可能性があります。これは患者さんの予後に影響を与える可能性があります。
予期しない副作用
十分な臨床試験を経ていない治療法では、予期しない副作用が起きることもあります。副作用への対応体制が十分でない施設で治療を受けた場合、適切な対処ができない恐れもあります。
免疫療法を選択する際の確認ポイント
免疫療法を選択する際には、以下のポイントを確認することが重要です。
保険適応かどうかの確認
まず、その免疫療法が保険適応になっているかどうかを確認しましょう。保険適応の治療は、効果と安全性が証明されている証です。
科学的根拠の確認
臨床試験のデータや論文など、科学的根拠があるかどうかを確認しましょう。医師に具体的なデータの提示を求めることも大切です。
実施施設の体制確認
緊急時の対応体制が整っているか、専門医が常駐しているかなど、実施施設の体制を確認しましょう。
費用の明確化
治療にかかる総額、支払い方法、返金制度の有無などを事前に明確にしておきましょう。
担当医への相談
免疫療法を検討する際は、必ず現在の担当医に相談しましょう。セカンドオピニオンを求めることも有効です。
2025年における免疫療法の展望
2025年現在、免疫療法の研究はさらに進んでおり、新たな免疫チェックポイント阻害薬や併用療法の開発が進められています。また、バイオマーカーによる効果予測の精度も向上しており、より適切な患者さん選択が可能になってきています。
一方で、自費診療として提供される免疫療法については、依然として効果が不確かなものが多く存在します。がん情報サービスが「受けない決断も必要」としている医療を、様々な施設が宣伝して実施しているのは問題がありますが、それが現状だと理解して選択をする必要があります。
まとめ:保険適応と自費の免疫療法の違いを理解した選択を
免疫療法を受けるにあたっては、保険適応の免疫療法と自費の免疫療法の違いを十分に理解することが大切です。保険適応の免疫療法は効果と安全性が科学的に証明されており、経済的負担も軽減されます。
自費の免疫療法を検討する場合は、効果の根拠、安全性、費用について慎重に確認しましょう。果が期待できるかわからない治療を受けないという選択も、時には必要な判断となります。
参考文献・出典情報
国立がん研究センター がん情報サービス「免疫療法 もっと詳しく知りたい方へ」
American Cancer Society "Immunotherapy for Cancer"
National Cancer Institute "Immunotherapy to Treat Cancer"
Nature Reviews Clinical Oncology "Cancer immunotherapy in 2024"
Journal of Clinical Oncology "Advances in Cancer Immunotherapy 2024"
New England Journal of Medicine "Immune Checkpoint Inhibitors - Clinical Update"














