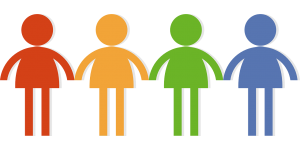
膣がんとは|発生部位と特徴
膣は子宮頸部と外陰部をつなぐ筒状の組織で、長さは約7~10センチメートルです。膣がんは、この膣の内側を覆っている粘膜上皮から発生する悪性腫瘍です。
膣がんには、最初から膣に発生する「原発性膣がん」と、他の臓器のがんが膣に転移した「転移性膣がん」の2種類があります。原発性膣がんは女性性器がん全体の1~3%程度と非常にまれな疾患です。実際の臨床現場では、子宮がん、絨毛がん、外陰がん、膀胱がん、直腸がんなどからの転移性膣がんのほうが多く見られ、原発性と転移性の比率はおよそ3対7となっています。
膣がんが発生しやすい部位には特徴があります。膣壁では後壁(直腸側)と前壁(膀胱側)に多く発生します。また、膣を入口から3分の1ずつに区切った場合、入口側の下部3分の1と、奥側(子宮側)の上部3分の1に発生することが多く、中間部に発生するケースは比較的少ないことが知られています。
がんの形状としては、球状または長い楕円形で、潰瘍を伴うかたい腫瘤(しこり)として認められます。膣壁は筋層が薄く、筋組織が少ないという解剖学的特徴があります。そのため、早期のがんであっても膣壁を破って容易に周辺臓器に浸潤しやすい傾向があります。
膣の入口側に発生したがんは外陰部へと広がり、奥側に発生したがんは子宮へと進展します。さらに、骨盤内のリンパ節を経由して肺などの遠隔臓器に転移しやすいことも膣がんの重要な特徴です。また、血行性転移として血管を経て肺に転移することもあります。発生頻度は低いものの、進行が比較的速く、治療が困難になりやすいがんといえます。
膣がんの原因と発生年齢
膣がんの明確な原因は現在のところ完全には解明されていません。しかし、いくつかのリスク因子が指摘されています。
原発性膣がんの発症年齢は45~65歳に多く、閉経後の女性に好発する傾向があります。ただし、まれに「明細胞腺がん」という特殊なタイプの膣がんが20~30歳代の若年女性に発生することもあります。この明細胞腺がんは、母親が妊娠中にジエチルスチルベストロール(DES)という合成エストロゲン製剤を服用していた場合に発生リスクが高まることが知られています。
また、ヒトパピローマウイルス(HPV)感染、特に高リスク型HPVの持続感染が膣がん発生に関与している可能性が指摘されています。子宮頸がんと同様に、HPVが膣の粘膜細胞に感染し、長期間にわたって持続感染することで、細胞の遺伝子に変異が生じ、がん化につながると考えられています。
その他のリスク因子としては、喫煙、免疫抑制状態(臓器移植後やHIV感染など)、過去の骨盤部への放射線治療歴などが挙げられます。
「自分の判断は正しいのか?」と不安な方へ

がん治療。
何を信じれば?
不安と恐怖で苦しい。
がん治療を左右するのは
治療法より“たった1つの条件”です。
まず、それを知ってください。
がん専門アドバイザー 本村ユウジ
膣がんの症状|初期症状と進行時の症状
膣がんの早期発見が難しい理由の一つは、初期段階ではほとんど自覚症状がないことです。症状が現れて受診した時点では、すでにがんがある程度進行しているケースが少なくありません。
膣がんの主な症状
膣がん発見の重要な手がかりとなる症状は不正性器出血です。特に性交時に出血が起こりやすく、これが最も多い初発症状です。はっきりとした出血として認識される場合と、おりものに血液が混じる程度の少量出血の場合があります。閉経後の女性で性器出血があった場合は、必ず婦人科を受診することが重要です。
また、悪臭を伴う水様性のおりもの、あるいは膿性のおりものが増加することもあります。おりものの性状の変化や量の増加に気づいた場合も、婦人科受診が推奨されます。
がんがやや大きくなると、患者さん自身が膣内に指を入れた際にしこりを触れることがあります。また、骨盤内への浸潤により、腰痛や下腹部痛が出現することもあります。
進行した膣がんの症状
さらにがんが進行して膀胱や尿道、直腸などの周辺臓器に浸潤すると、より重篤な症状が現れます。膀胱浸潤により排尿痛、頻尿、血尿などの排尿障害が生じます。尿道への浸潤が進むと、排尿困難や尿失禁が起こることもあります。
直腸への浸潤では、便秘、血便、排便時の痛み、便失禁などの症状が見られます。膀胱と膣の間、あるいは直腸と膣の間に穴が開いて交通してしまう「膀胱膣瘻」や「直腸膣瘻」が形成されると、膣から尿や便が漏れ出るという深刻な状態になります。
リンパ節転移が進行すると、下肢のリンパ浮腫により脚のむくみや痛みが生じることがあります。肺転移が起これば、咳、血痰、呼吸困難などの呼吸器症状が現れます。
膣がんの検査と診断方法
膣がんの診断には、問診・視診から始まり、細胞診、画像検査、生検まで、段階的な検査が行われます。
問診・視診・内診
まず、不正出血やおりものの異常などの症状について詳しく問診が行われます。その後、内診台で視診と触診を行い、膣壁の状態を観察します。視診では、膣鏡(クスコ)を用いて膣内を直接観察し、腫瘤や潰瘍の有無、出血の状態などを確認します。触診では、腫瘤の大きさ、硬さ、周囲組織への浸潤の程度などを評価します。
細胞診検査
細胞診は、膣がんのスクリーニングと診断に重要な役割を果たす検査です。綿棒やブラシなどで膣壁の細胞を軽くこすり取り、スライドガラスに塗抹して顕微鏡で観察します。この検査により、がん細胞や異型細胞の有無を調べることができます。
膣がんは、子宮がん検診の細胞診で偶然発見されることもあります。細胞診でがん細胞が検出され、子宮頸部や子宮体部にがんの所見がない場合には、膣がんが疑われます。
コルポスコープ検査
コルポスコープ診は、膣拡大鏡と呼ばれる特殊な拡大鏡を用いて、膣の内部を10~40倍に拡大して詳細に観察する検査です。肉眼では見えにくい微小な病変も発見できるため、細胞診とともに膣がんの早期発見に重要な役割を果たしています。
検査では、膣壁に酢酸溶液やヨード液を塗布し、正常組織とがん組織の色調の違いを観察します。がん組織は正常組織とは異なる色調変化を示すため、病変部位を特定しやすくなります。
組織生検
細胞診やコルポスコープ検査で膣がんが疑われる場合には、確定診断のために組織生検が必須です。病変部の組織を一部切り取って採取し、病理組織学的検査を行います。生検により、がんの組織型(扁平上皮がん、腺がんなど)や分化度を診断することができます。
画像検査
がんの進行度や周辺臓器への浸潤、リンパ節転移、遠隔転移の有無を評価するために、各種画像検査が行われます。
CT検査(コンピュータ断層撮影)では、骨盤内の腫瘍の大きさや広がり、リンパ節腫大、肺などへの遠隔転移の有無を評価します。MRI検査(磁気共鳴画像検査)は、軟部組織のコントラストに優れているため、がんの膣壁内での深達度や周囲臓器への浸潤範囲をより詳細に評価できます。
PET-CT検査は、がん細胞の代謝活性を画像化する検査で、遠隔転移やリンパ節転移の検出に有用です。ただし、すべての症例で必須というわけではなく、病期診断や治療効果判定、再発診断などの目的で選択的に実施されます。
膣がんのステージ分類
膣がんの病期(ステージ)は、国際産婦人科連合(FIGO)の分類が用いられます。病期は0期からⅣ期まであり、Ⅳ期はさらにⅣA期とⅣB期に分類されます。
| 病期 | 説明 |
|---|---|
| 0期 | 上皮内がん。がんが上皮内にとどまり、基底膜を超えて浸潤していない状態 |
| Ⅰ期 | がんが膣壁に限局している状態 |
| Ⅱ期 | がんが膣壁を超えて周囲の結合組織に広がっているが、骨盤壁には達していない状態 |
| Ⅲ期 | がんが骨盤壁にまで達している状態、または所属リンパ節に転移がある状態 |
| ⅣA期 | がんが膀胱や直腸の粘膜に浸潤している状態、または小骨盤腔を超えて広がっている状態 |
| ⅣB期 | 遠隔転移(肺、肝臓、骨など)がある状態 |
病期分類は、治療方針の決定や予後の予測に重要な指標となります。一般的に、早期の病期ほど治療成績が良好で、進行した病期では治療が困難になります。
膣がんの治療法
膣がんの治療法には、手術療法、放射線療法、化学療法があり、病期、がんの発生部位、患者さんの年齢や全身状態などを総合的に考慮して治療方針が決定されます。
手術療法
手術療法が選択されるのは、主に以下のような条件を満たす場合です。
・膣の奥側(上部3分の1)にがんが限局している
・がんの浸潤が比較的浅い(Ⅰ期またはⅡ期の一部)
・患者さんの年齢が比較的若く、全身状態が良好
手術の術式としては、「広汎子宮全摘出術」が標準的です。これは、膣の上部と子宮、子宮頸部、子宮周囲の組織(子宮傍組織)、膣の一部を広範囲に切除するとともに、骨盤内のリンパ節を郭清(リンパ節を摘出して転移の有無を調べる)する手術です。
がんが膣の下部に発生している場合や、周囲組織への浸潤が広範囲に及んでいる場合には、外陰部や膀胱、直腸の一部も含めて切除する「骨盤除臓術」が必要になることもあります。この手術では、膀胱や直腸を切除するため、尿路や消化管の再建が必要となり、人工膀胱や人工肛門の造設が行われます。
ただし、膣がんに対する手術療法は、解剖学的な制約や術後の機能障害が大きいことから、選択されるケースは限られています。
放射線療法
放射線療法は、膣がん治療の中心的な役割を果たしています。手術が適応とならない症例や、手術を希望されない患者さんに対して実施されます。また、Ⅰ期の早期がんから局所進行がんまで、幅広い病期で有効性が認められています。
膣がんに対する放射線療法では、「腔内照射(小線源治療)」と「外部照射」を組み合わせて行うのが一般的です。
腔内照射は、膣内に放射線源を挿入して、がん病巣に直接的に高線量の放射線を照射する方法です。線源と腫瘍の距離が近いため、高い治療効果が得られる一方で、周囲の正常組織への影響を最小限に抑えることができるという大きなメリットがあります。通常、週1~2回程度の照射を複数回行います。
外部照射は、体外から放射線治療装置を用いて骨盤部に照射する方法です。骨盤内のリンパ節領域も含めて広範囲に照射することで、リンパ節転移に対する治療効果も期待できます。一般的には、1日1回、週5回、計5~6週間程度の治療期間が必要です。
早期の膣がんで腫瘍が小さい場合には、腔内照射のみで治療が完結することもあります。一方、進行がんでは外部照射と腔内照射の併用が標準的な治療となります。
放射線療法の副作用としては、照射部位の皮膚炎、膣粘膜の炎症、排尿障害、下痢、直腸出血などがあります。また、長期的な影響として、膣の狭窄や癒着、卵巣機能の低下による更年期症状などが生じることがあります。
化学療法
膣がんに対する化学療法は、主に放射線療法との併用(化学放射線療法)として行われます。シスプラチンなどの抗がん剤を放射線療法と同時に投与することで、放射線の効果を増強し、治療成績の向上が期待されます。
また、遠隔転移がある場合や再発した場合には、全身化学療法が選択されることがあります。使用される抗がん剤としては、シスプラチン、カルボプラチン、パクリタキセル、5-FUなどがあります。
ただし、膣がんに対する化学療法の有効性については、症例数が少ないこともあり、まだ十分なエビデンスが確立されていないのが現状です。今後の臨床試験による検証が期待されています。
膣がんの予後と5年生存率
膣がんの予後は、病期によって大きく異なります。残念ながら、他の婦人科がんと比較すると、全体的に予後は良好とはいえません。
病期別5年生存率
膣がんの病期別5年生存率は、おおよそ以下の通りです。
| 病期 | 5年生存率 |
|---|---|
| 0期 | 約80~90% |
| Ⅰ期 | 約65~75% |
| Ⅱ期 | 約45~55% |
| Ⅲ期 | 約30~40% |
| Ⅳ期 | 約15~20% |
0期やⅠ期の早期がんでは比較的良好な生存率が得られていますが、Ⅱ期以降になると生存率は急激に低下します。これは、膣壁の筋層が薄いため、がんが早期から周囲組織に浸潤しやすいという解剖学的特徴によるものです。
また、腫瘍の大きさ、組織型、患者さんの年齢や全身状態なども予後に影響する因子です。一般的に、腫瘍が小さいほど、分化度の高い組織型ほど、若年者ほど予後が良好とされています。
再発について
膣がんは治療後3年以内に再発することが多いという特徴があります。再発部位としては、局所再発(膣やその周囲)が最も多く、次いでリンパ節再発、遠隔転移(肺、肝臓、骨など)の順となっています。
再発の早期発見のためには、治療終了後の定期的なフォローアップが重要です。治療後最初の2~3年間は3か月ごと、その後は6か月ごとに、内診、細胞診、画像検査などを受けることが推奨されます。
再発が発見された場合の治療は、再発部位や範囲、初回治療の内容などによって異なります。局所再発で切除可能な場合には手術が検討されます。初回治療で放射線療法を受けていない場合には、放射線療法が選択肢となります。遠隔転移や広範囲の再発に対しては、化学療法や緩和療法が中心となります。
膣がん治療後の生活における注意点
性生活について
手術で膣の上部を摘出した場合、術後の経過が順調であれば、退院後1~2か月程度で性生活を再開することが可能です。ただし、再開時期については個人差がありますので、必ず担当医に確認してください。
膣を全部摘出した場合や、広範囲の放射線照射を受けた場合には、膣の狭窄や短縮が生じるため、通常の性生活が困難になることがあります。このような場合でも、膣拡張器(ダイレーター)を使用した膣の拡張訓練や、膣再建術などの方法により、性機能の回復や改善が可能な場合もあります。パートナーとのコミュニケーションを大切にし、婦人科医や専門のカウンセラーに相談することをお勧めします。
排尿・排便機能について
放射線療法や手術により、膀胱や直腸が影響を受けた場合、排尿障害や排便障害が残ることがあります。頻尿、尿失禁、便秘、下痢などの症状が続く場合には、泌尿器科や消化器科での治療が必要になることもあります。
骨盤除臓術で人工膀胱や人工肛門を造設した場合には、ストーマ(人工的に作られた排泄口)のケア方法を習得する必要があります。専門の看護師(皮膚・排泄ケア認定看護師)から指導を受け、適切な管理方法を身につけることが大切です。
リンパ浮腫への対応
リンパ節郭清を受けた場合、リンパの流れが障害されることで下肢にリンパ浮腫が生じることがあります。予防のためには、下肢の清潔を保つ、適度な運動を行う、長時間の立位や座位を避ける、締め付けの強い衣服を避けるなどの注意が必要です。
むくみが生じた場合には、リンパドレナージ(マッサージ)、圧迫療法、運動療法などを組み合わせた複合的理学療法が有効です。リンパ浮腫外来や専門クリニックでの治療を検討してください。
精神的サポート
がん治療は、身体的な負担だけでなく、精神的にも大きな影響を与えます。不安、抑うつ、恐怖などの感情に悩まされることも少なくありません。家族や友人、医療スタッフに気持ちを話すことで、心の負担が軽減されることがあります。
多くの医療機関には、がん相談支援センターが設置されており、療養上の悩みや心配事について相談することができます。



