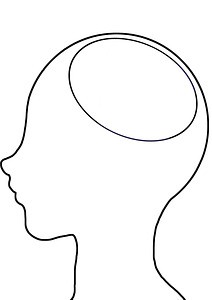
脳腫瘍の特徴と基本的な分類
脳に発生する腫瘍を「脳腫瘍」と呼びます。一般的に「脳がん」という言葉は使用されません。脳腫瘍は大きく分けて2つのタイプに分類されます。
まず「原発性脳腫瘍」は、脳の組織そのものから発生する腫瘍です。現在では30種類以上の原発性脳腫瘍が確認されており、これらを総称して脳腫瘍と呼んでいます。発生頻度が高いのは、脳実質から発生する神経膠腫(グリオーマ)や胚細胞腫などです。
もう一つは「転移性脳腫瘍」で、肺や肝臓、乳がんなど他の臓器に発生したがんが脳に転移したものです。転移することを「脳転移」と呼び、がん患者さんの約10%が転移性脳腫瘍を発症するといわれています。
脳腫瘍の悪性度は、WHO(世界保健機関)が定めた4段階のグレードによって分類されます。グレード1は良性腫瘍、グレード2は軽度悪性腫瘍、グレード3は中等度悪性腫瘍、グレード4は高度悪性腫瘍となります。
原発性脳腫瘍の主な種類
原発性脳腫瘍の中で最も多いのは髄膜腫で、全体の約35%を占めています。髄膜腫は脳を包んでいる髄膜に発生する腫瘍で、ほとんどが良性です。女性に多く見られ、40歳から50歳の成人に好発します。
神経膠腫(グリオーマ)は全体の約16%を占め、脳実質から発生する悪性腫瘍です。最も治療が困難とされる膠芽腫(グリオブラストーマ)は神経膠腫の一種で、45歳から65歳の成人男性に多く発症します。
下垂体腺腫も約16%を占め、脳の下方にある下垂体に発生する腫瘍です。ホルモン分泌に影響を与えることがあります。神経鞘腫は約9%を占め、脳神経を包む細胞から発生する良性腫瘍で、聴神経腫瘍が代表的です。
脳腫瘍の特徴的な症状
脳腫瘍の症状は、腫瘍が脳を圧迫することによって現れる特徴があります。症状は大きく3つのカテゴリーに分類されます。
頭蓋内圧亢進症状
脳腫瘍が成長することで頭蓋骨内の圧力が高まり、特徴的な症状が現れます。最も代表的なのが頭痛で、初期では2割、進行すると8割の患者さんに見られます。脳腫瘍による頭痛の特徴は、睡眠中や横になっている間に脳圧が高まるため、起床時に最も強く感じられることです。
起床時の頭痛は「朝が一番強く日中は軽くなっていく」「痛みの強さが日に日に強くなっていく」という特徴があり、副鼻腔炎や片頭痛による起床時頭痛とは区別できます。
嘔吐も重要な症状で、脳圧が高まると突然噴射するように勢いよく嘔吐することがあります。特に起床後の突然の嘔吐は脳腫瘍を疑う重要なサインです。
視力障害も頭蓋内圧亢進の症状として現れます。物が二重に見える、物がかすむ、視野で見えないところがある(視野欠損)といった症状が見られます。
局所症状
腫瘍が発生した脳の部位の機能が直接障害されることで現れる症状です。運動機能を司る領域が障害されると、片側の手足や顔のしびれ、麻痺、運動障害が出現します。歩きにくさやバランスの崩れなどの小さな変化も見逃してはいけません。
言語機能が障害されると、ろれつが回らない、失語症(話す、聞く、読む、書くができなくなる)などの症状が現れます。認知機能に関わる部位が障害されると、物忘れ、思考の混乱、判断力の低下などが見られることがあります。
けいれん発作
腫瘍が周囲の神経細胞を刺激することで起こります。大人になってから初めてけいれん発作が生じた場合は、脳腫瘍の可能性を疑う必要があります。体が硬直して意識を失う「大発作」、意識はあるが体の片側が意思と関係なく動く「小発作」などがあります。
| 症状の分類 | 具体的な症状 | 特徴 |
|---|---|---|
| 頭蓋内圧亢進症状 | 起床時頭痛、嘔吐、視力障害 | 朝に強く、日中軽くなる |
| 局所症状 | 片麻痺、言語障害、認知機能低下 | 腫瘍の部位により異なる |
| けいれん発作 | 全身けいれん、部分発作 | 成人初発は要注意 |
「自分の判断は正しいのか?」と不安な方へ

がん治療。
何を信じれば?
不安と恐怖で苦しい。
がん治療を左右するのは
治療法より“たった1つの条件”です。
まず、それを知ってください。
がん専門アドバイザー 本村ユウジ
脳腫瘍の検査方法の詳細
脳腫瘍の診断には、複数の画像検査を組み合わせて正確な診断を行います。現在では検査技術の進歩により、より精密な診断が可能になっています。
CT検査の特徴と活用法
CT検査は、X線を使用して頭蓋骨内部の断層画像を撮影する検査です。多くの医療機関でMRI検査よりも迅速に実施できるため、緊急性がある場合に優先して行われます。造影剤を使用することで、腫瘍の広がりや悪性度を術前に推定することができます。
CT検査では、脳浮腫や出血の有無、腫瘍の位置関係を把握できます。特に救急外来での初期診断において重要な役割を果たしています。
MRI検査の優位性
MRI検査は磁場と電磁波を使用して、より詳細な画像を得ることができます。脳腫瘍の診断においては最も重要な検査とされており、水平断面、前後方向(矢状断)、左右方向(冠状断)の三次元的な画像評価が可能です。
造影剤を使用したMRI検査では、腫瘍と正常脳組織の境界を明確に描出できます。また、特殊なMRI検査として、脳の機能を評価するfMRI(functional MRI)があり、言語野や運動野の位置を術前に特定することができます。
最新の3テスラMRIでは、より高画質で安定した画像が得られ、言語や運動の課題をしながら撮影することで、重要な脳機能の局在を同定できます。
PET検査の革新的な活用
PET検査は、放射性同位元素を用いて腫瘍の代謝活性を評価する検査です。一般的に使用される18F-FDG(フルオロデオキシグルコース)は、悪性腫瘍のブドウ糖代謝の亢進を利用して診断を行います。
しかし、正常脳組織でもFDGの取り込みが多いため、悪性度の低い神経膠腫では診断が困難な場合があります。そこで、11C-メチオニン(MET)を用いたPET検査が注目されています。MET-PETは脳腫瘍、特に悪性神経膠腫の評価に優れており、治療効果の判定や再発の鑑別にも有用です。
2025年現在、アミノ酸の取り込みを調べるPETトレーサー「フルシクロビン(18F)、アキュミン」が使用可能となり、神経膠腫の浸潤領域をより正確に可視化できるようになりました。
| 検査方法 | 所要時間 | 特徴 | 適用場面 |
|---|---|---|---|
| CT検査 | 5-10分 | 迅速、出血診断に優れる | 救急診断、初期評価 |
| MRI検査 | 30-60分 | 高分解能、多方向画像 | 詳細診断、手術計画 |
| PET検査 | 2-3時間 | 代謝活性評価 | 悪性度判定、治療効果判定 |
特殊検査と最新技術
MRスペクトロスコピーは、脳組織の化学的な情報を非侵襲的に得られる検査です。腫瘍の代謝産物を分析することで、良性・悪性の鑑別に役立ちます。
拡散テンソル画像(DTI)は、脳の神経線維の走行を可視化する技術で、手術計画において重要な神経線維の保護に活用されています。
脳血管造影検査は、以前は頻繁に行われていましたが、脳梗塞のリスクがあるため、現在では必要最小限に留められています。代わりに、MRAやCTAといった比較的侵襲性の低い血管画像検査が主流となっています。
2025年最新の治療法
脳腫瘍の治療は近年大きく進歩しており、手術、放射線治療、薬物療法に加えて革新的な治療法が導入されています。
手術治療の進歩
脳腫瘍治療において手術は最も重要な治療法です。現在では、脳機能を最大限に保護しながら腫瘍を摘出するための高度な技術が確立されています。
ナビゲーションシステムを使用した手術では、術中にリアルタイムで腫瘍の位置と重要な脳領域との関係を把握できます。術中MRIを併用することで、手術中に摘出状況を確認し、より完全な腫瘍摘出が可能になりました。
覚醒下手術は、言語機能を担う部位の腫瘍に対して実施される手術で、患者さんと対話しながら手術を行うことで、言語機能を保護します。電気生理学的モニタリングにより、運動機能や感覚機能をリアルタイムで監視しながら安全な手術が実現されています。
蛍光診断技術として、レザフィリン(5-ALA)を用いた光線力学的診断が実用化されています。腫瘍細胞に選択的に蓄積する物質を投与し、特殊な光を照射することで腫瘍を光らせ、正常組織との境界を明確にできます。
放射線治療の革新
放射線治療技術も大幅に進歩しています。強度変調回転放射線治療(VMAT)が導入され、正常組織への影響を最小限に抑えながら、腫瘍に対して効果的な照射が可能になりました。
定位放射線治療として、ガンマナイフやサイバーナイフが広く普及しています。これらの技術では、ミリ単位の精度で病巣に集中的に放射線を照射でき、特に3cm未満の小さな脳腫瘍や良性腫瘍に対して優れた治療効果を示しています。
陽子線治療も一部の施設で実施されており、周囲の正常組織への影響をさらに軽減できる可能性があります。
革新的な薬物療法
悪性脳腫瘍に対する薬物療法では、テモゾロミド(TMZ)とベバシズマブの併用療法が標準治療として確立されています。これらの薬剤は血液脳関門を通過できる特殊な設計がなされており、脳腫瘍に対して効果を発揮します。
分子標的薬の開発も進んでおり、腫瘍の遺伝子変異に応じた個別化治療が実現されつつあります。IDH変異陽性の神経膠腫に対しては、IDH阻害薬の開発が進んでいます。
画期的な電場治療
2020年に日本で承認された交流電場腫瘍治療システム(オプチューン)は、脳腫瘍治療における画期的な治療法です。患者さんの頭部に電極を貼り付け、腫瘍周囲に特殊な電場を発生させることで、腫瘍細胞の分裂を阻害します。
この治療法の最大の利点は、正常な脳組織には影響を与えず、副作用がほとんどないことです。膠芽腫の患者さんに対する臨床試験では、従来の標準治療に加えて実施することで、治療成績の向上が報告されています。
日本発の新規治療薬
2024年には、日本で開発された新規放射性治療薬64Cu-ATSMの安全性と有効性が確認されました。再発・難治性悪性脳腫瘍に対する治療として、第III相試験(STEP-64試験)が開始されており、日本発の脳腫瘍治療薬として期待されています。
この治療では、64Cu-ATSMを投与後にPET検査を行い、脳腫瘍病変への薬剤の集積を確認できます。初期の臨床試験では、再発膠芽腫患者の1年生存率が55.6%という良好な結果が得られています。
免疫療法の可能性
自家腫瘍ワクチン(AFTV)療法の臨床試験も実施されており、患者さん自身の腫瘍組織を用いたワクチン療法の開発が進んでいます。免疫チェックポイント阻害薬の脳腫瘍への応用も研究されており、将来的な治療選択肢として期待されています。
| 治療分野 | 治療法 | 適応 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 手術 | 覚醒下手術、術中MRI | 全ての脳腫瘍 | 機能温存、完全摘出 |
| 放射線 | VMAT、定位放射線治療 | 悪性・良性腫瘍 | 高精度、低侵襲 |
| 薬物療法 | TMZ+ベバシズマブ | 悪性神経膠腫 | 血液脳関門通過 |
| 電場治療 | オプチューン | 膠芽腫 | 副作用が軽微 |
| 放射性治療薬 | 64Cu-ATSM | 再発・難治性 | 日本発の治療薬 |
早期発見の重要性と受診のタイミング
脳腫瘍は早期発見により治療成績が大幅に改善されます。特に良性腫瘍の多くは、完全摘出により完治が期待できます。症状を見逃さないためのポイントを理解することが重要です。
受診すべき症状のチェックリスト
以下の症状が複数見られる場合、または症状が持続・悪化する場合は、速やかに医療機関を受診することをお勧めします。
起床時に最も強い頭痛が連日続く、原因不明の嘔吐(特に朝に多い)、視力の変化や視野の異常、片側の手足や顔のしびれ・麻痺、ろれつが回らない、記憶力や判断力の低下、成人になってから初めてのけいれん発作などです。
これらの症状は脳卒中でも見られることがありますが、脳卒中では症状が急激に現れるのに対し、脳腫瘍では徐々に悪化していくことが特徴です。
受診科と検査の流れ
脳腫瘍の専門科は脳神経外科ですが、症状によっては神経内科、眼科、耳鼻咽喉科での相談も可能です。初診では詳細な問診と神経学的検査が行われ、必要に応じてCTやMRIなどの画像検査が実施されます。
最終的な診断は、手術で採取した組織を用いた病理検査により確定されます。現在では遺伝子解析も併用され、より精密な診断と個別化治療の選択が可能になっています。
生活における注意点と予防
脳腫瘍の多くは遺伝子変異が原因とされており、確実な予防法は現在のところ確立されていません。しかし、症状の早期発見と適切な検査により、治療可能な段階での診断が重要です。
日常生活では、持続する頭痛や神経症状を「いつものこと」と決めつけず、変化に注意を払うことが大切です。特に40歳以降では、定期的な脳ドックの受診も検討に値します。
脳腫瘍の治療を受けた後は、定期的な経過観察が必要です。再発の早期発見や、治療に伴う機能障害に対するリハビリテーションも重要な要素となります。
まとめ
脳腫瘍は多種多様な疾患群であり、適切な診断と治療により良好な予後が期待できる疾患も多くあります。2025年現在、画像診断技術の進歩、手術技術の向上、新規薬物療法の開発により、治療選択肢は拡大しています。
特に電場治療や日本発の新規治療薬などの登場により、これまで治療困難とされていた悪性脳腫瘍に対しても新たな希望が見えてきています。



