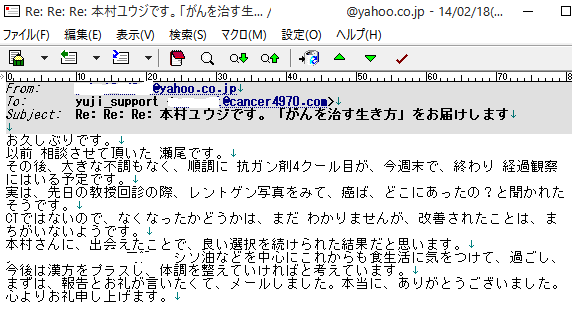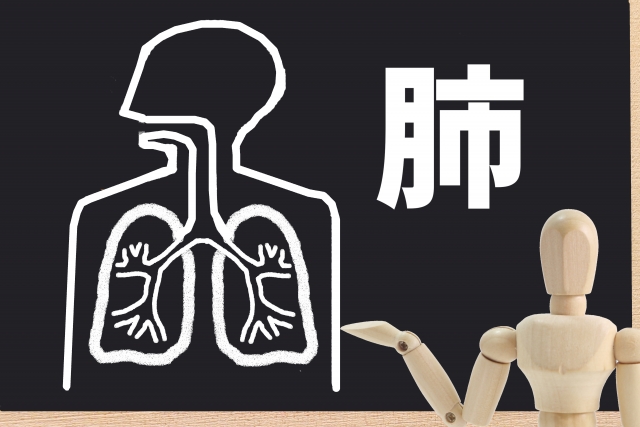
はじめに:進化する肺がん治療
肺がんは、日本において依然としてがんによる死亡原因の第1位であり、年間7万5000人以上の方が亡くなる、極めて深刻な疾患です。
この数字は、肺がんという病気の重さを物語っています。しかし、この厳しい現実の裏側で、肺がん治療の世界は進化しています。
近年の肺がん治療における最大の進歩は、「個別化医療」と「集学的治療」という二つの概念の深化と普及にあります。がん細胞の遺伝子レベルの特性を詳細に分析し、一人ひとりの患者さんに最も効果が期待できる薬剤を選択する「個別化医療」。
そして、外科医、腫瘍内科医、放射線治療医などの専門家がチームを組み、手術、放射線治療、薬物療法といった多様な治療法を最適に組み合わせる「集学的治療」 。これらが現在の標準治療の根幹をなしています。
この記事では、2025年現在の最新の知見に基づき、肺がん治療の最前線を専門家の視点から網羅的に解説します。
基礎知識から、がんの種類やステージ(病期)に応じた具体的な治療法、そして2024年から2025年にかけて登場した画期的な新薬や最新技術まで、患者さんとそのご家族がご自身の状況を理解し、希望を持って治療に臨むための一助となるよう、詳細かつ分かりやすくお伝えします。
第1部:肺がん治療を理解するための基礎知識
最適な治療法を理解するためには、まずご自身の肺がんがどのような種類で、どの程度進行しているのかを正確に把握することが不可欠です。
ここでは、治療方針を決定する上で最も重要な3つの要素、「組織型」「ステージ」「遺伝子・バイオマーカー」について解説します。
1-1. 肺がんとは? ― 種類と特徴
肺がんは、気管や気管支、肺の末端にある肺胞の細胞ががん化したものです。顕微鏡で見たときのがん細胞の顔つき(組織型)によって、大きく2つのタイプに分けられます。この分類は、がんの性質や進行速度、治療薬への反応性が全く異なるため、治療法を決定する上で最初の、そして最も重要な分岐点となります。
- 非小細胞肺がん(Non-Small Cell Lung Cancer: NSCLC)
肺がん全体の約85%を占める、最も一般的なタイプです。小細胞肺がんに比べて、比較的ゆっくりと増殖・進行する特徴があります。非小細胞肺がんは、さらにいくつかの組織型に分類されます。
- 腺がん(Adenocarcinoma): 非小細胞肺がんの中で最も多く、肺がん全体の半数以上を占めます。肺の奥深く、末梢の肺野部に発生することが多いのが特徴です。喫煙との関連が比較的低いとされ、タバコを吸わない人(非喫煙者)に発生する肺がんの多くがこのタイプです。咳などの症状が出にくく、健康診断の胸部X線写真などで偶然発見されることも少なくありません。後述する分子標的薬の治療対象となる特定の遺伝子異常が見つかることが多いのも、この腺がんの特徴です。
- 扁平上皮がん(Squamous Cell Carcinoma): 喫煙との関連が非常に強いがんで、主に肺の中心部、太い気管支(肺門部)に発生しやすいとされています。気管支を塞ぐように大きくなることが多いため、咳や血痰といった症状が現れやすいのが特徴です。
- 大細胞がん(Large Cell Carcinoma): 比較的稀なタイプで、細胞が大きく、腺がんや扁平上皮がんのような特徴を示さないものを指します。
- 小細胞肺がん(Small Cell Lung Cancer: SCLC)
肺がん全体の10~15%を占めるタイプです。その名の通り、がん細胞が小さいことが特徴で、増殖が非常に速く、診断された時点で既にリンパ節や脳、肝臓、骨などの他の臓器へ転移していることが多い、悪性度の高いがんです。ほぼ全てのケースで喫煙が原因とされており、ヘビースモーカーの男性に多く見られます。進行が速い一方で、抗がん剤(化学療法)や放射線治療が比較的効きやすいという性質も持っています。
1-2. 治療方針の鍵を握る「ステージ(病期)」
「ステージ(病期)」とは、がんがどの程度進行しているかを示す世界共通の指標です。ステージは、治療方針を決定し、今後の病状の見通し(予後)を予測するための最も重要な要素です。
ステージは、がんが肺の中にとどまっている早期のI期から、他の臓器に転移している進行期のIV期まで、大きく4段階に分けられ、さらに細かく分類されます。
このステージを決定するために用いられるのが、国際的なTNM分類です 。これは、以下の3つの要素を評価して、総合的にステージを判断するシステムです。
- T因子(Tumor): 原発巣(最初にがんができた場所)の大きさと、周囲の組織への広がり(浸潤)の程度を表します。T1(小さい)からT4(大きい、または重要な臓器へ浸潤)まで分類されます。
- N因子(Node): 周囲のリンパ節への転移の有無と、その広がり具合を表します。N0(転移なし)からN3(遠くのリンパ節まで転移)まで分類されます。
- M因子(Metastasis): 肺から離れた他の臓器(脳、骨、肝臓、副腎など)への遠隔転移の有無を表します。M0(遠隔転移なし)とM1(遠隔転移あり)に分類されます。
これらのTNMの組み合わせによって、最終的なステージが決定されます。
例えば、がんが小さく(T1)、リンパ節転移も遠隔転移もない(N0, M0)場合はステージIと診断されます。一方で、遠隔転移がある(M1)場合は、TやNの状態にかかわらず、全てステージIVと診断されます。
表1:肺がんのTNM分類とステージ対応の概略
| ステージ | T因子(腫瘍の大きさ・広がり) | N因子(リンパ節転移) | M因子(遠隔転移) | 概要 |
| ステージI | T1~T2a | N0 | M0 | がんは肺内にとどまり、リンパ節転移はない。 |
| ステージII | T2b~T3 | N0 | M0 | がんは肺内にとどまるが、やや大きい。 |
| T1~T2b | N1 | M0 | がんの大きさは比較的小さいが、肺門リンパ節に転移がある。 | |
| ステージIII | T3~T4 | N1 | M0 | がんが大きく、肺門リンパ節に転移がある。 |
| T1~T4 | N2~N3 | M0 | がんが縦隔リンパ節や、反対側のリンパ節まで広がっている。 | |
| ステージIV | すべてのT | すべてのN | M1 | がんが肺以外の臓器(脳、骨、肝臓など)に遠隔転移している。 |
これは簡略化した表であり、正確な分類はさらに細分化されます。
また、ステージには臨床病期と病理病期の2種類があることも重要です。臨床病期は、CTやPET検査など、治療を始める前の検査情報に基づいて決定されるステージです。治療方針はこの臨床病期を基に立てられます。
一方、病理病期は、手術で切除した肺やリンパ節の組織を顕微鏡で詳しく調べて最終的に確定するステージです。時に、臨床病期と病理病期が異なることがあり、その場合は病理病期の結果に基づいて、手術後の追加治療(術後補助療法)の必要性が判断されます。
1-3. 個別化医療の要「遺伝子検査」と「PD-L1検査」
かつて肺がん治療は、組織型とステージのみに基づいていました。しかし現在、特に非小細胞肺がんの治療は、がん細胞が持つ「分子の個性」を調べることで、劇的に変化しました。これは、治療方針を決定する第3の重要な軸であり、個別化医療の中核をなすものです。
この変化の背景には、なぜがん細胞が増殖し続けるのか、その根本的な原因が解明されてきたことがあります。多くの場合、がん細胞の増殖には特定の遺伝子の異常が「アクセル」として働いています。この異常をドライバー遺伝子変異と呼びます 3。
- 遺伝子パネル検査と分子標的薬:
進行・再発の非小細胞肺がん、特に腺がんでは、このドライバー遺伝子変異が見つかることが少なくありません。主なものにEGFR、ALK、ROS1、BRAF、MET、RET、NTRK、KRAS、HER2などがあります。これらの変異の有無を調べるために、一度に多数の遺伝子を解析する、遺伝子パネル検査が標準的に行われます。もし特定のドライバー遺伝子変異が見つかれば、その遺伝子が作る異常なタンパク質の働きだけをピンポイントで狙い撃ちする分子標的薬という薬を使用できます。これは、正常な細胞へのダメージを抑えつつ、がん細胞に高い効果を発揮します。 - PD-L1検査と免疫チェックポイント阻害薬:
もう一つの大きな柱が、患者さん自身の免疫力を利用してがんと闘う免疫療法です。私たちの体には、免疫細胞が正常な細胞を誤って攻撃しないようにするための「ブレーキ」機能(免疫チェックポイント)が備わっています。がん細胞は、このブレーキを巧みに利用して免疫細胞からの攻撃を逃れています。免疫チェックポイント阻害薬は、このブレーキを解除し、免疫細胞が再びがん細胞を攻撃できるようにする薬です。
この薬の効果を予測する指標の一つがPD-L1検査です。がん細胞の表面にあるPD-L1というタンパク質の発現率を調べる検査で、一般的にこの値が高いほど、免疫チェックポイント阻害薬の効果が期待できるとされています。
このように、現代の肺がん診断は、①組織型を確定するための生検、②進行度を把握するためのステージング検査(TNM分類)、そして③治療薬選択のための分子プロファイリング(遺伝子検査、PD-L1検査)という3段階のプロセスを経て行われます。
これらの情報を総合的に判断することで、一人ひとりの患者さんにとって最適な治療戦略が立てられるのです。このため、がんの診断が確定してから最終的な治療方針が決まるまで、ある程度の時間が必要となることを理解しておくことが重要です。
第2部:【ステージ別】非小細胞肺がん(NSCLC)の最新治療
非小細胞肺がんの治療は、ステージによってその目的と方法が大きく異なります。早期であれば「根治」を、進行していても「がんと共存しながらQOL(生活の質)を維持すること」を目指します。
ここでは、2025年現在の最新の治療法をステージごとに詳しく見ていきます。
2-1. ステージⅠ・Ⅱ期(早期がん):根治を目指す治療
ステージI・II期の非小細胞肺がんは、がんが肺の中、あるいは近くのリンパ節にとどまっている早期の段階です。この段階での治療の最大の目標は、がんを完全に取り除き、根治を目指すことです。5年生存率も比較的高く、いかに早期に発見し、適切な治療を受けるかが極めて重要となります。
治療の第一選択は、がんを物理的に取り除く手術(外科治療)です。近年、この外科治療の分野では、患者さんの体への負担を最小限に抑える技術が進歩しています。
- 手術(外科治療)の進化:
かつては胸を大きく切開する開胸手術が主流でしたが、現在ではほとんど行われなくなりました 。標準となっているのは、数か所の小さな切開創からカメラと手術器具を挿入して行う胸腔鏡下手術(VATS)です 。これにより、術後の痛みや回復期間が大幅に改善されました。
- 【最前線①】ロボット支援手術の普及と進化
この低侵襲化の流れをさらに加速させているのが、手術支援ロボット「ダビンチ」を用いたロボット支援手術です。ロボット手術は、3Dの鮮明な拡大画像を見ながら、人間の手以上に精密で震えのない操作が可能で、複雑な血管や気管支の処理、リンパ節の郭清(切除)をより安全かつ正確に行うことができます。日本肺癌学会のガイドラインでも、ステージI期のがんに対してロボット支援手術は有効な選択肢として推奨されています。
そして2025年現在ではその最前線にあるのが単孔式ロボット(da Vinci SP)です。これは、わずか一つの小さな創(約4cm)から全ての操作を行う究極の低侵襲手術で、術後の痛みのさらなる軽減、回復の促進、そして傷跡が目立たないという整容性の向上といった大きなメリットが期待されています。
- 放射線治療:手術に匹敵する「切らない」治療
高齢であったり、心臓や肺に他の病気を合併しているなどの理由で手術が難しい患者さんに対しては高精度の放射線治療が提案されます。 - 定位放射線治療(SBRT)
これは、多方向から放射線を病巣にピンポイントで集中照射する技術です。治療期間はわずか1~2週間、4~5回程度の照射で完了し、手術に匹敵する80~90%という高い局所制御率を誇ります。最も懸念される副作用は放射線肺臓炎(放射線による肺の炎症)ですが、照射範囲が限定的なため、症状を伴うものは5~8%程度と比較的低い頻度です。 - 【最前線②】粒子線治療(陽子線治療)の保険適用拡大
放射線治療の究極形ともいえるのが粒子線治療です。X線が体を通過しながら徐々にエネルギーを失うのに対し、陽子線などの粒子線は、体内の特定の位置でエネルギーを最大に放出し、その先では急激にゼロになる「ブラッグピーク」という物理的特性を持っています。これにより、がん病巣に線量を集中させつつ、その奥にある心臓や正常な肺、脊髄といった重要臓器への被ばくを劇的に減らすことが可能です。
これまで高額な先進医療でしたが、2024年6月から、手術が困難なステージI~IIA期の非小細胞肺がんに対して、陽子線治療が公的医療保険の適用対象となりました。
2-2. ステージⅢ期(局所進行がん):
ステージIII期は、がんが肺の外に広がり、胸の中心部にある縦隔のリンパ節まで達しているものの、まだ遠隔転移はない「局所進行」の状態です。
手術だけ、あるいは放射線治療だけといった単独の治療では太刀打ちできず、手術、放射線治療、薬物療法を組み合わせた治療が不可欠となります。このステージの治療戦略は非常に複雑であり、呼吸器外科医、腫瘍内科医、放射線治療医からなる専門家チームによる慎重な検討が求められます 。
近年、このステージIII期の治療は、新薬の登場によって変化しました。治療方針は、まず「手術で取り切れるか(切除可能か)」によって大きく二分されます。
- 切除不能なステージIII期の場合
がんの広がりから手術が難しいと判断された場合の標準治療は、抗がん剤治療と放射線治療を同時に行う化学放射線療法(CRT)です。しかし、CRT後も再発するケースが多く、長年の課題でした。この状況を打破したのが、CRT後の「維持療法」という新たな概念です。
- 【最前線③】CRT後の維持免疫療法
国際共同臨床試験であるADRIATIC試験の結果、CRT後にがんの進行が認められなかった患者さんに対し、免疫チェックポイント阻害薬であるデュルバルマブ(製品名:イミフィンジ)を1年間投与する維持療法を行うことで、全生存期間と無増悪生存期間が有意に延長することが示されました。これは現在、世界的な標準治療となっています。 - 【最前線④】EGFR陽性例の新たな標準治療(LAURAレジメン)
さらに、分子標的治療の進歩がステージIIIにも及びました。2024年に結果が発表され、2025年に日本でも承認されたLAURA試験では、EGFR遺伝子変異を持つ患者さんに限り、CRT後に分子標的薬オシメルチニブ(製品名:タグリッソ)で維持療法を行ったところ、病勢進行または死亡のリスクを84%も低下させ、無増悪生存期間の中央値を5.6か月から39.1か月へ延長させることが証明されました。これにより、ステージIIIにおいてもEGFR遺伝子検査が必須となり、陽性患者さんには新たな治療選択肢が生まれました。
- 切除可能なステージIII期の場合
手術が可能と判断された場合でも、手術単独では再発のリスクが高いため、薬物療法などを組み合わせます。
- 【最前線⑤】周術期免疫療法の登場
これまで、手術の前または後に行う化学療法が中心でした。しかし、KEYNOTE-671試験により、新たな標準治療が確立されました。この試験では、切除可能なステージII~IIIB期の患者さんに対し、手術前に免疫チェックポイント阻害薬ペムブロリズマブ(製品名:キイトルーダ)と化学療法を併用し、手術後にペムブロリズマブ単剤を投与する「周術期免疫療法」を行うことで、化学療法単独と比較して再発や死亡のリスクを有意に低下させることが示されました。この治療法は2024年8月に日本で承認され、切除可能な局所進行肺がんの治療成績を大きく向上させることが期待されています。
このように、ステージIII期の治療は、切除可能か否か、そしてEGFR遺伝子変異の有無によって治療戦略が大きく分岐する、非常に個別化が進んだ領域へと変化しました。
2-3. ステージⅣ期(進行・転移がん):がんと共存し、QOLを維持する治療
ステージIV期は、がんが肺を越えて脳、骨、肝臓などの他の臓器へ遠隔転移している状態です。
この段階では、残念ながら根治は困難な場合が多いのが現状です。ステージIV期の治療は、全身に効果を及ぼす薬物療法が中心となります 18。そして、その治療薬の選択は、第1部で解説した遺伝子パネル検査とPD-L1検査の結果にほぼ全面的に基づきます。
- ドライバー遺伝子変異が見つかった場合:分子標的薬が第一選択
特定のドライバー遺伝子変異が特定されれば、その「がんのアクセル」を直接叩く分子標的薬が治療の主役となります。
- 【最前線⑥】分子標的薬の進化と新たな併用療法
- EGFR遺伝子変異陽性: 第3世代のEGFR阻害薬であるオシメルチニブ(タグリッソ)が一次治療の標準薬です。さらに、FLAURA2試験では、オシメルチニブに化学療法を上乗せすることで無増悪生存期間をさらに延長できることが示され、より強力な初期治療の選択肢が加わりました。加えて2025年3月には、二重特異性抗体アミバンタマブとEGFR阻害薬ラゼルチニブの併用療法が一次治療として新たに承認され、治療選択の幅がさらに広がっています。
- ALK融合遺伝子陽性: アレクチニブ(アレセンサ)が標準治療として確立されています。
- KRAS G12C変異陽性: かつては「創薬不能」とされた標的ですが、近年、特異的な阻害薬が登場し、治療が可能になりました。
- その他の希少な遺伝子変異: ROS1、BRAF、MET、RET、NTRKなど、多くの希少な遺伝子変異に対しても、それぞれに対応した分子標的薬が開発・承認されており、遺伝子パネル検査の重要性がますます高まっています。
表2:非小細胞肺がんの主なドライバー遺伝子と分子標的薬(2025年版)
| 遺伝子異常 (Gene Abnormality) | 代表的な分子標的薬 (Representative Targeted Drug) |
| EGFR 遺伝子変異 | オシメルチニブ(タグリッソ)、ゲフィチニブ、エルロチニブ、アミバンタマブ+ラゼルチニブ |
| ALK 融合遺伝子 | アレクチニブ(アレセンサ)、ブリグチニブ、ロルラチニブ |
| ROS1 融合遺伝子 | クリゾチニブ、エヌトレクチニブ |
| BRAF V600E遺伝子変異 | ダブラフェニブ+トラメチニブ |
| MET エクソン14スキッピング変異 | カプマチニブ、テポチニブ |
| RET 融合遺伝子 | セルペルカチニブ、プラルセチニブ |
| NTRK 融合遺伝子 | エヌトレクチニブ、ラロトレクチニブ |
| KRAS G12C遺伝子変異 | ソトラシブ、アダグラシブ |
| HER2 遺伝子変異 | トラスツズマブ デルクステカン |
これは代表的な薬剤であり、実際の使用は患者さんの状態や治療歴に応じて決定されます。
- ドライバー遺伝子変異が見つからない場合:免疫療法が主役。特定のドライバー遺伝子変異がない場合は、免疫チェックポイント阻害薬が治療の中心となります。
- 【最前線⑦】免疫チェックポイント阻害薬の広がり
- PD-L1高発現(50%以上)の場合: ペムブロリズマブ(キイトルーダ)の単剤療法が選択肢の一つとなります。
- PD-L1の発現レベルを問わない場合: 現在最も広く行われている標準治療は、ペムブロリズマブなどの免疫チェックポイント阻害薬と、プラチナ製剤を含む化学療法との併用療法です。この併用療法は、化学療法単独と比べて生存期間を大きく改善することが証明されています。
- 【最前線⑧】抗体薬物複合体(ADC)の台頭
分子標的薬、免疫チェックポイント阻害薬に続く「第3の矢」として抗体薬物複合体(Antibody-Drug Conjugate: ADC)という新しいタイプの薬剤が大きな注目を集めています。ADCは、がん細胞の表面にある特定のタンパク質(抗原)に結合する「抗体」と、強力な殺細胞作用を持つ「抗がん剤(ペイロード)」をリンカーでつないだ薬剤です。抗体がミサイルのようにがん細胞を狙って結合し、細胞内に取り込まれた後に抗がん剤を放出するため、「標的型化学療法」とも呼ばれ、全身への副作用を抑えながら、がん細胞に集中的にダメージを与えます。
- ダトポタマブ デルクステカン(Dato-DXd): このADCは、非小細胞肺がん細胞の多くに発現しているTROP2というタンパク質を標的とします。TROPION-Lung01試験では、既存の治療後に病状が進行した患者さんにおいて有望な結果を示しており、承認されれば、治療選択肢が尽きかけていた多くの患者さんにとって新たな選択肢となります。
- その他にも、HER3を標的とするパトリツマブ デルクステカンなど、複数のADCが開発の最終段階にあります。
表3:2024-2025年に承認・注目される肺がん新薬一覧
| 薬剤名(製品名) | 種類 | 対象 | 根拠となった主な臨床試験 |
| ペムブロリズマブ(キイトルーダ) | 免疫チェックポイント阻害薬 | 切除可能なNSCLC(II-IIIB期)の周術期療法 | KEYNOTE-671 |
| オシメルチニブ(タグリッソ) | 分子標的薬(EGFR-TKI) | 切除不能な局所進行NSCLC(III期、EGFR陽性)のCRT後維持療法 | LAURA |
| デュルバルマブ(イミフィンジ) | 免疫チェックポイント阻害薬 | 限局型SCLC(LD-SCLC)のCRT後維持療法 | ADRIATIC |
| タルラタマブ(イムデトラ) | 二重特異性T細胞誘導(BiTE)抗体 | 化学療法後に増悪した進展型SCLC(ED-SCLC) | DeLLphi-301 |
| アミバンタマブ+ラゼルチニブ | 二重特異性抗体+分子標的薬 | 進行・再発NSCLC(EGFR陽性)の一次治療 | MARIPOSA |
| ダトポタマブ デルクステカン | 抗体薬物複合体(ADC) | 既治療の進行・再発NSCLC(TROP2陽性) | TROPION-Lung01 |
第3部:【ステージ別】小細胞肺がん(SCLC)の最新治療
小細胞肺がんは非小細胞肺がんに比べて悪性度が高く、長年治療法の進歩が乏しい状況が続いていました。しかし、近年ついに免疫療法や新たな作用機序を持つ薬剤が登場し、治療パラダイムが大きく変わりつつあります。小細胞肺がんのステージ分類は、治療方針を決定する上では、がんが片側の胸郭内に収まっているか否かで限局型(Limited Disease: LD)と進展型(Extensive Disease: ED)に分けられるのが一般的です。
3-1. 限局型(LD-SCLC):根治を目指す治療
限局型は、がんが片方の肺と、その周辺のリンパ節(縦隔や鎖骨上窩を含む)にとどまっている状態です。この段階では、非小細胞肺がんのステージIII期と同様に根治を目指した集学的治療が行われます。
標準治療は、化学療法と放射線治療を同時に行う化学放射線療法(CRT)です 。しかし、治療成績は決して満足のいくものではありませんでした。この状況を打開したのが「維持免疫療法」の概念です。
- 【最前線⑨】維持免疫療法の登場
国際共同第III相試験であるADRIATIC試験は、限局型小細胞肺がんの治療に歴史的な進歩をもたらしました。この試験では、化学放射線療法を終えた後にがんの進行が見られない患者さんに対し、免疫チェックポイント阻害薬デュルバルマブ(イミフィンジ)による維持療法を行うことで、プラセボ(偽薬)と比較して全生存期間と無増悪生存期間を有意に延長することを示しました。これは限局型小細胞肺がんにおける約30年ぶりの生存期間延長を示した成果であり新たな標準治療として確立されました。
3-2. 進展型(ED-SCLC):QOLを維持し、生存期間の延長を目指す
進展型は、がんが限局型の範囲を越えて広がっている状態で、診断時には多くの患者さんがこの段階にあたります。治療の目標は、がんの進行を抑え、症状を和らげ、QOLを維持しながら生存期間を延長すること、になります。
一次治療(初回治療)の標準は、**アテゾリズマブ(テセントリク)やデュルバルマブ(イミフィンジ)といった免疫チェックポイント阻害薬と、プラチナ製剤を含む化学療法との併用療法です。これにより、化学療法単独の時代に比べて生存期間が改善しました。
しかし、大きな課題は、この初回治療の効果がなくなった後の二次治療以降の選択肢が極めて限られていたことでした。
この「アンメット・メディカル・ニーズ(未だ満たされていない医療ニーズ)」に応える待望の新薬が、2024年末から2025年にかけてついに登場しました。
- 【最前線⑩】待望の二次治療以降の新薬(タルラタマブ)
タルラタマブ(製品名:イムデトラ)は、2024年12月に日本で製造販売承認を取得した、全く新しい作用機序を持つ薬剤です。これはBiTE(Bispecific T-cell Engager:二重特異性T細胞誘導)抗体と呼ばれるもので、その構造はユニークです。片方のアームで患者さん自身の免疫細胞であるT細胞に、もう片方のアームで小細胞肺がん細胞の表面に多く発現しているDLL3というタンパク質に結合します。これにより、T細胞とがん細胞を物理的に引き合わせる「橋渡し役」となり、T細胞ががん細胞を強力に攻撃するよう促します。
臨床試験では、標準的な化学療法が効かなくなった進展型小細胞肺がんの患者さんにおいて、有望な治療効果が示されました。DLL3を標的とする初の治療薬であり、長らく停滞していた小細胞肺がん治療におけるブレークスルーとして、大きな期待が寄せられていますす。
第4部:未来の肺がん治療 ― 臨床試験で開発中の最先端アプローチ
現在、標準治療として行われている治療法も、すべては過去の臨床試験の積み重ねによってその有効性と安全性が証明されてきたものです。そして今未来の標準治療となる可能性を秘めた治療法の開発が世界中で進められています。ここでは、今後5年から10年で実用化が期待される最先端のアプローチをいくつかご紹介します。
- CAR-T細胞療法(キメラ抗原受容体T細胞療法)
これは、患者さん自身の免疫細胞(T細胞)を一度体外に取り出し、遺伝子改変技術によってがん細胞を特異的に認識・攻撃する能力を持たせた上で、再び体内に戻すという「生きた細胞医薬」です。血液がんの領域では既に劇的な効果を示し、標準治療となっていますが、肺がんのような固形がんへの応用は、標的となる適切な抗原の選択や、がん組織内の過酷な環境でT細胞が機能し続けることの難しさなど、多くの課題がありました 。しかし研究は着実に進んでいます。現在、肺がん細胞に発現するCEA、DLL3、EPHB4といったタンパク質を標的としたCAR-T療法の早期臨床試験が進行中です。まだ初期段階ではありますが、固形がんに対するこの究極の個別化免疫療法が、未来の治療選択肢となることが期待されています。 - がんワクチン
「ワクチン」と聞くと感染症予防を思い浮かべますが、がん治療においても、患者さんのがん細胞だけが持つ特有の遺伝子変異(ネオアンチゲン)を標的として、免疫システムに「これが敵だ」と教育する治療用ワクチンの開発が進められています。これにより、免疫系がより効率的に、そして持続的にがん細胞を攻撃できるようになる可能性があります。これは、究極のオーダーメイド治療であり、免疫チェックポイント阻害薬との併用など、様々な形での応用が研究されています。 - 臨床試験への参加という選択肢
こうした未来の治療法は、臨床試験(治験)という形で開発が進められています。臨床試験は、新しい治療法が既存の標準治療よりも優れているかどうかを科学的に検証するための、厳格なプロセスです。標準治療では効果が不十分な場合や、より新しい治療法を希望する場合、臨床試験への参加が一つの選択肢となり得ます。日本国内で実施されている臨床試験は、医薬品医療機器総合機構(PMDA)のウェブサイトや、JAPIC-CTI、UMIN-CTRといったデータベースで検索することが可能です 。ご自身の病状に合った臨床試験があるかどうか、主治医に相談してみることも重要です。
第5部:治療と向き合うために ― 副作用対策と支持療法
最先端の治療法も、その効果を最大限に引き出し、治療を継続するためには、副作用の管理が極めて重要です。近年、副作用を予防・軽減するための支持療法も進歩しており、患者さんのQOL(生活の質)を高く保ちながら治療を続けることが可能になってきています。
緩和ケア/支持療法は、終末期の医療というイメージを持たれがちですが現代のがん医療において、緩和ケア/支持療法は、がんと診断されたその日から、痛み、息苦しさ、倦怠感といった身体的な苦痛や、不安や落ち込みといった精神的な苦痛を和らげるために、あらゆる治療と並行して行われるべきものとされています。
表4:主な治療法の副作用と対策の早見表
| 副作用 | 主な対策・セルフケア |
| 全般 | |
| 倦怠感・疲労感 | 無理をせず休息をとる。散歩など軽い運動を日課にする。栄養バランスの良い食事を心がける。 |
| 手術 | |
| 術後の痛み | 痛み止めを我慢せずに使用する。楽な姿勢をとる。 |
| 肺炎予防 | 術前・術後からの禁煙は必須。深呼吸や咳の練習(呼吸訓練)を積極的に行う。 |
| 放射線治療 | |
| 皮膚炎 | 照射部位を清潔に保ち、保湿する。刺激の少ない衣類を着用し、直射日光を避ける。掻いたり擦ったりしない。 |
| 食道炎(胸部照射時) | 熱いもの、硬いもの、香辛料などの刺激物を避ける。食事を細かく刻んだり、流動食にしたりする工夫をする。 |
| 薬物療法(共通) | |
| 吐き気・嘔吐 | 処方された吐き気止めを指示通りに服用する。食事を少量ずつ何回かに分ける。消化の良いものを選ぶ。 |
| 口内炎 | 口腔内を清潔に保つ(こまめなうがい、柔らかい歯ブラシの使用)。刺激物を避ける。 |
| 下痢・便秘 | 【下痢】水分を十分に補給し脱水を防ぐ。医師に相談し下痢止めを処方してもらう。 【便秘】水分や食物繊維を多く摂る。適度な運動を心がける。 |
| 細胞傷害性抗がん剤 | |
| 骨髄抑制(白血球減少) | 手洗い、うがいを徹底し、感染予防に努める。人混みを避ける。発熱時は速やかに医療機関に連絡する。 |
| 脱毛 | 治療前に髪を短くしておく。精神的なケアとして、かつらや帽子、バンダナなどを準備する。 |
| 末梢神経障害(しびれ) | 手足のマッサージやストレッチ。冷たいものや熱いものへの接触に注意する。ボタンがかけにくいなど日常生活に支障が出たらすぐに相談。 |
| 免疫チェックポイント阻害薬 | |
| 免疫関連有害事象(irAEs) | 【特に注意】乾いた咳、息切れ、発熱(間質性肺炎)、重度の下痢(大腸炎)、強い倦怠感(甲状腺機能異常など)、皮膚の発疹・かゆみなど、普段と違う症状が出たらどんな些細なことでもすぐに医師や看護師に連絡することが最も重要。早期発見・早期対応が重症化を防ぐ鍵。 |
特に注意が必要なのは、免疫チェックポイント阻害薬による免疫関連有害事象(irAEs)です。これは、活性化した免疫が正常な臓器を攻撃してしまうことで起こり、間質性肺炎、大腸炎、甲状腺機能障害、1型糖尿病、皮膚障害など、全身のあらゆる臓器に起こる可能性があります。発症時期も予測が難しく、治療中から治療終了後、数か月たってから現れることもあります。重要なのは、「いつもと違うな」と感じたら、どんなに些細な症状でもすぐに主治医や看護師、薬剤師に伝えることです。早期に発見し、適切に対処すれば、多くはコントロール可能です。
副作用と上手に付き合い、治療を完遂するためには、患者さん自身が積極的に医療チームとコミュニケーションをとり、症状を正確に伝えることが何よりも大切です。
おわりに:希望を持って、最適な治療法を
肺がん治療は、この数年で進歩を遂げました。かつては治療選択肢が限られていた状況から、今や遺伝子レベルでの個別化医療が当たり前となり、手術や放射線治療の技術はより低侵襲で効果的になっています。特に、これまで難治とされてきた進行がんや小細胞肺がんの領域においても、免疫療法や新しい作用機序を持つ薬剤が次々と登場し、治療成績は着実に向上しています。
肺がんという診断は、患者さんとご家族にとって計り知れない衝撃と不安をもたらすものです。しかし大切なのは、正確な情報に基づき、ご自身の病状を正しく理解し、希望を失わないことです。