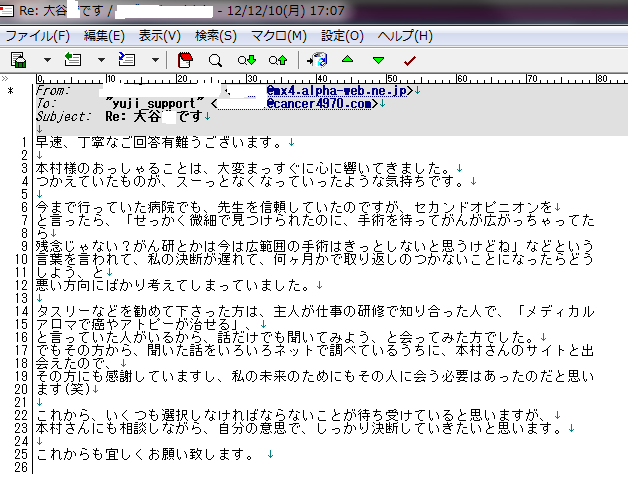こんにちは。がん治療専門アドバイザー、本村ユウジです。
子宮頸がんと診断された患者さんにとって、最初に知りたいのは「自分のがんはどの程度進行しているのか」という点です。これを示すのが「ステージ分類」であり、このステージによって治療方針が大きく変わってきます。
子宮頸がんのステージ分類は、国際産婦人科連合(FIGO)が定めた基準が世界的に使用されており、日本でもこの基準に従って診断と治療が行われています。
2018年に改訂された最新の分類では、画像検査やリンパ節転移の状態も考慮されるようになり、より正確な病期診断が可能となりました。
ステージは0期からIV期まで分類され、数字が大きくなるほど進行度が高いことを意味します。また、各ステージはさらに細かく分類され、それぞれに応じた適切な治療法が選択されます。
この記事では、各ステージの詳細な定義と、それぞれに推奨される治療法について、最新の医学的知見に基づいて解説します。
子宮頸がんのステージ分類の基礎知識
ステージ分類の目的と重要性
ステージ分類は、がんの進行度を客観的に評価し、最適な治療法を選択するための重要な指標です。同じステージの患者さんであれば、ほぼ同じ治療方針が適用され、予後(治療後の経過)もある程度予測することができます。
子宮頸がんのステージ診断には、内診、コルポスコープ検査(膣拡大鏡検査)、生検、CT検査、MRI検査、PET検査などが用いられます。これらの検査結果を総合的に評価して、最終的なステージが決定されます。
FIGO分類2018年改訂版の特徴
2018年に改訂されたFIGO分類では、従来の臨床所見に加えて、画像検査や病理学的検査の結果も考慮されるようになりました。特に重要な変更点は、リンパ節転移の有無を反映したIIIc期の新設です。
画像検査でリンパ節転移が確認された場合、たとえ局所的ながんの広がりが小さくても、ステージIIIc期と診断されます。これにより、リンパ節転移という予後に大きく影響する因子が、ステージ分類に明確に組み込まれることになりました。
ステージ0期とステージI期の詳細な分類と特徴
ステージ0期(上皮内がん)
ステージ0期は、がん細胞が子宮頸部の表面を覆う上皮内にのみとどまっている状態です。この段階では、がん細胞が基底膜を破って深部に浸潤していないため、「上皮内がん」または「高度異形成」と呼ばれます。
定期的な子宮頸がん検診で発見されることが多く、適切な治療を行えば完治が期待できる段階です。転移の可能性はほとんどなく、妊娠・出産を希望する患者さんでも子宮を温存した治療が可能です。
検診で「要精密検査」と判定された場合、コルポスコープ検査と組織診(生検)が行われ、病変の範囲と深さが詳しく調べられます。この段階で適切な治療を受けることで、将来的な浸潤がんへの進行を防ぐことができます。
ステージIa期(微小浸潤がん)
ステージIa期は、がん細胞が基底膜を破って間質に浸潤し始めている状態ですが、浸潤の程度が非常に浅い段階です。肉眼では確認できず、顕微鏡検査によって初めて診断されます。
Ia1期では、がんの浸潤の深さが3mm以内、横方向への広がりが7mm以内の状態を指します。リンパ管や血管への浸潤がなければ、リンパ節転移の可能性は1%未満と極めて低く、予後は良好です。5年生存率は95%以上と報告されています。
Ia2期では、浸潤の深さが3mmを超えるものの5mm以内、横方向への広がりは7mm以内にとどまっている状態です。Ia1期と比較するとリンパ節転移の可能性がやや高くなり、約3~5%の患者さんに骨盤リンパ節転移が認められます。
浸潤の深さが深くなるほど、脈管(リンパ管や血管)への侵襲の可能性が高まり、これが転移のリスクと関連しています。病理検査で脈管侵襲が確認された場合は、より慎重な治療方針が検討されます。
ステージIb期(臨床的に明らかながん)
ステージIb期は、肉眼的に病巣が確認できる段階で、がんは子宮頸部に限局していますが、より大きくなっている状態です。この段階になると、腫瘍のサイズが治療方針や予後に大きく影響してきます。
Ib1期は、がんの最大径が4cm以内の状態を指します。この場合、広汎子宮全摘出術による根治的な切除が可能であり、手術療法が標準治療として推奨されます。Ib1期の5年生存率は約85~90%と良好です。
Ib2期は、がんの最大径が4cmを超える場合を指します。腫瘍径が大きくなると、リンパ節転移のリスクが高まり、また手術による完全な切除が困難になる場合があります。このため、手術療法と化学放射線療法のいずれを選択するか、慎重な検討が必要となります。
Ib2期の5年生存率は約75~80%とIb1期よりもやや低下しますが、適切な治療により良好な予後が期待できます。腫瘍径が大きい場合でも、化学放射線療法により高い治療効果が得られることが、多くの臨床研究で示されています。
ステージII期からステージIV期の進行した状態
ステージII期(子宮を超えた浸潤)
ステージII期では、がんが子宮頸部を超えて周囲の組織に広がり始めている段階です。IIa期とIIb期に分類され、浸潤の範囲によって治療方針が異なります。
IIa期は、がんが膣壁の上2/3に浸潤している状態ですが、子宮の周囲を取り巻く子宮傍組織(パラメトリウム)には達していません。パラメトリウムは子宮を骨盤に固定する結合組織で、重要な血管やリンパ管、神経が通っています。
IIa1期は腫瘍径が4cm以内、IIa2期は4cmを超える場合を指します。IIa1期では手術療法も選択肢となりますが、IIa2期では化学放射線療法が推奨されることが多くなります。
IIb期では、がんが子宮傍組織に浸潤していますが、骨盤壁までは達していない状態です。この段階になると手術による完全な切除が困難になる場合が多く、化学放射線療法が標準治療となります。
IIb期の治療では、外部照射と腔内照射を組み合わせた放射線療法に、シスプラチンを中心とした化学療法を同時に行います。この併用療法により、放射線の効果が増強され、治療成績の向上が期待できます。
ステージIII期(骨盤内での広範な進展)
ステージIII期は、がんが骨盤内でさらに広範囲に広がっている状態です。この段階では、手術による根治的な治療は一般的に困難となり、化学放射線療法が治療の中心となります。
IIIa期は、がんの膣壁への浸潤が下1/3に達しているものの、子宮傍組織への広がりは骨盤壁までは達していない状態です。膣壁の下1/3は、外陰部に近い部分で、この領域への浸潤は治療をより複雑にします。
IIIb期では、子宮傍組織への浸潤が骨盤壁まで達している、または水腎症や無機能腎が認められる状態を指します。水腎症は、がんによって尿管が圧迫され、腎臓に尿が溜まってしまう状態で、腎機能の低下を招く可能性があります。
水腎症が認められる場合は、治療前に尿路変更術(腎瘻造設や尿管ステント留置)が必要となることがあります。腎機能が保たれていないと、シスプラチンなどの腎毒性のある抗がん剤が使用できないため、治療選択肢に影響が出ることがあります。
2018年の改訂で新設されたIIIc期は、画像検査や手術によって骨盤リンパ節や傍大動脈リンパ節への転移が確認された場合を指します。IIIc1期は骨盤リンパ節転移のみ、IIIc2期は傍大動脈リンパ節転移がある場合です。
リンパ節転移の有無は予後に大きく影響するため、この分類の導入により、より適切な治療方針の決定が可能となりました。傍大動脈リンパ節転移がある場合は、拡大照射野での放射線療法が検討されます。
ステージIV期(遠隔臓器への浸潤・転移)
ステージIV期は、子宮頸がんの中で最も進行した段階です。IVa期とIVb期に分類されます。
IVa期は、がんが膀胱や直腸の粘膜に直接浸潤している状態です。膀胱鏡検査や直腸鏡検査で粘膜へのがんの浸潤が確認されることによって診断されます。単に膀胱や直腸に接しているだけではなく、粘膜への明らかな浸潤が認められることが診断の条件となります。
骨盤内での局所的な進展は著しいものの、遠隔転移はまだ認められていない段階です。治療としては化学放射線療法が中心となりますが、症状緩和のための手術が検討されることもあります。
IVb期は、肺、肝臓、骨など、骨盤を超えた遠隔臓器への転移が認められる状態です。この段階では、完治を目指すことは難しく、がんの進行を抑えて症状を和らげ、生活の質(QOL)を保つことが治療の主な目標となります。
IVb期の治療では、全身化学療法が中心となります。シスプラチンまたはカルボプラチンとパクリタキセルの併用療法が標準的に使用され、効果が認められれば治療を継続します。近年では、免疫チェックポイント阻害薬や分子標的薬の併用により、生存期間の延長が報告されています。
| ステージ | がんの広がり | 5年生存率(目安) | 主な治療法 |
|---|---|---|---|
| 0期 | 上皮内にとどまる | ほぼ100% | 円錐切除術 |
| Ia1期 | 浸潤3mm以内 | 95%以上 | 円錐切除術/単純子宮全摘出術 |
| Ia2期 | 浸潤3~5mm | 90%以上 | 準広汎子宮全摘出術 |
| Ib1期 | 子宮頸部内(4cm以内) | 85~90% | 広汎子宮全摘出術 |
| Ib2期 | 子宮頸部内(4cm超) | 75~80% | 広汎子宮全摘出術/化学放射線療法 |
| IIa期 | 膣壁上2/3に浸潤 | 65~75% | 広汎子宮全摘出術/化学放射線療法 |
| IIb期 | 子宮傍組織に浸潤 | 60~65% | 化学放射線療法 |
| IIIa期 | 膣壁下1/3に浸潤 | 40~50% | 化学放射線療法 |
| IIIb期 | 骨盤壁に到達/水腎症 | 35~45% | 化学放射線療法 |
| IIIc期 | リンパ節転移あり | 30~40% | 化学放射線療法(拡大照射野) |
| IVa期 | 膀胱・直腸粘膜に浸潤 | 20~25% | 化学放射線療法 |
| IVb期 | 遠隔転移あり | 10~15% | 全身化学療法/免疫療法 |
ステージ0期からステージIa1期の治療法
円錐切除術による子宮温存治療
ステージ0期および浸潤が非常に浅いステージIa1期では、円錐切除術が標準治療として広く行われています。これは子宮頸部の病変部分を円錐状に切除する手術で、子宮本体を温存できるため、妊娠・出産を希望する患者さんに適しています。
手術は通常、全身麻酔または腰椎麻酔下で行われ、膣から専用の器具を挿入して子宮頸部を切除します。切除方法には、メスを使用する「冷刀円錐切除術」と、高周波電流を使用する「LEEP(ループ式電気切除術)」があります。
冷刀円錐切除術は、切除断端の焼灼による組織の変性が少なく、病理診断の精度が高いという利点があります。一方、LEEPは出血が少なく、外来での実施も可能な場合があるという利点があります。どちらの方法を選択するかは、病変の範囲や施設の状況によって決定されます。
入院期間は2~3日程度で、術後1~2週間で日常生活に復帰できることが多いです。ただし、性交渉は2~4週間程度控える必要があり、また重い物を持つなどの激しい運動も避けることが推奨されます。
切除した組織は病理検査に提出され、がんの広がりや断端(切除縁)にがん細胞が残っていないかが詳しく調べられます。断端が陰性、つまりがん細胞が完全に取り除かれていれば、この治療で完治が期待できます。断端陰性の場合の再発率は約5%以下と報告されています。
ただし、断端陽性の場合や浸潤がIa1期の基準を超えている場合は、追加治療として単純子宮全摘出術や広汎子宮全摘出術が検討されます。また、円錐切除術後に妊娠した場合、子宮頸管が短縮されているため、早産のリスクがやや高くなる可能性があり、妊娠中の慎重な管理が必要となります。
単純子宮全摘出術の適応と方法
妊娠を希望しない患者さんや、円錐切除術での完全な切除が難しいと判断された場合は、単純子宮全摘出術が選択されます。この手術では、子宮と子宮頸部を完全に摘出しますが、膣や子宮周囲の組織は切除範囲に含まれません。
手術方法には、開腹手術、腹腔鏡手術、ロボット支援手術、膣式手術などがあり、患者さんの年齢、体型、合併症の有無、施設の設備などを考慮して最適な方法が選択されます。
開腹手術は、下腹部を切開して直接手術を行う方法で、視野が広く確実な手術が可能です。腹腔鏡手術は、腹部に数か所の小さな穴を開けて、カメラと器具を挿入して行う方法で、傷が小さく術後の回復が早いという利点があります。
ロボット支援手術は、執刀医が専用のコンソールを操作し、ロボットアームに装着された器具を精密に動かして手術を行う方法です。3D画像により詳細な視野が得られ、手ぶれの影響を受けず、より精密な手術が可能となります。2018年から保険適用となり、実施施設が増えています。
膣式手術は、膣から子宮を摘出する方法で、腹部に傷が残らないという利点があります。ただし、子宮が大きい場合や癒着がある場合は実施が困難なことがあります。
入院期間は術式によって異なりますが、腹腔鏡手術やロボット支援手術では5~7日程度、開腹手術では7~10日程度が一般的です。術後の社会復帰までの期間も、腹腔鏡手術やロボット支援手術の方が短く、2~3週間程度で職場復帰が可能な場合が多いです。
ステージIa2期からステージIb期の治療法
準広汎子宮全摘出術と広汎子宮全摘出術
ステージIa2期では、がんの浸潤がやや深くなるため、単純子宮全摘出術では不十分な場合があります。このため、準広汎子宮全摘出術が標準的な治療として行われます。
準広汎子宮全摘出術では、子宮と子宮頸部に加えて、子宮周囲の組織(子宮傍組織)の一部と膣の一部を切除します。切除範囲は、子宮傍組織を約1~2cm、膣を約1cm程度とされています。また、リンパ節転移の可能性に備えて、骨盤リンパ節の郭清(切除)も同時に行われます。
ステージIb期では、より広範囲な切除が必要となるため、広汎子宮全摘出術が標準治療です。この手術では、子宮、子宮頸部、膣の上部1/3、子宮周囲の組織を広範囲に切除し、骨盤リンパ節郭清も行います。
広汎子宮全摘出術の切除範囲は、子宮傍組織を骨盤壁近くまで、膣を約2~3cm程度切除します。また、必要に応じて、卵巣や卵管も同時に摘出されることがあります。年齢が若く卵巣機能を温存したい場合は、卵巣を残すことも検討されますが、放射線療法の追加が必要となった場合は、卵巣機能が失われる可能性があります。
広汎子宮全摘出術は、子宮頸がんの根治を目指す最も標準的な手術ですが、手術による合併症のリスクもあります。特に、膀胱や直腸の神経が損傷されることによる排尿障害や排便障害が、術後の重要な問題となることがあります。
排尿障害は、術後数か月から1年程度で改善することが多いですが、長期的に自己導尿が必要となる患者さんもいます。近年では、神経温存術式の開発により、排尿障害のリスクが低減されつつあります。
リンパ浮腫も、広汎子宮全摘出術後の主要な合併症の一つです。骨盤リンパ節郭清により、下肢からのリンパ液の流れが障害され、足がむくむことがあります。術後早期からの予防的なリハビリテーションやマッサージ、弾性ストッキングの着用などにより、リンパ浮腫の発生や悪化を予防することが重要です。
手術後の追加治療
手術後の病理検査の結果、以下のようなリスク因子が認められた場合、再発のリスクを下げるために追加治療が検討されます。
高リスク因子としては、リンパ節転移、子宮傍組織への浸潤、切除断端陽性などがあります。これらの因子が認められた場合、術後化学放射線療法が強く推奨されます。
中等度リスク因子としては、腫瘍径が4cmを超える、間質浸潤が深い(子宮頸部の厚みの2/3以上)、脈管侵襲が認められるなどがあります。これらの因子が複数認められた場合、術後放射線療法が検討されます。
追加治療としての放射線療法は通常、骨盤全体に対して外部照射として行われ、5~6週間継続されます。総線量は45~50グレイ程度です。必要に応じて、腔内照射が追加されることもあります。
化学放射線療法では、シスプラチンという抗がん剤を週1回、40mg/m²の用量で投与しながら放射線療法を行います。この併用療法により、放射線の効果が増強され、再発率を下げることができることが、複数の大規模臨床試験で示されています。
術後化学放射線療法を受けた患者さんの5年無病生存率は、受けなかった場合と比較して約15~20%向上することが報告されています。ただし、手術と放射線療法の両方を受けることによる合併症のリスクも高まるため、治療の利益とリスクを十分に検討する必要があります。
ステージII期の治療選択肢
手術療法と化学放射線療法の選択
ステージII期の治療方針は、がんの広がりの程度、患者さんの年齢、全身状態、合併症の有無などを総合的に考慮して決定されます。
IIa期で腫瘍径が比較的小さい場合(IIa1期)は、広汎子宮全摘出術と骨盤リンパ節郭清が選択肢となります。手術によって病巣を完全に切除できれば、高い治癒率が期待できます。ただし、IIa2期や膣壁への浸潤が広範囲に及ぶ場合は、手術による完全切除が困難になることがあります。
一方、IIb期や腫瘍径が大きいIIa2期の場合は、手術による完全な切除が困難になることが多く、化学放射線療法が標準治療として推奨されます。日本の治療ガイドラインでは、IIb期には化学放射線療法が第一選択とされています。
化学放射線療法を選択した場合の治療成績は、手術療法と同等またはそれ以上であることが、複数の臨床研究で示されています。また、手術に伴う合併症のリスクを避けることができるという利点もあります。
化学放射線療法の実際
化学放射線療法は、外部照射と腔内照射(小線源治療)を組み合わせて行われます。外部照射では、骨盤全体に放射線を照射し、骨盤内のリンパ節も治療範囲に含まれます。
外部照射は1日1回、週5日(月~金曜日)のペースで実施され、総期間は5~6週間です。1回の照射時間は10~15分程度で、実際に放射線が照射されている時間は数分です。多くの場合、外来通院で治療を受けることができます。
腔内照射は、外部照射の終了後または並行して行われます。膣から特殊なアプリケーター(線源を保持する器具)を挿入し、子宮頸部や膣壁に密着させて放射線を照射します。この方法により、腫瘍部位に高線量を集中させることができ、周囲の正常組織への影響を最小限に抑えることができます。
腔内照射は通常、週1回のペースで3~4回実施されます。1回の治療時間は、線源の挿入と位置確認を含めて1~2時間程度です。治療中は動くことができないため、鎮痛剤や鎮静剤を使用することがあります。
化学療法としては、シスプラチンが週1回、40mg/m²の用量で点滴投与されます。投与は外部照射の日に合わせて行われ、通常5~6回投与されます。シスプラチンには腎毒性や神経毒性などの副作用があるため、投与前には必ず血液検査や尿検査で腎機能を確認します。
腎機能が低下している患者さんや高齢者では、シスプラチンの投与が困難な場合があります。そのような場合は、カルボプラチンなど別の抗がん剤への変更や、放射線療法単独での治療が検討されます。
ステージII期の治療成績
ステージII期の5年生存率は、IIa期で約65~75%、IIb期で約60~65%とされています。化学放射線療法の標準化により、以前と比較して治療成績は向上しています。
ただし、腫瘍径が大きい場合(4cmを超える)やリンパ節転移が広範囲に及ぶ場合は、再発のリスクが高くなります。特に、傍大動脈リンパ節への転移が認められる場合(IIIc2期と診断される)は、予後が不良となります。
治療後は定期的な経過観察が重要であり、再発の早期発見に努めることが予後の改善につながります。再発の約80%は治療後2年以内に起こるため、この期間は特に注意深い観察が必要です。
ステージIII期およびステージIV期の治療法
化学放射線療法が治療の中心
ステージIII期およびIVa期では、手術による根治的な治療は一般的に困難であり、化学放射線療法が標準治療となります。治療の目的は、がんを可能な限り制御し、症状を和らげ、生存期間を延長することです。
外部照射は1日1回、週5日のペースで5~6週間継続され、総線量として45~50グレイが骨盤全体に照射されます。リンパ節転移がある場合は、照射範囲を拡大して傍大動脈リンパ節領域も含めることがあります。この場合、総線量は40~45グレイ程度に減量されることが多いです。
さらに、腔内照射を週1~2回のペースで追加し、腫瘍部位に集中的に線量を増やします。外部照射と腔内照射を合わせた腫瘍部位への総線量は、通常80~85グレイ程度となります。
化学療法としては、シスプラチンが週1回40mg/m²の用量で投与されるのが標準です。患者さんの全身状態や腎機能に問題がある場合は、投与量を調整したり、カルボプラチンなど別の抗がん剤に変更したりすることがあります。
免疫チェックポイント阻害薬の使用
2024年以降、進行・再発子宮頸がんに対して、免疫チェックポイント阻害薬であるペムブロリズマブ(商品名:キイトルーダ)が使用できるようになりました。これは、がん治療における大きな進歩の一つです。
免疫チェックポイント阻害薬は、がん細胞が免疫細胞の攻撃から逃れるために使っている仕組みを阻害し、患者さん自身の免疫力でがん細胞を攻撃できるようにする治療法です。PD-1/PD-L1という分子の相互作用を阻害することで、T細胞ががん細胞を認識・攻撃できるようにします。
化学療法との併用により、従来の治療と比較して生存期間の延長が報告されており、特にPD-L1という蛋白質の発現が高い患者さんでより高い効果が期待されています。治療前に、腫瘍組織のPD-L1発現を検査することで、効果が期待できるかどうかの予測が可能です。
ペムブロリズマブは、3週間ごとに点滴で投与されます。副作用としては、免疫関連有害事象と呼ばれる特殊な副作用があり、甲状腺機能異常、肝機能障害、肺臓炎、大腸炎などが報告されています。これらの副作用は早期に発見・対処することが重要です。
分子標的薬ベバシズマブの併用
進行・再発子宮頸がんに対しては、ベバシズマブ(商品名:アバスチン)という分子標的薬も使用されます。この薬剤は、血管内皮増殖因子(VEGF)という蛋白質の働きを阻害し、がん細胞が増殖するために必要な血管の新生を抑制する作用があります。
化学療法にベバシズマブを併用することで、無増悪生存期間(がんが進行せずに安定している期間)の延長が示されています。特に、パクリタキセルとシスプラチンまたはカルボプラチンの併用療法に、ベバシズマブを加えることで、効果の向上が期待できます。
ベバシズマブは2週間または3週間ごとに点滴で投与されます。副作用としては、高血圧、蛋白尿、出血、血栓症、消化管穿孔などが報告されており、特に腫瘍が膀胱や直腸に浸潤している場合は、出血や穿孔のリスクが高まるため注意が必要です。
ステージIVb期の治療
遠隔転移を伴うステージIVb期では、完治を目指すことは難しく、がんの進行を抑えて症状を和らげ、生活の質を保つことが治療の主な目標となります。
化学療法が治療の中心となり、シスプラチンまたはカルボプラチンとパクリタキセルの併用療法が標準的に使用されます。この治療は3週間ごとに繰り返され、効果が認められれば治療を継続します。
一次治療で効果が不十分な場合や、効果が認められた後に再び進行した場合は、二次治療として別の抗がん剤が使用されます。ゲムシタビン、イリノテカン、トポテカンなどが選択肢となります。
症状緩和のための放射線療法も重要です。骨転移による痛みや、腫瘍による出血、神経の圧迫症状などに対して、局所的に放射線を照射することで症状の改善が期待できます。緩和的放射線療法は、比較的短期間(1~2週間程度)で実施されることが多いです。
IVb期の5年生存率は10~15%程度ですが、免疫チェックポイント阻害薬や分子標的薬の登場により、生存期間が延長する可能性が示されています。また、症状コントロールと支持療法により、生活の質を保ちながら治療を継続することが可能です。
子宮頸がんの組織型による治療の違い
子宮頸がんは、がんが発生した組織によって「扁平上皮がん」「腺がん」「腺扁平上皮がん」などに分類されます。子宮頸がんの約70%は扁平上皮がん、約25%は腺がんで、残りの約5%がその他の組織型です。
扁平上皮がんの特徴と治療
扁平上皮がんは、膣に近い子宮頸部の外側を覆う扁平上皮細胞から発生します。ヒトパピローマウイルス(HPV)感染との関連が強く、定期的な子宮頸がん検診で早期発見されやすいタイプです。
放射線療法に対する感受性が高く、進行例でも化学放射線療法で良好な治療成績が得られます。このため、ステージII期以降では化学放射線療法が標準治療として推奨されることが多いです。
腺がんの特徴と治療
腺がんは、子宮体部に近い子宮頸部の内側を覆う腺上皮細胞から発生します。扁平上皮がんと比較すると、以下のような特徴があります。
まず、検診で発見されにくいという点があります。腺がんは子宮頸部の奥深くで発生することが多く、通常の細胞診では検出されにくい傾向があります。このため、発見時には既にある程度進行している場合があります。
また、リンパ節転移や遠隔転移を起こしやすい傾向があります。腺がんは扁平上皮がんと比較して、早い段階からリンパ節転移を起こすことが知られており、同じステージでも予後がやや不良となることがあります。
さらに、放射線療法に対する感受性がやや低いという特徴があります。このため、早期であっても手術療法が優先されることが多く、特にステージI期やIIa期では広汎子宮全摘出術が推奨されます。
近年の研究では、腺がんの中でもサブタイプによって予後が異なることが明らかになってきています。通常型の腺がんは比較的予後が良好ですが、胃型腺がんなど特殊なタイプは予後不良であることが知られており、より積極的な治療が必要となります。
腺扁平上皮がんの特徴と治療
腺扁平上皮がんは、扁平上皮がんと腺がんの両方の性質を持つタイプで、比較的まれです。全子宮頸がんの約3~5%を占めます。
一般的に予後は良くない傾向にあり、扁平上皮がんや腺がんと比較して、リンパ節転移や遠隔転移のリスクが高いとされています。また、治療抵抗性を示すことが多く、標準的な治療法では十分な効果が得られない場合があります。
治療方針としては、早期であっても積極的な手術療法が推奨され、術後の追加治療として化学放射線療法が考慮されることが多いです。進行例では、化学放射線療法に加えて、免疫療法や分子標的薬の併用など、より集学的な治療アプローチが必要となります。
子宮頸がん治療にかかる費用と保険適用
手術療法の費用
子宮頸がんの手術費用は、術式や入院期間によって異なります。以下に、主な手術の費用の目安を示します(健康保険適用前の総額)。
円錐切除術の場合、手術費用は約15~20万円、入院費用を含めると総額で約20~30万円程度です。入院期間は2~3日程度が一般的です。
単純子宮全摘出術の場合、開腹手術で約50~70万円、腹腔鏡手術で約70~90万円程度です。入院費用を含めると、開腹手術で約80~100万円、腹腔鏡手術で約100~120万円程度となります。
広汎子宮全摘出術などのより大規模な手術では、開腹手術で約80~120万円、腹腔鏡手術で約120~150万円、ロボット支援手術で約150~200万円程度となります。入院費用を含めると、総額で約150~250万円程度です。
これらの費用は健康保険が適用され、患者さんの自己負担は3割(70歳未満の一般的な所得の方の場合)となります。さらに、高額療養費制度を利用することで、月々の自己負担額の上限が設定されます。
化学放射線療法の費用
化学放射線療法の費用は、治療期間や使用する抗がん剤によって異なりますが、総額で約150~250万円程度となります。
外部照射と腔内照射を含む放射線治療費が約80~120万円、化学療法(シスプラチン投与)の費用が約70~130万円程度です。治療期間が長くなる場合や、追加の検査が必要な場合は、さらに費用が増加することがあります。
これらも健康保険の適用対象であり、高額療養費制度の利用により、実際の自己負担額は大幅に軽減されます。所得に応じて月々の自己負担上限額が設定されており、一般的な所得区分(年収約370~770万円)の方で月額約8~9万円程度となります。
免疫療法・分子標的薬の費用
ペムブロリズマブやベバシズマブなどの新しい治療薬は、薬剤費が非常に高額です。
ペムブロリズマブの場合、1回の投与(200mg)で約40~50万円、3週間ごとの投与で年間約700~850万円の薬剤費がかかります。ベバシズマブでは1回の投与で約20~30万円、2週間ごとまたは3週間ごとの投与で年間約400~600万円程度の費用がかかります。
これらも保険適用となりますが、長期間の使用が必要となるため、総額では数百万円に達することもあります。ただし、高額療養費制度により、実際の患者さんの自己負担は大幅に軽減されます。
また、治療効果が認められる限り継続されるため、治療期間によって総費用は変動します。効果判定は通常、2~3か月ごとに画像検査で行われ、効果が認められない場合や副作用が強い場合は、治療の変更が検討されます。
高額療養費制度の活用
高額療養費制度は、1か月(同一月内)の医療費が一定額を超えた場合、超過分が払い戻される制度です。所得に応じて自己負担上限額が設定されており、以下のような区分があります。
| 所得区分 | 自己負担上限額(月額) |
|---|---|
| 年収約1,160万円~ | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% |
| 年収約770~1,160万円 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% |
| 年収約370~770万円 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
| ~年収約370万円 | 57,600円 |
| 住民税非課税世帯 | 35,400円 |
事前に「限度額適用認定証」を取得しておくことで、医療機関での支払い時から上限額までの支払いで済みます。認定証は、加入している健康保険の保険者(協会けんぽ、健康保険組合、国民健康保険など)に申請することで発行されます。
また、同一世帯で過去12か月以内に3回以上高額療養費の支給を受けている場合は、4回目からは「多数回該当」として、さらに自己負担上限額が引き下げられます。
がん治療では高額な医療費が継続的に発生するため、この制度の活用が非常に重要です。また、民間の医療保険やがん保険に加入している場合は、保険会社への給付金請求も忘れずに行うことが大切です。
治療後の経過観察と再発への対応
定期的な経過観察の重要性とスケジュール
子宮頸がんの治療後は、再発の早期発見のために定期的な経過観察が必要です。一般的な経過観察のスケジュールは以下の通りです。
治療後最初の2年間は、3か月ごとに受診します。この期間に再発の約80%が起こるため、特に注意深い観察が必要です。治療後3~5年目は、6か月ごとの受診となります。この期間も再発のリスクはありますが、徐々に低下していきます。治療後5年以降は、年1回の受診が推奨されます。5年を超えても長期的な経過観察は重要です。
経過観察では、以下のような検査が行われます。問診では、症状の有無(不正出血、下腹部痛、腰痛、下肢のむくみなど)を確認します。内診では、膣断端や骨盤内の異常を触診で確認します。細胞診では、膣断端からの細胞を採取して、再発の兆候を調べます。
血液検査では、腫瘍マーカー(SCC抗原、CEAなど)を測定します。ただし、腫瘍マーカーは必ずしも再発を正確に反映するわけではないため、他の検査と組み合わせて判断されます。
画像検査として、胸部X線検査は定期的に行われ、肺転移の有無を確認します。CT検査やMRI検査は、症状がある場合や腫瘍マーカーの上昇が認められた場合に実施されます。PET検査は、再発が疑われる場合に、全身の転移の有無を調べるために行われることがあります。
再発のサインと早期発見
再発の兆候として、以下のような症状に注意が必要です。不正出血や血性帯下があります。膣断端からの再発による症状として重要です。持続する下腹部痛や腰痛があります。特に、徐々に増強する痛みは注意が必要です。
下肢のむくみ(特に片側性)があります。リンパ節転移による圧迫症状の可能性があります。排尿困難や血尿があります。膀胱への再発や浸潤の可能性があります。便通異常や血便があります。直腸への再発や浸潤の可能性があります。
これらの症状が現れた場合は、次回の定期受診を待たずに、速やかに担当医に連絡することが重要です。早期に再発が発見されれば、救済治療により良好な予後が期待できる場合があります。
再発時の治療選択肢
再発部位や再発までの期間、前治療の内容などによって、再発時の治療法は異なります。
局所再発の場合、再発部位が限局しており、遠隔転移がない場合は、救済手術が検討されます。前治療が放射線療法だった場合は骨盤内臓器全摘術、前治療が手術だった場合は放射線療法が選択肢となります。
骨盤内臓器全摘術は、膀胱、直腸、膣、子宮(残存している場合)を一括して摘出する大規模な手術です。術後は人工肛門と尿路変更(尿管皮膚瘻または代用膀胱)が必要となり、生活の質への影響は大きいですが、局所再発の根治を目指せる唯一の治療法です。
遠隔転移を伴う再発の場合は、全身化学療法が中心となります。シスプラチンまたはカルボプラチンとパクリタキセルの併用療法が標準的に使用されます。
また、免疫チェックポイント阻害薬(ペムブロリズマブ)や分子標的薬(ベバシズマブ)の併用により、治療成績の向上が期待されています。一次治療で効果が不十分な場合は、二次治療としてゲムシタビン、イリノテカン、トポテカンなどが選択肢となります。
症状緩和のための治療も重要です。痛みに対しては、鎮痛剤(オピオイド系薬剤など)や緩和的放射線療法が有効です。出血に対しては、止血剤の投与や緩和的放射線療法が検討されます。
子宮頸がん予防の重要性
HPVワクチン接種による一次予防
子宮頸がんは、HPVワクチン接種と定期的な検診により、予防可能ながんです。HPVワクチンは、子宮頸がんの原因となるHPV感染を予防し、がんの発症リスクを大幅に低減します。
日本では、小学6年生から高校1年生相当の女子を対象に、HPVワクチンの定期接種が行われています。対象年齢の女子は、公費(無料)で接種を受けることができます。
2024年からは9価HPVワクチン(シルガード9)が定期接種に追加され、より広範囲のHPV型に対する予防効果が期待されています。9価ワクチンは、HPV 6、11、16、18、31、33、45、52、58型の9種類のHPVに対する予防効果があり、子宮頸がんの原因の約90%をカバーします。
接種スケジュールは、15歳未満で接種を開始する場合は2回接種(標準的には6か月間隔)、15歳以上で接種を開始する場合は3回接種(0、2、6か月後)となります。
キャッチアップ接種として、1997年度から2007年度生まれの女性(誕生日が1997年4月2日から2008年4月1日までの女性)は、2025年3月31日まで公費で接種を受けることができます。
定期検診による二次予防
HPVワクチンを接種していても、定期的な子宮頸がん検診は重要です。ワクチンですべてのHPV型を予防できるわけではないため、検診による早期発見が依然として重要です。
20歳以上の女性は、2年に1回の子宮頸がん検診受診が推奨されています。多くの市区町村では、20歳以上の女性を対象に、2年に1回の無料または低額での検診を実施しています。
検診では、子宮頸部から細胞を採取して顕微鏡で調べる細胞診が行われます。異常が認められた場合は、精密検査(コルポスコープ検査と組織診)に進みます。
検診により、がんになる前の段階である異形成(軽度異形成、中等度異形成、高度異形成)の段階で発見・治療することができ、浸潤がんの発症を予防できます。高度異形成の段階で治療を受ければ、浸潤がんへの進行をほぼ確実に防ぐことができます。
子宮頸がんは予防可能ながんであるという認識を持ち、HPVワクチン接種と定期検診を適切に受けることが、最も効果的な対策となります。若い世代へのワクチン接種の普及と検診受診率の向上により、将来的に子宮頸がんの発症を大幅に減少させることが期待されています。