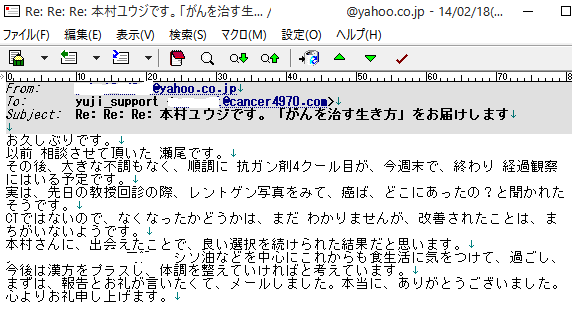こんにちは。がん治療専門アドバイザー、本村ユウジです。
肺がんと診断された際、患者さんやご家族が最も気になることの一つが「予後」、つまり治療後にどのような経過をたどるのかという点です。
肺がんの予後は、がんの組織型、発見時の病期(ステージ)、患者さんの全身状態、年齢など多くの要素によって変わります。そのため、一律に「このくらい」と断言することはできませんが、予後を考えるうえで重要な指標となるのが「生存率」です。
生存率とは、がんと診断された時点から一定期間が経過した際に、どれくらいの患者さんが生存しているかを示す統計データです。
この記事では、肺がんの生存率について、最新のデータをもとに詳しく解説します。治療方針を考えるうえでの参考情報として、また、医療者とのコミュニケーションを深めるためにお役立てください。
生存率の種類と意味
肺がんの予後を示す指標として使われる生存率には、いくつかの種類があります。まず理解しておきたいのが「5年生存率」です。これは、がんと診断されてから5年後に生存している患者さんの割合を示すものです。がん治療では、手術などでがんを取り除いた後、5年間再発がなければ治癒したと考えられることが多いため、5年生存率が広く用いられています。
一方、予後がよいとされる早期がんでは「10年生存率」を指標とすることもあります。逆に進行がんの場合は、1年生存率や3年生存率といった短い期間での指標が用いられることがあります。
生存率の算出方法にも種類があります。「実測生存率」は、死因に関係なくすべての死亡を含めた生存率です。これに対し「相対生存率」は、がん以外の死因による影響をできるだけ除外して補正したものです。さらに近年では、より正確にがん以外の死因を除いて計算できる「純生存率(ネット・サバイバル)」が国際的に採用されるようになっています。国立がん研究センターの院内がん登録でも、2015年診断例の5年生存率からこの純生存率が使われています。
肺がん全体の生存率
国立がん研究センターの院内がん登録データによると、2015年に診断された肺がん患者さん全体の5年生存率(ネット・サバイバル)は45.1%です。実測生存率では41.1%となっています。これは、がん全体の5年生存率が約64%であることと比較すると、肺がんは治療が難しいがんの一つであることがわかります。
また、10年生存率のデータを見ると、2012年に診断された患者さんの10年生存率(ネット・サバイバル)は30.3%、実測生存率は26%となっています。長期的な視点で見ても、肺がんは慎重な経過観察と適切な治療が求められる疾患です。
ただし、これらの数値は過去のデータに基づくものです。近年、分子標的薬や免疫チェックポイント阻害薬といった新しい治療法が登場し、特に進行がんに対する治療成績は目覚ましく向上しています。そのため、現在治療を受けている患者さんの予後は、これらの統計値よりも良好になる可能性があります。
病期(ステージ)別の5年生存率
肺がんの生存率は、診断時の病期によって大きく異なります。病期とは、がんの進行度を示すもので、通常0期からIV期までに分類されます。ステージが進むにつれて、がんが広がっている範囲が大きくなり、治療の難易度も上がります。
2015年に診断された肺がん患者さんの病期別5年生存率(ネット・サバイバル)は以下のとおりです。
| 病期 | 5年生存率 | がんの状態 |
|---|---|---|
| I期 | 81.9% | がんが肺の中だけにとどまり、リンパ節への転移がない状態 |
| II期 | 51.7% | 近くのリンパ節に転移がある、またはがんがやや大きい状態 |
| III期 | 29.3% | 肺の周りの組織や離れたリンパ節に広がっている状態 |
| IV期 | 8.6% | 離れた臓器(脳、骨、肝臓など)に転移がある状態 |
この表からわかるように、I期で発見された場合は約8割の患者さんが5年後も生存していますが、IV期になると1割を下回ります。早期発見がいかに重要かがわかるデータです。
病期(ステージ)別の10年生存率
長期的な予後を知るうえで参考になるのが10年生存率です。2012年に診断された患者さんの病期別10年生存率(ネット・サバイバル)は以下のようになっています。
| 病期 | 10年生存率 | 5年生存率との比較 |
|---|---|---|
| I期 | 63.9% | 5年を過ぎても6割以上が生存 |
| II期 | 30.9% | 長期的な経過観察が必要 |
| III期 | 14.8% | 慎重な治療と管理が求められる |
| IV期 | 2.5% | 新しい治療法により改善の可能性あり |
10年生存率を見ると、I期でも5年生存率より低下することがわかります。これは、5年を過ぎても再発のリスクがあることを示しています。ただし、I期で発見された場合は、10年後でも6割以上の患者さんが生存しており、早期発見の重要性が改めて確認できます。
組織型による生存率の違い
肺がんは組織型によって大きく「非小細胞肺がん」と「小細胞肺がん」に分類され、それぞれ予後が異なります。
非小細胞肺がんの生存率
非小細胞肺がんは、肺がん全体の約85%を占めます。さらに腺がん、扁平上皮がん、大細胞がんなどに分けられます。2023年現在のデータでは、非小細胞肺がん全体の5年生存率は47.5%です。
病期別の非小細胞肺がんの5年生存率は以下のとおりです。
| 病期 | 5年生存率 |
|---|---|
| I期 | 82.2% |
| II期 | 52.6% |
| III期 | 30.4% |
| IV期 | 9.0% |
非小細胞肺がんでは、I期・II期の早期段階で発見されれば手術による根治が期待できます。また、IV期であっても、EGFR遺伝子変異やALK融合遺伝子などのドライバー遺伝子変異が見つかった場合、分子標的薬による治療で生存期間を延ばせる可能性があります。実際、これらの変異がある患者さんでは、中央生存期間が2年から3年に延びるケースも報告されています。
小細胞肺がんの生存率
小細胞肺がんは、肺がん全体の約15%を占めます。進行が速く、転移しやすいという特徴があり、非小細胞肺がんと比べて予後が厳しいとされています。2023年現在のデータでは、小細胞肺がん全体の5年生存率は11.5%です。
病期別の小細胞肺がんの5年生存率は以下のとおりです。
| 病期 | 5年生存率 |
|---|---|
| I期 | 43.2% |
| II期 | 28.5% |
| III期 | 17.5% |
| IV期 | 2.2% |
小細胞肺がんは進行が速いため、発見時にすでにIV期(進展型)であることが多く、限局型(I期からIII期)は全体の約20%程度です。ただし、I期やII期の早期で発見され、完全切除できた場合には、5年生存率が50%から70%まで向上するという報告もあります。
近年では、小細胞肺がんに対しても免疫チェックポイント阻害薬と抗がん剤を併用する治療が行われるようになり、従来の5年生存率2%程度から12%程度まで改善したというデータも発表されています。小細胞肺がんの治療も確実に進歩しています。
性別による生存率の違い
肺がんの生存率には性別による差も見られます。国立がん研究センターのデータによると、男性よりも女性の方が生存率が高い傾向にあります。この理由として考えられるのは、喫煙習慣の違い、薬物療法の効果の違い、副作用の現れ方の違い、組織型の違いなどですが、詳しいメカニズムはまだ完全には解明されていません。
2009年から2011年に診断された肺がん患者さんの5年相対生存率を見ると、男性で29.5%、女性で46.8%、全体では34.9%となっています。女性の方が約1.5倍高い生存率を示していることがわかります。
再発率について
肺がんは再発しやすいがんの一つとされています。治療によって目に見えるがんがなくなった後に、再びがんが現れることを「再発」といいます。再発には、治療した場所に再び現れる「局所再発」と、別の臓器に現れる「転移」があります。肺がんの再発では、転移が圧倒的に多く、再発全体の約8割を占めるといわれています。
再発率は病期によって異なります。I期の非小細胞肺がんでも、約20%から30%の再発率があるとされています。II期やIII期になると、再発のリスクはさらに高くなります。再発のほとんどは治療後2年以内に起こり、5年を過ぎると再発は少なくなります。そのため、治療後5年間は特に慎重な経過観察が必要とされています。
再発の好発部位としては、脳、骨、肝臓、対側肺(反対側の肺)などがあります。これらの部位に転移した場合、それぞれの症状が現れることがあります。例えば脳転移では頭痛や神経症状、骨転移では持続的な痛みや骨折などです。定期的な検査により、これらの症状が出る前に再発を発見できる可能性が高まります。
生存率に影響を与える要因
生存率は統計的な数値であり、個々の患者さんの予後を正確に予測するものではありません。生存率には多くの要因が影響します。
まず、がんの病期と組織型が最も重要な要因です。前述のとおり、早期で発見されるほど、また非小細胞肺がんの方が、予後は良好です。
次に、患者さんの年齢や全身状態も重要です。若く体力がある患者さんの方が、治療に耐えられる可能性が高く、予後も良い傾向にあります。また、糖尿病や心臓病、慢性閉塞性肺疾患(COPD)などの併存疾患がある場合、治療の選択肢が限られたり、合併症のリスクが高まったりする可能性があります。
治療法の選択も予後に大きく影響します。手術が可能な早期がんでは、完全切除できれば治癒の可能性が高まります。進行がんの場合でも、遺伝子変異の有無によって適切な分子標的薬を使用できれば、生存期間を延ばせる可能性があります。
さらに、喫煙歴も重要な要因です。喫煙は肺がんの発症リスクを高めるだけでなく、診断後も治療効果や予後に悪影響を及ぼす可能性があります。がんと診断された後でも禁煙することで、治療効果の改善が期待できます。
治療の進歩による生存率の改善
肺がんの治療は近年、めざましい進歩を遂げています。特に過去10年間で、分子標的薬や免疫チェックポイント阻害薬といった新しい治療法が次々と登場し、生存率は着実に向上しています。
分子標的薬は、がん細胞に特有の分子(ドライバー遺伝子変異)を標的として攻撃する薬です。EGFR遺伝子変異やALK融合遺伝子、ROS1融合遺伝子、KRAS遺伝子変異などに対応する薬剤が開発されており、これらの変異がある患者さんでは高い治療効果が期待できます。従来の抗がん剤と比べて副作用も軽いことが多く、生活の質を保ちながら治療を継続できる可能性が高まっています。
免疫チェックポイント阻害薬は、患者さん自身の免疫力を高めてがんと闘う治療法です。PD-1阻害薬やPD-L1阻害薬などがあり、非小細胞肺がんだけでなく小細胞肺がんでも使用されるようになっています。効果が得られた場合、長期にわたって病状をコントロールできるケースも報告されています。
また、早期の非小細胞肺がんに対しては、手術後の補助療法としてオシメルチニブ(タグリッソ)などの分子標的薬を使用することで、再発リスクを減らせることが臨床試験で示されています。さらに、重粒子線治療が2024年6月から保険適用となり、I期からII期の非小細胞肺がんに対する新たな選択肢も増えています。
このように治療法が進歩しているため、現在公表されている生存率のデータ(2012年や2015年に診断された患者さんのデータ)よりも、今治療を受けている患者さんの予後は改善している可能性が高いと考えられます。
生存率データを理解するうえでの注意点
生存率のデータを見る際には、いくつかの注意点があります。
まず、生存率はあくまで過去のデータに基づく統計値であり、個々の患者さんの予後を正確に予測するものではありません。同じ病期でも、患者さんごとに年齢、全身状態、併存疾患、遺伝子変異の有無などが異なるため、実際の経過は人それぞれです。
また、公表されている生存率データは、数年前に診断された患者さんのものです。例えば2015年診断例の5年生存率は2020年の時点でのデータであり、現在(2026年)の治療水準とは異なります。前述のとおり、近年の治療法の進歩により、現在の生存率はこれらのデータよりも改善している可能性があります。
さらに、施設によって患者さんの構成が異なることにも注意が必要です。進行がんの患者さんが多い施設、高齢の患者さんが多い施設など、それぞれの特性があります。そのため、施設別の生存率を単純に比較して、治療の良し悪しを判断することはできません。
生存率データは、治療方針を考えるうえでの一つの参考情報として活用し、担当医とよく相談しながら、ご自身の状況に最も適した治療を選択することが大切です。
経過観察の重要性
治療後の経過観察は、再発や転移を早期に発見し、適切な対応をとるために欠かせません。肺がんでは、手術後5年以内の再発がほとんどであるため、治療後5年間は特に慎重な経過観察が推奨されています。
経過観察では、定期的に血液検査や画像検査(胸部X線検査、CT検査など)を行います。一般的には、治療後2年間は3カ月ごと、その後3年目から5年目までは6カ月ごと、5年以降は年1回程度の検査が目安とされていますが、患者さんの状態によって頻度は調整されます。
また、気になる症状が現れた場合は、定期検査を待たずに担当医に相談することが重要です。咳や痰、血痰、息切れ、胸痛、体重減少、持続する痛みなど、異常を感じたら早めに受診しましょう。
予後を改善するためにできること
生存率は統計的な数値ですが、患者さん自身が予後の改善のためにできることもあります。
最も重要なのは禁煙です。喫煙は肺がんの発症リスクを高めるだけでなく、治療効果を低下させ、再発リスクを高める可能性があります。がんと診断された後でも禁煙することで、治療成績の向上が期待できます。
また、バランスの取れた食事や適度な運動など、健康的な生活習慣を心がけることも大切です。体力を維持することで、治療に耐えられる可能性が高まります。ただし、無理は禁物です。体調に合わせて、できる範囲で取り組むことが重要です。
さらに、医療者とのコミュニケーションを大切にしましょう。わからないことや不安なことがあれば、遠慮せずに質問することが大切です。納得のいく治療を受けるためには、患者さん自身が治療内容を理解し、医療者と協力して治療に取り組むことが重要です。
精神的なサポートも予後に影響を与える可能性があります。家族や友人、カウンセラーなど、話を聞いてもらえる人や場所を持つことで、心の負担を軽減できます。多くの医療機関には相談支援センターがあり、治療や生活に関する相談ができます。
参考文献・出典情報
本記事は以下の信頼できる情報源に基づいて作成されています。