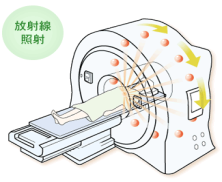
乳がん転移時の放射線治療|症状緩和を目的とした治療法
乳がんが他の臓器に転移した場合、最も一般的に放射線治療が適用されるのは骨転移と脳転移です。これらの転移に対する放射線治療の主な目的は、症状の緩和と局所制御であり、完治を目指すものではありません。
転移性病変に対する放射線治療は、2025年現在、技術の進歩により精度が向上し効果的が可能になっています。
骨転移に対する放射線治療の適応と効果
骨転移は乳がんの転移の中で最も頻度が高く、再発・転移がんの約30%の患者さんに起こります。骨に転移したがん細胞は骨を破壊していくため、痛みや骨折を起こしやすくなり、患者さんの生活の質を損ないます。
骨転移に対する放射線治療の主な適応は以下の通りです:
- 疼痛の改善:転移による骨の痛みを和らげる
- 骨折予防:骨の破壊が進行するのを防ぐ
- 脊髄神経麻痺の予防・改善:脊椎転移による神経症状の緩和
- 運動機能の維持:日常生活動作の維持・改善
特に脊椎に転移した場合、神経への影響が懸念されます。脊椎転移が進行すると神経にしびれや運動麻痺が起こることがあり、生活に支障をきたします。放射線治療により、これらの症状の進行を抑制することが期待できます。
2025年の最新の治療では、体幹部定位放射線照射という技術が普及しており、通常の照射と比較して周囲の正常組織への影響を極力減少させることが可能です。治療は病変がある骨に対し12グレイという強度の照射を2回行い、1回の照射時間は40~50分程度です。この治療により、腫瘍は60~90%という水準で局所制御することができると報告されています。
脳転移に対する放射線治療の種類と選択基準
乳がんの脳転移は、HER2陽性乳がんやトリプルネガティブ乳がんでより頻度が高いとされています。脳転移に対する放射線治療は、転移巣の数、大きさ、部位、患者さんの全身状態などを総合的に判断して治療法を選択します。
脳転移に対する放射線治療には大きく分けて2つの方法があります:
定位放射線治療(定位照射)
定位放射線治療は、病巣に対して多方向から放射線を集中させる方法で、ピンポイント照射とも呼ばれます。通常の放射線治療と比較して周囲の正常組織にあたる線量を極力減少させることが可能です。
定位放射線治療の適応は以下の通りです:
- 脳転移病巣が少数個(4個以下)
- 全身状態が良好
- 他の臓器の転移が制御されている
- 転移巣の直径が3cm以下
1回照射で終わる場合を特別に定位手術的照射(SRS)といい、小さな病巣に有効な治療法です。腫瘍サイズが大きい場合は脳壊死や照射後の浮腫の悪化が懸念されることから、1回線量を下げた定位放射線治療(SRT)を分割して行うことが多くなっています。
全脳照射
全脳照射は脳全体に放射線を照射する方法で、多発性脳転移に対する標準的な治療法です。以下の場合に適応となります:
- 脳転移が多発している場合(4個を超える転移)
- 予後不良と判断される場合
- 全身状態が良くない場合
- 他の臓器の転移が制御されていない場合
全脳照射により約70%の患者さんで神経症状の改善が認められますが、長期間頭蓋内病変を制御することは難しく、主に症状緩和を目的とした治療となります。治療スケジュールは、30グレイを10回、37.5グレイを15回、40グレイを20回など、患者さんの状況に応じて選択されます。
ガンマナイフによる集光照射の特徴と治療成績
ガンマナイフは脳病変に対する定位放射線治療の代表的な装置です。約200個のコバルト60線源から出るガンマ線が、コリメーターによって細いビームとなり、小さな領域(病巣)に集中するように設計されています。
ガンマナイフの特徴は以下の通りです:
- 開頭手術が不要で身体への負担が少ない
- 正常脳組織への影響を最小限に抑制
- 治療時間が30分から1時間程度に短縮
- 入院期間は1~3日と短期間
- 退院後すぐに通常の生活に復帰可能
2025年現在、日本国内には50台以上のガンマナイフが稼働しており、年間約200症例を超える治療が行われています。最新モデルのガンマナイフIconでは、従来のフレームでの頭部固定に加え、マスク固定による治療も可能になり、患者さんの負担がさらに軽減されています。
乳がんの脳転移に対するガンマナイフ治療は、特に放射線感受性が高いとされる乳がんにおいて良好な治療成績が報告されています。多発性転移性脳腫瘍に対しても、複数回にわたる治療により長期制御が期待できる症例があります。
| 治療法 | 適応 | 治療回数 | 局所制御率 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| ガンマナイフ | 脳転移4個以下 | 通常1回 | 85-95% | 高精度、短時間治療 |
| 定位放射線治療 | 脳転移4個以下 | 1-5回 | 80-90% | 分割照射可能 |
| 全脳照射 | 多発性脳転移 | 10-20回 | 症状改善70% | 症状緩和中心 |
放射線治療の副作用と対処法
放射線治療の副作用は、放射線が照射された領域に含まれた臓器に炎症が起こることが原因で発生します。そのため、照射部位に特有の症状が出現します。
急性期の副作用(治療中から数週間)
骨転移に対する放射線治療では、照射部位近くの皮膚や消化管の炎症により、腹痛や下痢が起こることがあります。腰椎に放射線を照射した場合、近くの皮膚に軽度の皮膚炎が生じる場合がありますが、保湿剤や消炎鎮痛剤の使用により1か月程度で改善します。
脳転移に対する放射線治療の急性期副作用には以下があります:
- 全身倦怠感:だるさや疲労感
- 消化器症状:吐き気、食欲不振
- 神経症状:頭痛、めまい
- 皮膚症状:頭皮の発赤、脱毛
全脳照射を受けた患者さんでは、頭全体の脱毛が治療開始から2~3週間後に始まります。多くの場合、治療終了から3~6か月で毛髪は再生し始め、6か月から1年程度でほぼ回復します。
晩期の副作用(数か月から数年後)
照射後、長期間経過してから以下の副作用が現れることがあります:
- 認知機能障害:集中力の低下、記憶障害
- 内分泌機能障害:甲状腺機能低下など
- 放射線壊死:照射部位の組織変化
- 皮膚の色素沈着や硬化
2025年現在では、認知機能温存を目的として海馬を回避した全脳照射技術も導入されており、従来よりも認知機能への影響を軽減できる可能性があります。
2回照射の原則と例外的な対応
放射線治療は原則として同じ部位に2回照射することはできません。これは放射線が同じ場所に重複して照射されると、著しく副作用が増加するためです。しかし、脳転移の場合には例外があります。
脳転移では、最初に全脳照射を行った後で、脳の一部分に限って定位照射を追加することがあります。この治療法は「サルベージ定位照射」と呼ばれ、全脳照射後の局所再発に対する有効な治療選択肢として確立されています。
また、2025年の最新治療では、Simultaneous Integrated Boost法という高度な照射法も普及しています。この方法では、全脳照射をしながら画像で見える転移には定位放射線治療並みの強い放射線量を同時に照射し、画像で見える転移と微小転移の両方を制御することが可能です。
転移時の放射線治療における治療選択の流れ
乳がんの転移に対する放射線治療の選択は、以下の要因を総合的に判断して決定されます:
- 患者さんの全身状態(KPS、年齢)
- 転移巣の数、大きさ、部位
- 他臓器への転移の有無と制御状況
- 乳がんのサブタイプ(ホルモン受容体、HER2の状態)
- 予想される生存期間
近年、乳癌特異的GPA(Graded Prognostic Assessment)という予後予測指標が開発され、年齢、全身状態、サブタイプ、頭蓋外転移の有無、脳転移の個数の5因子を点数化して生存期間を予測し、治療方針の決定に活用されています。
骨転移に対しては、症状の有無、転移部位、骨折リスクなどを考慮して治療方針を決定します。疼痛がある場合や脊髄圧迫のリスクがある場合は、速やかな放射線治療が検討されます。
最新の治療技術と今後の展望
2025年現在の放射線治療技術は大きく進歩しており、以下のような最新技術が実用化されています:
強度変調回転照射(VMAT)
領域リンパ節への照射において、従来の照射法と最新の高精度技術であるVMATを組み合わせたハイブリッドVMATが導入されています。この技術により、心臓や肺などの正常組織への影響を最小限に抑えながら、均一かつ集中した放射線治療が可能になりました。
画像誘導放射線治療(IGRT)
治療前に毎回CT撮影を行い、腫瘍の位置を確認してから放射線を照射する技術です。呼吸や体位の変化による腫瘍位置のずれを補正し、より正確な治療が可能になっています。
人工知能(AI)を活用した治療計画
AI技術を活用した治療計画システムにより、より個々の患者さんに最適化された治療計画の立案が可能になり、治療効果の向上と副作用の軽減が期待されています。
薬物療法との併用時の注意点
放射線治療と抗がん剤治療の両方が必要な場合、同時に行うと副作用が出やすいため通常は避けられます。一般的には、まず3~6か月間の抗がん剤治療で全身的な効果を狙い、その後で放射線治療を行うことが多くなっています。
ただし、症状が強い場合や急速に進行する場合は、症状緩和を優先して放射線治療を先行することもあります。治療スケジュールは、患者さんの状態や治療方針に応じて個別に決定されます。
また、分子標的薬や免疫チェックポイント阻害薬との併用についても研究が進んでおり、今後より効果的な組み合わせ治療の確立が期待されています。
患者さんの生活の質向上への取り組み
転移時の放射線治療において、症状の緩和だけでなく、患者さんの生活の質(QOL)の維持・向上が重要な目標となっています。2025年現在では、以下のような取り組みが行われています:
- 外来での治療実施:入院期間の短縮
- 治療時間の短縮:技術進歩による治療効率の向上
- 副作用の軽減:高精度照射技術の活用
- 症状管理:疼痛緩和や支持療法の充実
- 心理的サポート:緩和ケアチームによる支援
特に骨転移による疼痛については、放射線治療により多くの患者さんで痛みの軽減が得られ、鎮痛剤の使用量を減らすことができます。これにより、眠気や便秘などの鎮痛剤の副作用も軽減され、日常生活の質が改善されます。
参考文献・出典情報
- 国立がん研究センター がん情報サービス「乳がん 治療」
- 日本乳癌学会「乳癌診療ガイドライン2022年版 BQ12 乳癌脳転移に対して放射線療法は勧められるか?」
- SURVIVORSHIP.JP「転移性脳腫瘍の診断と治療|治療法」
- 国立がん研究センター がん情報サービス「放射線治療の種類と方法」
- 乳がんinfoナビ「転移部位別の治療法」
- MEDLEY「乳がんの放射線治療:効果・治療期間・費用・仕事への影響」
- 日本ガンマナイフ学会「定位放射線治療」
- 済生会熊本病院「ガンマナイフ」
- QLife がん「乳がんの『放射線療法』治療の進め方は?治療後の経過は?」
- 日本乳癌学会「患者さんのための乳がん診療ガイドライン2023年版 Q45 脳転移について教えてください」














