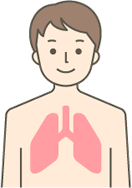
肺がんの疑いがある場合、確定診断のための精密検査が必要になります。しかし、入院期間や入院費用について不安を感じている患者さんも多いと思います。ここでは2025年現在の最新情報に基づいて、肺がん精密検査における入院期間と入院費用について詳しく解説します。
肺がんは日本人男性のがん死亡数第1位、女性では第2位を占める重要な疾患です。
2025年4月に公開された国立がん研究センターの最新ガイドラインでも、適切な精密検査の実施が治療成功の鍵として強調されています。入院期間や費用を正しく理解することで、安心して検査を受けることができます。
肺がん精密検査における入院期間と入院費用の概要
肺がんの精密検査では、検査手法によって入院期間と入院費用が大きく異なります。気管支鏡検査は多くの場合日帰りから1泊2日で実施され、経皮的針穿刺生検は通常外来で行われます。一方、胸腔鏡検査は全身麻酔を伴う手術的検査のため、数日間の入院期間が必要となります。
2025年現在、これらの精密検査はすべて保険適用の対象となっており、患者さんの自己負担は原則3割となります。ただし、高額療養費制度を利用することで、実際の自己負担額をさらに抑えることが可能です。
| 検査手法 | 入院期間 | 入院費用(保険適用前) | 自己負担額(3割負担) | 入院の必要性 |
|---|---|---|---|---|
| 気管支鏡検査 | 日帰り~1泊2日 | 約20万円~30万円 | 約6万円~9万円 | 外来可、状況により入院 |
| 経皮的針穿刺生検 | 原則外来(日帰り) | 約15万円~20万円 | 約4.5万円~6万円 | 基本的に外来検査 |
| 胸腔鏡検査 | 3日~1週間 | 約80万円~120万円 | 高額療養費制度適用 | 入院必須 |
気管支鏡検査の入院期間と入院費用詳細
気管支鏡検査は、肺がん精密検査における最初の選択肢として実施されることが多い検査です。入院期間は患者さんの状態や検査の複雑さによって決定されますが、多くの医療機関では効率的な検査体制を整備しています。
気管支鏡検査の入院期間パターン
気管支鏡検査は多くの場合、日帰りか、1泊2日で行われます。原則的には外来で行っていますが、高齢者、低肺機能の方、経気管支鏡的肺生検を行う方、希望者は一泊入院で行っております。医療機関によって方針が異なるため、担当医との相談が重要です。
1泊2日入院で実施する場合の流れは、入院当日は午前中に入院して頂き、入院後は採血やレントゲン、心電図、肺機能検査など検査前に必要な検査を実施します。午後には気管支鏡検査を実施し、検査時間のおおよその目安は30~60分です。検査終了後は副作用の有無を確認して問題がなければ翌日に退院となります。
日帰り検査の場合でも、検査前の4時間は絶食が必要で、検査後数時間の経過観察が行われます。検査時はつらくないように、局所麻酔薬と鎮静薬を使いますため、患者さんの負担は軽減されています。
気管支鏡検査の入院費用構成
気管支鏡検査の入院費用は、検査手技料、入院基本料、各種検査料、薬剤料などから構成されます。保険適用前の総費用は約20万円~30万円程度となり、3割負担の場合の自己負担額は約6万円~9万円となります。
1泊2日入院の場合、入院基本料に加えて食事代(1食あたり460円)が別途必要になります。また、個室を希望する場合には差額ベッド代が発生しますが、検査目的の短期入院では通常大部屋での対応となることが多いです。
高額療養費制度を利用する場合、年収約370万円~700万円の方であれば、自己負担限度額は8万100円+(医療費-26万7,000円)×1%となるため、実際の負担額はさらに軽減されます。
「自分の判断は正しいのか?」と不安な方へ

がん治療。
何を信じれば?
不安と恐怖で苦しい。
がん治療を左右するのは
治療法より“たった1つの条件”です。
まず、それを知ってください。
がん専門アドバイザー 本村ユウジ
経皮的針穿刺生検の入院期間と入院費用
経皮的針穿刺生検は、気管支鏡では組織が採取できない末梢型肺がんに対して実施される重要な検査手法です。基本的には外来で実施される検査のため、入院期間は原則として日帰りとなります。
経皮的針穿刺生検の実施体制
経皮的針穿刺生検は、局所麻酔をして肋骨の間から細い針を差し込んで肺の細胞を採取する精密検査です。CTガイド下肺針生検として実施される場合、CTで肺内部の様子を見ながら針生検を行うため、1cm以下の小さながんの確定診断も可能です。
検査は外来で行うこともあれば入院を必要とする場合もありますが、多くの場合は日帰りでの実施が可能です。検査時間は30分程度で、検査後は気胸や出血などの合併症がないことを確認するため、数時間の経過観察が行われます。
経皮的針穿刺生検では、体表に近い病変部の検査を得意としている一方で、出血や処置によりがん細胞を広げてしまうといった合併症のリスクがあります。特に血液をサラサラにするお薬を服用している方は、検査前に服薬状況の確認が必要です。
経皮的針穿刺生検の費用詳細
経皮的針穿刺生検の費用は、保険適用前で約15万円~20万円程度となります。3割負担の場合の自己負担額は約4.5万円~6万円程度です。CTガイド下で実施する場合には、CT撮影料も含まれるため費用がやや高くなります。
日帰り検査のため入院基本料は発生せず、検査手技料と画像診断料、薬剤料が主な費用構成要素となります。外来での実施により、患者さんの時間的・経済的負担も軽減されています。
胸腔鏡検査の入院期間と入院費用
胸腔鏡検査は、他の精密検査で診断が確定しない場合に実施される、最も侵襲的で確実性の高い検査手法です。全身麻酔を伴う手術的検査のため、入院期間は3日~1週間程度が必要となります。
胸腔鏡検査の入院期間と手術工程
胸腔鏡検査は特定の外科手術のために用いられることもあります。胸腔鏡を用いた手術は胸腔鏡下手術(VATS)と呼ばれます。全身麻酔下で行われますが、胸腔鏡検査であれば、目が覚めた状態で鎮静薬だけを投与して行われることもあります。
医師は、胸壁に最大3カ所小さな切り込みを入れ、胸腔内へ胸腔鏡を挿入します。通常は皮膚3箇所を1cmくらい切開し、1箇所からカメラを、他の2箇所からメスや鉗子などの手術具を挿入して処置や検査、手術をおこないます。
検査後は胸腔ドレーンを挿入し、処置中に胸腔に入った空気を抜いてつぶれた肺が再膨張するようにします。ドレーンの抜去時期によって入院期間が決定され、通常3日~1週間程度の入院が必要です。
胸腔鏡検査の入院費用と高額療養費制度
胸腔鏡検査の入院費用は、保険適用前で約80万円~120万円程度となります。これには手術料、入院基本料、麻酔料、各種検査料などが含まれます。3割負担の場合、理論上の自己負担額は約24万円~36万円となりますが、高額療養費制度の適用により実際の負担額は大幅に軽減されます。
年収約370万円~700万円の方の場合、高額療養費自己負担限度額は8万100円+(医療費-26万7,000円)×1%となります。例えば胸腔鏡検査で総医療費が100万円だった場合、自己負担限度額は8万100円+(100万円-26万7,000円)×1%=約8万8,430円となります。
入院期間が長くなる場合には、食事代(1食460円×3食×日数)や差額ベッド代(個室希望の場合)が追加で必要となります。入院期間が1日増減すると総治療費は2万円程度上下しますが、高額療養費制度により患者さんの実質負担への影響は限定的です。
2025年版肺がん検診ガイドラインと検査費用の動向
2025年4月に公開された国立がん研究センターの「有効性評価に基づく肺がん検診ガイドライン」では、重喫煙者(喫煙指数600以上)に対する低線量CT検査が推奨グレードAで推奨されています。これにより、精密検査が必要となる症例の早期発見が期待されます。
新ガイドラインでは、低線量CT検査の利益と不利益を比較検討した結果、対策型検診及び任意型検診として実施(対象年齢は50-74歳、検診間隔は1年に1回)が推奨されています。これにより、より早期の段階で精密検査が実施される機会が増加すると予想されます。
早期発見により、より負担の少ない検査手法での確定診断が可能となり、患者さんの入院期間短縮と入院費用軽減につながることが期待されます。
入院費用を抑える制度と支援体制
肺がん精密検査の入院費用負担を軽減するため、複数の公的制度が利用可能です。これらの制度を適切に活用することで、経済的負担を大幅に軽減できます。
高額療養費制度の活用
高額療養費制度は、1ヶ月の自己負担額(保険対象分)が限度額を超えた場合に、保険者に申請することで超えた分の医療費が数ヶ月後に保険者から払い戻される制度です。年収に応じて自己負担限度額が設定されており、所得が低い方ほど負担限度額も低く設定されています。
入院期間が2ヵ月以上にまたがった場合、月ごとの計算となるため上記金額をこえてのご請求となる場合があります。このような場合でも、各月について高額療養費制度を適用することで負担軽減が図れます。
限度額適用認定証を事前に取得しておくことで、医療機関の窓口での支払い時に既に限度額が適用された金額での精算が可能となり、一時的な高額負担を避けることができます。
医療費控除と民間保険の活用
年間医療費が10万円を超える場合、確定申告により医療費控除を受けることができます。肺がん精密検査の入院費用も控除対象となるため、翌年の所得税軽減につながります。
民間の医療保険に加入している場合、医師の指示による検査入院は、治療を目的とした入院として入院給付金をご請求いただけます。ただし、健康管理を目的とした「人間ドック」や「定期健康診断」等の入院は、治療を直接の目的としていないため、入院給付金のお支払い対象外となります。
精密検査を受ける患者さんへの入院期間中のサポート
2025年現在、肺がん精密検査における患者さんの心理的・身体的負担軽減のため、多くの医療機関で充実したサポート体制が整備されています。
検査時の苦痛を和らるために、点滴より鎮静剤投与を行っております。この投与の量や方法については患者さんのご協力を得て臨床研究を行い、安全かつ十分な鎮静方法を検討することができました。
多くの医療機関では、2名の気管支鏡指導医、3名の専門医の下で、気管支鏡検査前にカンファレンスがあり、安全性の評価や必要な手技の確認、どの気管支からどのように診断していくかなどを皆で議論し、より安全かつ有意義で時間を短縮した検査になるよう努めています。
入院期間中は、患者さんと家族に対して検査の内容や流れ、予定時間、検査後の状態やどのように回復していくかなどの説明が丁寧に行われます。不安や疑問がある場合は、遠慮なく医師や看護師に相談できる環境が整っています。
検査後の経過観察と継続的費用管理
肺がんの精密検査完了後も、定期的な経過観察が必要となる場合があります。これらの継続的な医療費についても、適切な費用管理が重要です。
確定診断後の病期診断検査では、胸腹部の造影CT検査や脳のMRI検査、PET検査、骨シンチグラフィなどが実施される場合があります。これらの検査も保険適用の対象となりますが、検査の組み合わせによっては高額になる可能性があります。
治療開始前の各種検査費用についても、高額療養費制度の適用が可能です。同一月内に複数の検査を受ける場合、合算して自己負担限度額を計算するため、効率的な検査スケジューリングが費用削減につながります。
入院期間と入院費用に関する最新動向と将来展望
医療技術の進歩により、肺がん精密検査の入院期間短縮と入院費用削減が継続的に進んでいます。2025年現在の傾向として、低侵襲性検査手法の普及により、より短期間での確定診断が可能になっています。
気管支鏡検査においては、新しい画像技術や人工知能を活用した診断支援システムの導入により、検査精度向上と時間短縮が実現されています。これにより、日帰り検査の適応範囲が拡大し、入院費用削減に寄与しています。
胸腔鏡検査についても、手術手技の標準化と低侵襲化により、入院期間の短縮と合併症率の減少が達成されています。通常の大きく胸を切開して行う手術と比較すると、切開する傷が小さいため患者さんの身体的負担は軽減され、早期退院が可能となっています。
今後は、遠隔医療技術の活用により、検査後の経過観察における通院回数減少や、在宅での状態監視システムの導入により、総医療費のさらなる削減が期待されます。
地域による入院期間と入院費用の違い
肺がん精密検査の入院期間と入院費用は、医療機関の規模や地域によって一定の差があります。大学病院やがん専門病院では最新の設備と専門医による検査が受けられる一方、地域の中核病院でも適切な精密検査が実施可能です。
医療機関選択の際は、入院費用だけでなく、検査の質や安全性、アクセスの利便性、継続的な治療体制なども総合的に検討することが重要です。がん相談支援センターでは、地域の医療機関情報や費用に関する相談も受け付けています。
セカンドオピニオンを希望する場合の費用についても、多くの医療機関で明確な料金設定がなされており、患者さんが安心して意見を求めることができる環境が整っています。
まとめ
肺がん精密検査における入院期間と入院費用は、検査手法によって大きく異なりますが、すべて保険適用の対象となっており、高額療養費制度の活用により患者さんの経済的負担は軽減されます。気管支鏡検査は日帰りから1泊2日、経皮的針穿刺生検は原則日帰り、胸腔鏡検査は3日から1週間程度の入院期間が標準的です。
2025年現在、検査技術の向上と患者サポート体制の充実により、以前と比較して身体的・経済的負担は大幅に軽減されています。
参考文献・出典情報
- 国立がん研究センター「有効性評価に基づく肺がん検診ガイドライン」2025年度版
- 肺がんとともに生きる「肺がん手術による入院期間と費用」
- がん治療費ドットコム「部位別がんの治療費:肺がんの治療費」
- 国立病院機構 東徳島医療センター「気管支鏡検査」
- 京都 西陣病院「気管支内視鏡検査について」
- プレシジョン「気管支鏡:何がわかるの?どんな時に必要なの?」
- ソニー生命保険「入院費用はいくらかかる? 1日あたりの相場や内訳をご紹介!」
- がん情報サイト「オンコロ」肺がんの診断・検査
- 国立がん研究センター がん情報サービス「肺がん 検査」
- 東京海上日動あんしん生命「検査を受けた場合に請求できる給付金はありますか?」



