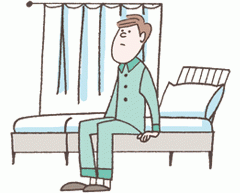
大腸、胃など他のがんから肝臓に転移したがんを「転移性肝臓がん」と呼ぶことがあります。
肝臓は、腸から血液に乗って運ばれてきた栄養素をもとにして、体内で必要なたんぱく質などを合成したり、血液をろ過して毒物を分解するなどの重要な機能をもっています。そのため、大量の血液が肝臓を通過します。
肝臓以外の臓器には、動脈から血液が流れ込み、静脈から流れ出るようになっています。ところが肝臓には、動脈(肝動脈)のほかに、「門脈」と呼ばれる血管からも血液が流入します。
門脈は、おもに腸管(胃、小腸、大腸などの消化器)から静脈血を集めて、肝臓に送り込んでいます。このため肝臓には、血液に入り込んだがん細胞、とくに消化器のがんから血液中に入り込んだがん細胞が流れ着く可能性が高くなっています。
たとえば、大腸がん患者の場合、原発がんである大腸がんの発見とともに、肝臓に転移したがんも発見される「同時性転移」の症例が、全体の18パーセントにのぼります。また、大腸の手術を行った後に肝臓への転移が発見される「異時性転移」も6パーセントほどあります。胃がん患者では、同時性転移は約6パーセントですが、異時性転移は20パーセントに及びます。
異時性の転移といっても、実際には、原発がんの手術が行われたときには、すでにその転移は存在していたはずです。そのため、解剖で確かめると、実に50パーセント近い確率で肝転移が見つかるとされています。
つまり、胃がんや大腸がんで手術を受ける患者の半分近くには、すでに肝転移が起こっているということになります。膵臓がんでは肝転移の確率はさらに高く、70パーセントにのぼるとみられています。
もちろん消化器がん以外のがんからも、肝転移は生じます。前述のように、消化器がんからの転移は、静脈に流れ出たがん細胞が門脈に流れ込んで肝臓に到達します。しかし、消化器がん以外のがんからは、全身の血流に流れ出たがん細胞が、肝動脈を通って肝臓に流れ込んだことになります。
したがって、消化器がん以外のがんから肝転移が発生した場合には、肝臓以外にも転移が起こっている可能性が高いことになります。
転移性肝臓がんの特徴
転移性肝臓がん(がんの肝転移)は、もともと体内の他の場所で発生したがん細胞が増殖して血管に入り込み、血液の流れに乗って肝臓の組織にたどり着き、そこで成長したものです。
そのため多くの場合、肝臓内に1カ所でもそのような病巣が見つかれば、ほかにも小さな病巣が隠れている可能性が高いと考えなくてはなりません。
さらに、原発性のがんが肝臓以外の場所に転移している可能性もあります。そのため、かつては、転移性肝臓がんとわかっただけで、多くの医師が手術は不可能と判断していました。
また、転移性肝臓がんの治療にさしあたり、成功したとしても、もとになった原発性のがんが完全に治療されていなければ、いずれその病巣からふたたび転移が起こります。したがって、転移性肝臓がんの場合、肝臓だけを治療しても、がんの治療としては成り立ちません。
転移性肝臓がんは、他の場所で生じたがんが肝臓の内部で成長したものであるため、腫瘍の特徴は、もとのがん細胞の性質を反映したものになります。
転移性肝臓がんの多くは、消化器に発生したがんがもとになっていますが、これらは「腺がん」と呼ばれる種類のがんです。腺がんは原発性肝臓がんの大部分を占める肝細胞がんとは、腫瘍の性質や画像診断で見る特徴が大きく異なります。そのため、CTや超音波などの検査によって、比較的容易に両者を区別することができます。
一方、原発性肝臓がんのうち、胆管の細胞から発生する肝内胆管がん(胆管細胞がん)もやはり腺がんの一種です。そのため、肝臓だけに腺がんと思われるがんが見つかった場合、それが転移性肝臓がんか原発性の肝内胆管がんかの識別は、困難なことが少なくありません。
転移性肝臓がんの症状
転移性肝臓がんの場合も、その症状は原発性肝臓がんと変わりません。一般にかなり進行するまでは無症状です。ある程度進行すれば、がんが大きく成長したために肝臓が腫れて、触診によって見分けられるようになったり、胆管が詰まって黄疸が出たりすることがあります。
つまり、何らかの症状によって転移性肝臓がんが発見されるということはほとんどありません。多くの場合、原発性のがんが見つかったときに、あるいは治療後の経過観察中に行われる検査によって発見されます。
以上、肝臓がんについての解説でした。




